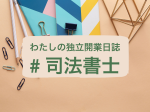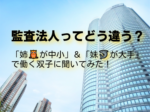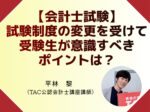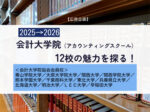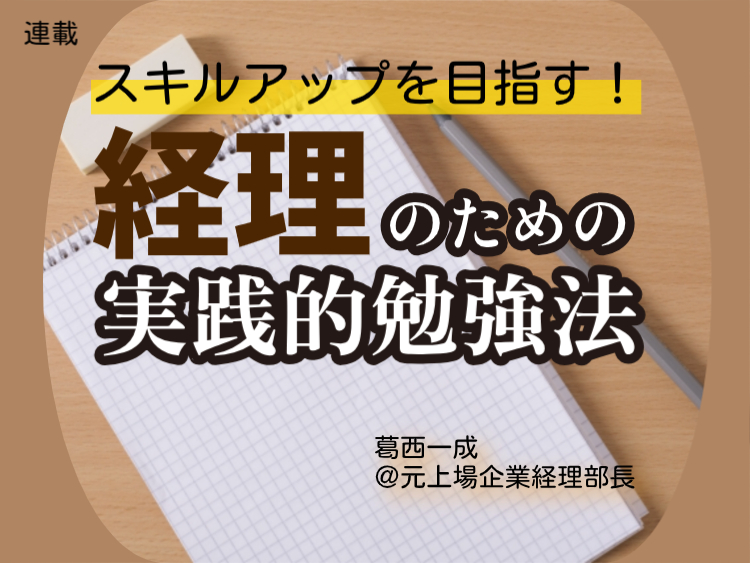
葛西一成@元上場企業経理部長(経理部IS)
【編集部より】
経理部に配属され、会計のことを勉強しないといけなくなったけど、仕事に直結する勉強法ってどうすればよいの? 担当することになった業務について知りたいとき、どのようにアプローチして、どんな本を読めばいい? そんな悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そこで、複数の上場企業で経理の実務経験のある、経理部ISこと葛西一成氏に、経理のための実践的な勉強法についてアドバイスをいただきます。ぜひ、スキルアップにお役立てください!(隔月掲載予定)
はじめに
前回は、中小企業の経理パーソン向けに、一人前の経理になるための勉強ステップ事例をご紹介しました。
今回は、上場企業や中堅・大企業で働く経理パーソンに向けに解説いたします。
一人前の経理パーソンとなるには、実務で活用できるスキルの習得が不可欠です。
そして、そのスキルの習得には順序があり、基礎から応用へと段階的に学んでいく必要があります。
本記事では、より専門性の高い経理業務に携わる経理パーソンが一人前になるまでの道のりを具体的な実務内容を用いてステップごとに解説します。
今後の経理実務の勉強にぜひお役立てください。
企業規模によって異なる経理業務と勉強ステップ内容
企業規模によって経理業務の特性は大きく異なります。
中小企業では、限られた人数の経理担当者が日次から月次、年次決算まで幅広く担当し、さらには人事や総務といった業務にも携わり、広く浅い経理実務スキルが求められます。
一方、今回対象となる上場企業や中堅・大企業では経理業務が専門化され、単体決算、連結決算、原価計算など、それぞれの専門領域に特化した担当者が配置され、各担当領域での高い専門性が求められます。
このため、まずは自分の担当領域の専門性を高めるための勉強を進め、さらに次の分野を経験しながら、徐々に経理実務の経験を深めていくことが望ましいといえます。
今回は、上場企業や中堅・大企業の経理にスポットを当てて、経理パーソンに必要なスキルの習得のための勉強ステップを解説していきます。
中堅・大企業の経理パーソン勉強ステップ事例
ステップ1:経理実務に必要な基礎知識の習得
まずは、自分の担当業務を通じて、自社の勘定科目体系や会計システムの操作を理解することから始めます。
これに加えて、経理部門における資料の管理ルール(紙の証憑類の保存場所やExcel等で作成したファイルの保存)を把握します。また担当する業務によっては、基幹システムなど会計以外のシステム操作理解も必要となります。
日々の業務においては、担当する業務を実施するにあたって必要となる運用ルールやマニュアルといったものを常に確認することを心がけます。
例えば経費精算業務を担当する場合、経費精算のルールの基となる職務権限規程の決裁権限一覧表や旅費規程などをしっかり読み込み、経理処理がその規程に従って適切に行われているかを理解することに注力します。
●勉強すべき内容
・会計システムの操作手順
・スプレッドシート(Excel等)の実務的な操作方法
・自社の勘定科目体系の理解
・資料の管理保存ルールの把握
・担当業務で必要となる基幹系システム操作方法
・担当業務の根拠となる規程や社内ルールの理解
・担当業務における「作業~承認」までの業務フローの把握
ステップ2:担当業務の専門性を高める
月次決算や年次決算において、複数の業務を担当し、その業務の専門性を高めていく段階です。
典型的な例としては、各勘定科目の残高確定のための作業を担当することが挙げられます。
例えば固定資産の場合、取得から除売却、固定資産への計上判定といった基本事項から、リース取引、圧縮記帳や税務調整、連結決算における未実現利益消去など、さまざまな作業を通じて勘定科目の残高確定を行います。
さらには決算開示のための集計や固定資産管理システムの設定や導入といった、勘定科目に紐づく幅広い作業も実施します。
この段階では、担当業務の理解を深め、「この業務なら自分が一番詳しい」と自信が持てるまで専門性を高めることが重要です。
そのためには、関連する会計基準や税法を読んだり専門書籍で知識を補強したりすることに加え、自分に不足している知識を補うためにセミナーを受講するなど、専門性を高めるための効果的な学習法法を身につけていきます。
これにより、現在担当している業務を完璧にこなせるようになるだけでなく、次に担当する業務の効率的な学び方についてのスキルも身に付けることができます。
●勉強すべき内容
・担当業務の本質的理解(なぜこの作業が必要なのか、会計基準や税法から作業の意義を理解する)
・担当業務における決算開示関連作業の理解
・監査法人とのコミュニケーション力(担当業務における資料提出や質問への回答)
・担当業務の専門性を高めるための学習方法の確立(会計基準や税法の読解方法、専門書の効果的な活用方法などの習得)
ステップ3:担当業務を広げる
このステップでは、複数の担当業務を経験し、会計税務に関する専門知識の幅を広げていくことを目指します。
例えば、これまで債務管理を担当していた場合は、債権管理業務へ担当替えを申し出て、債権債務全般業務の理解を深めます。
さらに、連結決算業務における債権債務や取引高消去といった業務にも携わり、実務経験を幅を広げていきます。
また、固定資産の担当であれば、有価証券や出資金といった投資その他の資産に関する業務も経験し、貸借対照表の資産の部に関する総合的な業務理解を深めていきます。
各社の組織体制や役割分担によって状況は異なりますが、例えば単体決算で棚卸資産の管理を担当していた場合、さらに業務範囲を広げるべく、連結決算における棚卸資産未実現利益消去などの作業も含めて対応することでより高度なスキルアップを図ることができます。
ただし、ここで注意が必要なのが、担当業務を広げることについて部門のマネージャーの理解が必要であるということです。
組織によっては、経理部門の人事異動が少なく、担当替えも行われず、同じ作業が繰り返されてしまうこともあります。
これはマネージャーの方針に左右されるため、自身が一人前の経理になるために学びたい経験を積みたいと思っていても簡単には実現できないこともあるでしょう。
そのような場合は、自ら他のメンバーの担当業務を積極的に理解しようと努めることが重要です。
例えば、他のメンバーが行っている退職給付会計処理について、作成されたExcel等の資料を参考に、自分なりにその内容をを分析し、計算方法を理解するといった取り組みを通じて、実務理解を広げていきます。
通常であれば、担当外の業務を自主的に学ぶことは少ないでしょう。
しかし、こうした積極的な姿勢が、経理実務のスキルを向上させることに繋がるのです。
●勉強すべき内容
・現在の担当業務と関連する周辺業務の把握
・関連業務の実践的理解(自主的に作業を検証し、業務範囲を拡大する)
ステップ4:高度な専門知識の習得
中堅・大企業において一人前の経理パーソンとなるには、より専門性の高い会計税務に関する知識の習得が求められます。
ステップ3で複数の業務理解が進むと、より高度な専門業務を担当することになります。例えば引当金や減損会計、税効果会計といった将来予測や仮定による見積り処理に関する業務、法人税や消費税の計算、申告書作成といった税務実務を経験します。
連結決算においては、資本連結や連結キャッシュ・フロー計算書の作成といった高度な業務も担当します。
イレギュラーで発生する組織再編に関する会計・税務対応、国際税務の理解、管理会計(予算管理)など、幅広い分野の業務を経験し、高度な専門知識を身に付けて行きます。
また、内部統制における適切な業務プロセスの構築や、資金調達などの財務業務、IR業務への関与も深めていく必要があるでしょう。
このステップで最も重要となるのが、「さらに専門性を高めていきたい」という強い意欲です。
この意欲なければ、複雑かつ難易度の高い業務に挑戦しようという意識が高まらず、結果、知識習得を諦めてしまうことになります。
このステップが一人前の経理パーソンになるための最大の難関かもしれませんが、ここで得た知識はその後の経理職人生において非常に役立つ(転職でも十分生かせる)財産となります。
ぜひ積極的な習得を心掛けていただきたいと思います。
●勉強すべき内容
・見積りが関係する会計処理(減損会計や税効果会計)の体系的理解
・単体、連結決算業務の全体像の把握
・実践的な税務申告実務
・決算開示業務全般の理解(決算短信、招集通知、有価証券報告書作成)
・内部統制への対応(決算財務報告プロセスの整備、継続的な改善)
・組織再編に関する会計・税務実務
・管理会計実務(予算管理等)
ステップ5:説明力の習得
一人前の経理パーソンとして不可欠なのが、説明力の習得です。
特に上場企業や中堅・大企業では、経理処理を行うにあたって監査法人との意見調整、各部門や子会社からの情報収集や意見調整が必須となります。
この際、いかにわかりやすく簡潔に関係者へ説明することが求められます。例えば、減損会計において必要となる情報を事業部から入手する際には、減損を知らない方にもその意味や情報の必要性をわかりやすく説明する必要があります。
この説明力は一長一短には身に付きません。
やはり実践を通じて場数を踏むことが必要がです。
そしてこの経験を踏むために特に有効なのが以下のような機会を活用することです。
●経験すべき内容
・新システム稼働に伴う業務運用変更の説明会への登壇
・税法改正による実務への影響に関する説明
・年次決算に向けた子会社への決算方針説明
・新会計基準適用に関する社内勉強会での講師
経理というと、PCに向かって黙々と処理をしているイメージがありますが、実際は上記のような対外的な説明の機会が数多くあります。こうした機会を積極的に活用して説明力を磨くことが、一人前の経理パーソンへの近道となります。
まとめ
経理パーソンとして一人前になるには、5つの重要なステップを着実に進むことが求められます。
まず基礎知識として、会計システムの操作や社内ルールの理解から始め、次に担当業務の専門性を高めていきます。
その後、業務範囲を広げて様々な経理実務を経験し、さらに減損会計や税効果会計などの高度な専門知識を習得します。
そして、監査法人や社内外の関係者とのコミュニケーションに必要な説明力を磨きます。
中堅・大企業では各分野の専門性が重視されるため、担当領域での深い知識と幅広い実務経験の両方が求められます。
一人前になるためには、自ら積極的に学ぶ姿勢と、新しい分野に挑戦する意欲が不可欠です。
これらのステップを着実に進んで専門性の高い経理パーソンを目指してください。
<執筆者紹介>
葛西一成@元上場企業経理部長
東証プライム・グロース上場2社で経理部長を経験後、独立開業。独立後は上場企業の決算業務フォロー、会計関連システム開発導入サポート、経理パーソン向けキャリアサポート、執筆活動に注力。X(旧Twitter)では、フォロワー1.7万人超の「経理部IS」アカウントにて、経理の仕事に関する情報を発信中。
著書に『経理のExcelベーシックスキル』(中央経済社)がある。
経理部IS(@keiri_IS)
<著書紹介>
『経理のExcelベーシックスキル』(葛西 一成 著、中央経済社)
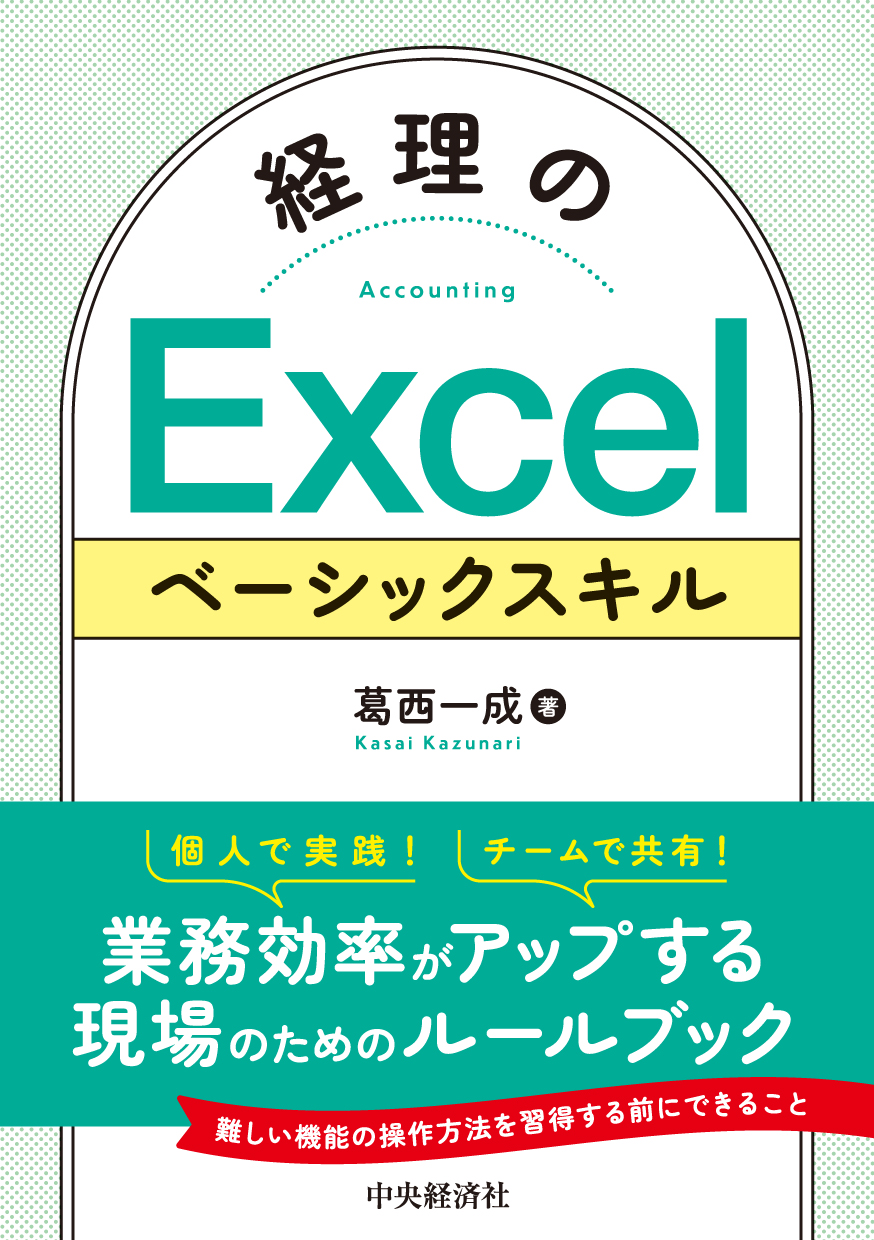
▶︎業務効率がアップするノウハウを現場経験豊富な著者が伝授します! Excelの難しい機能を極める前に知っておきたい使い方から管理方法まで。チーム全員に必須の1冊です。
【「経理のための実践的勉強法」バックナンバー】
第1回:スキルアップを目指そう!
第2回:前払費用の実務
第3回:賞与引当金の実務(前編)(中編)(後編)
第4回:固定資産実務をマスターするまでの道のり
第5回:固定資産の実務における基本的な理解(前編)(後編)
第6回:法人税等の計算スキルを身につける(前編)(後編)
第7回:税効果会計の勉強の進め方<基礎スキル>(前編)(後編)
第8回:税効果会計の勉強の進め方<実務スキル>(前編)(後編)
第9回:リスタートにあたってのイントロダクション
第10回:一人前の経理になるためのステップ事例(中小企業編)
*
経理部ISこと、葛西一成@元上場企業経理部長さん執筆のバックナンバー記事もぜひご覧ください!
【連載バックナンバー(全10回)】
第1回:現役経理部長が教える! 経理の仕事でExcelがマストな3つの理由
第2回:現役経理部長が教える! 経理に必要な4つのExcelスキル~ミス削減&作業効率化にマスト!
第3回:現役経理部長が教える! 仕事が効率化するExcelを‟見やすくする”スキル
第4回:現役経理部長が教える! 今すぐやるべき‟Excelでミスを防ぐ”方法
第5回:現役経理部長が教える! 仕事で評価される‟わかりやすいExcelの表”を作成する方法
第6回:現役経理部長が教える! Excelを使いやすくする5つの方法(前編)(後編)
第7回:現役経理部長が教える! 経理業務の効率化に役立つ! 使いやすいExcelファイルの管理方法(前編)(後編)
第8回:現役経理部長が教える! 仕事スピードを速くするExcel関数とショートカットキー
第9回:現役経理部長が教える! Excelピボットテーブル活用術
第10回:現役経理部長が教える! 作業効率化に役立つExcel機能3選
<こちらもオススメ!>
経理部ISさんに聞く! 上場企業経理への就職・転職 FAQ
経理部ISさんに聞く! いま欲しい上場企業の経理人材はどんな人?