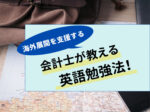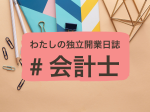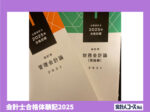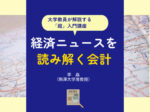【編集部から】
士業の魅力は、独立開業できることにもあります。「将来は独立」を目標に合格を目指している方も多いのではないでしょうか。
そこで、「わたしの独立開業日誌」では、独立した先輩方に事務所開業にまつわるエピソードをリレー形式でお話しいただきます(木曜日の隔週連載)。
登場していただくのは、税理士・会計士をはじめ、業務で連携することの多い士業として司法書士や社労士などの実務家も予定しています。
将来の働き方を考えるヒントがきっと見つかるはずです。
27歳、北千住で独立開業!
はじめまして、北千住税理士事務所を経営している佐藤響と申します。
2023年6月、27歳で独立開業しました。
今回は税理士を目指したきっかけから独立開業後までの道のりを振り返り、受験生や将来的に独立を考えている方の参考になれば幸いです。

独学+大学院で税理士試験に合格!
私が税理士を目指すようになったきっかけは、父の何気ない一言でした。
父が事業を営んでおり、ある日「税理士になってくれたらうれしいな」と言われたことが、心の片隅に残っていました。
大学入学当初は税理士という職業を深く意識していたわけではありません。
転機が訪れたのは大学2年生の頃です。
当時の私は、証券会社に勤めることを目指しており、証券アナリストの資格試験に向けて勉強していました。
しかし、業界研究を進めるうちに、理想とする働き方とは異なると感じ始めました。
そんなある日、資格試験の帰りにふと立ち寄った書店で「税理士試験でもやってみようか」と思い立ち、簿記論と財務諸表論のテキストを1冊ずつ購入しました(小林秀行・並木秀明・長島正浩著『実戦テキスト簿記論』『実戦テキスト財務諸表論』(中央経済社)※現在は刊行していません)。
本来であれば、予備校に通うのが一般的ですが、「自分の力でどこまでやれるか試したい」という思いがあり、独学でスタートすることを決めました。
大学2年生の秋頃から本格的に勉強を始め、不思議と勉強にのめり込んでいきました。
その後は、簿記論と財務諸表論を交互に学習し、初年度は財務諸表論に合格。
2年目には、簿記論と法人税法を受験し、法人税法に合格することができました。
法人税法は市販の問題集が少ないため、1問1問を丁寧に解き、理論は国税庁の判例や通達を活用しながら法律の解釈力を養いました。
3年目には、新卒として税理士事務所に入社し、仕事と並行して簿記論と相続税法の勉強を続けました。仕事に慣れるまで時間がかかりましたが、何とか簿記論には合格することができました。
その後、消費税法と相続税法にも挑戦しましたが、残念ながら合格には至らず、方向転換として大学院へ進学し、科目免除制度を活用することを選びました。
独立までの経緯
税理士試験の受験を始めた頃から、私は漠然と「いつかは独立したい」という思いを抱いていました。
特に大きなきっかけとなったのは、業界に広く浸透していた「みなし残業」という制度でした。
私はこの制度に違和感を覚え、「頑張った分だけ正当に報われる環境を自分でつくりたい」と強く思うようになりました。
税法科目の選択においても、将来的な独立を意識し、実務で頻繁に使う法人税法・消費税法・相続税法を選びました。
また、私は独立までに3つの税理士事務所で勤務しましたが、それぞれの職場選びも「独立後に必要なスキルを得られるか」を軸に決めていました。
1社目では、さまざまな業種のお客様に対応するための総合力を身につけ、2社目は税務調査対応、3社目は規模の大きな法人や事業承継等の税務を経験させていただきました。
これら3社での経験は、いずれも独立を見据えた「戦略的なキャリア形成」の一環でした。
そして、3社目に勤務している最中に税理士登録が完了。
2023年5月に正式に登録され、同年6月1日、念願だった自身の事務所を開業するに至りました。
独立後について
幸いにも、私は“顧客ゼロ”からのスタートではありませんでした。
開業時点で数社のお客様がすでにおり、前職時代の収入程度は確保できる状況でした。
しかし、目指していたのは「規模を拡大し、成長し続ける事務所」。
そのためには、売上の継続的な増加が不可欠であると考え、まずは制度融資を活用して500万円の資金を調達しました。
その資金をもとに、集客に本格的に取り組みました。
ホームページの強化に時間をかけ、異業種交流会や経営者の集まりにも積極的に参加。
その中で、最も効果が高かったと感じているのは、やはりWebマーケティングの取り組みです。
ブログを定期的に執筆し、コンテンツを地道に増やすことでSEO効果が現れ、問い合わせ数が徐々に増加。
さらに、お客様対応の質を高めることで、紹介につながる信頼関係も構築できました。
開業から3か月間ほどは、知人や紹介会社経由での新規顧客が中心でしたが、次第にホームページからの直接問い合わせが増えていき、安定した集客の流れができ始めました。
当初は自宅を兼ねた小さな事務所からのスタートでしたが、半年後にはシェアオフィスへと移転。
それに合わせてアルバイトスタッフにも入社してもらい、業務体制を少しずつ整えていきました。

固定費を抑え、その分を人件費に回す
私は「固定費を抑え、その分を人件費に回す」ことを重視しています。
華美なオフィスよりも、従業員への還元を優先する方が長期的に良い組織づくりにつながると考えているため、今後支店展開をする際にもこの考え方は維持する予定です。
こうした取り組みの結果、現在では顧問先は70~80社まで増え、従業員も5名体制にまで拡大しました。
今後の目標としては、2025年には10名規模、2026年には15~20名規模の組織へと成長させていくことです。
もちろん、ただ人数を増やすだけではなく、「お客様へのサービス品質」と「従業員の働きやすさ」の両立を目指し、質の高い事務所運営をしていきたいと考えています。
独立して苦労したこと
現在のところ、独立してから大きな苦難に直面したということはありません。
ただし、日々「どのように集客を伸ばしていくか」「事業の成長スピードをどう高めるか」「優秀な人材に選ばれる環境をどう整えるか」など、考えるべき課題は多く、経営者としての思考量は確実に増えました。
そうした課題に取り組む中で、知識の必要性も強く実感しています。
独立後は本を読む時間が明らかに増えました。
たとえば、Google広告を運用する際には「どんなコピーが検索されやすいのか」「どういったLP(ランディングページ)が成約率を高めるのか」といった視点で分析を行い、自分の中に仮説と検証のサイクルを構築しています。
また、採用活動においては、事務所の雰囲気や価値観を伝える手段としてYouTubeでの情報発信にも着手しました。どのようなコンテンツが求職者の心を動かすのか、目的に応じてどの表現が効果的なのかを試行錯誤しながら改善を重ねています。
受験生へのメッセージ
税理士試験は、非常に難易度が高く、長期的な努力を要する試験です。
合格までの道のりは決して平坦ではありませんが、その先には大きな自信と、何よりも「人生の選択肢の広がり」が待っています。
税理士としてのキャリアは、実に多様です。
私のように独立し、自分の裁量で事務所を経営していく道もあれば、大手法人や専門分野で高度な税務を極め、自分にしかできない仕事を追求する道もあります。
いずれの選択を取るにせよ、税理士という資格は、その理想を現実にするための確かな力になります。
だからこそ、試験合格を「ゴール」ではなく、「理想の自分に近づくためのプロセス」として捉えてみてください。
自分が将来どんな税理士になりたいのかを意識しながら勉強に取り組めば、モチベーションの維持もしやすく、学ぶ意味もより深まるはずです。
試験勉強は孤独で苦しい場面もあると思いますが、税理士という資格は確実にあなたの人生を豊かにする「武器」になります。どうかあきらめず、最後まで走り抜いてください。
プロフィール
佐藤 響(さとう ひびき)
北千住税理士事務所代表。
法人税務を中心に複数の税理士事務所を経験後、中小企業のお客様を中心とした北千住税理士事務所を開業。みなし残業がなく従業員が働きやすい環境づくりを心がけています。
1996年 秋田県生まれ
2014年 高崎経済大学入学
2016年 財務諸表論合格
2017年 法人税法合格
2018年 簿記論合格
2020年 青山学院大学大学院入学
2023年 税理士登録・北千住税理士事務所開業
ホームページ:https://www.kitasennjuzeirisi.com/
Youtube:https://www.youtube.com/@kitasennjuzeirisi