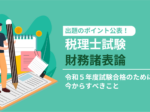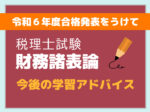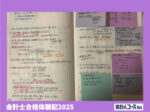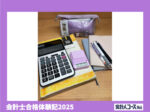ななな(20代後半)
<受験情報>
・学習スタイル:TAC(通信講座)
・受験歴:短答式(令和5年12月)→論文式(令和6年8月)
▶トップ画像は勉強していたデスク(本人提供)
退職後、短答式と論文式に一発合格
私の場合、退職したあとに公認会計士資格が必要と判断し、受験を開始しました。
そのため、現実的な最短ルートで合格することを目標にしていました。
結果的に、2023年2月から勉強を始め、2023年12月の短答式試験に合格、2024年8月の論文式試験に合格しました。それぞれ1回で合格できたので、自分としては理想的な結果でした。
結果としては良かったものの、そこまでの過程で実はいくつかのターニングポイントがありました。
それぞれでの行動次第では結果も大きく異なっていたかもしれないと考えています。
そこで、この合格体験記では、合格までの道のりにおけるターニングポイントについて、そのときにどのように考えて行動していたのかを記そうと思います。
受験生の一助となれば幸いです。
まずは持続的なスケジュールを組む
私が学習を開始した時点で、2024年8月の論文式試験合格を目標とするカリキュラムはすでに開講して数ヶ月が経過していました。
Web上で視聴できる講座数も軽く数十を超えていたと記憶しています。
ここでいきなり講義を受け始めるのではなく、短答式試験までの受講スケジュールを明確にすることからはじめました。
なぜこのように判断したのかというと、公認会計士受験は数年を要することが明らかなため、なるべく集中を切らさずに学習を継続できるようにすることが重要になると考えたためです。
具体的には、①短答対策として最低限受ける講義の数を把握し、②いつ頃までに受講を終えるか期限を設定し、③復習等も加味して1週間に何コマ受講できそうか検討しました。
①〜③をしたことで、大体いつ頃に予備校の校舎での受講日程に追いつけるか、1週間あたりどのくらいの時間を確保すればよいかを見積もることができました。
また、全体のうちどれくらい自分が講義を受講できているのかも常に把握できるようになったので、学習期間を通じて不必要に焦りを感じることなく学習に集中できました。
もし、いきなり受講をはじめていたら、どこかでスタミナが切れて学習が中断してしまっていたかもしれません。
※下記画像は、実際のスケジュールの例です。人付き合い、気分で予定を微調整したくなることも多かったので、変更しやすいように紙ではなくデジタルツールで管理していました。


短答直前期は油断大敵
最低限受講が必要な講義を受け終えたのは9月中旬でした。
そこから12月の本番までは基本的には新しいインプットは少なく、問題演習が中心となります。
その時期に一番怖いのが慢心でした。
気付かぬうちに簡単な問題にばかり手をつけていたり、演習範囲にバイアスが生じることで実力を過信し、本番で足元をすくわれることが心配でした。
そこで、予備校で提供される答練や模試、公開されている過去問を利用して、本番までほぼ毎週短答式試験のシミュレーションをしました。
シミュレーションの結果は、画像のように毎回記録しました。
過去の試験の合格ラインも参考にしつつ、自分が今どれくらいの位置にいるのか把握でき、継続のモチベーションにもなっていました。

短答対策から論文対策への移行における発想の転換
実は受験期間を通じて最も試行錯誤したのが、短答式試験を終えて論文式試験対策に移行する時期でした。
私の場合は、短答式試験の自己採点が論文式試験対策に集中して問題ない水準だったので、短答式試験の翌日から、論文式試験対策のスケジュールを立てはじめました。
論文式試験の対策を考える上で難しかったのが、点数だけでは出来の良し悪しが分かりにくくなると想定される点でした。
どういうことかというと、短答式試験は自己採点が容易で、制限時間内にどれだけの点数を取れたかどうかで、ある程度出来を測ることができます。
しかし、論文式試験の場合は、論述式の問題が登場し、自己採点が比較的難しくなります。
明らかに誤りかどうかは判別できたとしても、どれくらいの点数になるか予想しにくくなると想定されました。
予備校の模試や答練で採点してもらえたとしても、受けてから点数が判明するまでにどうしても時間がかかり、解いたその日のうちにフィードバックを得ることは困難になると考えられました。
実際、手応えと実際の採点結果とにギャップが生じることも少なくありませんでした。
さらに本番は調整後の得点で合否が判定されるので、一層判断が難しくなると考えられました。
そこで、短答対策期から論文対策期にかけて、学習におけるスタンスについての発想を転換しました。具体的には、短答式試験対策は「出来が悪かった(間違えた or 時間がかかった)問題はとにかく出来るようにする」という考え方でしたが、論文式試験対策(特に論述問題)は「典型的な問題で適切にキーワードを用いて答えられるようにする」という考え方に転換しました。
ここでいうキーワードとは、論文対策問題集で用いられているような専門用語や言い回し、条文などのことです。
つまり、点数で出来の良し悪しを判断するのではなく、適切にキーワードを用いて答えることができているかどうかで出来の良し悪しを判断するようにしました。
とはいえ、出来の判断といいつつ、だいぶ感覚的にやっていた面もあります。
あえて言語化するならば、下記のように判断していたと思います。
模試などで得られた自分の肌感覚として、問題集や答練で出題されている典型論点について、Bくらいに達していれば、十分に合格圏内と見立てていました。
| 出来 | イメージ |
| A | 文章レベルで思い出して解答できている |
| B | キーワードをほぼ全て使って解答できている |
| C | キーワードを一部使って解答できている |
| D | キーワードを誤用して解答している |
| E | キーワードが思いつかない、ほぼ白紙 |
結果として、上記を念頭に置きつつ学習を進めるようにしたところ、論述問題で明らかに遅れをとることは次第になくなっていきました。
ちなみに、学習の方法は人それぞれだと思いますが、自分の場合は、①問題を読む→②キーワードを思い浮かべる→③テキスト(あるいは解答例)を読むを繰り返していました。
さいごに
受験期間を振り返ると、学習方法や環境の整備など色々と工夫しながら取り組んできたので、過程を楽しみながら過ごせたことはよかったです。
もちろんプレッシャーや不安、迷いを感じることもありましたが、良くも悪くも自分の頑張り次第で結果が変わる試験と捉えていたので、割り切ることができていたと思います。
この体験記が受験生の方に少しでも役に立つものであれば嬉しいです。ここまで読んでいただきありがとうございました。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧