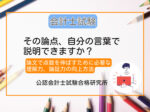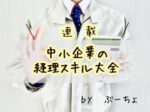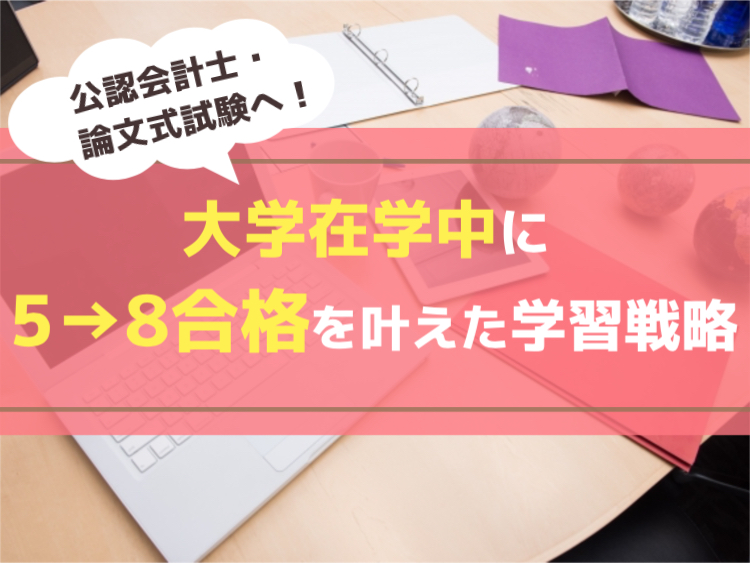
かん(中央大学4年)
【編集部より】
公認会計士試験では5月短答式試験が終わり、合格発表を来月に控える中、8月論文式試験に向けて一息つくまもなく論文対策をスタートさせています。いわゆる「5→8合格」(5月短答・8月論文に合格)を目指し、ここからの3ヵ月を1日も無駄にすることなく過ごせるかが結果につながるという厳しい戦い…。
そこで今回は、昨年の公認会計士試験で5→8合格を達成した在学中合格者のかんさんに、5月短答後の取り組みにフォーカスを当てて教えていただきました! 学生受験生はもちろん、論文式を受験予定の方にとって、学習戦略のヒントが満載です。
▶︎かんさんの合格体験記「5月まで短答式の学習に特化して8月の論文式をクリアするには?」
5月短答の手ごたえと自己採点結果
私は、2023年公認会計士試験において、5月短答式→8月論文式試験に合格しました。短答式受験後の手ごたえとしては、「多分いけたかなぁ」という感じでした。
正直、ここまで勉強したのに受かっていなかったらこれ以上は続けられないと思いました。ただ、自己採点が本当に嫌いだったので、試験当日ではなく、次の日に行いました。
<23年5月短答式試験の自己採点結果>
・企業法 :90点
・管理会計:54点
・監査論 :70点
・財務会計:152点
得意科目であった監査論で点数が伸びなかったので若干焦りましたが、この時のボーダー予想が69〜70%であったため、「合格しているな」と思いました。
自己採点結果を踏まえて、タブレットを活用した学習へシフト!
もともと、できれば5→8合格を目指したいと考えていたため、短答式試験の次の日から論文式試験の学習を始めました。
その時に大きく変えた勉強方法があります。それは、プリントからタブレットへのツール変更です。
というのも、短答式試験までは、パソコンとプリント(紙媒体)を使用して学習していました。そこから論文式試験まで3ヵ月もなかったのですが、思い切ってタブレットを購入し、パソコンとタブレットで学習することにしました。
タブレットを導入したことによって学習効率が飛躍的に上がったと感じています。12月短答や過年度の短答合格者が、私が短答式の学習を行っている間に受けていた模試の問題や、その他のプリントをいちいち印刷する時間がなくなり、その分学習時間を増やすことができました。
また、紙媒体のプリントは管理にも手間がかかりますが、タブレットでは自分の欲しいプリントをすぐに見つけ出すことができるのでとても便利でした。新しいものを使用して学習することはワクワクして、学習意欲も上がったのかなと感じています。
ちなみにですが、タブレット端末は公認会計士試験合格後にも会計士になるための修了考査という試験の学習や、語学の学習などにも使用しており、今でもとても役に立っています!
合格発表までの謎のプレッシャー
合格発表に近づくにつれて、謎のプレッシャーがありました。友人や中央大学経理研究所のスタッフからは、「絶対合格しているから大丈夫だ」と言われていたのですが、「マークミスをしているのではないか」、「名前や受験番号を書き忘れたのではないか」という不安がだんだん募っていきました。
論文式試験の学習を始めているのにも関わらず、「ここで落ちてしまったらどうしよう」と思っていました。皆から期待されているからこそプレッシャーを感じていました。
5月短答から1ヵ月後、ようやく合格発表があり、結果を見て一安心することができました。心置きなく論文式の学習に取り組めるようになりました。
8月論文式に向けて、頻出論点を徹底的に押さえる!
私は、それまで全く8月論文の学習をしておらず、5月短答が終了した後から論文式試験の学習を始めました。そこで、論文式の学習では、「他の受験生が確実に押さえてくる論点」に重点を置きました。なぜなら、論文式では偏差値で合否が決まるため、みんなができるところを押さえれば合格できると考えたからです。
5月から8月までの3ヵ月という短期間で合格するためには、マイナーな論点を学習する余裕はありません。頻出論点を徹底的に押さえるようにしました。
目標とする偏差値としては、以下のように考えていました。
<論文式の目標偏差値>
・会計学 60
・その他の教科 47
短答式でもそうですが、会計学は得点の比重が非常に大きいため、この科目で点数を伸ばそうと考えました。新しく学習する経営学と租税法は足切りを防ぐために、得点が容易であると考えられる計算に重きを置いて学習しました。
6月中旬までにはインプット学習を終え、後の期間はすべてアウトプットに専念しました。インプット期間中も会計学の計算は毎日学習していました。
<論文式試験までの1日の時間割>
7:00〜9:30 企業法
9:30〜11:00 経営学(計算)
11:00〜12:30 経営学(理論)
▶昼食をとりながら勉強
12:30〜15:00 租税法
15:00〜17:00 管理会計(計算)
17:00〜17:30 管理会計(理論)
17:30〜18:00 監査論
▶夕食などで少し休憩
19:00〜20:00 財務会計(理論)
20:00〜23:00 財務会計(計算)
私は暗記科目が好きだったので、朝一番は企業法の学習を行い、やる気を出していました。好きな科目から学習を始めると良い1日のスタートが切れると思います。
また、論文式試験の山あてをいろいろな予備校講師がSNSなどで公表してくれています。その情報を自分で集計して、出題されそうなところだけを学習していました。
最後に〜将来の自分が後悔しないために、今すべきこと
短答式試験が終了したのにも関わらず、奇跡とも言われている5→8合格を目指すために、まだあと3ヵ月も学習を継続することは精神的にも体力的にも厳しいと思います。今でも思い出すと苦しくて辛い期間だったなと思います。
周りにも5→8合格を目指す人が少なく、孤独を感じ、成績も思ったようにあがらず、不安になることもありました。ですが、ここで5→8合格を逃したら、あと1年以上も学習を続けなければなりません。逆に、合格できたら3ヵ月で終わります。
「学生としての貴重な3ヵ月を可能性の低いものにかけていいのか」、「学生だからこそ、遊びを優先すべきかどうか」など、悩むかもしれません。何を優先すべきかについては、人それぞれだと思います。
ただ、私は今、とても楽しいです。あの時頑張ってよかったと本当に思います。私は常に「後悔」について意識していました。将来の自分が後悔しないために今、自分がすべき行動を考えていました。「あの時こうしていれば…」と思うことがないように将来の自分が今の自分に納得できる行動をしていました。
奇跡と言われる5→8合格ですが、誰でも努力すれば実現できます。後悔のない選択をしてほしいです。
この記事が受験生の皆さんに少しでも役に立てたら幸いです。
<執筆者紹介>
かん
中央大学4年。大学3年生の2023年に、公認会計士試験(5月短答式・8月論文式)に合格。
大学に入学してから簿記の学習を始め、1年生の時に簿記3級と2級を取得、2年生の夏頃まで学習をサボってしまったものの、夏から簿記1級の学習スタート。2年生の11月下旬頃から中央大学経理研究所で公認会計士短答式試験の学習を開始。
<こちらもオススメ>