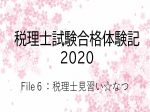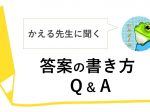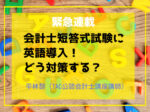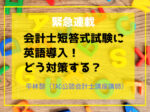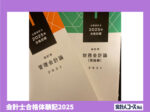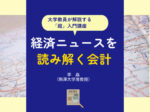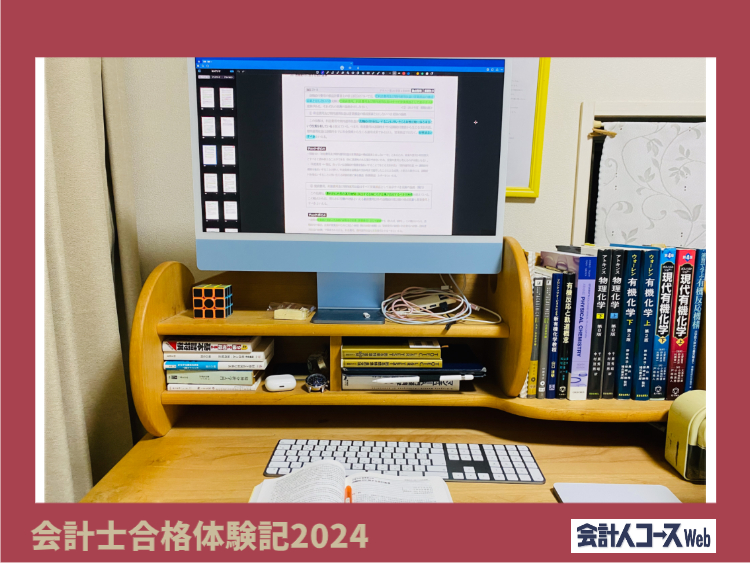
服部海斗
(24歳、東京工業大学大学院)
〈受験情報〉
学習スタイル:通信、CPA会計学院
▶トップ画像は服部さんの学習スペース(本人提供)
東工大という理系からの転身
大学院に進学するも、意欲を失う
令和5年の3月、学士課程修了後そのまま大学院に進学する予定でしたが、1年間研究室での生活に忙殺されたことで意欲を失っていました。
そもそも実験があまり好きではないうえ、週6日で10時間のコアタイムにあと2年耐える自信がありませんでした。
しかしながら、就活を始めてすらいなかったため、ここから就活を始めたとしてもなぜ1年就活の開始が遅れたのか鋭く追及されるでしょうし、それにうまく答えられる気もせず、八方塞がりのような感覚を抱いていたのを覚えています。
一緒に起業しないか、という誘い
そんな折、高校の同級生から「一緒に起業をしないか」という提案を受けたことが転換点となりました。
大人数の組織でうまくやっていける自信もなかったため、気の知れた友人と一緒に1から事業をつくりあげるということを想像すると、久しく感じていなかった高揚を覚えました。
大学院を休学し、起業に役立ちそうな情報収集で簿記に出会う
しかし、私は長らく理系分野の学習に専念していたため、企業やその経営について知っていることがほとんどありませんでした。
そこで、大学院を休学し専門外の分野について広く学習しながら、起業に役立ちそうな情報収集を始めてみようと考えました。
これが後々会計士試験の受験のきっかけとなります。
まずは、手当たり次第に気になったタイトルの本を読み漁るところからスタートしたのですが、そのなかで一際魅力的だったのが、國貞克則著『財務3表一体理解法』(朝日新書)でした。
財務3表の読み方に重点を置きながら、複式簿記の概要を簡単に学ぶことができるという新書の優れている要素がふんだんに盛り込まれた本でした。
これをきっかけに簿記の学習を始めることを決め、無料で講義とテキストを使用できるCPAラーニングをアルバイトの合間に見る生活を送っていました。
CPAラーニングの商業戦略にハマり、会計士試験受験を決める
2ヶ月ほど経つと簿記1級の内容まで一通り見終わってしまい、簿記検定を受けるにしても1年という休学期間でまだまだ学べることがあるのではないかと考えるようになりました。
このとき、CPAラーニングの講義中に言及されていた会計士試験の存在を思い出しました。
まんまと商業戦略にハマったわけです。
簿記の計算分野に関しては得意意識すらありましたし、会計士試験の受験科目のうち企業法と経営学については起業にあたって役に立ちそうな分野であったため、受験を機会にそれらすべてを習得するというプランが眼前に浮かび上がってきました。
加えて、会計士のいる業界は人材の流動性が高く、もし起業に失敗したとしても監査法人に戻るなり、一般事業会社の経理で働くなり、その後のキャリアを狭めることがないという意味でもその資格を得ることに妥当性がありました。
以上のような背景が私が公認会計士試験を受けるに至ったきっかけとなります。
具体的な学習方法や学習計画
会計士試験にかかわらず、基本まずおおよその全体像を掴んでから、内部の詳細についてその全体像に対する位置付けを意識しながら情報を整理していくというのが私の好む学習スタイルです。
そのため、CPAでの学習も、演習や答練などは後回しで、とりあえずテキストと講義を一周してしまい、あとから一気に演習するというスタイルを選びました。
ただ、試験範囲は膨大ですし、講義の中で全体像や扱っている内容の位置付けについて頻繁に解説を入れているため、受講後に考えてみると予備校の指示通りの順番で学習を進める方が効率的かもしれません。
学習計画
予備校に入る判断が遅れたこともあり、一通り講義を受け終わるともう直前期であるようなスケジュールであったため、学習計画については直前期のみ立てていました。
意識していたこととしては、毎日の学習量に科目間でばらつきが大きくなりすぎないようにすることでした。
カレンダーアプリで1日を通した科目ごとの学習時間の予定を入れておき、学習を終えるごとに実績を入力しながら、学習量のバランスを調整していました。
短答対策
特に短答の直前期は、計算科目の学習時間が膨らみすぎないように注意していました。
また、短答直前期の学習方法として答練を中心とした学習は、特に対策時間が足りていない受験生にとって効率的な得点アップが狙えるものではないかと思います。
特に直前答練の解答冊子には、単元別に重要度が記載されており、その重要度が高い順に受験済の答練を全て切り分け、単元ごとに整理しその単元において理解不足がある論点や、どのような問われ方をするのかなど、テキストの読み直しと並行して答練の内容を整理する時間は学びが多かったように思います。
論文対策
論文式については、必要な学習量がかなり多いと思われるため、ほとんどの受験生が十分に対策できていないように思われます。
とくに私は5月短答合格後の受験でしたが、論証暗記はほとんどできていないまま試験に臨むことになりました。
ただ、今回の論文式についてはそこまで徹底されていなかったものの、単純な論証暗記に走るとほとんど得点できないような出題が増えてきているようでした。
私自身、論証暗記は早々に諦め、それぞれの論点についての論証の内容をざっくりイメージできるようにすることに注力していたので、もしかしたら多少有利に働いた部分があるのかもしれません。一言一句再現できるようにするトレーニングよりも、前提や論調、比較される他の考え方をイメージして整理していく作業の方が精神的負荷は小さいので、継続性もありました。
モチベーションの保ち方やマイルール等
正直なところ、私にはそこまで会計士自体にこだわる大きな理由がなかったため、学習モチベーションには波がありました。
とくに1〜3月という5月短答を見据えれば非常に大事な時期に、ほとんど学習時間を取れていませんでした。
そこで友人に相談し、ビデオ通話で起床後から就寝直前まで監視してもらうというルールを作りました。
知っている人に見張られていると自然とさぼっている姿を見せることに抵抗を感じるようになり、学習から離れる時間を極端に減らすことに成功しました。
特にビデオ通話のカメラとしてスマホを使用することによって、ビデオ通話中にスマホを使用すると画角が代わり友人にばれてしまうことになり、スマホの使用時間も大きく減らすことができました。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧