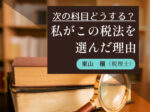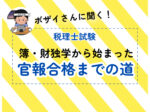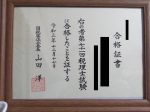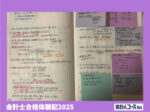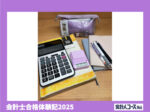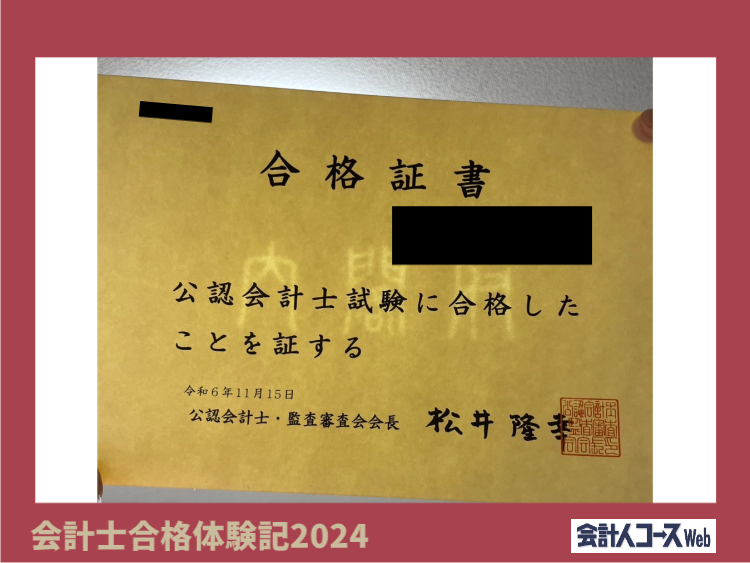
ティー
(30代)
〈受験情報〉
学習スタイル:CPA会計学院(通信)
▶トップ画像はティーさんの合格証書
働く中で会計士への憧れを募らせる
私は複数のきっかけや理由が積み重なり、会計士を目指しました。
根底に、働きながら毎夜仕事の勉強をする両親の姿から、継続して学び続ける姿勢を得ており、そこから職人気質が芽生えていたと思います。
また高校生で3年程スーパーのレジアルバイトを経験し、「お金を扱う仕事ってどの企業でもあるし、応用の利く具体的な専門性のある仕事として極められるのでは?」と会計士に興味をもちました。
その頃、家庭環境が大きく変わる機会があり、将来どう生きていくかを考えました。
「働きながらでも大学等に通って、会計関係の資格に長期的に挑戦し、職を極めて仕事をし、しっかり稼いで家族を守りたい」という気持ちが徐々に明確になりました。
その時は、日商簿記等に挑戦しだした程度ですが、「どうせやるなら会計関係の資格の中で最難関といわれる会計士までやろう」と漠然と目標にしていました。
できるだけ会計関係の実務経験を積めるように実務や転職等を進める中で、会計士や税理士の方と協働する機会があり、誠実に仕事をしている姿勢を見て、かっこよさや憧れを強く感じ、こんな風に働きたいと思い、はっきりと目指すようになりました。
妻の許可を得て挑戦期間を決めて受験に専念
働きながら会計・簿記の勉強をする中で、結婚して子供が生まれ、自身の能力では家庭と挑戦との両立が困難であると強く感じるようになりました。
この頃、日商簿記1級・全経簿記上級・公認会計士試験短答を受験することはしていましたが、ボーダーに少し及ばないところで足踏みしており、まだまだ地道に学習経験を積む経験が必要でした。
私の気持ちは、「自分自身にいつまでも夢見てられないし、けじめをつけたい。家族を優先したから、夢を諦めたと子供に思われたくないし、そんな姿見せたくない」といったところでした。
妻と年齢や転職可能性等を考慮して話し合いました。
かなり悩みましたが、妻からの「今まで努力が報われてほしい」と後押しをもらい、2022年の夏に仕事を辞め、挑戦期間を区切り、試験に専念することとしました。
「ろくに大学も出ていない私をよく信じてくれたな」と今となっては感謝の気持ちでいっぱいです。
学習方法1(短答式試験合格までの学習時間4,248時間)
勉強の経験値の浅さから、最もやってはいけない勉強方法で勉強を進める
2018年目標CPA会計学院で学習をスタートしました。
当初は仕事の疲れ、自分自身の甘さにより、平日帰宅してから3時間の講義を見るだけでヘロヘロになっていました。
しばらく続けると、勉強する気がなくなり、1か月何もしないなど大変不真面目な学習態度でした。
今となって思うのは、本気で受験勉強をした経験がなかったので、こうなるのは必然だったということです。
自分の能力をまったく把握できておらず、無茶な勉強を繰り返していました。
当時、社会人としてフルタイムで勤務していたので、平日3時間、休日は10時間、残りの時間は家族と過ごす時間や家事としていました。
週35時間という枠をまず作りはしましたが、授業を見るので精いっぱいです。
ろくに復習や例題の反復をせず、どんどん進めていきました。
予備校のガイダンス等で声高々に叫ばれていますが、俗にいう「最もやってはならない勉強方法」です。
このような感じで、学習に本腰が入る2022年夏まで月0~100時間程度の学習をしていました。
教材を手当たり次第に回転学習するパワー型で勉強
講義を一通り見終わった頃、学習に対する意識が変わってきました。
復習の重要性、暗記力は鍛えれば身につくといったレベルです。
ようやく自分は1時間でどれだけの問題に取り掛かることができて、何をしたらどれだけ覚えられるのかを意識しだし、論点重要度もお構いなしに教材を手当たり次第に回転学習して、2022年5月のお試し短答60%を超えたあたりの実力でした。
私にとっての回転とは、とにかく回数をこなすといパワー型の勉強スタイルでした。
非常に身に付きにくく、非効率でしたが、一日8時間以上の長時間勉強する素地ができたと考えています。
勉強時間の長さから、とんでもない「肩こり」に
2022年12月短答を本命にして、本試験3ヵ月前から専念し、1日13時間以上、とにかく経験値の足りない自分は、量をこなすしかないと意気込んでいましたが、とんでもない「肩こり」に襲われました。
30年以上生きていて初めての経験で、寝転んでWEB問題集を解く等、体に負担のかからない工夫が必要でした。
直前期でしたので、CPAの直前答練をペースメーカーに、2週間区切りでやるべきことを書き出し、重要度AB論点と手間のかからないC論点を1回転ないし2回転していました。
監査論と管理会計の計算が勉強時間に対して、得点力が伸びず苦戦します。
そのため他の科目の勉強時間を削って強化する等の調整をしていました。
成績もほぼC判定以下で、合格可能性は五分五分でした。
焦る心がいっぱいだったのを覚えています。
そのためCPAのとある講師の方が配信されているラスト1か月からの大逆転動画を定期的に視聴して「なんとかなる!」と前を向いていました。
本試験は問題の相性がとてもよく、またマーク式のため運にも恵まれ、予備校の予想ボーダー丁度の自己採点でした。当然1か月間の結果待機期間が辛く、ろくに勉強が手につかないという愚行を犯しています。本当にメンタルが試される試験だと感じます。
また暗記や理解も手探り粗削りで、計算は問題集をとにかくやりまくる!など、本質的な事が出来ていなかったため、ボーダーを大きく超えるようなブレイクができなかったと感じています。
それでも合格できた決め手は、メンタルを保ち、答練結果から判明した弱点等のやるべきことを事前に書き出して、勉強時間中は目の前の問題に集中することだと思います。
学習方法2(論文式試験合格までの5,406時間 短答式と合わせて9,654時間)
経営学に苦戦
ギリギリ短答式に合格したものの、ボーダー勢として不安に押しつぶされ、出遅れていました。
論文式で新たに増えた租税法と経営学の基礎的な講義を慌てて受けましたが、SNSでデザート(?)科目と噂の経営学がかなり難しく、苦戦します。
大学受験を経て、数学等の素養がある人にとっては稼ぎどころなのでしょうが、そうでない自分には非常に厳しい科目となりました。
この後1度論文式試験に落ちますが、明らかに経営学に対応できていませんでした。
勉強仲間を作り、自分の甘さを思い知る
短答式の勉強の延長線上で1度目の論文を迎える中で、初めて勉強仲間ができました。
そこで自分の勉強がいかに論文式試験に対応できてないか思い知ります。
論文模試の打ち上げで知り合った人たちの勉強の質が、自分の暗記や計算演習の質をはるかに凌駕しており、いかに自分が甘い勉強をしていたか思い知ったからです。
これが転機となり、成績がいい勉強仲間を増やしていった結果、自分に足りないものがどんどん見えてきました。
しかし1度目の受験では気づいたときには手遅れ状態で、不合格となりました。
1回目の不合格の理由
最も大きな不合格の決め手は、暗記と理解の精度です。
論証1つひとつを徹底的にやれていない。
自分の中で、「どこかこのくらいかければいいだろう」「こんな表現でもいいだろう」という甘えがありました。
それが各問素点1点の差となり全体で大きな差になっていました。
また計算も演習不足であり、身につかない暗記に時間を割きすぎていました。
合格の決め手
二度目の受験では気づきを反映させた勉強で、総合偏差値を10近く上昇させ総合偏差値56付近で合格しました。
合格の決め手は、暗記の記述精度を「できる人」と同じ速度、反射レベルでやるという目標を立てて、答練をペースメーカーにして目標達成を積み重ねること。
そして、計算フローも含めて、「できる人」に説明して伝えられるようになることでした。
相対試験であることを初めて意識できたと思います。
具体的には、不合格となった11月下旬以降、合格者のやり方をマネすることから始めました。
財務理論であれば、次のCPA上級答練までの期間で、出題予定分野の暗記を1日目1~10P、二日目1~20P、三日目1~30Pのように前日の学習範囲もやる。そして完全暗唱できるか厳しく確認する。
とても脳みそにストレスがかかり苦しかったです。
しかし所要時間で見れば過去のやり方より効率的で、いかに自分が楽な勉強をしていたかと反省し、愚直に続けました。
そして計算問題については、基礎的な計算フローとなぜこの計算方式なのかを説明できるか確認し、テキストの例題・網羅性のある問題集と答練を、時間を図って解き続けました。身の回りの「できる人」からの指摘では、圧倒的な演習不足だったのです。
演習不足解決のために、時間割を作る
これらの解決は一筋縄ではいきませんでした。
無計画に学習するとある科目を1か月やってない!みたいな事態に陥るタイプでしたので、紆余曲折しながら、4月頃からは朝一番に管理会計2時間、次に監査論・企業法を1時間ずつ。
昼あたりで租税法・経営学。
以後財務会計と完全に時間割を作りました。
管理会計は朝一番にやらないと一生やらないので定位置としました。
また周囲と比べて、勉強時間に対して企業法と監査論の出来がいい傾向も見えていました。
このため、本試験と同じ午前中に1時間ずつ徐々に暗記を詰めていき得点源とする。
租税法と経営学は答練の出来に応じて勉強時間は流動的でしたが、大体2時間ずつで計算と理論を詰めていく。
租税は稼げそうな感触でしたが、経営学計算が本当にダメで、1度講師相談した後、理論で稼いで計算は守るスタンスで直前期を過ごしました。これらをこなした後、残りは会計学です。
必ず総合問題1問・個別論点で2時間・そして財務理論1時間のバランスを基本としました。
本試験当日まで、納得して暗記が詰まったなと感じたのは監査論くらいで、あとは忘却とメンテナンスの程度が納得できるレベルには到底達していませんでした。
受験期間を通して、答練の成績はA~Eまで満遍なく取り、模試は第一回A判定→第二回C判定という結果で、時間がとにかく足りない!今の自分の最善では、何かの科目の忘却速度が上回るといった状態でした。
特に、第二回模試の頃は、財務理論では論証は出てくるが、問いに対してどの論証を使えばいいのか分からないという本末転倒な事態に陥り、7月の半ばからは管理計算のいくつかの分野と租税法理論と経営学計算を犠牲にして補強しました。
結局、財務理論以外は思い通りの成績を残すことになります。
自分自身の甘さの認識からすべてが始まる
つまるところ、受験という経験のない私には、勉強できる人と付き合い自分自身の甘さを自覚する。
これが合格への最も大きな要素でした。
答練で高偏差値を取れる人はどんな意識で暗記をし、計算演習はどのレベルでやっているのか。
それをやりきった理想の自分とのギャップがそのまま行動指針となってくれました。
気づけばあとはそのギャップを解消するための行動を1つ1つ考え実行していき、詰まればCPAの講師陣に相談して解決していきました。
講師との相談については、企業法と監査論を自己評価するにつかみどころがないように感じ、毎月1回答練の解答を講師に送って、課題の洗出しをしてもらっていました。
次の相談までにいかに指摘事項を詰められるかを行動指針とすることで、やるべきことが明確になり合格の大きな要素となったと感じます。
また体力がとても落ちていたので、一日20分でもランニングすべきだったようにも思います。体がしんどく、寝たまま論証暗記などしていました。
子育てしながらの受験について
妻は私の挑戦を理解して応援してくれていたとしても、8歳と2歳の子供にとっては当然よくわからないことでした。
「一緒に遊びたい。公園に連れて行ってほしい。宿題のわからないところも教えてほしい。友達付き合いの話もしたい。やりたいことが上手にできないので、なんとかしたい」などの子供の気持ちに応えられるのは自分しかおらず、遊びはしっかりと事前計画を立てて時間を作りました。
最後の直前期1ヵ月ほどは遊びに出かけるのは土日に1時間だけにして、一緒に宿題や100マス計算などを一緒にしていました。
また本試験当日には朝早く出かける私を呼び止めて手作りの合格チケットを渡してくれるなど、心から応援してくれました。
後から私は「セルフ育休」と勝手に呼んでいますが、子供の成長を間近に見て生きる喜びを感じ、とてもいい経験になったと思います。
本当に合格できてよかった。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧