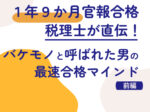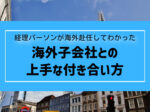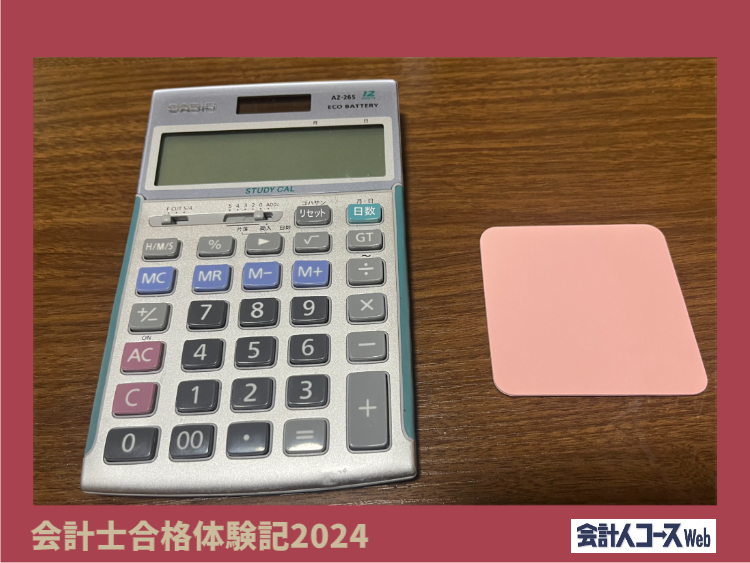
M.T(20代)
〈受験情報〉
受験スタイル:
受験情報:令和4年5月短答⇒令和6年8月論文
▶トップ画像は愛用の電卓と付箋(本人提供)
はじめに
私は、短答式試験2回目、論文式試験3回目で合格しました。
そのため、今回は会計士論文式試験に2回落ちた中で反省すべき点と、3回目の論文式試験に向けて行った勉強方法を中心に執筆いたします。
自分の経験が、何か皆様の参考になれば幸いです。
合格までのモチベーション
会計士試験は、基本的に長期間勉強する必要があるため、モチベーションの維持が重要です。
私は、合格体験記を読んだり、現職の会計士の方々に、実際の業務内容や体験談、監査法人の福利厚生、仕事だけでなくプライベートの充実具合などを詳しく聞き、自分が合格した後のことを具体的に考えることでモチベーションを維持していました。
また、勉強仲間を作りお互いに監視しあうことで、やる気が出ないときも勉強する環境を作っていました。
論文式試験に2回落ちた反省点
私が論文式試験に2回落ちてしまった反省点は、たった1つです。
それは勉強量の不足です。
よく量より質といいますが、大前提として量が足りなければ受からない試験だと思います。
5月の短答式試験後、すっかり燃え尽きたのか勉強量がかなり減ってしまいました。
たとえ、論文式試験合格は無理と見通していても、計算力維持のための勉強をすることが必要だったと思いました。また、論文式試験が終わってから頑張ればいいという甘い考えを捨て、自分の引き延ばし癖を直視すべきだったと反省しています。
今、その時の自分に言うなら、「未来の自分に期待するな」でしょう。引き延ばし癖が、論文試験後に急に直せるはずがありません。
実際、論文終了後もほとんど勉強せず、12月から本格的に勉強を再開しました。落ちた計算力を元に戻すところから始め、この時期の勉強不足が2回目の論文式試験不合格の最大の原因です。
論文式試験3回目に向けて
論文式試験3回目に挑むにあたり、勉強量はもちろん、勉強中特に意識した点が3つあります。
朝一に苦手教科を集中的にする
早朝、まだ疲れてない時間帯に自分の苦手教科である管理会計の計算を勉強する習慣をつけるようにしました。
そして、苦手教科に関しては他の教科と違い、「この範囲を終わらせたら休憩!」と範囲で区切るのではなく、「朝アルバイトに行くまでの1時間する!」と時間で区切ることで、メリハリがつき、苦手な教科でも集中して取り組むことができました。
そして、朝やり残した部分をあえて残すことで、アルバイトの空き時間や終了後に苦手教科に手を付けざるを得ない状況を作っていました。
間違えた箇所にチェックを入れるだけでなく、なぜ間違えたのかを徹底して追及する
具体的には、大きめの付箋を使い、どうして間違えたのかを書き、問題演習の表紙に貼ったり、ルーズリーフにまとめたりしていました。
そうすることで、自分がいつも引っかかるところや解き方が曖昧な箇所などが明確になり、計算の正確性、解き方の網羅性が強化されました。
自分を信じない
自習室で集中が途切れた時、残ったものは家でしようと思い、帰るときが多々ありました。しかし、自分は意思が弱く、また家は人目がなく娯楽にあふれていたため、結局ほとんど集中できないことが多かったです。
そのため、勉強は家の外ですること、スマホは自習室のロッカー入れるなど、娯楽に夢中にならないように徹底していました。
おわりに
会計士試験に合格するには長い勉強期間が必要です。
そのため、勉強を始めても、短答式試験を受ける前に勉強をやめてしまう人もいます。
しかし、自分の頑張り次第では、大学在学中にでも取れる資格で、公認会計士ほど将来に直結し、生涯にわたって活躍の幅が広い資格はないと思っています。 人によって様々な事情はあれど、ぜひ、最後まであきらめず挑戦し続けてほしいです。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧