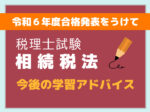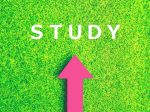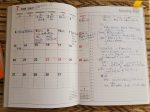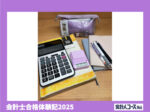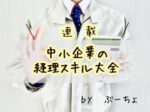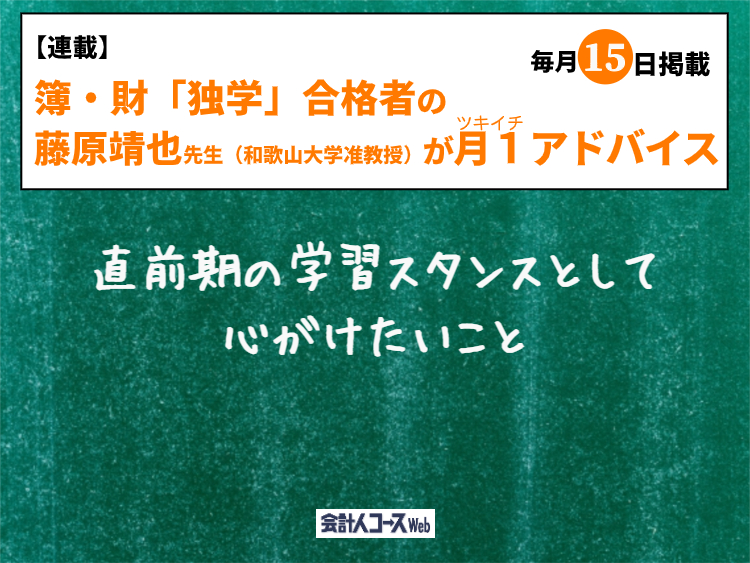
藤原靖也(和歌山大学経済学部准教授)
【編集部より】
会計人コースWebの読者アンケート結果によると、税理士試験簿記論・財務諸表論受験生には「独学」の人が一定数おり、その多くが情報の少なさから、勉強方法に対する不安を持っているようです。
そこで、本連載では、独学で税理士試験簿記論・財務諸表論、公認会計士試験に合格したご経験があり、現在は大学教員として研究・教育の世界に身を置かれる藤原靖也先生(和歌山大学准教授)に、毎月、その時々に合わせた学習アドバイスをしていただきます(毎月15日・全11回掲載予定)。
ぜひ本連載をペースメーカーに本試験に向けて正しい勉強法を続けていきましょう!
本試験まであと2か月弱というタイミングになりました。出題予想も、予想問題集も出ている今、試験への対応力を付ける時期だという意識が強くなってきていることと思います。
今回は、そんな時期だからこそのアドバイスになります。
<今月のポイント>
・取捨選択・時間配分は容易にはできない。知識の精度が相当程度まで上がり、会計学的な思考ができるようになった時にできるようになる。
・直前期は、闇雲に問題を解く時期ではない。インプット・アウトプットの繰り返しによって、「合格のために必要な力を上げる時期だ」という意識をもとう。
・本試験までに何をすべきかを見据え、良好なサイクルを回し学習することが何より大事。
知識は、完璧に定着していますか?
簿・財の本試験問題は容易に正答へと辿り着かせてくれません。
「取捨選択・時間配分が大事」、「A論点を見抜き、取り切る」。簿・財合格のためにはその通りなのですが、これらも簡単にはさせてくれません。
理由は明確です。分量が多く時間制限が非常に厳しい中で、思考力・判断力を問うてくるからです。
とりわけ本試験形式のアウトプットが上手くできないと悩んでいる場合、いったん問題演習の手を止め、こう自分に問いかけてみて下さい。
「今まで使ってきた教材の内容が、知識として完璧に定着しているか?」
きっと、ドキッとする方も多いのではないでしょうか。
問題を用いて「知識定着のサイクル」を回し実力を上げる
取捨選択も時間配分も、A論点を見抜き得点につなげるにしても、十分な思考力・判断力が伴っているからできることです。
そして、思考力・判断力の源泉は他でもない「知識」です。
もちろん知識さえあれば十分な思考力が身につくわけではなく、場数を踏み解答感覚を掴むことも重要です。しかし、会計学的な思考・判断をする際には精度の高い会計学の知識が絶対に必要です。
もっと言えば、直前期だからといって闇雲に問題を解くことは必ずしも得策ではありません。
それよりも、「うまく問題が解けない」と思ったときは、今まで皆さんが使ってきたテキストの内容を見返して下さい。きっと、忘れていたり曖昧なままだったりする箇所があるはずです。
それらを「覚え、忘れ、そのことをアウトプットで自覚し、覚え直す」という知識定着のサイクルを粘り強く繰り返しましょう。一連のサイクルの中で、思考力も、問題の質や解答時間の目安などに関する判断力も自然と上がっていくはずです。
その繰り返しの結果、十分に取捨選択や時間配分ができるようになっているはずです。
知識は抜けていくものだ、という気持ちで冷静に進めましょう。躓いたときはもう一度テキストに戻り、しっかりと定着させましょう。
本試験までに何をすべきかを明確にし、自分と向き合えるようにしよう
また、どうしてもこの時期は些細なことでも焦りや不安を感じがちです。ただ、これは当たり前のことです。
その中で最も重要なことは、本試験までに何をするのかを冷静に分析し、実行することに尽きます。
自分が今、重点的にすべきは知識そのものの習得なのか、知識を活用した思考力の涵養なのか。または、取捨選択や時間配分の実践なのか別のことなのか。
冷静に分析・実行できれば、一番の敵だと前回指摘した焦りや不安とも真正面から向き合うことができるようになるはずです。
簿・財の本試験では何がどういう形で出題されるかはわかりません。
とくに簿・財の第三問では分量や問題の質が高い箇所・低い箇所は毎回のように変わります。商品売買関連の会計処理が容易で固定資産に係る会計処理が煩雑・難解な回もあれば、逆の場合もあります。
直前期は、どんな問題が出ようとも取捨選択・時間配分が的確かつ冷静にできるようにする時期です。そのためには、弱点を埋めつつアウトプットを行う経験をどれだけ積めたかが何よりも重要です。
往々にして得点は急に上がるものです。知識の水準を上げ、簿・財独特の問題形式にも慣れるサイクルを繰り返すことによって本試験問題に対応できるようになっていきましょう。
最後に
この時期は些細なことに感情が揺さぶられることも、きっと多くなると思います。例えば、予想問題集を解いても箸にも棒にも掛からないと憂慮してしまうかもしれません。
ただ、その原因を突き止めずに些末な論点や安易なテクニック論に走るのではなく、インプットーアウトプットの繰り返しにより知識を定着させ得点力を上げる、という王道の学習のままで進みましょう。
そもそも1つのトピックを完璧だと言えるレベルにまで定着させるのは、非常に難しいことです。その精度を上げる練習をしましょう。
苦しい時期ですが、冷静に問題と向き合い、内容を吟味し、解答順序や解答時間を決め、落ち着いて点数を重ねることができるようになるために現在の学習やそのための教材がある、という意識を忘れないようにして下さい。
〈執筆者紹介〉
藤原 靖也(ふじわら・のぶや)
和歌山大学経済学部准教授、博士(経営学)
日商簿記検定試験1級、税理士試験簿記論・財務諸表論、公認会計士試験論文式試験に合格。神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了後、尾道市立大学経済情報学部講師を経て現職。教育・研究活動を行いつつ、受験経験を活かした資格取得に関する指導にも力を入れている。
<本連載バックナンバー>
第1回(9月掲載):会計の学習は‟積み上げ式”を意識しよう!
第2回(10月掲載):何をどこまで学習すればよいか、「到達目標」を確認しよう!
第3回(11月掲載):基礎期の「間違った箇所」は、絶対に見逃さないように!
第4回(12月掲載):モチベーションを維持するために心掛けてほしいこと
第5回(1月掲載):過去問を有効活用し、合格に向けて着実に進もう!
第6回(2月掲載):長い問題文の中で「どこがA論点なのか」を見抜く力を養おう
第7回(3月掲載):「どの問題に、どれくらい時間配分するか」判断力を養おう
第8回(4月掲載):自分なりの解答アプローチを身に付けるために試行錯誤しよう!
第9回(5月掲載):本試験に対する「不安」とうまく向き合うには
第10回(6月掲載):直前期の学習スタンスとして心がけたいこと
第11回(7月掲載):「今は自信をつける時期」という意識で学習を続けよう!