
藤井太郎
【前回まで】
第1話「所得税と筑前煮」
野球にまつわる古い2枚の写真である。
1枚目は始球式の光景。投げているのは昭和35年当時の祖父。そのとき四日市税務署長をしていた。「うちのジイさんすげぇな」と思った。退官後は税理士事務所を開業し、父を職員として迎え、僕が生まれた。

2枚目は中学の卒業アルバムに収められた試合の光景。僕が所属するチームは、負ければ引退という夏の地区大会で、一度も勝ったことのない相手に劇的な逆転勝利を収めた。その原体験をもとに学生時代に書いたのが『サンシャイン』という小説である。

学生時代の就職活動
新聞記者が夢だった。東京の武蔵境。大学4年間は学生新聞の編集にのめり込んだ。でも夢を叶えるための計画や戦略は絶望的に欠如していた。就職活動によって、自分がなにひとつスキルを身につけていないという現実を突きつけられた。
僕には就職活動の記憶があまりない。「どうしてそんなに余裕なの? 焦んないの?」周囲は僕をいぶかる。当時の僕は「働くということは、自分がやりたいことを叶える手段」だと思っていた。だから合同説明会やOB訪問で無理やり興味を掘り起こそうとする友人たちを見て謎だらけだった。
とはいえ、反省はしていた。人生を豊かにするには、自分に足りないものと真剣に向き合う必要がある。コツコツ努力を続ける力。達成するまでやり遂げる力。社会で生きていく力。それらを鍛えてくれるものが身近にないものか……見上げた空に映ったのは、始球式の写真。「税理士ってどうよ?」悪くないひらめきだった。
僕は早速『だれでも税理士になれる本』を購入して読んでみた。東京から新幹線に乗って三重の実家の両親に会いに行き、大学を卒業したら事務所を手伝いながら予備校へ通わせてくれと頼んだ。祖父は、僕が大学3年生のときに帰らぬ人となっていた。線香をあげると、僕の就職活動は終わった。
言葉の壁にぶち当たってしまうことがよくある。
『サンシャイン』の書き出し。学生生活で描いた理想と、突きつけられた現実との間のやり切れない思いが込められた小説は、なんと学内のコンクールで学長賞を受賞するという栄誉を得てしまう。4年間打ち込んだことが報われたことが嬉しかった。3年で税理士試験に合格して、もう一度東京で勝負してやる! 僕は意気揚々と大学を卒業した。

税理士を目指したことを後悔
税理士を目指す勉強は、目標の3年を過ぎ、5年6ヶ月続くことになる。その間に官報合格に必要な5科目のうち3科目に合格した。
最初の3年間は「勉強することが働くこと」だと思っていた。予備校に通い、実務のあと毎日5時間は机に向かった。知識は実務に直結したし、自分も目標をもてばコツコツ努力できるんだということは新しい発見だった。富士山の麓にある全寮制の予備校にも1年間こもり、仲間とともに無我夢中で勉強した。でも結果は芳しくなく、目標の3年を過ぎた頃から苦悩が始まった。
実務では、税務調査の立会いも経験し、担当も何件かもたせてもらった。でも経験を積むにつれ膨らむのは、税理士という職業への疑問だった。自分が提供するサービスにまるで誇りをもてなかった。受験勉強のうち、実務で使うのはほんの一握りの知識。会計や税務ソフトがあれば誰でも簡単にできる仕事なんじゃないかと思えた。高度なファイナンス理論や財務分析も田舎の小規模な事業者には押し売り以外のなにものでもないと感じられた。そして何より、みんな税金を嫌っていた。
「自分の選んだ仕事は本当に世の中の役に立つのか……」
「税」を扱う仕事を選んだことを悔やんだ。
短かったサラリーマン生活
東京に戻る気持ちは変わらず、飲み屋で夜のアルバイトを始めてみた。上京資金を貯めるためでもあり、違う業界の仕事に就いてみるためでもあった。学生時代は長く接客のアルバイトをしていたので、久々の仕事は楽しかった。そこで働く人たちは、みなそれぞれ必死に生きていた。「働くということと折り合いをつけている」ように見えた。呑気に勉強していた自分を恥じた。
少年時代は「いい子」だった。だから大人になっても自然と「いい人」になるんだと思っていた。でも結果が出ず、誇りももてず、仲間たちの成長を目の当たりにするうちに、僕は見事なくらい完全に心のバランスを崩してしまっていた。誰もがもつ負の部分や、社会の不条理に、遅ればせながら苦悩していた。それはかつて『サンシャイン』で表現したようなどこか繊細な壁ではなく、生き抜いていくための険しい壁だった。いまとは違う場所に一刻も早く逃げ出すことしか考えられなかった。
2005年9月、僕は半ば強引に、夜行バスに揺られ池袋に降り立った。何のアテもなく、とある中小企業の経理職をハローワークで見つけた。クライアントの立場で税理士と接してみたかったのだ。でも3ヶ月もすると、また辞めてしまいたくなっていた。それは直属の上司も同じで、2人でよく会社の悪口を言って笑った。会社のパソコンでこっそり転職サイトを覗いては、良い条件の職場を見つけたといちいち僕に報告した。「働くことは生きるための苦労。少なくとも自分の足で立とうとしている」その手応えだけが僕を支えた。
ある日出勤すると、社長が上司にただならぬ様子ですごんでいた。「お前、自分が何したかわかってるな」。上司は無言で荷物をまとめて出て行った。その上司は会社のパソコンを使い、社長のクレジットカードで高級時計を購入していのだと知らされた。僕はもっともっと遠くへ行きたくなった。サラリーマン生活は4ヶ月しか続かなかった。
バックパックひとつ背負い
2006年2月、今度はさらに強引に、貯金を引っかき集め、1ヶ月分の家賃を前払いし、退職願をポストに投函すると、成田発ニューデリー行きの飛行機に乗っていた。学生の頃からずっと訪れてみたかった国。迷惑も省みず、何もかもどうにでもなれという気になっていた。バックパックひとつ、気まぐれに旅をした。インドでは、常に何らかのトラブルを抱えながら旅をすることになる。
楽しい旅だったか? ぜんぜん。ひどい思い出ばかり。
また行きたいか? もちろん。それがインドである。
それは吹っかけてくる商売人たちとの毎日の格闘である。乗り合いジープの荒っぽい運転である。クソまみれのトイレでの得体の知れない色の下痢であり、薄いシーツを頭からかぶって遠く聳えるヒマラヤを見ながら飲んだチャイの温かみである。子供たちの澄んだ瞳と決して抜け出せない現実。大勢の若者たちが日がな一日軒先で手持ち無沙汰に寝そべっていた。「そこは働くこともままならない世界」だった。約40日の濃密な日々。そこでは嫉妬も欲望も無力だった。日本での苦悩が一気にちっぽけなものに思えた。帰りのフライトまで数日となったある日、現金の盗難に遭い、日本人が泊まりそうな宿を渡り歩き手持ちのCDや本を売って帰国日までをしのいだ。

飛行機が離陸すると、僕は自分が激しく泣いているのに気づいた。涙はずっと止まらなかった。何の涙なのか、いろいろありすぎてよくわからなかった。キャビンアテンダントが近づいてきて、僕にやさしく微笑みかけると、何も言わず通り過ぎていった。
これが僕の「働く」ということにも「税」というものにもきちんと向き合えなかった挫折と苦悩の日々である。
ひと回りして戻ってきたスタート地点
人はなぜ働くのでしょう?
出張で都内の電車に乗ると、当たり前のように転職サイトの広告が溢れている。僕が大学を卒業した20年前と変わらない光景。それは終身雇用が当たり前じゃなくなり、派遣労働が増えはじめた頃でもある。時代は変わっても、いまとは違う職場を求める人の多さはあの頃と変わらないのだ。どれくらいの人がギリギリの心でしがみついているのだろう……。受験者数が激減している税理士試験。この業界で働く人たちの中にも、誰かがどこかでかつての僕と同じ苦悩を抱えているかもしれない。僕は必死でもがき続けた。確かなことは「その頃があるからいまがある」ということだけだ。
帰国して2週間は下痢が続いた。腹痛を抱えながらも、駒込のアパートから池袋まで自転車を走らせ、やけに眺めのいいハローワークで職探しを始めた。せっかくドロップアウトしたんだから、自分が絶対足を踏み入れないことをやろう。目に留まったのは「全国巡業公演役者募集」の求人。また旅に出られることは魅力だった。担当の職員に連絡を入れてもらい、面接の日時を決めた。
僕はひと回りしてもう一度スタート地点に戻ってきたんだと思った。今度こそ、壁に立ち向かえるだろうか。勇気と不安が半分ずつ。まだ肌寒い早春の夕暮れ、僕はしばらく、西日に照らされた『サンシャイン』を見上げていた。
第3話「歌って踊れる税理士をめざして」へとつづく
〈執筆者紹介〉
藤井 太郎(ふじい・たろう)
1977年三重県伊勢市生まれ。亜細亜大学法学部法律学科卒業。2015年藤井太郎税理士事務所開業。夢団株式会社会計参与(http://www.yumedan.jp/)。東海税理士会税務研究所研究員。









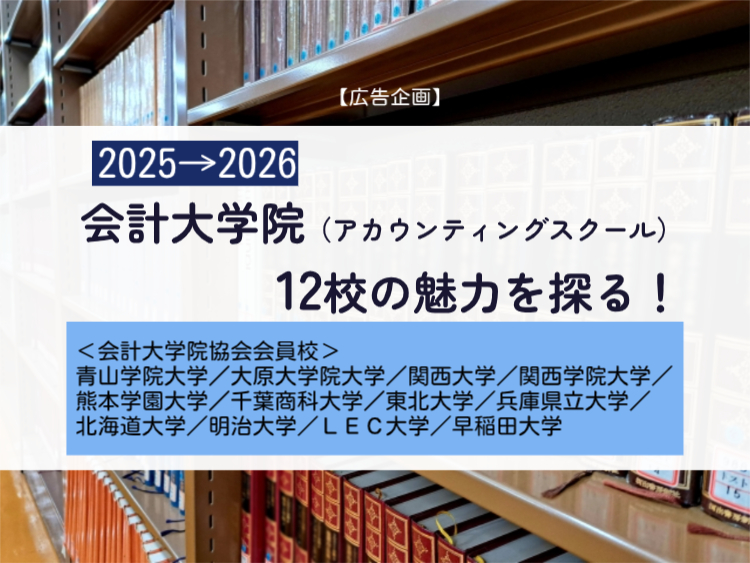


-150x112.jpg)




