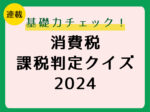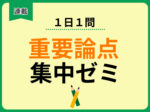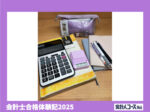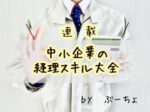渡邉 圭
重要性の原則は、「大事なものは厳密な会計処理を、重要でないものは簡単な会計処理を」とイメージすれば覚えやすいですよ。
消耗品のボールペンを例に解説していきます。たとえば、ボールペンを100本購入したとします。

決算になり未使用の本数を調べたところ1本が未使用でした。
厳密な会計処理をするのであれば、未使用の1本分は消耗品勘定(資産)として計上し、使用した99本は消耗品費勘定(費用)として処理します。

この1本を資産として計上することが重要でなければ、資産計上しない簡単な会計処理が認められます。

重要性の原則を適用して、重要性に乏しいものについて簡便な処理で行うことは、正規の簿記の原則に従った処理として認められ、真実な報告をゆがめないとされています。
資産および負債の省略が容認される例を、一部ですが紹介します。
●資産
消耗品や貯蔵品等、重要性に乏しいものについては、購入時または払出時に費用として処理することができます。
●負債
修繕引当金等、重要性に乏しい引当金は負債に計上しないことができます。