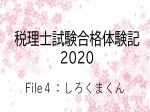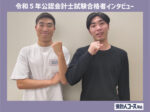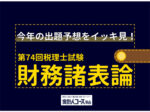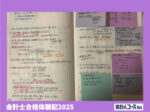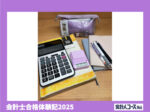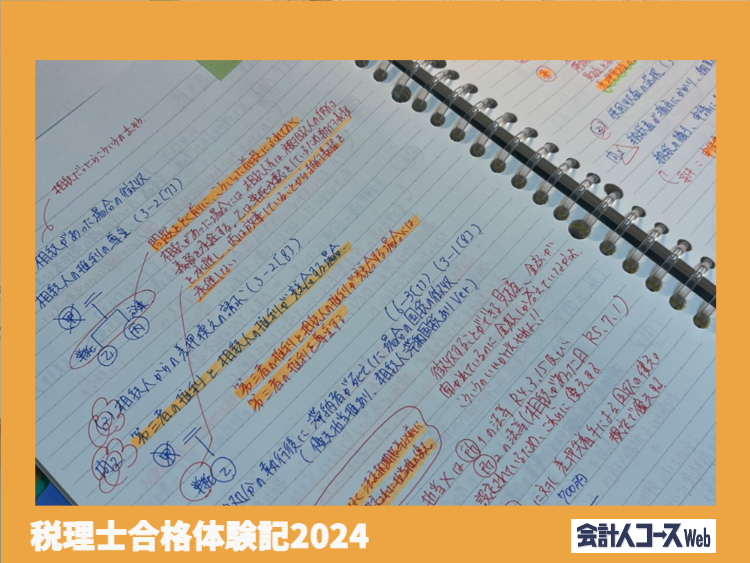
ゆりか(30代半ば、上場企業勤務)
【受験プロフィール】
合格科目と合格年、受験回数:国税徴収法(2024年、2回目)、簿記論・財務諸表論(2018年、2回目)
学習スタイル:専門学校(通信)
▶サムネイルは過去問を解いた際の分析ノート。こんな感じのものが27年分!苦手をつぶすお守りに。
女性上司の言葉をきっかけに税理士を目指す
初めまして。ゆりかと申します。
4歳と2歳の子供がおり、平日はフルワンオペで家事育児仕事を回すワーキングマザー大学院生です。
私が税理士を目指したのは、1人目の子供を産んで復職した際の面談で、尊敬する女性上司から言われた言葉がきっかけでした。
女性上司は、お子さんが2人いらっしゃる50代で、聡明でいつも明るい方でした(この前提をお伝えしないと、この後の文章で語弊を生んでしまいそうなのでしっかりお伝えします(笑))。
「お子さんがいたりすると仕事と家庭の両立で悩んだり、自分よりも出来ない人が先に出世したり、なかなか悔しい思いをすることもあると思うけど、ゆりかさんは優秀だし絶対にめげずに頑張ってほしい」というエールをいただいたのです。
今のようにテレワークや時短勤務などもない時代に、彼女は歯を食いしばって頑張ってきたそうで、唯々毎日必死で走ってきたとのことでした。
私のことを力強く応援してくださっている気持ちが伝わってきました。
と同時に、女性がぶつかるいわゆる「ガラスの天井」を、復職初日に突き付けられたような気持ちにもなりました。
そして、「ガラスの天井に抗うより、自分の強みを活かして勝負していきたい」と、今後のキャリアを考えるようになりました。
大学時代、体育会の部活動に勤しみすぎて学業を疎かにしてしまっていたものの、商学部に在籍していたこともあり、部活動をするための隠れ蓑として日商簿記1級を取得していました。
また、新卒で金融機関に入社をしてFP1級を取得したり、業務の関係で会計を教えなければならなくなった際に、どうせ教えるなら自分も理論をしっかり押さえたくなり、簿記論・財務諸表論を勉強して科目合格がありました。
色々調べ、「税法科目をあと1つとれば院に進んで科目免除で税理士になる道がある」ことを知り、その後1年も経たずに2人目の妊娠が発覚したので、それを期に税法科目の受験を決めて、大原の通信教育に申し込みました。
税法科目の中でも国税徴収法に決めた理由
税法科目を受験しようと決めた際に、上の子のお世話や仕事や自分の体調の変化(つわり等)もあるので、ミニ税法の中で選択することを決めました。
本当は一番興味のあった相続税法を受験したかったのですが、ボリュームが全くミニではないことを知り、早々に諦めました。
次に、実務で申告等を行っていた消費税法を受験しようかと考えたのですが、ちょうどインボイス導入の時期で、もし落ちた場合には次年度に新たに勉強しなければならない部分が多いところを苦痛に感じたので(消費税の場合には追いかけなければならない通達も多く、インボイスが入ってくると尚更大変に感じました)、選択を見送りました。
そこで、もし落ちて次年度に受けることになったとしても、例年改正点が少ない科目で、かつ実務に役立てられ、子育てで時間が強制的にぶつ切りにされる中でも学習しやすいものという部分を軸に選定した結果が国税徴収法でした。
結果、この軸で国税徴収法を選択して本当に良かったと思っています。
産後3カ月で受験した1年目は不合格に
1年目は大原の通信講座(9月開講)、2年目は大原の通信講座(1月開講)とTACの直前対策を利用しました。
時間が全くないので、通信以外の選択肢はなく、かつ簿記論・財務諸表論も大原の通信でお世話になっていたので国徴も何の迷いもなく大原の通信講座に申し込みました。
1年目の学習は特に変わったことはしておらず、学校から送られてくる学習計画表どおりに粛々とこなすだけでした。
ただ、わからないことは書き留めており、不明点を次の講義に持ち越さないように意識はしていました(が、それが出来ない時も多く、心の重石になっていたこともありました)。
直前期は市販されている書籍にも手を出したかったのですが、直前期に出産があり、その後も赤ちゃんのお世話で眠れない日が続いたので、手を広げるのはやめて、とにかく解いた問題でわからない部分をなくすことや、理サブ(大原の理論教材のこと)を片時も離さず、隙間を見つけては理論を頭に叩きこむことだけに注力しました。
試験前日は生後3か月の娘の夜泣きがひどく、一睡もすることなく受験会場に向かい試験を受け、結果5点足らずに不合格でした。
出産後はマミーブレイン(出産後の女性の脳が縮むこと)で記憶力が落ち、通常の自分であれば1年で決められたはずなのにと悔しい気持ちになりましたが、そうは言っても状況は変わらないので、「今の自分でどうしたら合格できるか」を真剣に考えて、2年目の受験に挑みました。
2年目の合格の決め手となった徹底的な理論暗記
2年目は育児休業中だったので、家事育児との並行学習でした。
大原の通信講座を使用し、基本的な部分は変えずに学習計画表どおりに勉強しました。
1年目の反省点は、理論を完璧には覚えきれておらず、自分の武器に出来ていないところでした。
その点を強化すべく、とにかく毎日理論を回しました。
その際、大原の「最終チェックテキスト」にある理論回転表がとても役立ちました。
理論回転表を大量にコピーしてノートに貼り付け、2年目スタート時は1週間で1回転するようにしました。
そして、直前期前半には5日で1回転、直前期後半には3日で1回転、試験8日前からは2日で1回転理論を回しました。
回した理論のチェックボックスにチェックをつけ、どこに行く時にも理サブを鞄に入れ、武器を磨くことを意識しました。
自分の中で決めたことが1つだけあり、それが、「毎日その日のノルマを終えること。次の日の分のノルマを前もって行うことはOKだけど、当日のノルマを次の日に持ち越さないこと」というものでした。
このルールに後悔をしたこともありましたが、試験までほぼやり切りました(子供たちの看病をしたり、子供の風邪がうつって寝込んだ時はさすがにできませんでしたが)。
嫌なことはルーティンに落とし込むといいと何かの本で読んだのですが、確かにそうだと実感しました。
また、先生がボイスレコーダーの活用をお勧めしてくださっていたのですが、1年目にはそこまで出来ませんでした。
そこで、2年目は、ボイスレコーダーをフル活用しました。
子供たちの寝かしつけの際に子供にばれないようにこっそり聞いたり、犬の散歩をする時や調理や洗濯物を干す際などに録音した音声を聞き、ありとあらゆる時間を勉強に充てました。
しかしながら、本当に暗記が苦手で、読んだり書いたりするだけでは覚えられず困り果てました。
キッチンをうろうろ歩きながら声を出して理論を読み上げてみたり、下の子を抱っこして上の子をおんぶしてゆらゆらしながら二宮金次郎スタイルで学習をしてみたり、それでも覚えられない時は替え歌を作ってみたり、変な振りをつけて踊りながら読み上げてみたりと、五感をフル活用してなりふり構わず覚えました。
本を写真で撮るように暗記をすることが苦手です。
ただ、苦手であっても、何がどこに書いてあるか思い出せるくらい徹底的に暗記をしないと受からないと聞きました。
上記の試行錯誤で、試験前には写真で撮ったように暗記をすることが何とか出来ていたと思います。
過去問を25年分×2回
練習問題を解いていた際、読解を間違えて全然違った方向に解答を作成してしまったことがありました。
その際、「これが本試験だったら…」と本当に怖くなりました。
専門学校の問題は、受験生が解きやすく出来ています。
しかし、過去問を見ると、そうでもない年も多々あります。
「国語の読解力が必要だ!」と思い、過去問25年分を解き、その際に自分が出来た点、出来なかった点、なぜできなかったのか、何の理解が足りなかったのかを◎〇△×を付けながら、コメントをしたノートを作成しました。
意識したのは、できるだけ短い時間で聞かれていることを正確に理解することでした。
結局、2週したので、50年分解きました。
もちろん、子育て中なので、2時間集中して問題を解くことは到底出来ません。
毎回問題をバラバラにしつつ、「第1問(1)を20分でやりきる!」と時間を意識して解きました。
加えて、大原とTACの模試や市販の問題等でも、同じように苦手潰しをし、自信をつけていきました。
通信なので、答練は家で問題を解いて提出すればいいのですが、本番の緊張感に慣れたかったので、シッターさんに子供を預けたり、主人に有給を取ってもらって子供を預けたり、何とか時間を作って教室受験を何度もしました(日頃質問電話をしていたこともあり、教室に行くと先生がよく声をかけてくださってとても嬉しかったです)。
ここまでする必要は、正直なところ無いとは思います。
本当はこんなに泥臭く勉強せずにもっと効率良く受かりたかったです。
しかし、子供たちとの時間も私にとっては大切なので、「もし2回目で受からなかったら税理士の道は諦めよう」と決め、「もし諦めることになってしまったとしても、自分がやり切ったと思えるくらいやろう」と、徹底的にやれることをやりました。
1年で受かるなら、理論暗記のルーティンの早期形成が大事
2年かかってしまった反省として、誰かに助言をするのであれば「理論暗記のルーティンは早期に作ったほうが絶対いい!」「とにかくたくさん問題に触れて!」ということです。
理論の内容理解は当然のことながら、国徴は他の税法と比べて理論が少ないです。
しかし、暗記の精度を高めないと似たような文言がたくさんあるので問題が出た時に迷ってしまって回答作成の軸を持てません。
理論の暗記が進めば自ずと自信もついてくるので、早期暗記を強くおすすめします。
また、年に一度の試験で問題文を読み間違えるのは致命傷です。
どのような書きぶりの文章に出くわしたとしても、読解できる力(もはやこの試験は国語力だと思っています)を磨くことも大事です。
おわりに~家事・育児・仕事・勉強と何足も草鞋を履きすぎて、もうムカデになりそう!な中で
「まだ子供が小さいのに、子供の顔を見る時間もそこそこに、私はこんなに理マスばかり見ていていいのだろうか…」「この選択は正しいのだろうか」と悩んだこともありました。
ただ、私は常々、何事も自分で決めた道はねじ曲げてでも正解にしていけたら人生は楽しいと思っていてます。
「あの時の自分が『今だ』と思って始めたんだから、絶対にやり切る!」と悩むたびに邪念を振り払っていました。
また、勉強時間を確保するために、勉強前には子供とたくさん遊んで疲れさせ、子供を満たした状態で昼寝をさせている時間に勉強をして、罪悪感を減らしていました。
今は大学院で勉強をしているのですが、今も子供と遊ぶときは徹底的に遊んでいます。
先日はスマホの記録を見たら、2日で25キロ歩いていました(笑)。
特に上の男の子は体力おばけなので、疲れさせるのがとても大変ですが、勉強するときは勉強に集中し、子供たちとの時間は全集中で子供たちに向き合っているので、おかげで濃い時間を過ごせていると思っています。
「家事・育児・仕事・勉強と何足も草鞋を履きすぎて、もうムカデになりそう!」と思っています。
やりたいことがあったら全力で頑張る姿を子供たちに見せて、いずれ子供たちが全力で頑張りたいことを見つけた時に全力で応援できる親になりたいという気持ちが今の私の一番のモチベーションだと思います。
大人になってからの勉強は、皆さんそれぞれ事情も異なり大変だと思います。
これから受験される皆さんが、それぞれの道をそれぞれの正解にできるようにお祈りしています。
私も自分自身を諦めず、自分が選んだ道を私の正解に出来るようこれからも頑張りたいと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。