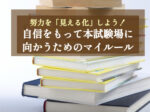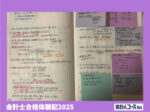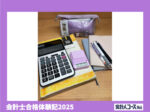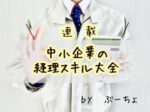【連載・第11回】伝わる!ピッチデックの作成ガイド~チームの作り方
- 2025/9/2
- コラム

【編集部より】
ますます注目が増すスタートアップ企業。資金調達、マーケティング、人材採用など、ビジネスモデルを説明するさまざまな場面で、「伝わるピッチデックを作れるかどうか」がカギとなります。とはいえ、そもそもピッチデックとは何か? 事業計画書とはどう違うのか? ぼんやりしたイメージのままでは、よい資料には仕上がりません。
そこで本連載では、公認会計士として多くのスタートアップ企業をサポートし、ピッチデックの作り方についてもセミナーを行う大野修平先生(公認会計士・税理士)にその作成ノウハウを教えて頂きます。
<本連載バックナンバー>
第1回:「そもそもピッチデックとは?」
第2回:「オーバービューの主要な構成要素」
第3回:「環境セクション」
第4回:「ペインとターゲット」
第5回:「解決策と提供価値」
第6回:「市場規模」
第7回:「競合との優位性」
第8回:「収益モデル」
第9回:「チャネルとプロモーション」
第10回:「トラクションとKPI」
はじめに
スタートアップのピッチで、事業やプロダクトの魅力を語ることはもちろん大切です。
しかし、結局のところ事業を進めるのは人です。投資家も「このチームに任せられるか」ということはとても気にしています。
本記事では、チームセクションをわかりやすく、かつ説得力高く仕上げるための考え方と作り方を詳しく解説します。
是非参考にしてみてください。
なぜチームが最重要なのか
投資家はプロダクトやビジネスモデルだけに投資するわけではありません。実行する人々にも、時にそれら以上の期待をもって投資します。
市場は動きます。仮説は外れます。想定外の出来事も起きます。それでも軌道修正し、学び、前進できるのは「人」の力です。だからこそチームセクションでは、以下を明確に示す必要があります。
- このチームの知識・経験・技術が、事業成功にどう寄与するか
- 役割分担と、意思決定・実行がスムーズに回る運営体制
- メンバー同士の相互補完性(組み合わせの強さ)
- そして、不足リソースがあるなら正直に開示し、どう埋めるかを語る
特に不足しているリソースについて、多くの起業家がこれを隠したがりますが、スタートアップが十分なリソースを持っていないことを投資家は百も承知です。
むしろ、足りないものを自覚し、獲得しにいけるチームは信頼を得ます。
押さえるべき三本柱
まずはチームセクションの主な要素を、投資家の見方に沿って3つに整理します。
経歴とスキル
各メンバーの専門性、業界経験、実績を、事業の勝ち筋と直結させて記載します。単なる肩書き羅列ではなく、「この経験が現状の仮説検証や成長戦略にどう効くか」を一言で添えるのがコツです。
役割と責任
CEO/CTO/COO/CFOなどの責任範囲を明確化。プロダクト、売上、採用、ファイナンス、法務などのオーナーが誰かを示し、意思決定の流れが投資家にもわかるようにします。
相互補完性
異なる強みの組み合わせや重なりが価値を生みます。3~5個のキーワードでスキルマトリクスを示し、穴(つまり不足)がどこにあるかも併せて開示することで信頼感を得ます。
1人ずつの「見せ方」—3行テンプレ
チームメンバーの紹介は長くしないのが鉄則です。以下の3行テンプレを活用してみてください。
1. 役職/担当領域:例「CTO(AI・基盤開発)」
2. 関連実績:例「大手テックでレコメンドアルゴリズムを主導、MAU3,000万規模を運用」
3. 事業への貢献:例「当社の学習最適化モデルの精度・スケールを担保」
肩書き→実績→貢献メカニズムの順番で伝えると投資家の理解と信頼度が高まります。
役割・責任は「領域×KPI」で
曖昧な役割は、実行のボトルネックとなるだけでなく、投資家からも疑問に思われてしまいます。領域×KPIで示すことをおすすめします。
- プロダクト:CPO/月次NPS、リテンション、リリース速度
- グロース:VP Growth/獲得CAC、LTV、チャネル別ROI
- テック:CTO/システム安定性、技術負債返済速度、開発リードタイム
- レベニュー:CRO/MRR/ARR、パイプライン、受注率
- ピープル:CHRO/採用タイムトゥフィル、オンボーディング定着率
KPIが定まれば、投資家は運営の解像度を感じ取れます。
相互補完性は「スキルマップ」で一発
文章で説明するより、小さな表にしましょう。
横軸に主要スキル(例:リサーチ、PM、デザイン、アプリ、UX、バックエンド、セールス、カスタマーサクセス、ファイナンスなど)、縦軸にメンバー名。この表を◎○△で埋め、空白が不足人材となります。
ポイントは、空白を隠さないこと。「採用計画中」「外部アドバイザーで補完」「候補者説得中」「是非ご紹介ください!」など、空白欄の埋め方の戦略を添えましょう。
例えば以下の表を参考にしてみてください。
| 学習科学/ カリキュラム | ユーザー調査 | プロダクト/ PM | デザイン/ UX | BE/ インフラ | AI/ 適応学習 | マーケ (個人/学校) | セールス/ 導入 | |
| CEO | 〇 | 〇 | ◎ | 採用計画中 | ― | △ | 〇 | 〇 |
| CTO | △ | ― | 〇 | 同上 | ◎ | ◎ | ― | ― |
| VP Marketing | ― | 〇 | △ | 同上 | ― | ― | ◎ | △ |
| Dir. Content | ◎ | 〇 | △ | 同上 | ― | ― | △ | △ |
不足人材は「要件×成果」で正直に書く
不足を隠す必要はありません。むしろ、要件定義の精度が高いほど評価されます。
- 募集ロール:Head of Design(デザイン組織立ち上げ)
- 必須経験:SaaS/モバイルでのデザイン組織リード/デザインシステムの立ち上げと運用ガバナンス/計測駆動の改善と合意形成
- 初期KPI:6ヶ月でデザイン負債バーンダウン○%/デザインシステム採用率○%(主要プロダクトへの展開率)
- 支援のお願い:シニアデザイナー候補・アクセシビリティ/情報設計の顧問のご紹介
このように書くことで「課題認識→解決計画→求める支援」が1枚で伝わり、投資家の関与余地を明確にします。
内製か外注か
チームの設計は、内部化 or 外部化の意思決定とセットです。ピッチデックを作成する前に十分検討しましょう。
以下の4観点で評価し、合計スコアが高いほど内製寄りと判断します(各0–2点)。
1. 効率性:他業務と密接に連動し、調整コストが高いか
2. 効果性:差別化の源泉に直結するか
3. 整合性:生産量・タイミングを自社で精密に制御する必要があるか
4. 学習:組織に蓄積したい能力か(将来の競争優位に効くか)
例:
レコメンドAIのコア開発=8点→内製。
広告運用のバナー制作=2点→外注。
データ収集のクレンジング=4点→ハイブリッド(プロセス設計は内製、実作業はBPO)。
また、外部委託時は、情報収集・管理コストや機密性、マネジメント負荷も合わせて検討しましょう。
経営資源の確保:3つのルートの使い分け
外部調達には、市場取引による方法と提携による方法の2つがあり、それぞれの長所と短所は以下のとおりです。
- 市場取引(短期・外部調達)
長所:選択肢が豊富、量と質を柔軟に調整。
短所:重要資源では交渉力が弱まる。必要時に入手不能の可能性。 - 提携(共同で獲得)
長所:単独では難しいリソースも協働で獲得可能。
短所:相手選定・信頼構築の時間とコスト。ガバナンス設計が鍵。
一方、内製化の長所と短所は以下のとおりです。
- 内製化(長期・自前主義)
長所:コア能力を完全に掌握。標準化しにくいノウハウが蓄積。
短所:採用・育成の時間とコスト。確保できないリスク。
これらの長所・短所を踏まえて、採用計画、ベンダー選定、業務提携の三位一体で、資源ポートフォリオを最適化していく必要があります。
提携戦略:なぜ組むのか、どう勝つのか
上記の3つの中でも、特に提携については注意が必要です。
提携は拡大・補完・効率化・リスク分散のために非常に有効な戦略ですので、目的が明確であればリソースの乏しいスタートアップは積極的に活用したい戦略です。
提携戦略の目的例
- 市場拡大/認知向上:例)エコシステムや規格の普及
- 業界競争への対応:例)地域/チャネル競合への共同戦線
- ラインナップ補完:例)自社の強み×相手の穴(4WD×軽自動車のような補完)
- 市場・チャネル補完:例)海外販売網とプロダクトの相互補完
- 新しい付加価値:例)上流パートナーとの共創でサービス高度化
- 需要の調査:例)川下企業とのPoCで検証スピードを上げる
- コスト削減・効率化:例)規格統一やデータ共有
- リスク分散:例)共同開発・JV
提携戦略の成功を左右するのは、①相手の戦略に合わせる柔軟性、②相手のメリット設計、③カニバリ回避の設計です。
一方で、提携戦略には①カニバリゼーション、②情報流出、③一方的な利用、④長期的競合化など、クリティカルなリスクも内在されています。
守秘義務・非競業・成果物の帰属など、契約とガバナンスでしっかりとコントロールすることが重要ですが、多くのスタートアップがこのあたりがずさんです。提携契約の作成・レビューには必ずスタートアップに詳しい弁護士のチェックを入れるようにしましょう。
まとめ
強いチームとは、専門性があり、役割が明確で、補完関係が設計され、推進力のある集団です。ピッチのチームセクションは、単なる紹介ではありません。
チームセクションは、「この問題に挑む必然」と「成功までの道筋」を人の力で語り、投資家に「このチームなら成功する可能性が高い」と思ってもらえるものにしなければ、資金調達はままならないでしょう。
そして起業家にとって何より重要なのは、ピッチデック上のアピールだけでなく、実際にそういったチームメンバーをビルドアップすることです。チームセクションを作成しながら改めてどの様にチームを作り上げていくか、不足しているスキルを補うのかを考えていただければと思います。
<執筆者紹介>
大野修平(おおの・しゅうへい)
公認会計士・税理士
セブンセンス税理士法人 ディレクター 大学卒業後、有限責任監査法人トーマツへ入所。金融インダストリーグループにて、主に銀行、証券、保険会社の監査に従事。
トーマツ退所後は、資金調達支援、資本政策策定支援、補助金申請支援などで多数の支援経験を持つ。
また、スタートアップ企業の育成・支援にも力をいれており、各種アクセラレーションプログラムでのメンタリングや講義、ピッチイベントでの審査員および協賛などにも精力的に関わっている。
さらに、セブンセンス税理士法人が運営する『セブンセンスビズマガジン(https://consulting.seventh-sense.co.jp)』では、ビジネスに関する様々な情報を発信し、中小企業やスタートアップのお悩み解決にも力を入れている。