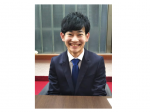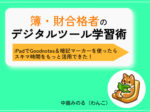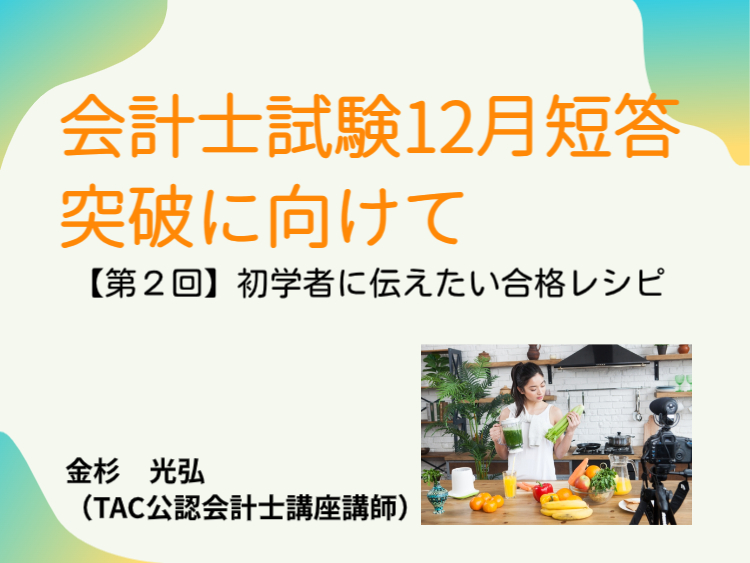
金杉光弘(TAC公認会計士講座講師)
はじめに
会計士をこころざして学習をスタートし、初めて短答式試験を受ける皆さんへ。
勉強は料理に似ています。
正しい分量の材料を用意して、手順に従って進めていけば美味しい料理(=合格)が完成します。
今回は12月の短答式試験までの学習を料理のレシピを紹介するようにご説明します。
材料(準備するもの)
・基本テキスト……各科目必要冊数ずつ、熟成(授業を受けて書き込み済)しているとなお可
・問題集……これも各科目必要冊数ずつ、栄養バランスの取れたもの(必要論点が網羅できるもの)
・答練……新鮮なもの(最新年度のもの)
・過去問……直近数年分(ただし古くても味わい深いものもあり)
・粘り強さ……半年分程度
・やる気……お好みに応じて大量に用意
つくり方(学習の流れ)
Step1:基礎をじっくり漬け込んで下ごしらえ(重要論点のインプットチェック)
①基本テキストを大まかにでいいので、全体を読み直し,重要論点をじっくりと「弱火」で復習します。このとき、焦げ付き(特定の論点に時間を取られすぎて全体を見失う)に注意してください。この段階では範囲の全体像を把握することが大切です。
②調理に手間のかかりそうな材料を別皿に移して(理解に時間がかかる論点をリストアップして)、専用の場所で加熱します(重要かつ苦手な論点を別途対策する)。
③各材料ごとに下味が十分についているかを(各テーマの例題や問題集を解いて理解度を)チェックします。
(ポイント)
この時期の「下ごしらえ」が料理の出来栄えを左右します。すべての材料の味付け(主要論点すべての理解)と別皿の調理(苦手論点を放置せず対策する)を同時に進めてください。
Step2:材料を強火で煮込んでいく(各論点のアウトプットを通じた実践力強化)
①材料は決められた分量を守ります(範囲指定のある答練は事前にしっかり準備して受ける)。
②調理は時間をしっかり守ることが大事です(問題は制限時間を意識して解く)。
③ごつごつした材料も加熱でまろやかになることがあります(難しくとも粘ると解けることがある)。
(ポイント)
アウトプットすることで材料がこなれ(各分野の理解が深まり)、全体の調和が得られます(論点間のつながりが明確化する)。また,固い材料は芯を除いてつぶす(総合問題は論点に分解して復習する)とよいでしょう。
Step3:味付けと盛り付け(アウトプットからのインプットと直前対策)
①生煮えの部分は火入れを強めに行う(重要論点なのに得点が低い箇所は重点的に復習する)。
②香味野菜やスパイスを加えることで味わいが引き立ちます(解ける論点も下書きの工夫などでスピードアップ)。
③皿への盛り付けは足し算でなく引き算も大事(正誤選択問題は「正しい」を選べるだけでなく,「誤り」を消せることも大事)。
(ポイント)
最後の味の調整です。完璧を求めるより、食事に間に合うよう提供することを心がけましょう(満点を目指さず合格点を目指すことを意識する)。
シェフの一口アドバイス
・「焦がさず、冷まし過ぎず」(特定論点に偏らない、また長く放置する分野を作らない)
・「いい肉も火を通さないとおいしくならない」(半端な理解でなく十分な実力でないと戦えない)
・「毎日キッチンに立つ」(毎日机に向かう)
最後に
このレシピ、味付けは少し濃いめかもしれませんが,短答合格というごちそうを完成させるための養分は十分に含まれています。
「努力」というソースは、時間を掛けてじわじわと効いてきます。
「解法」という包丁さばきは、繰り返すことで上達します。
長い勉強時間には「遊び心」というスパイスも時に必要です。
合格後の未来に思いをはせ、「熱意」をオーブンで予熱しておいてもよいでしょう。
試験本番で、マークシートを前に、自信をもって「いただきます!」と言えるように料理を完成させましょう。
〈プロフィール〉
金杉光弘(かなすぎ・みつひろ)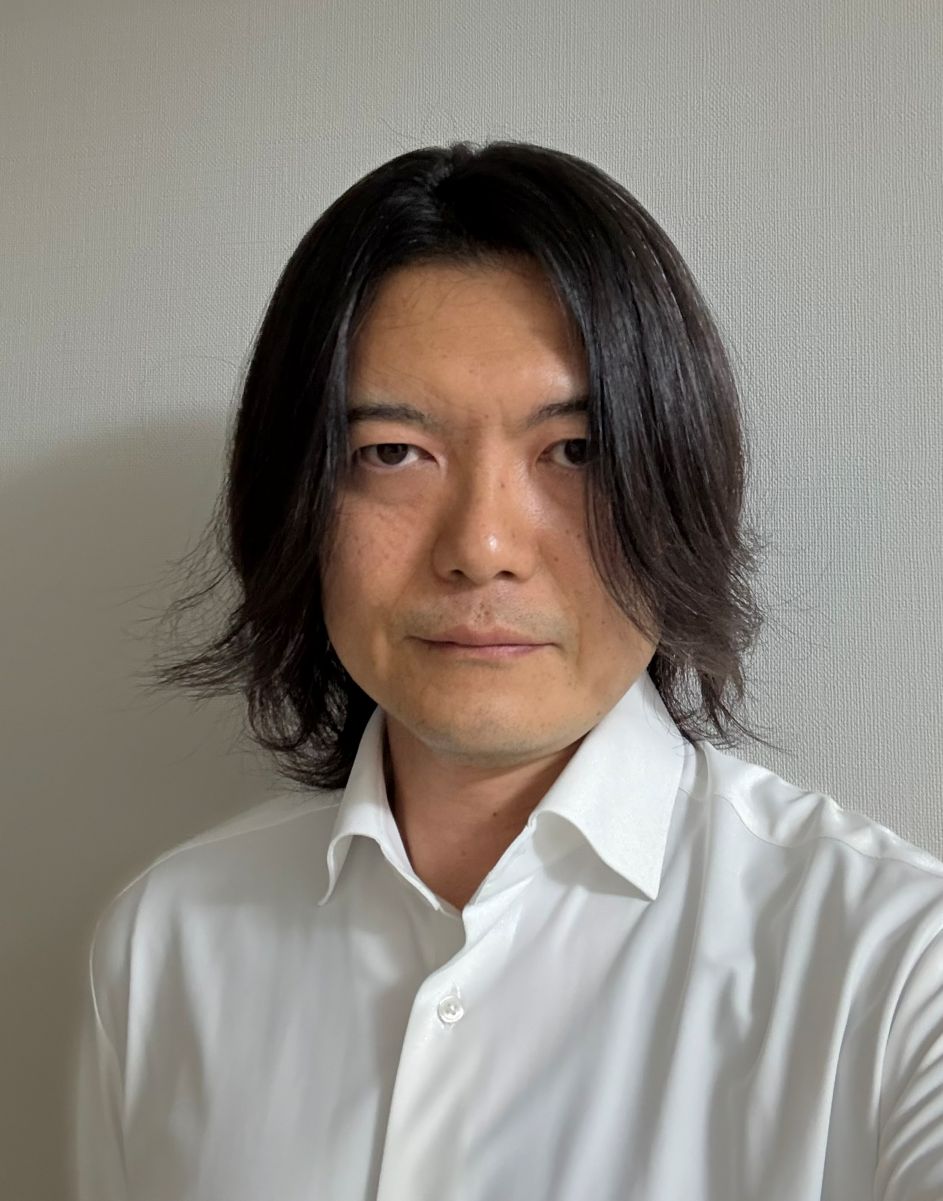
TAC公認会計士講座で財務会計論の講師としてWeb講義、教材開発、問題作成を行う。また、FASS(経理・財務スキル検定)や企業研修なども担当。監査法人にて上場企業、金融機関、IPO等の監査業務を行う他、コンサルティング会社で経営改善計画の策定、アドバイザリー業務など幅広く従事。現在,東京実務補習所運営委員を務めている。
Xアカウント(会計ポエム)https://x.com/kanasugi_tac



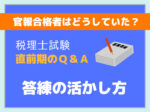
-150x112.jpg)