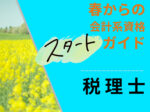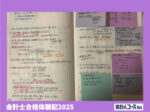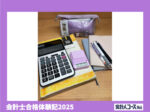KAZU
(20代、国際基督教大学4年)
〈受験情報〉
学習スタイル:CPA会計学院(通信)
合格履歴:2023年12月短答⇒2024年8月論文
▶トップ画像はKAZUさんの学習スペース(本人提供)
はじめに
会計士と聞いて世間の人はどのような資格であると思うだろうか。
弁護士・医師と並び三大国家資格に数えられてはいるが、具体的に何をしているかわかっている人はそう多くないであろう。
私自身もこの試験の勉強を始めるまで同じような状態であった。
このような状態であった私がなぜ会計士を目指し、どんな受験生活を送り、合格することができたのかについてまとめてみたい。
本体験記が多くの受験生の励みになればと思う。
会計士を目指した理由
コロナ禍で簿記2級を取得
私が会計士を目指したきっかけにたいそうな理由はない。
私の父と祖父は経営者であり、税務や会計には、大学に入学する前からなんとなく興味を持っていた。幸いなことに、入学する段階において学問領域を定めなくてよい大学であったため、興味が湧いたらそういった領域を勉強してみるのもいいかな程度の興味であった。
その後、大学に入学し、コロナ禍で持て余し気味となった時間を利用して、一年生の夏に自主的に簿記2級を取得した。
その時は会計士志望ではなく、「英語を勉強して一年留学に行き、英語を生かした職業に就こう」と考えていたため合格点ギリギリではあった。
しかし、簿記は高校までの勉強とは全く異なるタイプの勉強であり、嫌だと感じることは全くなく、楽しんで学習することができた。
就活の仕組みに違和感
そんな私が会計士を目指そうと考え出したのは、大学二年生の時、一学年上の先輩が就職活動を始める中で話を聞く機会が増え、一般就職の仕組みに違和感を感じたことだった。
一般的な就活生は企業の面接を何社も受けて内定をもらった企業の中から就職先を選ぶという具合であると思う。
しかし、私は「なぜ自分が企業に選んでもらう立場にならないといけないのか」疑問に感じた。
就職活動の流れは、何社もインターンに行き、1次面接から始まり人間性などを採用側が総合的に評価した上で通過する人としない人がいる。
このような総合的に評価するという就職活動の性質上、人事の人との相性やE Sを読む人の感性によって多少の偶発性が生まれてしまう可能性がある。
さらに言えば、大学の学閥や人数調整など不確定要素も非常に多い。
同期に優秀な人物がいたら入社しにくいし、業績が悪ければ多くの企業では新入社員の採用を絞る。
詰まる話、中学・高校・大学は自分が選んで決めてきたのに、最後の最後である就職だけは客観的な指標で評価してもらうことができない現実が、私には理不尽に思えた。
そこで私は「どうしたら私が企業を選べる立場になれるのか」を考えた。
この答えとして「自分が何か社会に対して高い付加価値を与えられるような人材になること」であると考えた。
ではどうしたら希少な人材になれるのか、自問自答を繰り返した。
6週間の短期留学プログラムで、海外生活が肌に合わないと知る
そんな時、たまたま大学のプログラムで6週間の短期留学プログラムを募集していた。
大学に入学する前から一年間の留学に興味があった私にとって、自分の適性を図るための良い機会だと思い参加することにした。
実際、海外の大学で簡単な論文を書いてみるというプログラムで現地の大学生や教授と触れ合ったり文化を学んだりと充実した時間を過ごすことができた。
しかし、この留学で私は海外での生活が自分の肌に合っていないことに気づいてしまった。
短期留学を通じて、とても一年間留学に行くことはできないと感じた私は、この後の大学生活をどのように過ごしていくか思い悩んだ。
会計士であれば、自分の希望を叶えられると確信
そんな時にふと大学一年生の時に勉強した簿記2級を思い出した。
調べてみると、簿記の学習の先にある税理士や会計士は独占業務だけではなく、不確実性が高まる現代社会において需要も高く希少な人材として活躍できるフィールドが広いということがわかった。
また、多くの会計士が所属する監査法人は売り手市場であり、自分の方から就職する会社を選べるような状態であるということがわかり、高度な会計人材になることが自分の疑問に対する答えであると確信した。
帰国してすぐにCPA(通信)に入る
帰国するとすぐにCPA会計学院に入校した。
勉強に注ぐ時間をできるだけ増やすため、専門学校は通学する時間も無駄であると考えたため通信を選択した。
1日10時間以上勉強し、2回目の短答で合格
そこからは毎日それまでの人生でなかったくらいの猛勉強をした。
一日平均10時間以上の勉強を目標とし、大学の講義以外の時間は図書館で22時まで勉強し、帰ってからも余力がある日は勉強した。
マイルールとして、携帯があると集中力が削がれてしまうため、携帯は家において出ることにしていた。
また、基本的に不要な友達との遊びは断ったし、サークルの合宿なども休んだ。さらに、年末年始も1月2日から図書館に行き、休みを作らないようにした。
その結果、初めての短答式試験(5月)を前に、スタートから8ヶ月でB判定まで達することができた。
もしかしたら、という思いで初めての短答式試験に挑んだが、結果はあと2%足りなかった。
ショックではあったが、自分の勉強方針が間違っていなかったことを確認できた。
試験後、6,7,8月はあまり勉強せず自由な時間を過ごし、そこから徐々に勉強時間を増やしその次の短答式試験(12月)まで学習を進め、合格することができた。
自由な時間を時折楽しみながらも、論文式試験に一発合格!
その後論文式試験(8月)であったが、3月に少し休んで旅行にも行った。
今から考えればこういった少しの小休止が最後まで集中力を切らさずに試験勉強を乗り切ることができたコツであると思う。
多くの会計士受験生にとって辛いのは周りの友達は勉強していないのに、なぜ自分はこれほど勉強しているのかと考えてしまうことであると思う。
私も同じであり、自分で決めたはずなのに遊んでいる同級生を見て羨んだり、自分の状況を卑下したりすることもあった。
やっても終わらない答練・講義・テキスト、漠然とした人生に対する不安を感じ、焦燥感に駆られる夜もあった。そんな受験生活の中で、それでも日々勉強を続ける中で、効率的に勉強するためにはメンタルが重要であると心底感じた。
メンタルが安定していれば記憶の定着も良く、授業も集中して受講することができる。
毎日、のんべんだらりと勉強するくらいなら多少旅行に行ったり、自由な時間を楽しんだ方が結果的に勉強効率がいいと感じた。
自分自身を労ることも重要な受験テクニックであるということを知っていて欲しいと思う。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧