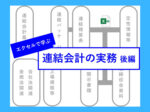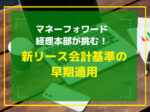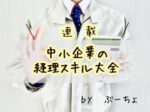5月は法人顧問をメインにしている会計事務所にとって、繁忙期の集大成。
なぜなら3月決算法人は法人全体の2割を占めており、5月は他の月に比べ法人申告数が多くなるからです。
国税庁HP 決算期月別法人数
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/hojin1997/11.htm
さて、今月のテーマは、「役員報酬の決め方」です。
決算を迎えた法人は、新年度が始まって3ヶ月以内に、役員報酬を改定するかしないか、また改定する場合は月額いくらにするか、決めなくてはなりません。
役員報酬は、税務上では一定の要件を満たさなければ損金として認めないとされています。役員報酬で損金算入が認められているのは、次の3つです。
① 定期同額給与…一定期間(通常は毎月)同額を支払う
② 事前確定届出給与…あらかじめ税務署に「誰に・いつ・いくら払うか」を事前に届け出た上で、その通りに支払う
③ 業績連動給与…上場企業などが、業績(利益、株価など)に連動して支払う
中小企業でおさえておくべきなのは①と②です。それぞれに気をつけるべきポイントをチェックしていきましょう。

定期同額給与を改定できるタイミングを知ろう
役員報酬を毎月一定額にしているのは、恣意的な利益操作をしないため、また株主等の信用を高めるためです。ただし、次の3つの事由がある場合には、継続して一定額を支給することを前提に、支給額を改定することができます。
・三月(みつき)改定事由
事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までの改定
・臨時改定事由
役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などやむを得ない事情による改定
(例:取締役から代表取締役への昇格、常勤から非常勤への変更)
・業績悪化改定事由
経営状況が著しく悪化したことによる改定
役員報酬は法人経費になりますので、増えれば利益は少なくなります。翌期の利益見込みをたてた上で、利益を圧迫しない金額設定をしましょう。また、役員報酬が増えれば役員個人の所得が増えますので、所得税とのバランスをとることも重要です。


事前確定届出給与のリスクをおさえておこう
顧問先から問い合わせが増えているのが、事前確定届出給与。事前に届出をすれば、役員賞与を支給できる(損金算入も可能)というものです。
経営は先が見えないため、毎月の給与(定期同額給与)をできるだけ低く設定し、年度の後半で利益が出た場合には役員賞与を支給できる、という趣旨で設定された制度ですが、近年はこれを「社会保険料の削減スキーム」として利用しているケースがよく見受けられます。
賞与に係る社会保険料は上限が設定されています(R7年5月現在、東京都で健康保険は年間573万円、厚生年金等は150万円)。
同じ年収でも毎月の給与を低く、賞与を著しく高額にすることで、年間の支払い保険料が安くなるのです。
しかし、事前確定届出給与は以下のようなリスクがあります。
・届出には支給対象者の氏名・支給時期(年月日)・支給額を記載するが、支給時期は1日たりとも、支給額は1円たりともズレてはいけない(全額損金不算入になってしまう)
・賞与が高額になると支給月の資金繰りが悪化する可能性がある
・毎月の給与が減少するため役員の生活に影響する恐れがある
・退職間近の役員の場合は退職金が減る(役員退職金は「退職時の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率」で計算されるため)
・役員個人の所得税の計算上、社会保険料控除が減少する
・将来の年金給付額が減少する
・届出の手間がかかる
上記のようなリスクを分かった上で、それでも届出をする場合には、支給について会計事務所側では責任を負わないことをしっかり伝えておきましょう。
また、届出の提出期限は、次の①②のうちいずれか早い日から1ヶ月を経過する日(新たに設立した法人の場合は、設立の日以後2ヶ月を経過する日)になります。
① 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日(またはその職務執行を開始する日)
② 会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日
株主総会の決議の日は、一般的に決算確定日と同日になります。申告書に記載した決算確定日の1ヶ月後が届出期限となりますので、提出を忘れないように注意しましょう。

さいごに
事前確定届出給与は高リスクのため、そもそも届出業務は受けないなど敬遠している会計事務所もあります。ただ、現行の税制で認められている制度です。
顧問先から希望があれば、わかりやすく制度内容を説明し、考えられうるリスクを伝えられるようにしておきましょう。
<著者紹介>
定岡 佳代(さだおか かよ)
税理士
兵庫県出身。1980年生まれ。神戸大学工学部建設学科、神戸大学大学院自然科学研究科(土木工学)修了。
関西で技術職に就くも、結婚・出産・上京を機に専業主婦に。次男の妊娠中に簿記の勉強を始め、日商簿記3級・2級に独学で合格。そこから税理士試験に挑戦し、パート勤務、大学院通学と並行しながら3科目合格。立教大学大学院経済学研究科を2020年3月に修了。2021年4月、税理士登録。
硬式野球男子2人の母。「税理士を目指すママ」コミュニティで知り合った友人のママ税理士4人で、セミナーや対談など活動をしている。都内の税理士事務所、税理士法人で約10年の修行を経て、2023年8月に独立開業。「お客様はピッチャー、私はキャッチャー。どんな球でも受け止める。」をモットーに、お客様との対話を大切にしている。