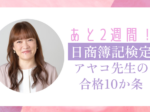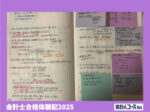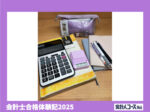GEN
(20代半ば)
〈受験情報〉
学習スタイル:CPA会計学院(短答時:通学、論文時:通信)
受験歴:2023年12月短答⇒2024年8月論文
▶トップ画像はGENさん愛用の電卓(本人提供)
大学中退し、簿記を勉強。1級から会計士試験へ
私が会計士を目指し始めたのは今から約3年ほど前になります。
当時大学を中退した私は、簿記2級まで独学で取得したのち、まずは簿記1級を通信講座を利用しながら目指しました。
そして、運に味方されたこともあって、約1年後の簿記1級試験に無事合格し、その後本格的に会計士の勉強をスタートすることとなりました。
受験期
短答式
CPA会計学院に入校したのは2023年2月くらいであり、現実的に考えて5月の短答式試験には間に合わないと感じていたので、12月の試験を本命と捉え勉強を進めていきました。
短答式試験に向けた勉強に関しては、スケジュール通りに授業を受け、余った時間で復習を行うというような一般的なものでした。ただし、勉強を進めていくにつれて、財務会計論の理論分野、監査論、そして企業法といった暗記が必要とされる領域の出題範囲が、あまりにも膨大で到底単純暗記では乗り切れないと感じました。
そこで、授業のたびに学んだ分野を精度高く覚えるのではなく、直前期といわれる本試験前3ヶ月の間に必要な知識を頭に詰め込めるように、趣旨といった根底にある考え方を意識しながらできるだけ暗記量を減らせるように日々の勉学に努めました。
1つ具体例を出すと、企業法という分野において株主総会について学習しますが、そこでは“8週間”という期間が度々登場します。招集通知や議題提案などを行う際は株主総会が開催される“8週間前”までに行う必要があるという決まりがあり、この“8週間”という数字は本試験を突破するためには暗記しないといけません。
このような場合において私は、「株主総会の招集通知は株主総会の“8週間前”」、「議題提案は株主総会の“8週間前”」といったように個々の結論を分けて暗記することはせず、代わりに、「株主総会の準備には約8週間ほどの期間を要するはずだと当該規則を作った方々は考えているのだな。では、株主総会の招集に関する事項には“8週間”という数字がよく出てくるのかな。」といったように捉えることで、1つの論点を他の論点と結びつけることができるよう努めました。
結果、本試験直前に暗記しないといけない量を減らすことに成功し、苦手意識が特に強かった企業法で90点という高得点を本番に取ることができました。私のような暗記があまり得意ではない方々にとっては、それが正しいか否かに関わらず、自分なりに個々の論点を結びつけることで絶対的な暗記量を減少させるというやり方は効果的ではないかなと思います。
論文式
短答式試験突破後の論文式試験に向けた勉強については、参考にしていただけるようなアドバイス等はあまりないですが、1つお伝えしたいことは、予備校で行われる答練は全て受けなくても合格できるということです。
私自身が通っていたCPA会計学院に関してしかわからないのですが、当予備校は週に3回ほどの周期で行われる答練が半年くらい続きます。無職専念で時間が有り余っている私でさえも、復習等が追いつかず、途中から受験するのをやめてしまいました。それでも本試験において合格できたので、無理してまで答練を受け切る必要はないのかなと思います。
ただ、本試験における最適な時間配分の仕方や、わからない問題が出てきた時に少し時間を使うのか、それともすぐに捨てるのかといった判断などは、本番と同等の難易度そして同じ形式である答練を解くことで身につけることができるため、数回分は時間を測って受験することが大事だと思います。
また監査論と企業法に関しては、短答式試験と論文式試験で出題形式がかなり異なることを考慮すると、スケジュール通りにこなせなくても構わないので、できる限り全てに目を通すことをお勧めします。
出題予測
短答式試験及び論文式試験に共通して言えることは、予備校が出している出題予想はかなりの精度で当たると感じるということです。ですので、なんとなく一度見ておくといったことで済ますのではなく、予想された範囲を直前期はしっかり意識しながら勉強することを強くお勧めしたいと思います。
ちなみに、私自身は論文式試験において、模試等で偏差値50付近を前後していて、本試験ではボーダーである52を取れたら十分かなと考えていた監査論の偏差値が、出題予想のおかげもあって60を優に超えることができました。
最後に
最後になりますが、会計士試験を突破するには、一部の天才秀才を除いて、勉強漬けの日々を数年間続ける必要があり、モチベーションがどうしても出ない日も当然出てくるのかなと思います。そのような時は無理をせずにしっかり休んでください。
完璧主義になりすぎず、好きなことをして定期的にリフレッシュすることが長期間にわたって勉強を続けるという観点においては大事だと思います。皆さんが無事に試験を突破されて、同じ業界で共に働けることを楽しみにしています。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧