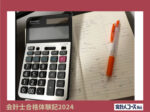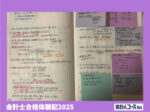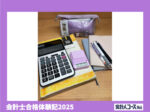りうぼう
(20代)
〈受験情報〉
学習スタイル:CPA会計学院(通信)
▶トップ画像はりうぼうさん愛用のG-SHOCK
公務員志望から会計士志望に変更
会計士を目指したきっかけは、大学に資格の予備校の先生を招いて行われた簿記の講義でした。
その時まで、会計士という資格はおろか、簿記という存在さえ知りませんでした。
初めて簿記というものに触れ、大学受験時代から数学が好きだったこともあり、とても興味を持ちました。
講義は簿記検定3級を目標としたものでしたが、その後独学で簿記検定2級まで取得しました。
簿記検定2級を取得後、簿記検定1級を取得するか会計士試験を受験するか悩みましたが、調べていくうちに会計士資格の将来や監査業務という独占業務に強く惹かれました。
そこで、当時所属していた資格試験の予備校の公務員コースから、会計士講座にコース変更を行いました。
その後、CPAに移籍し、会計士試験に合格しました。
アルバイト・インカレサークルと受験勉強の両立
受験生時代は、アルバイトをしていました。
大学では、インカレサークルにも所属していました。
ここでは、両立のコツについて少し紹介したいと思います。
アルバイトについては、自宅からアルバイト先までのバス乗車時間約30分の間に、一問一答や自分が覚えたいことや間違えた問題についてメモをしたまとめ帳を見ていました。
結果、往復で1時間の勉強時間を確保できました。
また、休憩時間やバスを待っている間など、ちょっとした隙間時間に勉強することは常に意識していました。
大学では、講義と講義の間の休み時間に早めに教室に移動して講義が始まるまで勉強したり、サークルの活動も外部の施設を借りて行われていたので自宅からそこの施設までの移動時間を使って勉強していました。
色々やると、まとまった勉強時間がとりづらく大変ですが、「塵も積もれば山となる」という言葉もあります。
毎日の積み重ねが、いずれ大きな成果につながるので、隙間時間を利用して学習を進めるのはいいと思います。
短答は3回かかるも論文は一発合格!
私は、短答式試験を3回、論文式試験を1回受験しました。
学習を始めてから1回目の短答式試験までは「会計士試験では計算が大切」と思い、財務会計論や管理会計の計算演習に力を入れすぎて理論科目で全く点数が取れませんでした。
1回目の受験での失点部分を分析し、2回目の受験では企業法や監査論などの理論科目に力を入れた結果理論科目の点数は安定しましたが、財務会計論や管理会計論の理論に勉強時間を割くことができず、理論で大量失点してしまい、2回目の短答式試験も不合格でした。
これらの2回の受験を通して理論科目と計算科目の理論での点数を安定させ、計算問題で攻めるのが自分自身にとって1番合計得点安定することに気が付いたので3回目の短答式試験の受験に向けては計算のメンテナンスを定期的に行いながら、理論科目や計算科目の理論を重点的に勉強しました。
無事、3回目の受験で合格しました。
論文式試験では、短答式に合格するまでに培った計算力を武器に論証の暗記や理解に勉強時間を集中させ、また、定期的に実施される答練をタイムリーで受験し続けることで、常に自分の立ち位置や弱点を常に確認し勉強に組み込むことで1回目の受験で論文式試験に合格することが出来ました。
論文式試験は短答式試験より科目が増え、暗記量も増えるため、短答式の時代にどれだけ計算力をつけることが出来るかが合格への分岐点となります。
頑張ってください。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧