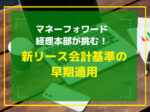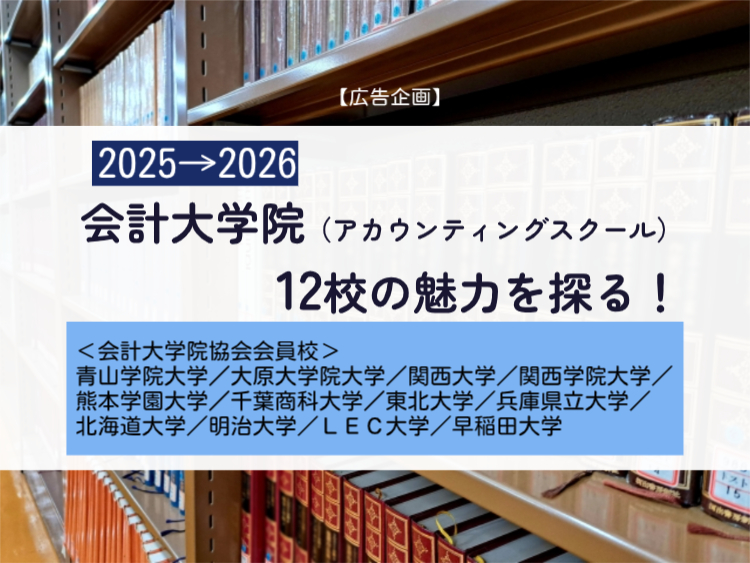藤井太郎
【前回まで】
第1話「所得税と筑前煮」
第2話「サンシャイン」
第3話「歌って踊れる税理士をめざして」
僕が入団した2006年は、劇団の学校公演が軌道に乗り出した時期で、本番数は毎年伸び続け活気に満ちていた。大きな要因は、シンプルに作品がよかったからだ。座長(第3話参照)の演出と脚本は、理屈や常識では説明できない子どもの心をがっちり掴む要素が溢れていた。
僕は役者の傍ら、経理業務を皮切りに、増え続ける裏方作業の中心を担うようになっていった。座長の斬新なアイデアはしばしば周囲を振り回し困惑させた。その調整も重要な任務のひとつだった。いつのまにか座長の右腕のような存在になっていた。
その頃の劇団の学校公演活動は、母体となる会社の一部門に過ぎなかった。座長のエネルギーが会社の枠にとどまるものでないことはよくわかっていた。だからやがて、独立して新劇団を立ち上げたいと思うのは自然な流れだった。サポートしたかったし、それは僕の決断でもあった。
東京の片隅で
僕の住まいは、駒込と田端の間の線路横の崖に立つ6畳2間の木造アパートだった。部屋から山手線の車内を覗き込め、外回りと内回りが交差すると轟音とともに部屋が揺れた。長期間の巡業から帰ると、ネズミにお菓子を齧られていたこともあった。
アパートには同居人がいた。劇団でドサ回りを共にしていた女優で、歳は僕のひとつ下。芝居についていつまでも語り合った。記録的なゲリラ豪雨の夜に稽古場から自転車に二人乗りして妙なテンションで帰った。270円の弁当を分け合い、遠くに見える建設中のスカイツリーをときどき観察した。文句ひとついわず、僕の愚痴を聞いてくれた。脳裏に浮かぶ決断と、経済的な不安の間で揺れていた。
税理士試験への思い
地元の伊勢から、何度か両親が僕に会いに上京してきた。僕が半ば強引に上京したせいで、事務所ではいくつかの問題が生じていた。複数のクライアントが去っていた。伊勢に戻って事務所を継いでほしい……ときには懇願された。そのたびにいつもはぐらかした。ぷっつり切れてしまった気持ちはそう簡単に戻るものではない。
ただ「税理士試験合格」という目標は切れずにいた。それはこの先どういう仕事を選ぼうと、達成すべき自分との約束なのだ。信頼と多忙と責任を言い訳に生半可な準備で合格するほど甘い試験じゃないことは、よくわかっていた。いずれは勉強に打ち込める環境を整える決断をすべきだった。
快感と、葛藤と
スポットライトを受けながら自分を表現する役者の快感は、いちど取り憑かれるとなかなか抜け出せるものではなかった。新しく入ってくる役者たちのレベルは年を追うごとに上がってくる。それに引き換え、デビューから何年経っても、歌もダンスも思うように上達することはなかった。少しはマシな芝居ができているのかも、ひどく怪しいものだった。思い切って武者修行する道もあったけれど、結局のところその劇団が僕の居場所だった。快感と葛藤を繰り返しながら、本番数は何百と積みあがっていった。
劇団が成長していく過程では、つらい出来事もあった。さまざまな人がやってきては、さまざまな人が、さまざまな理由で去っていった。台本に書いてあるような「友情」や「信頼」がときに損なわれることは、本番を見てくれる子どもたちに申し訳なかった。
僕はときどき、アパートの窓から見える山手線の乗客たちの人生と、自分が歩んできた道のりを重ね合わせた。もしも20代の頃からずっと、足を踏み外さずに税理士事務所で働いていたら、どんな人生を送っていただろう? 税務とはかけ離れた役者の世界で、仕事に向き合うという壁を乗り越えられたのだろうか? 修羅場が過ぎていくたびに増えていく心の奥の「しこり」とともに、僕は少なくとも逞しくなれた気がしていた。
2010年2月14日
そして2010年2月14日の本番を迎えた。
渋谷区児童会館は、学校公演の聖地と呼ばれる劇場である。無料で劇を鑑賞できる歴史あるイベントが定期的に開催され、その舞台に立つことは劇団にとってひとつの集大成といえた。僕はその日、幸運にもその舞台に立つことができた。満員の客席。出演者を増強した特別バージョン。役者もスタッフも普段とは違う異様な緊張感に包まれていた。
芝居は、その人が歩んできた人生が投影される。登場人物たちは、悩みながら困難に立ち向かっていく。それは僕自身でもある。物語がクライマックスへと向かうナレーションを、僕は舞台袖で目を閉じて聞き入る。
『人に信じてもらいたければ、まず自分が人を信じることです』
ばらばらになった仲間は、その言葉をきっかけに再び力を合わせて敵に立ち向かう。迷いも悩みもすべて吹っ切り、すべて舞台においてくる。万雷の拍手とともに幕が閉じると、僕たちは劇場出口に急ぎお客さんを見送る。外は冷たい風。お客さんの笑顔や言葉から、物語のメッセージが深く伝わったことがわかる。
5歳くらいの女の子がはにかみながら駆け寄ってきて、握手や記念写真をせがむ。主役を差し置いて、僕の大ファンになってくれたみたいだ。それまでの苦労が報われた気がして、一瞬気を緩めると、堰を切ったように感情が押し寄せてきた。登場人物が子どもの前で見せてはいけない涙だ。僕は感情の波を必死で止めようとする。でも無理だった。女の子はちょっと困った顔をしていた。彼女の名はルルちゃん。
後日、彼女の母親から、劇団のHPにメッセージが届いた。僕の夢を見るために、劇団のパンフレットを枕に敷いて寝ていること、パパと結婚するんじゃなくて太郎と結婚するんだからねと言っていることが記されていた。彼女の言葉は、僕が葛藤の中できちんと仕事に向き合い続けた成果なんだと思った。それと同時に直感したのは、たぶんこれが役者としてのハイライトなんだろうなということだった。僕には気持ちの変化が生じていた。
踏み出した新しい一歩
同居人はプロポーズを受け入れてくれた。引越し先の西日暮里の10階建マンションからは完成したスカイツリーが見えた。
実家の事務所とは、ビジネスライクに賃金の交渉を始めた。守るべき家族ができたのだ。役者としては一線を退き、スタッフとして座長の独立をサポートした。なんとか独立資金の融資を取り付けることができ、新劇団は初演を迎えることができた。僕は座長に、1年間働いた後、伊勢に帰り実家の事務所に転職する決意を伝えた。
役者から足を洗ってできた時間とエネルギーは、残り1科目に迫った税理士試験合格のために充てるのだ。はじめての受験から12回目、何度も跳ね返された難関「法人税法」へ向けての挑戦が始まった。
Dear Miss Lulu
『ルルちゃんは、だいじな人にきちんとありがとうのきもちを伝えていますか? おとなになるとね、いろいろあって、きちんとありがとうを言うことができなくなるのです。だから、ありがとうのきもちや、だいじな人との絆をいつまでもたいせつにできる、ステキなおとなになってください。』
そのとき書いた返事だ。僕は彼女のその後をいっさい知らない。いまたぶん高校生だ。僕の決断を後押ししたことなど、もちろん知る由もない。とめどない決断の日々。でもその決断がどれほど大きいかなんて、あとになって振り返ってみるからわかるのであって、そのときは気づかない。だからいま改めて。ありがとうルルさん。
第5話「8年前の合格体験記」へとつづく
〈執筆者紹介〉
藤井 太郎(ふじい・たろう)
1977年三重県伊勢市生まれ。亜細亜大学法学部法律学科卒業。2015年藤井太郎税理士事務所開業。夢団株式会社会計参与(http://www.yumedan.jp/)。東海税理士会税務研究所研究員。