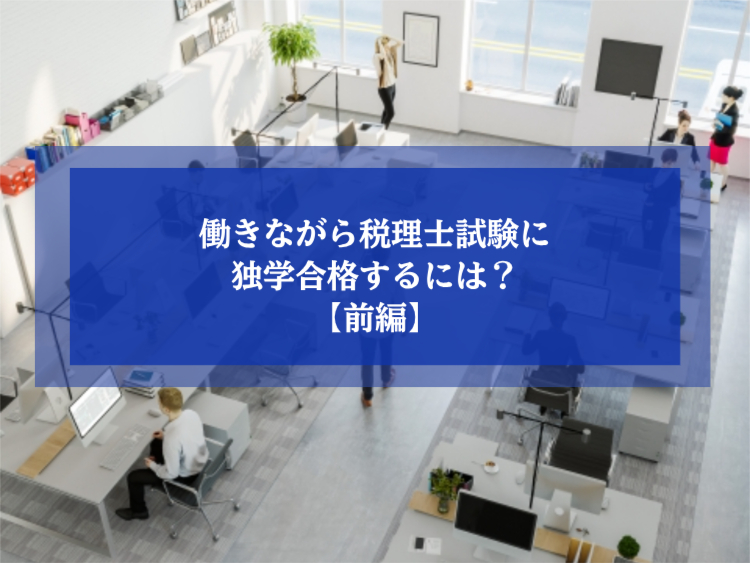
まえさん(20代後半・会社員)
はじめに
社会人として一般企業に就職をし、22歳で簿記一級に合格後、先輩の勧めにより24歳から税理士試験の受験を始めました。
会社と試験勉強を両立しながら毎年1科目ずつ合格を積み重ね、27歳で官報合格を達成しました。
合格科目は簿記論(R3)、財務諸表論(R3)、消費税法(R4)、固定資産税(R5)、法人税法(R6)です
受験生時代は独学で勉強を進めました。
本稿では、会計人コース編集部のリクエストにこたえ、私の勉強法を書かせていただきます。
受験生の皆様の参考になれば幸いです。
まえさんの合格体験記はコチラ
独学にした理由
独学にした理由は、金銭的な面と時間的な面になります。
金銭的な面としては、当時の自分にとって取れるかもわからない資格に二桁万円ポンと支出するのはハードルが高かったです。
独学であれば、テキストの購入費用+αくらいで勉強を進めることができるので税理士試験を目指す初期段階としては始めやすかったです。
また、時間的な面としては、予備校のカリキュラム通りに勉強を進めていくことに不安があったことがあります。
仕事をしながらの受験となるため、平日に十分な勉強時間を確保することが難しく、であれば自分のペースで勉強を進めたいと思い、独学という方法を選択しました。
仕事との両立について
有給休暇を使用する以外は仕事の調整は特にしておりませんでした。
私は受験生である以前に社会人(会社員)でしたので、勉強したいから仕事を減らしてほしいというようなことはしていませんでした。
その代わり、前もって(試験日程が出たくらいから)「この日に試験があるのでいつからいつまでお休みいただけますか?」というような感じで有給休暇を取得して、直前期の勉強時間にあててました。
税理士試験を進めるにあたって職場との関係は良好に進められたと思ってます。
また、職場の人には税理士試験の勉強をしているのことを話してました。
もともと試験を受け始めたきっかけが、職場の先輩に誘いを受けたことだったので、どうせ後々噂が立つことなどを考えたら自分から話したほうがいいと思いました。
幸運にも、職場の方々も受験を応援してくださったので、それも自分のモチベーションの一つにはなりました。
ただ、話したといっても毎月「勉強どんな感じ?」というような感じではなく、大体申し込みくらいの時期に「今年何受けるの?」「あと何科目だっけ?」や、受験後に「試験どうだった?」、結果発表後に「今年は○○、合格しました」といった世間話程度の会話をするくらいでした。
私としても過度な期待を感じず、かつ科目合格したら自分のことのようにほめてくださったので官報合格を目指すモチベーションにもなりました。
モチベーション管理について
勉強と休憩のメリハリを意識
「勉強するときは勉強する」「休憩するときは休憩する」というメリハリを意識していました。
後述する隙間時間の話とも少し関連してきますが、机に向かって勉強する際に、いかに集中してできるようにするかということを意識していました。
勉強時間を記録できるアプリを使用し、日々の勉強時間を記録することで「今週はこれだけできた」とプラス方面で考えるようにしていました。
定期的にリフレッシュの時間を設ける
また、税理士試験の勉強は長丁場になるため、定期的にリフレッシュの時間を作っていました。
その際にも、「~~のせいで勉強時間が取れなかった」とならないように、リフレッシュの前日又は翌日に勉強時間をしっかりと確保するようにして必要以上に自分にプレッシャーをかけないようにしていました。
隙間時間は休憩時間にあてる
例えば「通勤中の電車内で理論マスターを使用し、理論暗記を進める」や、「移動時間に昨日覚えた理論の復習をする」といったように、隙間時間を活用されている方が多いと思います。
しかし、私はそういったことを計画に組み込むことは一切しませんでした。
隙間時間は基本的に「次の勉強時間に最大限集中するための休憩時間」にあてていました。
例外的に、どうしても気になってしまう場合にのみ、理論の復習をしたり、言い回しを確認したりすることにしました。
私としては、隙間時間に頑張るよりはONとOFFをしっかりと切り替えて勉強すべき時に最大限の集中力を発揮できるようにするほうが向いてました。
隙間時間を活用した経験は、法人税を受験した年に、会社の昼休憩を使って、理論暗唱をしていたことくらいでした。
「昨日より成長できたか」に注目
モチベーションの管理方法はたくさんあるかと思いますが、私は、昨日(過去)の自分と今日(今)の自分を比べて、自分ができるようになったことに注目するようにしてました。
内容としては「固定資産の減損処理ができるようになった」や、「CF計算書の作成ができるようになった」など自分ができるようになった問題を思い浮かべていました。
こうすることで「できる自分」をイメージしモチベーションを保つとともに、そのできるようになった知識を思い浮かべさらなる定着をはかることができました。
【後編】勉強計画と科目ごとのルーティン、本試験での作戦 に続く
(7月4日アップ予定)
〈プロフィール〉
まえさん@maesan0810
独学で毎年合格を積み重ね、令和6年官報合格。


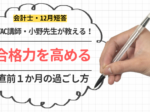

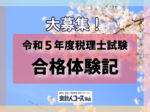
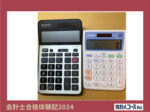
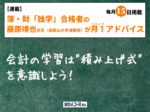







--150x112.jpg)

