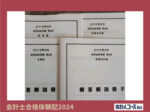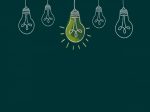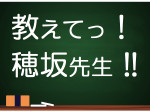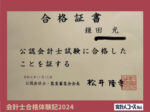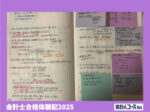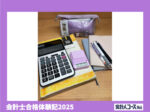佐々木大輔
(30歳)
〈受験情報〉
学習スタイル:CPA会計学院(通信)
▶トップ画像は佐々木さんが図書館に通うために2年半愛用したリュックサック(本人提供)
ゼネラリストではなく、固有のスキルが欲しい。「迷ったら厳しい道」会計士を目指す
私が公認会計士を目指したのは27歳のころでした。
それまでは工場の中で作業管理や製品の品質管理を担当していました。
いわゆるゼネラリストな生き方をしていましたが、コロナ禍で会社の業績が下がったことをきっかけに、自分の将来を不安視することが増えました。
私自身には固有のスキルが現状なく、会社が傾けば路頭に迷うかもしれない。どんな時代でも生きていけるような「固有のスキル」が欲しい。
そう考え退職した後、はじめはプログラマーになるための勉強をしていました。
勉強してから3か月がたったころ、知人からの勧めで会計士という職業の存在を知りました。
会計士は監査を独占業務としていること、また合格率が非常に低いことから「固有のスキル」として成り立ちそうでした。
また社会的評価も高いことで、将来のキャリア形成も広がりそうでした。
いわゆる3大国家資格、並大抵の努力では受かりません。
プログラマーの道を行くか、会計士か悩みましたが、迷ったら厳しい道を行こうと決断し、挑戦を決めました。
退職し、実家の宮崎県に戻って学習開始
予備校は最も合格実績が高いCPA会計学院を選択しました。
退職後は実家の宮崎県に戻っていたため、校舎がありません。
通信教育一択でした。
合格者の平均年齢は24歳。
当時27歳だった私は、なるべく早期の合格を目指し、2年超速習コースにはいりました。
CPA会計学院には様々なコースがあり、コースに合わせた勉強の日程表が配布されます。
例えば4月1週目は財務会計と管理会計、監査論を1コマ進めてください。
2週目は財務のテストがあるので受けてください、等。
基本はその日程表通りに進めていくことになります。
日程表通りに進めていけば特段問題は生じないのですが、授業が進むにつれ、私は計算科目が苦手だと判明しました。
計算科目を重点的に勉強したかったのですが、そうすると理論科目の勉強が遅れてしまい、日程表に遅れが生じてしまいます。
そこで、講師の受講相談を活用しました。
CPA会計学院では、電話やzoomで講師といつでも相談ができます。
受講相談では、「とにかく計算重視。理論科目は試験半年前から始めればよい」というアドバイスをいただき、計算強化に取り組めました。
その講師とはその後も頻繁に相談させてもらいました。
間違いなく合格の1ピースになったこと間違いありません。
図書館に通って毎日10時間勉強
先述の通り、私は通信教育だったので校舎に通って勉強ということができません。
そして自宅ではなかなか集中して取り組めません。
そこで活用したのが、付近にあった図書館です。
週に一度の休館日以外は毎日通いました。
開館前からシャッターの前に並び、閉館のチャイムが鳴ると同時に帰る、という生活を2.5年続けました。
図書館では勉強時間9時間を確保し、帰宅後も少し勉強しました。
帰宅後の勉強は通常期は1時間ほど、試験直前期は3時間ほど勉強しました。
図書館にはロッカーがないので、教材の持ち運びが大変でした。
現在はテキストも電子化されているので、タブレットがあれば持ち運びが楽ではあったものの、紙派の私は、どうしても現物のテキストを使いたかったです。
毎日10kgを超えるテキストをリュックに詰めて、図書館を往復していたので、そこもなかなか辛かったです。
10kg以上のリュックを背負い、雨の日も合羽を着て図書館に通いました。
逆に、図書館の閉館日は一切勉強しませんでした。
週に一度は休み、一日中ゲームをしていました。
今思うと、こういった息抜きも合格の一ピースであったことと思います。
具体的な学習方法
計算科目
計算科目については、講義を受けて内容を理解する→テキストの例題を解く→問題集を解く、が1セットです。
知識の忘却を防ぐため、上記の1セット後も3日後、7日後、14日後、と復習を繰り返すことになります。
そしてテストを受けて課題を把握し、弱点をつぶしていくという、王道の勉強を実施していきました。
理論科目
対して理論科目は少し邪道です。
授業を受けた後はひたすら問題集を回転させることに終始しました。
講師によっては推奨しない勉強法です。
しかし、私が頻繁に受講相談をしていた講師からは「その勉強方法でよい」と言っていただけたため、その方法で私は勉強していました。
この点は、人によって適性があるか否かで勉強方法が分かれるので、講師に受講相談をしてから勉強法は確立したほうがいいと思います。
失敗したこと
受験仲間を作らなかった、これが受験時代を思い返すと失敗です。
図書館で一人で勉強していたので、私にとって会計士試験は、孤独との戦いでもありました。
たびたびモチベーションが低下し、日によっては3時間とかで図書館を後にする日もありました。
特に、一回目の論文式試験の直前にやる気がロストしてしまい、直前期にもかかわらず1か月勉強しないこともありました。
もちろんその年は落ちています。
こんな時、周りに仲間がいればどうなっていたでしょうか。
仲間がまだ勉強しているから私も勉強する、ライバルの成績が良かったから私も勉強するなど、受験仲間がいたほうが勉強に対するモチベーションが維持しやすいように思えます。
地方で勉強していると、身近な勉強仲間は作りにくいです。
しかし今はSNSで人とつながれる時代。
そういった面でカバーできるので、使わない手はなかったように思えます。
最後に
この試験は並大抵の努力では受かりません。
だからこそ挑戦しがいがあり、合格した時の喜びは何にも表現できません。
迷っている方はぜひ挑戦していただきたいと思います。
そして、挑戦するとなると、周囲との協力は不可欠です。
自分の力だけで受かる人は一握りの天才だけです。
私の場合、実家に戻っていたので、食事や洗濯といった家事は家族がしてくれました。
27にもなって親に頼りっぱなしであることの情けなさはあったものの、合格してから恩返ししたいと思いながら勉強しました。
家族だけではなく、私の合格を支えてくれた講師の方々、勉強場所として活用していた図書館職員の方々、すべての人に感謝です。
ぜひ、皆様も感謝の気持ちをもって勉強してください。
その気持ちを強く持てば持つほど、勉強に対するモチベーションの維持につながります。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧