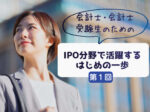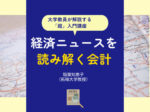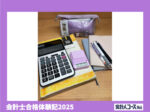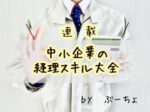【経済ニュースを読み解く会計】確実に儲かるとは限らない投資に、企業はどう意思決定するのか
- 2025/11/6
- コラム
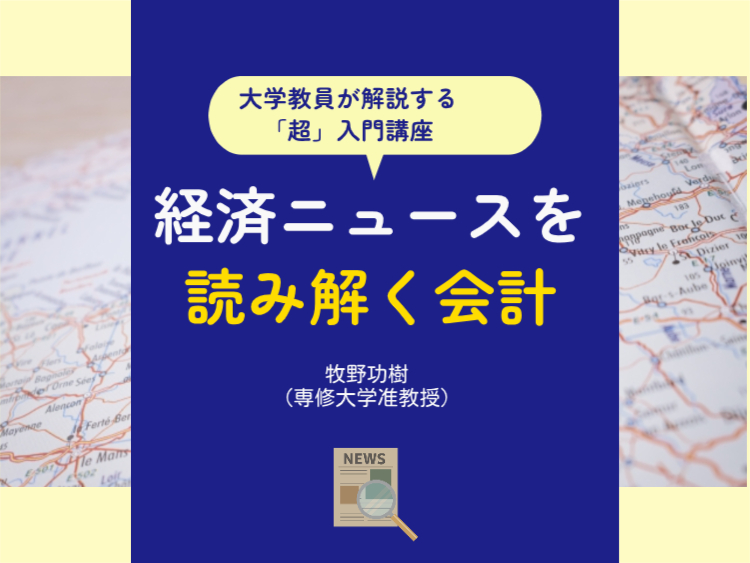
専修大学商学部・准教授 牧野功樹
【編集部より】
話題になっている経済ニュースに関連する論点が、税理士試験・公認会計士試験などの国家試験で出題されることもあります。でも、受験勉強では会計の視点から経済ニュースを読み解く機会はなかなかありませんよね。
そこで、本企画では、新聞やテレビ等で取り上げられている最近の「経済ニュース」を、大学で教鞭を執る新進気鋭の学者に会計・財務の面から2回にわたり解説していただきます(執筆者はリレー形式・不定期連載)。会計が役立つことに改めて気づいたり、新しい発見があるかもしれません♪ ぜひ、肩の力を抜いて読んでください!
はじめに―WBCがテレビで見られなくなるかも!?
みなさん、こんにちは! 専修大学で管理会計を教えている牧野です。
さて、2023年の「WORLD BASEBALL CLASSIC:WBC」での大谷翔平選手の活躍は記憶に新しく、多くの人が野球に関心を持つきっかけとなりましたよね。2026年には再び大会が開催される予定で、ファンの期待は高まっています。
WBCの開催が近づく中、「WBCの日本国内放映権をNetflixが独占的に取得する」というニュースが報じられ、驚いた人も多いのではないでしょうか。これまでテレビをつければ無料で観戦できたWBCが、配信サービスに登録しなければ見られないということを不便に感じるかもしれません。
今回はこのニュースを管理会計の視点で捉え、単なる放送形態の変化ではなく、不確実な投資案件の意思決定という題材として検討します。
跳ね上がるWBCの放映権料
放映権の取得は典型的な資本予算(Capital Budgeting)の題材です。過去大会の日本国内放映権料は報道によると30億円前後とされていますが、今回は150億円規模に跳ね上がると報道されています。
ただし、これはあくまで推定であり、実際の契約額は公式には明らかにされていません。ここで重要なのは、この契約額そのものが不確実である点です。30億円なら比較的容易に投資回収が可能ですが、150億円となれば損益分岐点は一気に高くなります。つまり、前提条件の不確実性自体が投資判断の大きなリスク要因となるのです。
不確実な投資へのシナリオ分析とは
管理会計では、こうした不確実性に備えて複数のシナリオ分析を行います。たとえば「100万人の契約者増なら損失、150万人増なら損益トントン、200万人増なら黒字」といったシナリオを設定します。その際には、①時間選好、②資本コスト、③リスクプレミアムを考慮し、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて、割引キャッシュ・フロー(Discounted Cash Flow:DCF)を計算し、投資全体の正味DCFの総額を計算する正味現在価値(Net Present Value:NPV)や、将来のキャッシュ・フローから逆算して得られる投資の実質的な利回りを示す内部収益率(Internal Rate of Return:IRR)をシナリオごとに求め、各シナリオの採算性を比較します。
さらに、不確実性が大きい場合にはモンテカルロ・シミュレーションなどの手法を用いて、獲得できるNPVの全体的な確率分布を明らかにし、投資結果のばらつきやリスクを定量的に判断します。こうして不確実性を前提に合理的な投資判断を行うことが求められます。
短期的な収益獲得v.s.ファンの拡大
WBCの主催者であるWorld Baseball Classic Inc.(WBCI)にとっても放映権は重要な意思決定の問題です。
前回までの大会と同様に地上波のテレビ局に売るという選択肢もあれば、Netflixのような配信サービスと独占契約を結ぶ方法もあります。これは代替案比較の問題です。地上波であれば契約額は低いかもしれませんが、全国放送による広告効果やファン拡大効果が見込めます。一方で、Netflix独占であれば短期的な収益は高くても、視聴者層が狭まりファン層拡大の効果は限定的です。
このように管理会計の視点で検討すると、単純な金額比較ではなく、戦略目標の達成度まで含めた総合的な評価が求められます。配信独占は既存の加入者や熱心なファンが能動的に見に行く仕組みであり、短期的な収益は見込めますが、潜在的ファンの開拓は難しくなります。一方、地上波放送は「たまたまテレビをつけたら放送していた」や「無料で見れるなら見てみようかな」という野球に興味のなかった層が視聴し、新たなファン層獲得の可能性を生みます。
非財務情報を業績評価に活用できるBSC
非財務的な長期成果を評価するために、管理会計ではバランスト・スコアカード(Balanced Scorecard:BSC)が用いられます。放映権料という短期的な収益だけでなく、野球ファンの増加という無形資産を築き、長期的な収益基盤を構築するという財務指標+非財務指標の両面で評価する視点が求められます。
投資は実行して終わりではありません。投資後には予算実績差異分析による事後評価が欠かせません。仮に新規加入者数が想定を下回った場合、それが外部要因(競合配信サービス、景気動向)によるものか、それとも内部要因(料金設定や宣伝不足)によるものかを分析します。
資本予算研究によれば、このような投資後の事後評価を実施する企業ほど、好業績を上げる傾向があることが示唆されています。投資後の事後評価は単なる結果確認にとどまらず、差異の原因を明らかにし、次の意思決定に反映させることが、戦略的管理会計の学習プロセスとして重要です。経営者が計画と実績の差異から原因を特定し、学びを得ることで、企業の持続的な価値創造が可能となります。
おわりに
多くの人がWBC放映権のニュースは「テレビで観られないのは残念」という側面で捉えたでしょう。しかし、管理会計の視点で見れば不確実な投資案件の評価という実践的な学びにつながります。
放映権料の不確実性、代替案比較、そしてファン拡大という非財務的成果という要因を組み合わせて総合的に検討し、最適な判断を導くことが戦略的意思決定の本質です。スポーツビジネスの世界でも管理会計思考が投資判断と戦略の質を左右することになるでしょう。
牧野功樹(まきの・こうき)
大学卒業後は銀行へ就職し、企業経営の現場について学ぶ。その後、大学院修士課程を修了し、釧路の短期大学で講師をしながら大阪府立大学の博士後期課程へ進学し、博士(経済)を取得。拓殖大学商学部助教・准教授を経て、現在は専修大学商学部准教授。専門は中小企業の管理会計、資本予算。詳細はウェブページから参照が可能。