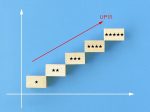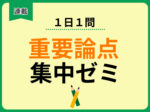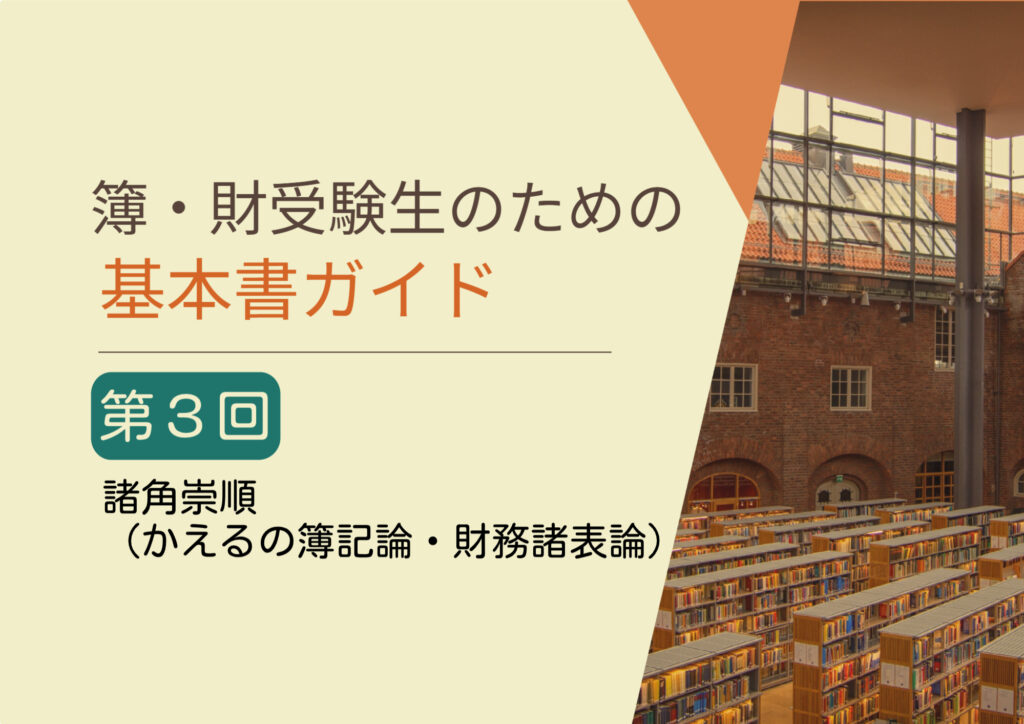
諸角崇順(かえるの簿記論・財務諸表論)
【編集部から】
税理士試験の“新年度”がスタートした9月は、比較的時間に追われず勉強に集中できる時期。
そんな時期だからこそ、腰を据えて「基本書」を読むこともできると思われます。
そこで、受験生時代に学習に「基本書」を取り入れられ、現在も「基本書」の活用を推奨されている、“かえる先生”こと諸角先生に、「基本書」の選び方・読み方を教えていただきました。
はじめに
さて、第1回では基本書の選び方、第2回では、基本書の読み方(使い方)について解説してきました。
最終回となる第3回では、具体的な書籍を紹介していきます。
入門レベル(基本書の基本書)
並木 秀明 著『税理士・会計士・簿記検定はじめての会計基準〈第2版〉』(中央経済社)

2020年7月8日発行 168ページ 2,090円(税込)
立ち読み ⇒ https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-35021-4
基礎レベル
井上 達男・山地 範明 著『エッセンシャル財務会計〈第5版〉』 (中央経済社)

2025年3月11日発行 416ページ 4,290円(税込)
立ち読み ⇒ https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-53231-3
佐藤 信彦・河﨑 照行・齋藤 真哉・柴 健次・高須 教夫 編著『スタンダードテキスト財務会計論Ⅰ 基本論点編〈第18版〉』(中央経済社)

2025年4月30日発行 542ページ 5,610円(税込)
ホームページ:https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-54271-8(立ち読みはなし)
佐藤 信彦・河﨑 照行・齋藤 真哉・柴 健次・高須 教夫 編著『スタンダードテキスト財務会計論Ⅱ 応用論点編〈第18版〉』(中央経済社)

2025年4月30日発行 550ページ 5,610円(税込)
ホームページ:https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-54281-7(立ち読みはなし)
中級レベル
辻山 栄子 編著『財務会計』 (中央経済社)

2025年2月4日発行 540ページ 4,950円(税込)
立ち読み ⇒ https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-52151-5
桜井 久勝 著『財務会計講義〈第26版〉』(中央経済社)

2025年3月27日発行 464ページ 4,290円(税込)
立ち読み ⇒ https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-53911-4
勉強とは別に・・・
一通りの学習が終わっていることを前提に、「勉強」としてではなく「教養」として会計を楽しみたい方はこちらがオススメです!
田口 聡志 著『財務会計の思考法』(中央経済社)

2025年4月10日発行 420ページ 4,290円(税込)
立ち読み ⇒ https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-53101-9
私は、日商簿記、全経簿記、税理士(簿記論、財務諸表論、法人税法)の講師をしたことがあるのですが、その中でも税理士財務諸表論の講師歴が最も長く30年近くのキャリアがあります。
そんな私が今でも何か新しい会計基準等を理解しようとするときは、最初に「マンガで分かる○○○○」、「○○○○ 入門の入門」といった細かい部分の説明が省略された、全体のイメージをつかむことがメインの本を手に取って、その理解する対象である新しい会計基準等の方向性やイメージをおおまかにつかみます。
これをせずいきなり全てのことを厳密に説明している書籍から入ると「木を見て森を見ず」になる可能性が高いからです。
つまり、何を言いたいかというと、友だちが薦めてくれたからといって自分には難しいレベルの基本書を見栄で選んだり、背伸びをして1ページ読み進めるのに30分も1時間もかかるような基本書を選んだりせず、自分の現時点の知識レベルに合った(もしくは少し簡単と思うぐらいの)基本書を選んでほしいということです。
最後になりますが、今回挙げた基本書は、
① 私が今まで読んだ基本書の中からセレクト
② 受験生レベルのもの
となっていることは知っておいてください。
もちろん、ここに挙げた基本書以外にも本当にすばらしい基本書はたくさんあります。
ぜひ、みなさんが自分の目で書店に並ぶ数多くの宝物からもっとも自分に合うであろう宝物を見つけてください。
おまけ~私が受験生のときの基本書
平松 一夫 著『基本会計学』(中央経済社)
この本は、下記の「おまけ②~私が新人講師の頃お世話になった基本書」を執筆された、「会計学の大御所」と呼ばれる方々のどの著書よりも「受験生」だった頃の私にはわかりやすかったです。
当時、平松先生は「大御所」ではなかったですが、本当にかみ砕いてわかりやすく書いてくださっていいました。
私のまわりの受験生仲間は、「自分に合った基本書か」ではなく、「著者が有名か」で選んでいて、私が資格学校で平松先生の『基本会計学』を開いていたら「誰やねん、それ?」とバカにしてきました。
けれど、「受験生」の私にとっては、平松先生の『基本会計学』が本当にわかりやすかったのです。
※ ちなみに、その後の平松先生のご功績を見れば、当時の私にはすばらしい先見の明があったことになります(笑)。
おまけ②~私が新人講師の頃お世話になった主な基本書
飯野 利夫 著『財務会計論』(同文館出版)
新井 清光 著『新版財務会計論』(中央経済社)
嶌村 剛雄 著『体系財務会計論』(中央経済社)
武田 隆二 著『最新財務諸表論』(中央経済社)
一方、受験生を卒業し講師になってからは「自分だけが理解できればいい」というレベルから「すべての内容をわかりやすく説明できるようにならないといけない」というレベルになったため、基本書を切り替えました。
「私にとってわかりやすい」から「多少専門的であっても少数説まで網羅してあって、受講生の方からのどんな質問にも耐えられるよう隅から隅まで正確な知識を得たい」というように得たい知識のレベルが上がりましたので、上記のような当時名著と呼ばれるものは片っ端から手に取り読んでいきました。
その中でも「新人」講師の私に合っていたのが上記の4冊でした。
「なつかしい」とおっしゃってくださる方がいれば、とてもうれしいです。
<執筆者紹介>
諸角 崇順(もろずみ・たかのぶ)
大学3年生の9月から税理士試験の学習を始め、23歳で大手資格学校にて財務諸表論の講師として教壇に立つ。その後、法人税法の講師も兼任。大手資格学校に17年間勤めた後、関西から福岡県へ。さらに、佐賀県唐津市に移住してセミリタイア生活をしていたが、さまざまなご縁に恵まれ、2020年から税理士試験の教育現場に復帰。現在は、質問・採点・添削も基本的に24時間以内の対応を心がける資格学校を個人で運営している。
ホームページ:「かえるの簿記論・財務諸表論」