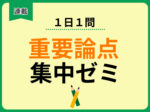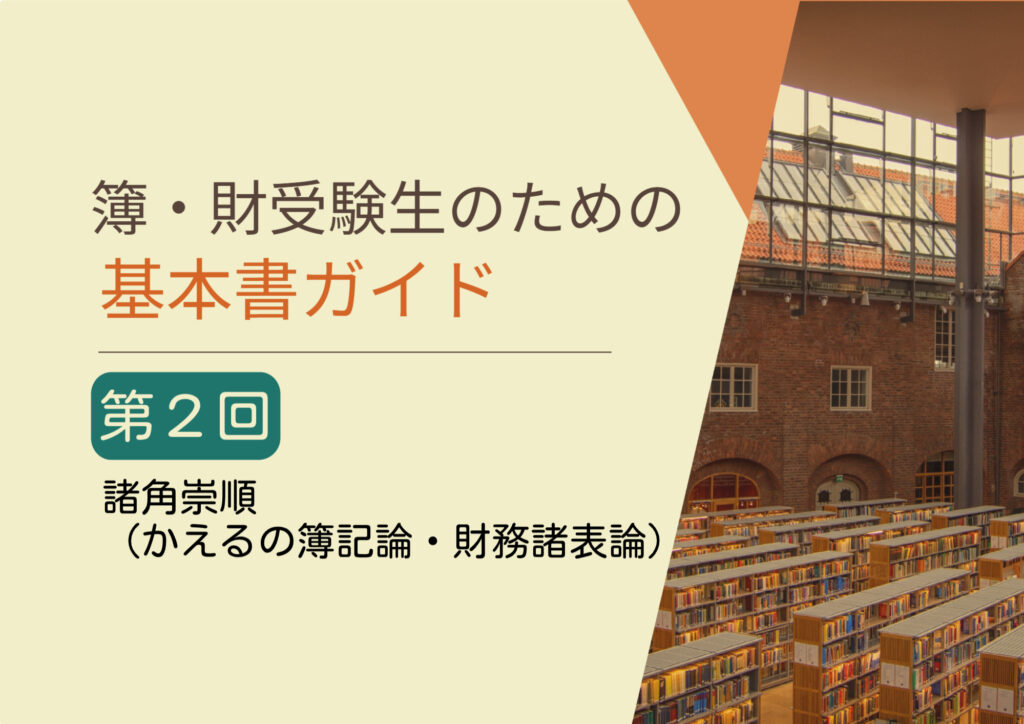
諸角崇順(かえるの簿記論・財務諸表論)
【編集部から】
税理士試験の“新年度”がスタートした9月は、比較的時間に追われず勉強に集中できる時期。
そんな時期だからこそ、腰を据えて「基本書」を読むこともできると思われます。
そこで、受験生時代に学習に「基本書」を取り入れられ、現在も「基本書」の活用を推奨されている、“かえる先生”こと諸角先生に、「基本書」の選び方・読み方を教えていただきました。
第1回はコチラ
基本書の読み方(使い方)は2つある
私が考える基本書の読み方(使い方)は2つあります。
以下で紹介していきます。
日々の学習において辞書代わりに(精読)
まず1つめは、日々の学習において辞書代わりに使う方法です。
授業を聴いてもなかなか理解しづらい論点に関して基本書を活用するのです。
講師は難しいことをわかりやすく説明するプロなのですが、受講生が100人いたとして、その100人全員が一瞬で理解してもらう説明ができることはまずありません。
受講生の方の会計学に対する習熟度が一律ではないからです。
講師は過去の経験で、もっとも多くの受講生が理解できた説明方法で授業を展開しますが、どうしてもその説明が合わない受講生も出てきてしまいます。
個別レッスンであれば、先生の説明を遮って「違う角度から説明してください!」と言えますが、学校形態の場合は、授業(一対多数の形態)であり、また、授業時間にも制約があるのでそうはいきません。
そんなときに役に立つのが基本書です。
資格学校の講師とは違った角度からの説明がされていることもありますし、また、時間の制約なくじっくり理解に努めることができるので、授業で理解できなかった論点であっても基本書の説明を読むことで理解できることがあるからです。
個々の論点に横のつながりを与える(通読)
次に、2つめの基本書の使い方は、個々の論点(点の知識)に横のつながり(線の知識)を与える使い方です。
1つめの基本書の使い方が「精読」なら、2つめの基本書の使い方は「通読」になります。
受験生の大多数は点の知識は多い(個々の論点の「丸」暗記はちゃんとできている)のですが、知識を一本につながった線の知識にできていません。
つまり、「理解を伴った」暗記ができていないため、テキストに書かれている内容の問題や過去に一度解いた問題であれば解答できるのだけど、ちょっとひねられた問題(いわゆる応用問題)や初見の問題だと途端に手が止まってしまうのです。
そこで基本書を「通読」することによって、点の知識を線の知識に変えていきます。
「精読」、つまり1ページ1ページを理解しつつ読み進めていくのではなく、「通読」、つまりできる限り短期間(例えば3日以内など)で一気に読み通します。
精読+通読が効果的な理由
この「通読」が効果的な理由は、何日間にもわたってゆっくりじっくり読み進めると、基本書の最後のほうにたどり着く頃には最初のほうで読んだ内容を忘れてしまい、知識の横のつながりに気付かなくなるためです。
読む際は、小説を読むような感じで分からない専門用語があったとしてもイチイチ調べたりせず、どんどん先へ先へと読み進めましょう(小説などを読む際は意味が分からない言葉があっても前後の文脈でなんとなくの意味を把握しますよね?
実は、このことも重要なことで、小説ではなく会計学においても前後の文脈で知らない会計用語の意味をなんとなくわかるようになる練習をしておくのです)。
これが、日々の勉強において辞書代わりに活用するときの「精読」ではなく、「通読」です。
そのようにある程度のスピード感とともに読み進めると、突然あることに気付きます。
「あれ?この論点、昨日読んだあの論点と前提は同じやん」「あ~、おとつい読んだ論点、この論点の理解があって初めて全体が見えてくるんだ」という感じです。
そして大事なことは、この「通読」を月1回(もしくは2ヵ月に1回)のペースで行ってほしいということです。
一度だけでの通読では気付かないつながりもあるでしょう。
例えば、お気に入りの映画があったとして、1回目の鑑賞では気付かなかったストーリーの伏線に2回目の鑑賞で気付くことはありませんか?
勉強も同じです。
繰り返すことでしか見えてこないものがあります。
1回目の通読では気付かなかったつながりが、ある程度学習が進み基礎力がついてきた時期、例えば5ヵ月後の5回目の通読で気付くこともあると思います。
基本書の繰り返しの通読で今まで見ることができなかった会計学の美しさに気付いてほしいと思います。
1つの論点を深く掘り下げる場合は、基本書のその論点が説明されたページのみを「精読」、会計理論のつながりをおさえたいときは基本書全体を短期間で「通読」。
この2つの使い方をうまく使い分けて、理解を伴った理論学習を行ってみてください。
<執筆者紹介>
諸角 崇順(もろずみ・たかのぶ)
大学3年生の9月から税理士試験の学習を始め、23歳で大手資格学校にて財務諸表論の講師として教壇に立つ。その後、法人税法の講師も兼任。大手資格学校に17年間勤めた後、関西から福岡県へ。さらに、佐賀県唐津市に移住してセミリタイア生活をしていたが、さまざまなご縁に恵まれ、2020年から税理士試験の教育現場に復帰。現在は、質問・採点・添削も基本的に24時間以内の対応を心がける資格学校を個人で運営している。
ホームページ:「かえるの簿記論・財務諸表論」