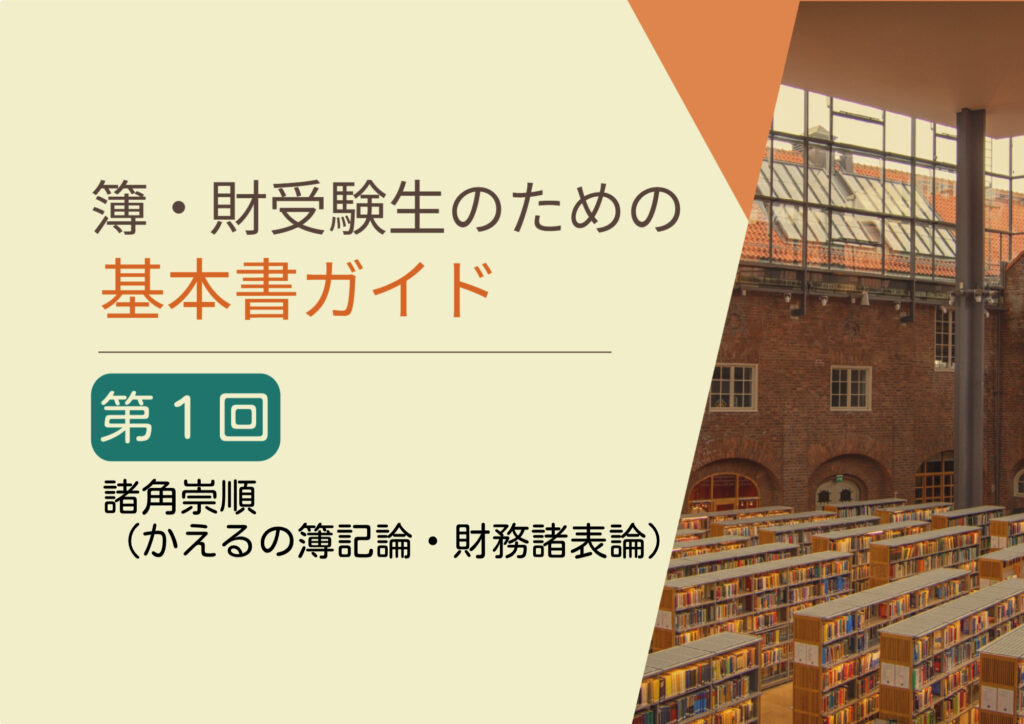
諸角崇順(かえるの簿記論・財務諸表論講師)
【編集部から】
税理士試験の“新年度”がスタートした9月は、比較的時間に追われず勉強に集中できる時期。
そんな時期だからこそ、腰を据えて「基本書」を読むこともできると思われます。
そこで、受験生時代に学習に「基本書」を取り入れられ、現在も「基本書」の活用を推奨されている、“かえる先生”こと諸角先生に、「基本書」の選び方・読み方を教えていただきました。
はじめに~誰かにとっての「わかりやすい」が自分に当てはまるとは限らない
簿記論・財務諸表論受験生の方(その他、いろいろな資格試験の学習されている方も)で、X(旧Twitter)等のSNSを活用されている方は多いと思います。
SNSでは、大先生とも呼べる大学教授(なんなら過去の本試験委員の先生も)や受験の先輩(合格者)たちが日々有益な情報を投稿してくださっています。
しかし、SNSでは字数制限があったりすることで、どうしても情報発信者が伝えたいと思っている情報の前提部分が省略されていたりします。
例えば「○○先生の『詳解!パーフェクト財務会計』(※架空の書籍です)の最新版、めっちゃわかりやすい!!!!」といった投稿などです。
仮にこの投稿をされた方が公認会計士試験短答式合格者だったとして(こちらはそのことを知らない)、これから簿記会計を学ぶ初心者の方がその投稿を読んで『詳解!パーフェクト財務会計』を購入し読んだとしたら・・・。
おそらく「なにこれ??専門用語ばかり使って説明が端的すぎ!!どこがわかりやすいの??」となると思います。ただ、先ほどの投稿をしてくださった公認会計士試験短答式合格者は何もウソなどついていないのです。
もうおわかりですよね?
ある程度の知識のある方にとっては、専門用語をかみ砕いて(悪く言えば、まわりくどく)説明してあるより、専門用語を使って端的に書いてもらった方が圧倒的にわかりやすいのです。
しかし、SNS等の情報は、その情報提供者の基礎スペックや簿記会計の知識レベルが通常示されていないため、情報の受け手であるみなさんと情報のミスマッチが起きてしまうのです。
よって、これから基本書を選ぼうという方は、決して他人のオススメを鵜呑みにするのではなく、大型書店や大学図書館等(市民図書館等では専門書の蔵書がほとんどないので)で実際に立ち読みしていただき、自分の目で自分の「今の」簿記会計の力に応じた基本書を選んでいただきたいのです。
基本書を選ぶステップ
ステップ1:出版社のホームページで刊行年やページ数をチェック
もう少し具体的に書いてみます。
(会計関連の資格に限らずどのような資格試験でもそうだと思うのですが)毎年のように法改正等が行われるため、発行から少しでも年数の経過した古い基本書を資格試験の勉強に使うのは非常に危険です。
よって、まずは今年もしくは昨年に出版された基本書に絞り込みましょう。
次にページ数がその資格の難易度に適した基本書を選びます。
例えば税理士試験の財務諸表論の場合は、300~500ページぐらいのものがよいと思います。これよりもページ数が少ないと受験レベルに耐えられないですし、逆にこれ以上のページ数だとオーバースペックになりかねないからです。
ここまでは各出版社のホームページ等で確認できますので、しっかり確認していったん対象を絞り込んでください。
ステップ2:書店や図書館で実際に手に取って見てみる
そして、次はできれば実際に書店や図書館に出向き、実際に自分の目でその絞り込んだ基本書全てに目を通し、下記のような感じで徐々に選択肢を絞り込んでいってください。
①「わかりやすそうな本」or「わかりにくそうな本」に分類
⇒ これはフィーリングでかまいません。要するに感覚的に「合う」「合わない」を見分けるだけなので、「イラストが多くてわかりやすそう」「カラーで見やすい」「仕訳がたくさん示されているからありがたい」「例題が多いから理解が早そう」などで選んでいただいて大丈夫です。
②次に、「わかりやすそうな本」とした基本書の同一論点を読み比べします。
⇒ 例えば、Aという基本書の「税効果会計」の章とBという基本書の「税効果会計」の章を読み比べする、ということです。このとき自分が苦手にしている論点で比べるとよいと思います(もし、日商簿記2級レベルの方が基本書を選ぶときは、未学習論点ではなく、日商簿記3級・2級で学習した論点、例えば、有価証券、有形固定資産などで比較するとよいと思います。)。
※ 注意点
実務家や経営者が書いたものは避けましょう。「受験」には適しません。合格してから読めば大丈夫です。
予算に余裕があれば…
予算に余裕があれば、基本書を2冊用意するとよいと思います。
1冊は、ここ数年(5、6年前のものでもOK)で出版された基本書で、かつ、ページ数が200ページ前後のもの。
いわゆる「基本書の基本書」的な感じの本です。
私は講師になって30年になるのですが、講師になってからも、まずは「基本書の基本書」で学ぼうとしている論点の「イメージ」をつかみます。
その後、2冊目として今回紹介した方法で探した「基本書」で細部を詰めていきます。
<執筆者紹介>
諸角 崇順(もろずみ・たかのぶ)
大学3年生の9月から税理士試験の学習を始め、23歳で大手資格学校にて財務諸表論の講師として教壇に立つ。その後、法人税法の講師も兼任。大手資格学校に17年間勤めた後、関西から福岡県へ。さらに、佐賀県唐津市に移住してセミリタイア生活をしていたが、さまざまなご縁に恵まれ、2020年から税理士試験の教育現場に復帰。現在は、質問・採点・添削も基本的に24時間以内の対応を心がける資格学校を個人で運営している。
ホームページ:「かえるの簿記論・財務諸表論」

















