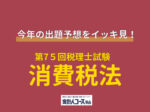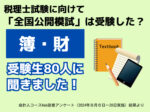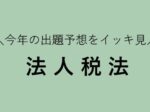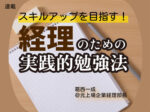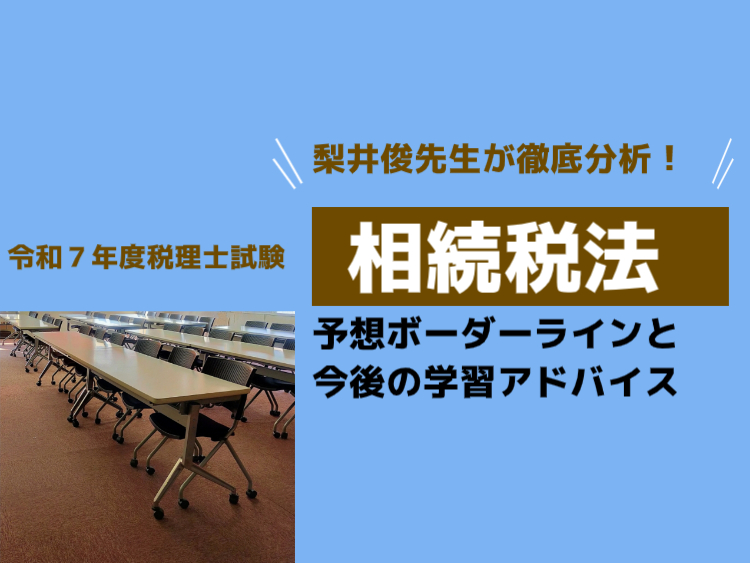
梨井 俊(税理士)
【編集部より】
2025年8月5日(火)〜8日(木)の3日間にわたり、令和7年度(第75回)税理士試験が実施されました。
そこで、本企画では、「簿記論」・「財務諸表論」・「法人税法」・「相続税法」・「消費税法」について、各科目に精通した実務家・講師の方々に本試験の分析と今後の学習アドバイスをご執筆いただきました(掲載順不同)。ぜひ参考にしてください!
はじめに
第75回税理士試験(相続税法)は、形式・難易度ともに近年まれにみる異例の構成で出題されました。
例年の「理論2題・計算1題」から、「理論1題・計算2題」への変更。
加えて、各問題における論点の深さと情報量から、実力者であっても、「書ききること」自体が難しい構造だったと言えます。
出題の特徴と難易度
問題の難易度も高く、特に以下の点において従来の試験水準を超えた複雑さが見受けられました。
1.理論問題の傾向変化
理論は事例形式で出題されましたが、問題文が長く、解答事項も法律条文ではなく、政令や質疑応答事例レベルの細かい内容についての解答が求められました。資料の読み込みと整理に時間を要する問題でした。
2.計算問題の複雑化
計算問題にも、従来の出題傾向に収まらない難しさがありました。問一ではひとつの財産評価に複数の論点の理解が必要であり、問二では国税庁の提供する自動計算式(エクセルのダウンロード)を用いるような複雑な計算を資料なしのノーヒントで解答させる問題もありました。また、過去の試験では避けられてきた「将来の相続に関する課税」(法改正により実際には施行されない可能性もある論点)の出題も含まれており、「正解にたどり着く応用力」よりも「できないところはできないと割り切る自己分析」が求められる問題になっていました。
3.本試験としての“適切さ”への問い
模範解答作成の場でも、講師陣の間でさまざまな意見が交わされました。
・解答要求が重複していないか?
・不足している情報次第では答えも変わらないか?
・13歳の放棄した孫に葬式費用を負担させることはあるのか?
・平成19年の非常に古い制度の知識を知っている人はいるのか?
など、多くの疑問があがったのも事実です。
合否を分けたポイント
このような“読み解き型”の試験において、合否の鍵となったのは以下の3点です。
1.時間配分:全体を見通し、難問に執着しすぎず、点が取れる問題に時間を割けたかどうか。
2.取捨選択:書ける問題・拾える部分を優先的に拾う、自己分析と相対化ができる冷静な戦略。
3.文語によるコミュニケーション能力:設問の聞き方を読み取り、聞かれたことに端的に・正確に・もれなく解答する力。
まとめると、知識の量だけではなく「どう使ったか」「どこで勝負したか」が明暗を分けた試験だったとも言えるでしょう。
今後の学習へのアドバイス
今回の試験傾向を踏まえ、次年度以降に向けて意識しておきたい学習として以下をおすすめします。大変かもしれませんが事実です。
基礎事項の早期定着と反復
→ できる問題を「誰よりも早く・正確に処理する力」は、最も大きな武器です。
→ 難問対策に偏らず、“確実に取る”基礎の地力を徹底的に磨きましょう。
国税庁ホームページ等の周辺資料に慣れておく
→ 質疑応答事例やQ&Aのような実務寄り・補足情報からの出題が近年増加傾向にあります。
→ 情報源の幅を広げ、情報検索とリテラシーの習慣をつけておくことが望まれます。
最後に──試験制度へのささやかな問い
普段はあまりこういった話はしませんが、今回の試験については言わせてください。
国税庁ホームページ「税理士試験の概要」(https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/gaiyo/gaiyou.htm)には、税理士試験の目的として「税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として行われます。」とあります。
私自身も過去の講評では難易度の差こそあれ、「しっかり積み重ねた人が順当に合格できる」と述べてきました。
しかし、今年の問題については「知識や知見の積み重ね」よりも「作問者に対する読みや運」に左右される側面が強く、努力がそのまま報われる試験ではなかったのではないかと、残念ながら感じています。
採点箇所や基準によって「しっかりと頑張った受験生が報われる試験ではあってほしい」と、合格発表まで願っています。
だからこそ、今年の受験生には、心からの敬意を伝えたいと思います。
難しさそのものではなく、120分間全力で向き合って書ききったこと。
そのこと自体が、みなさんの大きな力です。
【執筆者紹介】
梨井 俊(なしい・しゅん)
税理士
大手専門学校で相続税法の講師を務めるかたわら、月次顧問を主な業務とする開業税理士。大学受験の学習塾で英語講師を8年間務めた経験から、学習法や覚える仕組みを資格試験の勉強にもあてはめ、活用法や座学と実務の違いなど、積極的に情報発信も行っている。