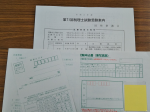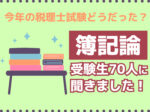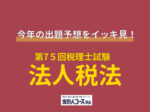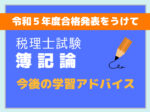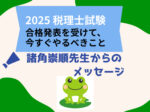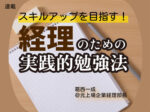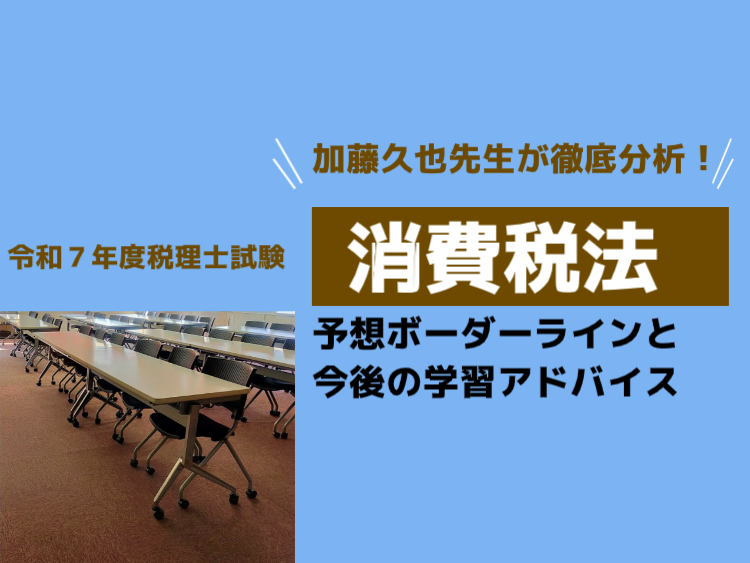
加藤 久也(税理士/名城大学大学院非常勤講師)
はじめに
受験生のみなさん、お疲れ様でした。近年の傾向通り、計算問題のボリュームが多かったため、いかに要領よく解答し、基本論点について正解できたかどうかが合格の決め手になったと思います。では、問題を振り返ってみましょう。
〔第一問〕の講評
第一問は、問1と問2の2問が出題され、どちらも事例問題が出題されました。
問1は、用語の意義を述べさせたうえで事例の取引がこれらに該当するか否かを問う問題と事例の法人の納税義務の有無について、規定の適用関係に触れながら説明する問題が出題されました。
問2は、課税売上割合に準ずる割合の規定について問う問題と事例についてその適用関係について解答させる問題が出題されました。各問題についてみていきましょう。
問1(配点35点)
この問は、消費者向け電気通信利用役務の提供を行う外国法人A社について、その役務の提供が消費税の課税対象となるか否かの判定と、A社の消費税の納税義務の有無について説明させる事例問題でした。
基本的項目であるため、十分に解答できたのではないかと思います。
(1)問題文に従い「資産の譲渡等」の意義(消法2①八)および「特定資産の譲渡等」の意義(消法2①八の二)を正確に記述する必要がありました。そのうえで、この取引が課税対象となるかどうかについて問われていることから、消費税の課税の対象は、消費税法4条1項により「国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れ」であることから、これに当てはまるかについて説明することなります。この事例では、①国内取引に該当するかどうか(消法4③三)、②事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するかどうか(消法2①八の三)、③特定資産の譲渡等(消法2①八の二)に該当するかどうかについて、定義に当てはめながらその判定について説明する必要がありました。
(2)A社の設立3期目の課税期間について、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定により納税義務が免除されるかどうかを、特定期間における課税売上高の特例(消法9の2)、新設法人の特例(消法12の2)の適用関係に触れたうえで説明することが求められる問題でした。A社は外国法人であることから、特定期間における課税売上高の特例の判定において、特定期間中に支払った給与等の金額による判定はできないこと(消法9の2③)、新設法人の特例の判定において、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、その事業年度について基準期間がないものとみなすこと(消法12の2③)を指摘し、正しく判定できるか否かを試す問題でした。
問2(配点15点)
課税売上割合に準ずる割合の適用について、事例に即して解答する問題でした。この問題も、基本的項目であるため、十分に解答できたと思います。
(1)課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の承認の効果について問う問題でした。
申請書を提出した日の属する課税期間の末日の翌日から同日以後1月を経過する日までに承認を受けた場合(消令47⑥)に該当することを指摘し、その申請書を提出した日の属する課税期間から適用されることについて、具体的に説明する必要がありました。
(2)仕入税額控除において、課税売上割合を使用するのは、①95%以上となるか否かの判定、②個別対応方式の計算のうち共通対応の課税仕入れ等の税額の合計額に乗ずる割合、③一括比例配分方式の計算で課税仕入れ等の税額の合計額に乗ずる割合の3か所ありますが、これらのうち、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合を使用するのは②のみです。この規定の適用関係について、事例で与えられた金額と割合を使いながら説明できるかどうかを試す出題でした。
〔第二問〕の講評
第二問(配点50点)は、8年続いた2問体制から久しぶりに1問体制となりました。
食料品製造業を営む法人の納付税額を計算する問題で、資料には製造原価報告書も与えられていました。納税義務の有無の判定は不要でしたが、調整対象固定資産の調整計算と居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の調整計算のある解答に時間を要する問題でした。では、ポイントとなる項目についてみていきましょう。
(1)【資料】(1)【損益計算書に関する付記事項】ハ「他勘定振替高」
甲社が製造した製品を贈答したものと廃棄したものについて他勘定に振り替えたものですが、両方とも販売目的で製造された製品であるため課税売上対応課税仕入れとして取り扱うため、特段区分して計算する必要はありませんでした。
(2)【資料】(1)【損益計算書に関する付記事項】ニ「役員報酬」「給料手当」
在宅ワークのため一人当たり一律に支給される通信費用の補助手当については、役員報酬および給料手当の一計算要素と考えられるため、仕入税額控除の対象とはなりません。
(3)【資料】(1)【損益計算書に関する付記事項】ホ「福利厚生費」
博覧会の入場チケットは、物品切手等に該当して課税の対象とされないため仕入税額控除の対象とはなりません。ただし、実際に役務の提供を受けた場合において、課税の対象となり引き換え給付を受けた事業者において課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります。
(4)【資料】(1)【損益計算書に関する付記事項】ト「旅費交通費」(ハ)
国内空港旅客サービス施設利用料については、国内線のみならず国際線を利用する場合においても、免税とはなりません。したがって、国内において行われる課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります。
(5)【資料】(1)【損益計算書に関する付記事項】ワ「雑費」(ホ)
その他の資料について、「課税仕入れに該当する金額1,237,054円」のうちに、「適格請求書発行事業者以外の者に対して支払った金額」880,000円が含まれているか否かについて判然とせず、どちらで解答しても、点数に影響しないように扱われるものと考えられます。
(6)【資料】(1)【損益計算書に関する付記事項】レ「不動産賃貸収益」(ロ)、同上ラ「固定資産売却益」(ハ)
建設協力金は、問題文にある通り前受賃料として賃貸借契約期間に応じて不動産賃貸収益に振り替えます。問題文に与えられた収入金額50,000,000円にはこの金額が含まれているため加減算する必要はなく、買主に引き継いだ180,000,000円についても消費税の課税対象とはならないため、計算に関係させる必要はありませんでした。
(7)【資料】(2)【製造原価報告書に関する付記事項】ホ「試験研究費」(ロ)
電子書籍および専門誌の電子版の購読費用については、電気通信利用役務の提供の対価の支払に該当します。いずれも「消費者向け」であることからリバースチャージの適用はありません。役務の提供者である国外事業者が適格請求書発行事業者ではないことから、仕入税額控除の対象とはなりません(消令平成30年改正令附則24)。
(8)【資料】(4)ハ
ビルBは、自己建設高額特定資産に該当することにより居住用賃貸建物として、仕入税額控除の適用を受けられないこととされます。ただし、「居住用賃貸部分以外の部分」と「居住用賃貸部分」とに建設費の比により合理的に区分しているとの文意から、取得時にこの区分を行い「居住用賃貸部分以外の部分」を仕入れ税額控除の対象としたと考えられます。この点については、問題文のはじめに記載されている【計算にあたっての前提事項】(5)によれば、「納付税額の計算に当たって・・・・・・納付税額が最も少なくなる・・・・・・方法を採用するものとする。」とあるため、取得時に区分しないほうがこの意図に沿うとも考えられます。いずれの解答をしても点数に差がつかない措置が取られるものと思います。
(9)納付税額の計算
項目の多さ、題意の読み取りの困難さから、すべてを解答することは難しかったと考えられます。このよう場合には、売上、仕入の分類、売上に係る対価の返還等に係る消費税額、貸倒れに係る消費税額、中間納付税額の計算を正しく示すことができたかどうかがポイントになると思います。
合格の決め手
つぎに合格の決め手について考えてみましょう。各設問の配点をつぎのように予想しました。
〔第一問〕50点
問1(1)20点、(2)15点とし、計35点。
問2(1)5点、(2)10点とし、計15点。
〔第二問〕50点
内訳
課税標準額に対する消費税額の計算まで 6点
仕入れに係る消費税額の計算まで 34点
仕入れに係る消費税額の調整 5点
納付税額の計算まで 5点
上記の配点予想を前提に合格の決め手について検討します。
〔第一問〕
問1は、配点35点中32点を合格点と予想します。
問2は、配点15点中13点を合格点と予想します。
第一問の合格点は合計配点50点中45点と予想します。
〔第二問〕
第二問の合格点は合計配点50点中30点と予想します。
したがいまして、第一問、第二問合計で75点を合格予想得点とします。
おわりに
本年度の試験問題は、第一問では、基本的な項目について問われ、解答しやすい出題だったと思います。
一方、第二問は、1問体制となったものの依然として問題量が多く、納付税額まで解答を終えることが困難な分量の出題でした。
特に第二問の作問において、実務上迷う項目について積極的に出題する意図はうかがえるものの、問題文を一意に理解できない箇所があったことは残念でした。
第一問を「書けるものをすべて書く」のではなく、外せない項目に絞って解答を作成し、最大45分程度で手早く切り上げ、残りの時間を第二問に配分できたかどうかが、合格の決め手となったと思います。特に理論の解答においては、模擬試験で培った「捨てる勇気」を持てたかどうかがカギになったのではないでしょうか。
ここまで、本試験の問題について講評し、合格の決め手について考えてきました。
しかし、税理士試験の正解及び詳細な配点は公表されないため、あくまでも私個人の検討に過ぎないことをお含みの上お読みください。大手専門学校からは模範解答と詳細な予想配点が公表されるものの、受験生のみなさん自身が答案用紙に書いた答案を正確に復元することは難しく、自信のない箇所を不正解として保守的に自己採点すると、実際の得点よりも低い点数となります。
その結果、合格予想得点やボーダーラインに届かず、がっかりされることも多いと思います。では、模範解答を確認すること、自己採点することは無意味なのでしょうか。
合格確実ラインやボーダーラインに届いていなくても、どの程度の点数が取れたかと、講評や模範解答で「基本的な項目」「簡単な内容」とされた箇所について正解できたかどうかで、次の行動すなわち次の科目へ進むのか、同じ科目の勉強を再度行うのかが変わります。
税理士試験の合格するためには、現実をしっかり受け止め、次の行動に活かすことが大切です。
最後になりましたが、受験されたみなさんに吉報が届くことを願っています。
本当にお疲れ様でした。
<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)
税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒業。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。