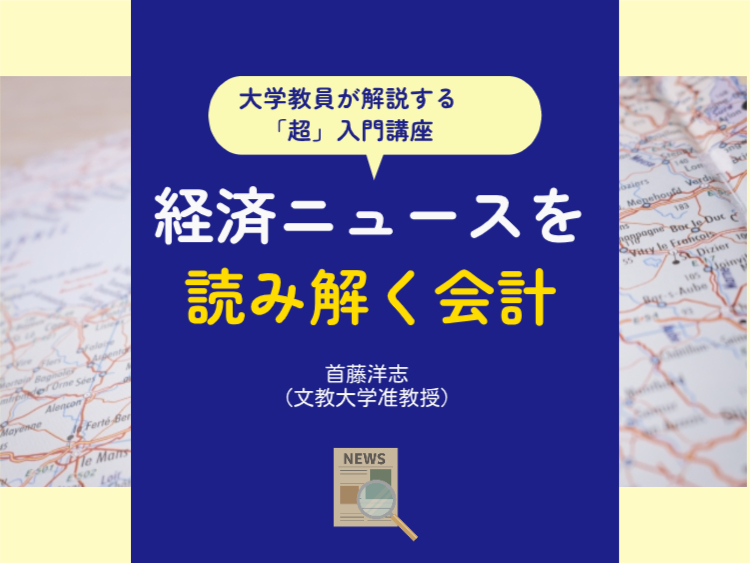
【編集部より】
話題になっている経済ニュースに関連する論点が、税理士試験・公認会計士試験などの国家試験で出題されることもあります。でも、受験勉強では会計の視点から経済ニュースを読み解く機会はなかなかありませんよね。
そこで、本企画では、新聞やテレビ等で取り上げられている最近の「経済ニュース」を、大学で教鞭を執る新進気鋭の学者に会計・財務の面から2回にわたり解説していただきます(執筆者はリレー形式・不定期連載)。会計が役立つことに改めて気づいたり、新しい発見があるかもしれません♪ ぜひ、肩の力を抜いて読んでください!
首藤洋志(文教大学経営学部・准教授)
こんにちは、文教大学の首藤洋志です!
今回のコラム(第2弾)では、2024年に井上慶太先生(東京経済大学)がご執筆された、非財務情報に関するコラムとも関連する、サステナビリティ(sustainability: 持続可能性)について考えてみましょう。
サステナビリティとは?
国際的に、サステナビリティの定義や概念は、様々な文書において説明が行われてきました (金融審議会、 2022) 。
例えば、国際財務報告基準(IFRS)S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」によれば、「サステナビリティの概念は「持続可能な開発」と結び付けられることが多い」 (BC42)とされています 。
「持続可能な開発」は、1987年に、国際連合の環境と開発に関する世界委員会によるブルントランド報告書によって「将来の世代が自身のニーズを満たす能力を損なうことなしに、現在のニーズを満たす開発」と定義されました (United Nations、1987、 Chapter 2、par. 1) 。
日本では、例えば、コーポレートガバナンス・コード (東京証券取引所、2021、8頁) やスチュワードシップ・コード (スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会、2020、5頁) において、サステナビリティの概念は「ESG(注1) 要素を含む中長期的な持続可能性」と定義されています。
(注1)Environment(環境)、Social(社会)、そしてGovernance(ガバナンス)の頭文字からなる言葉。近年、ESG投資といった文脈でよく使われるようになりました。
サステナビリティ情報の開示と保証
このように、長い間、国際的に議論されてきたサステナビリティの考え方や概念は、会計・監査実務の中で、ホットトピックの1つになっています。
つい最近も、サステナビリティ関連情報の開示(非財務情報の開示などともいわれます)に関連する「サステナ開示義務化、「全プライム対象」は見送り 金融庁」というタイトルの新聞記事(注2)を目にしました。
(注2)2025年7月8日、日本経済新聞朝刊。
この記事を簡単に要約すると、次のようになります。
<新聞記事の要約>
2027年3月期から始まるサステナビリティ情報の有価証券報告書における開示について、時価総額が一定額未満の東証プライム上場企業は、義務化を見送ることになった。
サステナビリティ情報の開示の一例として、気候変動リスクに対する戦略の開示(気候変動対応)や、女性管理職比率、男女間の賃金格差といった一部の人的資本に関する開示(人的資本・多様性)が挙げられる。
日本では、時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期、1兆円以上3兆円未満の企業は2028年3月期から開示が義務化される。国際的には、「公的説明責任のある企業の全てまたは大半」に当該開示を求める動きがある中で、日本の企業からは「負担が重い」という意見も出ている。プライム上場企業でも、規模によって、開示(新しい実務)に対応できるリソースに差があることなどを金融庁は考慮したとみられる。
このような動きは、企業の財務報告に関する重要な媒体の1つである「有価証券報告書」等における非財務情報の重要性が高まり続けていることを意味します。
企業における財務報告の範囲の拡張とも捉えられる(開示)実務の変化は、「有価証券報告書」等の開示内容をチェックする、公認会計士による会計監査にも影響を及ぼします。
また、企業のサステナビリティ情報開示に関して、国際的な比較可能性の観点から考えてみると、「どのようなサステナビリティ情報を開示するのか」、「その開示内容はどのようなことを意味するのか」、「その開示内容については誰が保証するのか」、といった議論も重要です。
サステナビリティ情報の開示を巡る実務の変化は、今後さらに、会計関連資格の試験問題でも、直接的・間接的に取り上げられていくことが予想されるでしょう。
サステナビリティとパーパス(経営)
昨今、組織のパーパス(一般に、存在意義を意味します)が注目されています。
近年、企業は(株主のための)利益を追求するのみならず、すべてのステークホルダーにとっての社会的な利益を重視することが求められる時代になっています。
その結果、企業は自らのパーパス(存在意義)を掲げ、サステナブルに社会貢献していく姿勢を見せていくことが求められているのです。
サステナビリティ情報の開示に対する関心の高まりと、パーパス(経営)に対する実務・学術的な関心の高まりは、相互に共鳴し合っているのかもしれませんね。
監査法人や一般事業会社への就職を考える際には、興味のある組織のサステナビリティへの取組みやパーパスにも目を向けてみてはいかがでしょうか?
以下に、サステナビリティ情報とも大きく関係する「パーパス(経営)」に関するおすすめの書籍をいくつか紹介するので、勉強の休憩時間にでも手に取ってみてください!
きっと社会(世の中)の動きがこれまで以上に見えてくるはずですよ。
<パーパス経営に関するおすすめ書籍>
名和高司 (2021) 「パーパス経営―30年先の視点から現在を捉える―」東洋経済新報社。
Gulati, R. (2022) Deep purpose: The heart and soul of high-performance companies, Great Britain: Penguin Business.(山形浩生訳 (2023) 『DEEP PURPOSE―傑出する企業、その心と魂―』東洋館出版社)
Serafeim, G. (2022) Purpose + profit: How business can lift up the world, Canada: HarperCollins Leadership.(倉田幸信訳 (2023) 『パーパス+利益のマネジメント』ダイヤモンド社。)
将来における会計・監査の意義
最後になりますが、会計や簿記の勉強に頑張って取り組んでいるあなたは、もしかすると、生成AIなどの議論を耳にする中で、将来に対する漠然とした不安を抱えているかもしれません。
しかし、本コラムの議論を踏まえれば、会計・監査実務の社会的な重要性(存在意義)は持続的に高まるといっても過言ではないでしょう。それに伴い、広く会計に関連する学問やスキルは、これからの社会でなくなるどころか、ますますその存在意義が高まっていくと私は思っています。
社会で求められる情報に変化が生じるとき、そのプロセスや手段、ひいては概念そのものものも変わっていく可能性があります。
しかし、会計はその変化の中においても、いわゆるアンカーのような重要な役割を担いうる知識体系だと、私は考えます。
1人の人間として、社会の中でこれから求められるモノやコトに注意を払いながら、今できること(取り組むべきだと思っていること)に、全力で取り組み、挑戦し続けてください!
応援しています。Good luck!!!
<参考文献>
金融審議会 (2022) 「ディスクロージャーワーキング・グループ報告―中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて―」令和4年6月13日。
スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会 (2020) 「「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫―投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために―」。
東京証券取引所 (2021) 「コーポレートガバナンス・コード―会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために―」。
United Nations (1987) Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Brundtland Report. URL: https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html(最終アクセス:2025年7月31日).
<執筆者紹介>
首藤 洋志(しゅとう ひろし)

文教大学経営学部准教授。公認会計士。
九州大学経済学部卒、博士(経済学・名古屋大学)。
2011年~2020年:公認会計士として監査業務に従事。
2020年~:大学教育及び財務会計・監査研究。
<主な論文>
「サステナビリティとパーパス経営―人的資本を中心とした会計学研究からのアプローチ―」『経営教育研究』2025年, Vol.28, 51-61頁(単著)。
「大手監査法人のダイバーシティ実現と公認会計士の人事業績評価における課題」『国際会計研究学会年報』2024年度第1号, 31–58頁(共著)。
“Impact of Voluntary IFRS Adoption on Accounting Figures: Evidence from Japan” Accounting, Economics, and Law: A Convivium, 2023, pp. 1–55(共著).
著者情報の詳細は、こちらよりご覧ください!




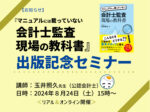
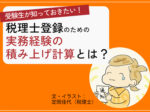
-150x112.jpg)










