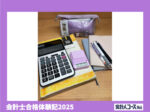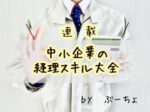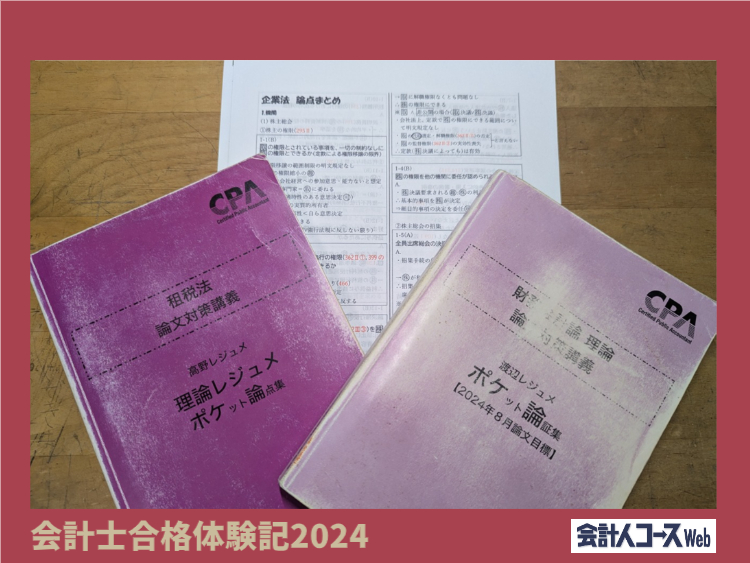
Y.N
(22歳、慶應義塾大学4年)
〈受験情報〉
学習スタイル:CPA会計学院(通学)
電卓につられてCPAの入門講義を受けるも、会計学に魅せられる
私が会計士を目指すきっかけとなったのは、大学の最寄り駅で配られていたCPA会計学院の簿記3級無料入門講義のチラシでした。
そのチラシには、「講義を受けると電卓がもらえる」と書かれていて、当時の私は特に深い考えもなく、その特典に惹かれて講義を受講することにしました。
しかし、実際に講義を受けると、簿記や会計の仕組みに触れる中で、数字を使って物事を整理し、企業の活動を可視化する会計学の魅力に気づきました。
単なる「電卓目当て」で始めた講義が、私にとって学ぶことの楽しさを教えてくれるきっかけとなったのです。
その後、さらに会計学を深く学びたいという思いが芽生え、将来のキャリアとして会計士を目指すことを決意しました。
専門的な知識を活かして多くの人や企業を支えたいという目標を持ち、資格取得に向けた勉強を本格的にスタートさせました。
この経験が、私の人生における大きな転機となりました。
各教科の勉強方法
続いて、各教科の具体的な勉強方法について書きたいと思います。
財務会計論
財務会計論(計算)はレギュラー講義を受講し、テキストを中心に勉強しました。
テキストの例題は人に完璧に説明できるレベルまでやりこみ、連結会計や企業結合会計はタイムテーブルを使わずに仕訳で解けるようにしていました。
短答式試験対策のアウトプットには短答対策問題集を試験まで10回ほど回転し、答練で時間配分などの対策をしていました。
論文式試験対策にはテキストで計算力を維持し、答練でアウトプットをしていました。
財務会計論(理論)はテキストで講義を受け、短答式試験前にコンパクトサマリー(コンサマ)に情報を集約し回転していました。
短答期のアウトプットはWeb問題集を通学時や寝る前に行い、間違えた部分をコンサマへメモするのを繰り返し行いました。
論文期はテキストやコンサマは一切使わず、論文対策集だけを使用していました。
CPAが論証につけたランクは気にせず、会計基準ごとに勉強の緩急をつけていました。
収益認識に関する会計基準は実務でも活きそうと思っていたので、監査法人が出版している実務書を一冊読み、そのおかげでCランクレベルの問題でも満点が取れるようになりました。
管理会計
管理会計はテキストの例題だけを回転し、短答も乗り切りました。
論文期は例題で計算力を維持し、答練で試験慣れをしていました。
管理会計は下書きの固定化が計算の上達・迅速化につながると考えていたので、それを意識して学習を進めていました。そのおかげで、答練で何度も1桁順位をとることができました。
企業法
企業法は短答期はコンサマを回転し、論文期は自作の論証集と条文マップ、法令基準集を使い、条文の位置や使い方を身に付けました。
監査論
監査論は短答・論文期ともにテキストを中心に勉強していました。
監査論で重要なのは自分が今勉強しているのは監査のどの時期なのかを意識することと講師がおっしゃっていたので、監査の俯瞰図をテキストの隣に置きながら勉強を進めていました。
租税法
租税法はポケット論点集を中心に計算・理論を勉強していました。
理論は条文の場所だけを暗記し、試験中にその場で考えて書き写すことで暗記量を減らしていました。
経営学
選択科目は経営学を選択し、コンサマを回転していました。
キーワードを中心に暗記し、論述は答練で出てきた重要なもののみを暗記し、基本は覚えたキーワードをつなぎ合わせてその場で文章を作れるようにしていました。
その他
答練の回転・解きなおしは、論文の財務会計論(計算)と租税法だけ行い、それ以外は解き捨てしていました。
また、計算科目については、勉強方法を大きく二つに分けていました。
財務会計論(計算)と租税法は何度も同じ問題を解き、高回転を意識していました。
一方で、管理会計と経営学は何度も問題を解くというより、1回深く理解することを重視していました。加えて、全科目下書きは保存し、ある程度回転した後は下書きを見るだけにし、回転率を上げていました。理論科目の論証の暗記は、原文があるものは一字一句丸暗記、それ以外はキーワードだけ覚えてうまくつなげるか法令基準集を使うことにより、できるだけ暗記量は減らすようにしました。
以上の勉強をした結果、短答式試験はボーダー+5%で合格、論文式試験は総合16位で合格し、全教科得点率60を超えることができました。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧


-003-150x112.jpg)