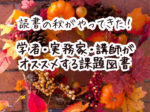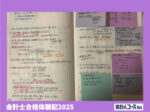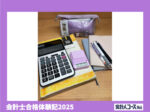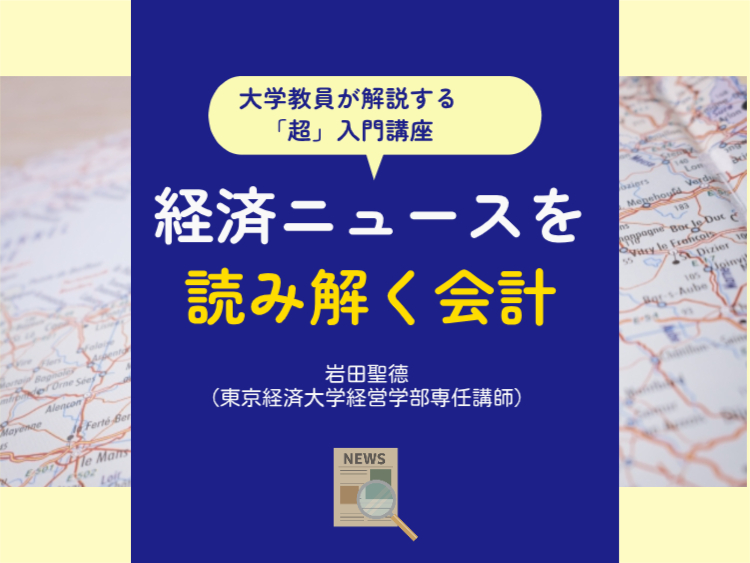
岩田聖德(東京経済大学経営学部専任講師)
【編集部より】
話題になっている経済ニュースに関連する論点が、税理士試験・公認会計士試験などの国家試験で出題されることもあります。でも、受験勉強では会計の視点から経済ニュースを読み解く機会はなかなかありませんよね。
そこで、本企画では、新聞やテレビ等で取り上げられている最近の「経済ニュース」を、大学で教鞭を執る新進気鋭の学者に会計・財務の面から2回にわたり解説していただきます(執筆者はリレー形式・不定期連載)。会計が役立つことに改めて気づいたり、新しい発見があるかもしれません♪ ぜひ、肩の力を抜いて読んでください!
こんにちは、東京経済大学の岩田聖德です。
前回は株主総会の話をしたので、今回はバランスを取って(?)株式の売買をテーマにコラムを書いてみます。最近では、2024年末時点で国内の資産運用会社の運用資産が1,000兆円近くまで増加したというニュースがありました(日本経済新聞「アセマネの運用資産、2024年末に999兆円 株高で」)。新NISA(少額投資非課税制度)が始まり、個人投資家の資金流入があったことも増加に寄与したようです。本コラムを見ていただいている読者の中にも、新NISAをきっかけに投資にチャレンジした方が沢山いらっしゃるのではないでしょうか。
実は、会計・ファイナンス領域の学術研究では、「個人投資家」に着目した研究が一定数存在します。今回はそれらの知見の一部をご紹介したいと思います。
平均的な個人投資家は会計情報を見ていない?
皆さんは、株式投資家は会計情報を使っていると思いますか?
いきなり何をまた当たり前のことを、と思われるかもしれません。財務会計の概念フレームワークを見ても、投資家にとっての意思決定有用性が財務報告の目的として明言されているじゃないか、と。
それはそうなのですが、投資家が実際に会計情報を使っているかどうかは、理屈がどうかというよりは実証的な問題ですよね。実は、過去の実証研究の分析結果を見ると、個人投資家が会計情報の内容を無視するかのような取引行動を取っていることが示唆されています。
投資アプリのデータを利用した最新の研究結果を見てみよう
最新のエビデンスを紹介します。
米国パデュー大学のミッシェルズ准教授の研究では、Robinhoodという投資アプリのデータから、同アプリを利用する個人投資家の売買行動が分析されています(Michels(2025))。
一般に実証会計研究では、ある企業の利益が市場の期待していた値よりも大きければポジティブ、小さければネガティブなニュースだと想定します。特に、分析能力の高い投資家で構成される効率的な市場では、利益ニュースが出たときにはその良し悪し(とその程度)に従って株価が瞬時に反応し、その後は価格推移が安定すると予想されます。これは「効率的市場仮説」と言われています。
個人投資家が気にするのは「極端なニュース」!?
Michels(2025)で報告された個人投資家の売買行動は、このストーリーとは異なるものでした。Robinhoodユーザーの多い銘柄では、ニュースの良し悪しにかかわらず、極端なニュースがあった場合にユーザーの銘柄保有が増加するという現象が報告されたのです。ここでの極端なニュースとは、大幅な利益サプライズや、決算発表による株価の大幅な変動を指します。
重要なのは、決算の良し悪しにかかわらず関心を引くような極端なニュース・株価変動を見て買い注文を入れるという行動が見られることです。Michels(2025)では、これを個人投資家によるattention-driven trade(関心主導型取引)と呼んでいます。決算ニュースそのものの情報内容に従った取引ではない、という意味ですね。
効率的市場仮説と合わない現象も
また、小型株や空売りの困難な銘柄に絞ってみると、極端なニュース・株価変動に反応したRobinhoodユーザーの買い注文によって株価がズルズルと上がるという現象も観察されています。これは、理論的には決算発表直後に株価が安定すると言われてきた効率的市場仮説とは整合しない現象です。
なお、Michels(2025)はRobinhoodがもたらす社会厚生への影響について結論を出しているわけでも、投資アプリを批判しているわけでもないので、その点は中立的に解釈する必要があります。
何が個人投資家による会計情報の活用を妨げているのか?
公開情報をうまく活かしきれない「情報処理コスト」の存在
「なぜ個人投資家が会計情報そのものを無視しているように見えるのか?」という点について仮説を提示した研究としては、ワシントン大学のブランクスプール教授らの研究(Blankespoor et al.(2019))が挙げられます。同論文では、知覚(Awareness)コスト、取得(Acquisition)コスト、統合(Integration)コストの3つを総称して、情報処理コスト(Information processing costs)という概念を導入しています。
簡単に言えば、情報が公開されていたとしても、財務諸表利用者がそれを意思決定に反映できているとは限らないという議論です。情報の存在に気付かないこともある(知覚コスト)し、データを収集する作業が煩雑すぎて使えないこともある(取得コスト)し、投資意思決定に示唆のある分析結果を得られないこともある(統合コスト)でしょう。
Blankespoor et al.(2019)では、AP通信の自動生成記事で企業の決算情報が取得できるようになったタイミングを、AwarenessおよびAcquisitionのコストが突然小さくなったイベントと仮定して実証分析を行っています。
同論文のアイディアは以下のとおりです。
決算発表に気づいていない投資家がAP通信の決算情報記事を見て取引を行うのなら、それは知覚コスト(決算発表に気づかないこと)が問題となって会計情報が無視されていたことを意味します。くわえて、AP通信の記事にはアナリスト予想のコンセンサス情報が含まれる記事とそうでない記事があるのですが、投資家の取引行動がそれぞれの記事で異なるのであれば利益関連情報の取得コストが問題であったことが示唆されます。
通常、会計利益は他の情報(定性情報や市場の「期待値」)とセットでないと適切に解釈するのが困難なものですが、それらの情報の追加取得にはコストがかかるだろうという発想です。
「投資家は会計情報を活用している」前提を疑ってみると…
Blankespoorらの研究結果は、AP通信による生成記事の公開前後で対象銘柄の利益と株価反応の関係に有意な変化が見られないというものでした。知覚コストおよび取得コストのいずれも、「個人投資家が会計情報を無視して取引を行う」という行動を説明する重要な要因とはいえないのかもしれません。
Blankespoorらの議論によれば、残された原因は統合コストの高さか、心理的なバイアスのいずれかということになります。
前者は、企業価値評価モデルに会計情報を織り込んでアウトパフォームすることが極めて困難であるために、個人投資家が会計情報を使わない取引戦略を合理的に選択しているという見方です。
後者は、本来的に会計情報が有用かつ平易に活用できるにもかかわらず、特定の有名な取引戦略に過剰に依拠しているという見方です。
今回紹介したような研究結果を踏まえると、「株式投資家は会計情報を適切に活用している」という言明も、当たり前とはいえないのかもしれません。そうした株式市場の実態を踏まえて何を考えるのかはプレイヤーごとに異なると思いますが、立ち止まって考えてみると興味深いテーマの1つに思えます。
【参考文献】
Blankespoor, E., Dehaan, E., Wertz, J., & Zhu, C. (2019). Why do individual investors disregard accounting information? The roles of information awareness and acquisition costs. Journal of Accounting Research, 57(1), 53-84.
Michels, J. (2025). Retail investor trade and the pricing of earnings. Review of Accounting Studies, 30(1), 575-610.
<執筆者紹介>
岩田 聖德(いわた・きよのり)
2022年3月一橋大学大学院経営管理研究科にて博士(商学)を取得し、東京理科大学経営学部助教を経て、現在は東京経済大学経営学部専任講師。専門はディスクロージャー・コーポレートガバナンス。Webページはこちら。
【主な論文等】
Fujitani、 R.、 Iwata、 K.、 & Yasuda、 Y. (2024). How does stock liquidity affect corporate cash holdings in Japan?: A pre-registered report. Pacific-Basin Finance Journal 83、 102205.
Iwata、 K. (2024). Earnings quality and voting shareholders’ reliance on earnings information: evidence from the top executive director election in Japan.
岩田聖徳(2021)「機関投資家による議決権行使結果の個別開示と社外取締役の選任」『経営財務研究』41(1・2)、2-20.
『財務・非財務報告のアカデミック・エビデンス』(共著、中央経済社、2025年)