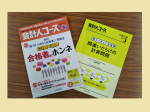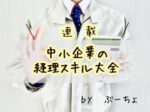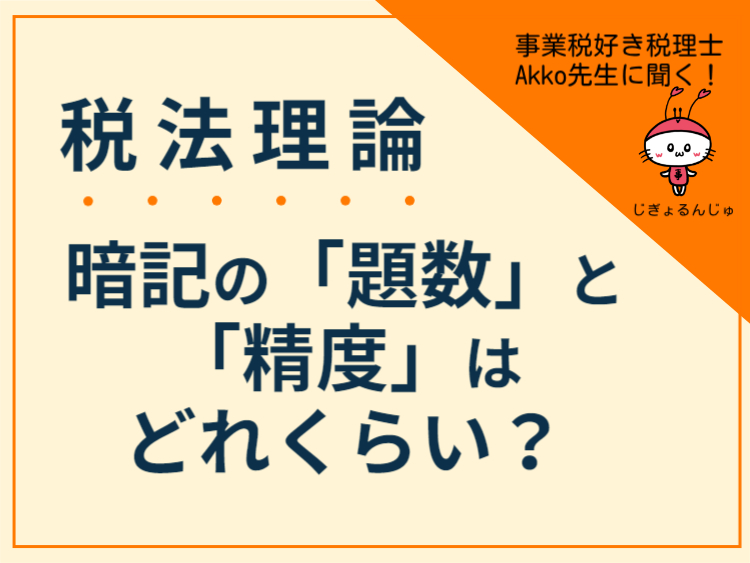
事業税好き税理士Akko
【編集部より】
いよいよ、模試が本格化する時期になりました。税法受験生にとっては、理論暗記の量を増やし、質を高めて、得点に結び付けたいところです。その一方で、この時期は「題数は足りているか?」、「一字一句覚えるか?」など、気になることも増えてきます。
そこで、国税の科目・地方税の科目ともに合格経験のある事業税好き税理士のAkko先生に、受験エピソードを交えながら、理論暗記との向き合い方をアドバイスいただきます。
直前期における理論との向き合い方
こんにちは、事業税好き税理士のAkkoです。税理士試験が近づいてきましたね。
税理士試験では避けて通れない理論暗記。この時期、特に受験生の皆さんを悩ませ、不安になっていることでしょう。
今回は私なりの直前期における理論との向き合い方を暗記題数と暗記の精度に分けて振り返ってみます。少しでも学習の参考になれば幸いです。
暗記すべき理論は何題?
突然ですが、理論暗記って何題すればよいと思いますか?
答えは実は単純です。そう、すべての理論を暗記することです! これができれば怖いものはありません。
…とは言え、それができないからなかなか悩ましいですよね。もう少し掘り下げて考えてみましょう。
具体的な題数となると、消費税や事業税など題数50題程度の科目(それ以下の題数の科目も含む)はすべての理論、法人税のようなボリュームの大きい科目は全体の2/3程度の理論を暗記することが1つの目標となりそうです。2/3程度というのは予備校で言うランクの低いものを除いた数といったところでしょうか。
このハードルはなかなか高いのですが、もちろんこの通りじゃないと合格できないというわけではありません。私自身この目標に届かないまま本試験を迎えたこともあります。
理論暗記の精度はどのくらい?
次に暗記の精度についてですが、これは一字一句覚えることをおすすめします。”てにをは”くらいは多少間違っていても大勢に影響はないでしょう。
少し話はそれますが、ちょっと気になるのが定期的に議論になる一字一句丸暗記の是非です。
私としては、やはり一字一句を推奨します。
一字一句でないと合格できないわけではないのですが、実は一字一句の丸暗記って楽なんです。
何が楽かというと、大きく2つあります。
1つ目は、アウトプットが圧倒的に楽になります。一字一句の丸暗記は問題に対して該当のページをそのまま書くだけなので、何も考えることはありません。
それに対し、いわゆる「理解している」場合はその内容を文章にするという工程が発生します。そのため、丸暗記の方が理論を書くスピードが段違いに早いです。
余談ですが、演習で理論問題を解くスピードが遅いという悩みがあるなら、たいていは暗記不足によるものだと思います。文字を書くスピードが気になったりもするのですが、スピードが上がらないのはペンが止まっているからなんですよね。
2つ目は、暗記状況の把握が楽になります。毎回文章を作る場合、アウトプットされるものは同じ文章ではないでしょう。講師の採点がない場合、どのように理解度や暗記具合などを定量的に判断するのでしょうか。
その点、一字一句の丸暗記であればテキストと比べれば一目瞭然です。そう考えると学習がとてもシンプルなものになりますよね。
大切なのは優先順位と割り切り
さて、ここからがようやく本題になります。目標通り理論暗記が進んでいるのであればよいのですが、そうではない場合どう向き合うのがよいのでしょうか。
「題数が少し足りなさそうだな」という場合には無理に暗記題数を稼ぐのではなく、しっかり優先順位をつけて暗記をしていくのが良いです。
優先順位の考え方は、周りの受験生が書けるものが上位となります。具体的には各予備校で設定される重要度順となるのでしょうが、その中でも特に公開模試や5月以降直前期の演習問題で出題されているものを上位におきましょう。
これらは多くの受験生が書けるものですので、書けないと不利になります。試験で大切なことは、「誰も書けない理論を書けること」ではなく、「誰もが書ける理論を確実に書けること」なんですよね。
理論暗記ですが、すべてを暗記していない以上は、何題暗記すれば合格するという明確なものはありません。身も蓋もないですが、試験で覚えていた理論から出題があれば合格します。極論、5題しか覚えていなくてもそこからすべて出題されれば試験は合格できてしまいます。なので、どんなに進捗が悪くてもあきらめる必要はありません。
次に精度についてですが、以下のように濃淡をつけるのも一つの手段です。
① 一字一句書ける状態
② 理論の見出しと内容の概要(いわゆる「作文」)を書ける状態
③ 理論全体を数行でざっくり書ける状態
優先順位に精度を掛け合わせていくのですが、私は既に述べているように①を原則としていました。
②は、ボリュームの小さい科目のうちランクの低い理論や、予備校の重要度は低いが個人的に気になるもの(近年試験で出題があったため重要度が下がっている理論)などで、一字一句まで仕上げる余裕がない場合です。これはもう概要の文章を作ってそれを丸暗記してしまうのが良い気がします。
また、ランクが低いといわれて対策不要に思えるけどさすがに何も覚えてないと不安だなというものは③としていました。
この③については、正直それが試験で出題されたところで合否に影響があるとは思えません。
では、「なぜ③の話をしたのか?」というと、これはどちらかというと、精神安定剤に近いものです。実は理論暗記ってめちゃくちゃメンタルが影響してきます。まったく覚えていない理論を1つでも減らすことによって精神的な余裕が少し出てきたりするんですよね。
また、メンタルの話で言うと、暗記が順調に進んでいない場合に大切なのが、「割り切り」です。暗記題数が足りていないからと言って、不安になって中途半端にすべてに手を出すのが一番よくありません。
「もし覚えていない理論が試験に出てしまったら…」と、勉強中に何度も思うことがあるかもしれませんが、「それはもう仕方ない!」そう割り切ってしまうのが一番です。変な焦りは暗記を邪魔してきますし、試験ではプレッシャーにより頭の中が真っ白になってしまうこともあります。
経験のある方も多いかもしれませんが、悩みだしたら本当に暗記できませんし、緊張しすぎるとペンも頭も動かなくなりますからね。割り切っていきましょう!
おわりに
計算はある程度機械的に解けるところがありますが、理論は自分の頭から絞り出していく必要があるため、非常にメンタルに左右されます。メンタルを健やかに保つためには勉強が順調な人もそうでない人も、書けないことや出来ないことを恐れないことです。もう、ある程度割り切って、思い切って学習を進めていただくのが結果的に良いと思います。
完璧に準備して試験に臨める受験生なんてほとんどいません。「最大限努力した!」と試験開始の瞬間に思えるよう、直前期の学習頑張ってくださいね。
【執筆者紹介】
Akko
税理士
高校卒業後紆余曲折あるも、たまたま拾ってくれたIT企業に勤めている中で会計に興味を持つ。日商簿記2級を取得後会計事務所に転職。いくつかの職場を転々としながら試験勉強を続け2021年官報合格。現在は事業税の知識を活かすため上場企業で税務担当として勤務しつつ副業で税理士として開業中。天性のジョブホッパーでありファーストキャリアは宅配ドライバー。
アイコンのキャラクター名は「じぎょるんじゅ」
・Xアカウント(@Akko_natsudazei)