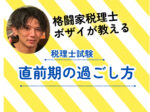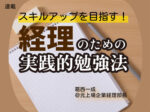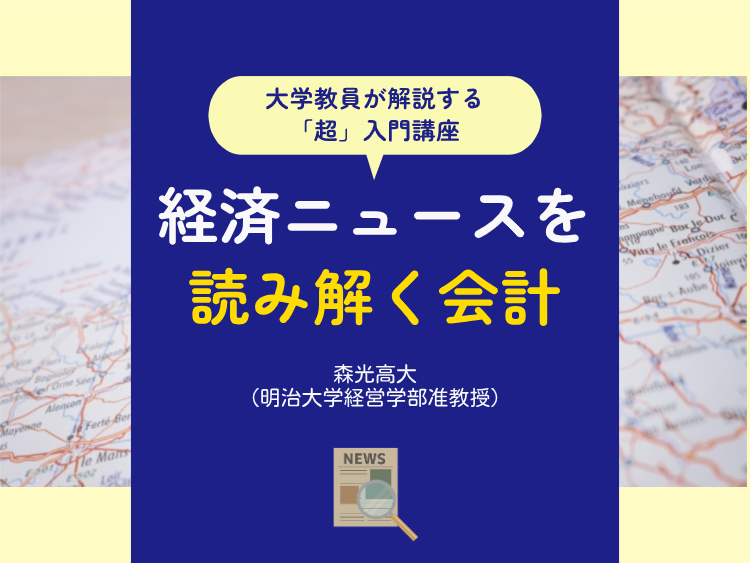
森光高大(明治大学経営学部准教授)
【編集部より】
話題になっている経済ニュースに関連する論点が、税理士試験・公認会計士試験などの国家試験で出題されることもあります。でも、受験勉強では会計の視点から経済ニュースを読み解く機会はなかなかありませんよね。
そこで、本企画では、新聞やテレビ等で取り上げられている最近の「経済ニュース」を、大学で教鞭を執る新進気鋭の学者に会計・財務の面から2回にわたり解説していただきます(執筆者はリレー形式・不定期連載)。会計が役立つことに改めて気づいたり、新しい発見があるかもしれません♪ ぜひ、肩の力を抜いて読んでください!
ミスリーディングなインセンティブ
原価計算というと、正確である方が望ましいと多くの人が考えるでしょう。普通に考えれば、あえて原価を大きくしたり、歪ませたりする理由はないような気がします。
ところが、前回お話したように、防衛調達においては、製造企業があえて原価を大きくすると、より大きな利益が得られる可能性があるという問題点が指摘されており、この問題を打開するための様々な検討がなされています。
近年、2023年12月22日付の時事通信の記事「防衛費、過去最大7.9兆円=イージス搭載艦を建造―来年度予算」などのように、防衛関連予算の増大を指摘する記事をよく目にします。
予算額が増加傾向なほど世間の注目も集まり、予算や原価の削減プレッシャーも大きくなることは世の常ではないでしょうか。
実は、防衛調達における「原価計算による価格決定」の問題点は、長らく議論されてきました。
今回は、少し古い米国の話ですが、この議論の中で提起された、コスト・シフティング仮説という仮説について少し紹介したいと思います。
コスト・シフティング仮説
コスト・シフティング仮説とは端的に言うと、防衛契約企業が、競争の激しい一般製品の原価の一部を、競争性に乏しく原価が補償される防衛装備品のコストに転嫁し、自身の利益を増大させようとしているかもしれないという考え方です。
また、この仮説を考えるうえで留意が必要なのは、コスト・シフティングは必ずしも違法行為とは限らないという点です。
存在しない項目を追加して原価を水増しすることは違法ですが、製造間接費配賦基準の設定やセグメントの区切り方など、裁量の範囲内で原価を転嫁することは合法にもなりえます。
この仮説を検証するために1990年代以降、いくつかの研究が発表されています。
まず、Rogerson(1992)は、数理モデル分析を用いて、契約企業が製造間接費の配賦方法の操作によってコスト・シフティングを行う誘因が存在することを主張しました。
さらに、Thomas and Tung(1992)は、政府の原価監査の目の届きづらい企業年金に注目し、企業が防衛装備製造に従事する従業員の企業年金を過大に積立てることで、年金コストを防衛契約に賦課しているのではないかという仮説を実証しました。
加えて、Lichtenberg(1992)は、コスト・シフティングの有無を検証するために、防衛契約を行っている企業の各セグメントを、防衛装備製造と民生品製造に二分し、収益性を比較しました。
検証の結果、彼らは防衛契約セグメントの方が高く、コスト・シフティングの存在が強く疑われると結論づけています。
これらはコスト・シフティング仮説を支持する先行研究ですが、しかし反証も存在します。
McGowan and Vendrzyk(2002)らは、Lichtenberg(1992)の研究結果を受けて、従来の2分類から、防衛装備のみ、防衛装備と一般製品の両方、そして、一般製品のみの3つに分類して検証を行いました。
その結果として彼らは、防衛契約セグメントの高収益性は間違いないが、その原因はコスト・シフティングではなく、原価計算や会計のコンテクストを超えたところにあると結論づけています。
原価計算の奥深さ
これらの研究は、各防衛調達契約の個別データを直接的に検証したものではなく、またその結果も賛否両論あるため、コスト・シフティングが存在するか否かについては、まだはっきりとはわかっていません。
ただし、この仮説から得られる重要な教訓は、原価計算には様々な思惑や経営上の意図が入る可能性があるということです。
原価計算を学習する際は、ただ計算して解答を出すことに終始するのではなく、「その計算結果がどういった利用者にどのように使われるか」ということまで考えてみれば、より面白く、奥深く感じられるかもしれません。
【参考文献】
Lichtenberg, F.R. (1992). “A perspective on accounting for defense contracts.” The Accounting Review, 67(4): 741-752.
McGowan, A. S., and V. P. Vendrzyk. (2002). “The relation between cost shifting and segment profitability in the defense-contracting industry.” The Accounting Review, 77(4): 949–969.
Rogerson, W.P. (1992). “Overhead allocation and incentives for cost minimization in defense procurement.” The Accounting Review, 67(4): 671-690.
Thomas, J. K. and S. Tung. (1992). “Cost manipulation incentives under cost reimbursement: Pension costs for defense contracts.” The Accounting Review, 67(4): 691-711.
(おわり)
<執筆者紹介>
森光高大(もりみつ・たかひろ)
明治大学経営学部教授 博士(商学)一橋大学
1985年生まれ。一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了。一橋大学大学院特任講師、日本経済大学准教授、西南学院大学准教授・教授を経て現職。防衛装備庁特別研究官(2016-2017年度)を歴任。
主な著書・論文に、『防衛調達論』中央経済社、2022年(共著)、『全経簿記能力検定試験標準問題集 1級原価計算・管理会計』中央経済社、2024年(共著)、「水産経営における収益性分析についての一考察—漁業の収益性に関する文献レビューに基づいて」『西南学院大学商学論集』 69(3・4): pp. 227-245、2023年(単著)、”Cost-based Pricing in Government Procurement with Unobservable Cost-reducing Actions and Productivity.” Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics 30(2): pp. 373-390、2023(共著)ほか多数。
<こちらもオススメ>
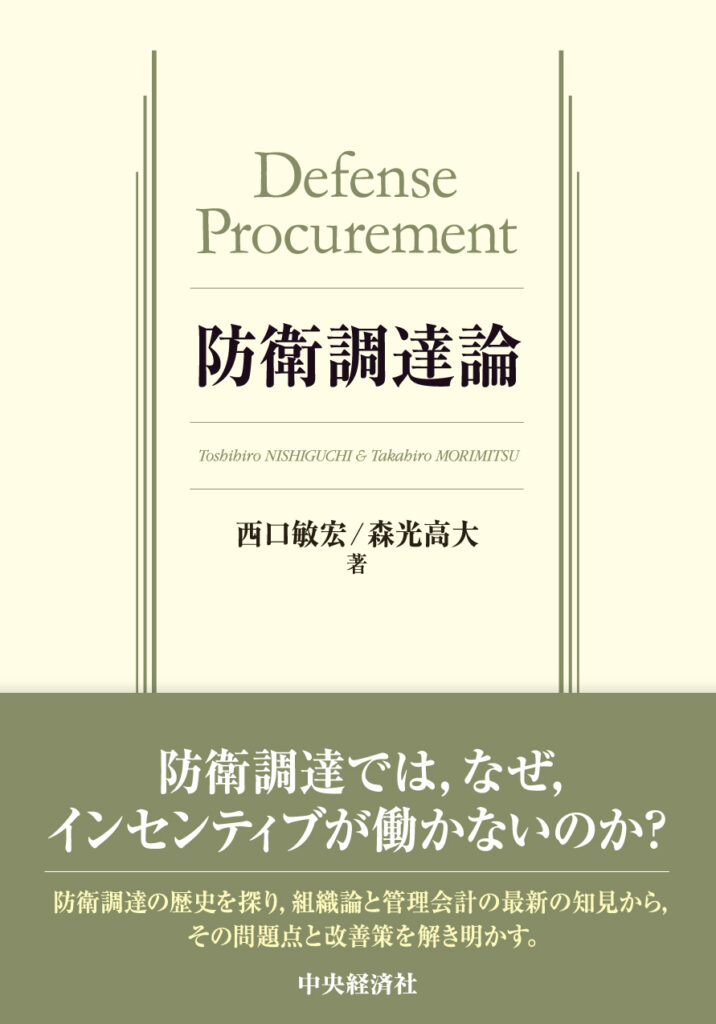

(奥村 雅史 監修・渡邊 章好 編著、中央経済社)