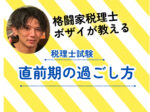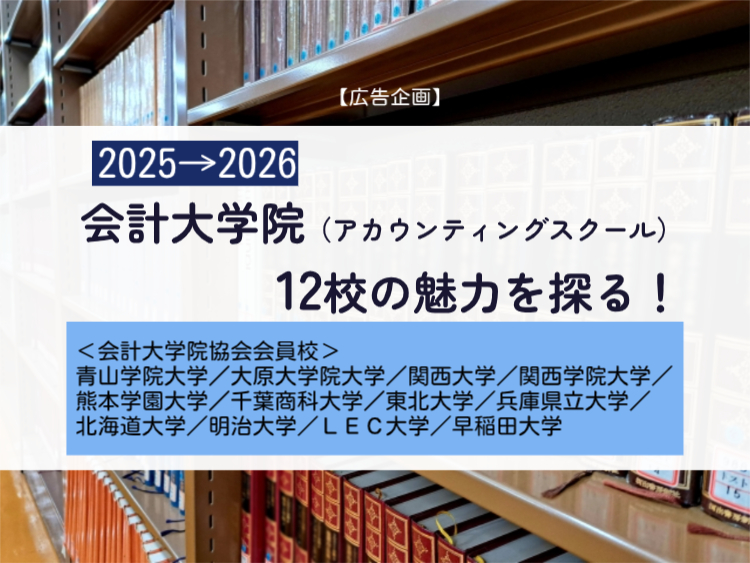井上 修
(福岡大学講師・公認会計士)
財務会計論では短答式試験の論点が出題される傾向があります。具体的には「適用指針(実務指針)」からの出題です。これは「配布される基準集」にはない論点として出題しやすいものとなります。配布されていない以上、「会計処理」そのものを聞くこともありますし、「根拠(理由)」を聞くこともあります。過去どのような短答式論点のような内容が論文式試験で聞かれてきたか、7つの問題からみてみましょう。これらを通じて、「このような論点も論文式試験で問われるんだな」と心の準備をしてもらえれば十分です。
例題1(平成25年 第3問 問2(2))
「固定資産の減損に係る会計基準」によれば、減損の兆候を判定する基準として「対象資産の市場価格の著しい下落」があるが、①著しい下落の具体的な判定基準について説明し、②固定資産の観察可能な市場価格が存在しない場合、減損の兆候を把握するための市場価格とみなされるものには何があるか述べなさい。
【解答例】
① 市場価格が帳簿価額から50%程度下落した場合
② 実勢価格や査定価格などの評価額や土地の公示価格や路線価(路線価による相続税評価額や固定資産税評価額)など適切に市場価格を反映している指標
【解説】
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」第15項からの出題です。4つの減損の兆候は配布される基準集に記載されていますが、その細かい内容については配布されない適用指針の内容となります。実務では近年のコンバージェンスの影響で「どうやって時価を把握するのか」という点に強い関心があります。ただし、本問の論点は非常に細かいため、受験生に問うような問題ではないと考えられます。
補足論点としましては、なぜ「対象資産の市場価格の著しい下落=減損の兆候」なのかという点です。これは、①実務上、過大な負担を考慮したという実践的な理由と、②事業投資であるという理論的な理由によるものです。すなわち、固定資産については、有価証券や販売用不動産等と異なり、通常、市場平均を超える成果を期待して事業に使われているため、市場の平均的な期待で決まる市場価格が変動しても、企業にとっての投資の価値がそれに応じて変動するわけではないという点が踏まえられています(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」第89項)。本来、事業投資目的の固定資産は、時価の変動は投資の成果と関係がないことから、時価評価せず取得原価に基づいて評価されます。それゆえ、「市場価格の(通常の範囲内の)変動」と「減損の兆候」は本来的には結びつかないものといえます。だからこそ、減損基準は「市場価格の著しい下落(50%超の下落)」までの事象じゃなければ「減損の兆候があるとはいえないよ」と規定しているわけです。
例題2(平成25年 第4問 問2(2))
外貨建借入金等に直先フラット型の通貨スワップを付した場合、振当処理が認められる理由を説明しなさい。
【解答例】
外貨建借入金等に直先フラット型の通貨スワップを付すと、借入金額と返済金額が同額となるため、実質的に円建の借入と同じ効果がある。このように、為替予約と同様に円貨でのキャッシュ・フローが固定されることから、振当処理が認められる。
【解説】
「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」第6項からの出題です。ポイントは「振当処理」が認められる理由をうまく使うという応用問題です。
なお、キャッシュ・フローが固定されるという点で他の論点ではありますが、「金利スワップ等の特例処理」が認められる理由についても注意が必要です。金融商品会計基準注解14では、「資産又は負債に係る金利の受払条件を変換することを目的として利用されている金利スワップが、金利変換の対象となる資産又は負債とヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件(利率、利息の受払日等)及び契約期間が当該資産又は負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産又は負債に係る利息に加減して処理することができる」とされています。これが認められる理由として、金融商品会計基準第107項の内容を書く出題も考えられます。すなわち、「金利スワップの想定元本、利息の受払条件(利率、利息の受払日等)及び契約期間が金利変換の対象となる資産又は負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、両者を一体として、実質的に変換された条件による債権又は債務と考えられるから」という理由です。
例題3(平成26年 第4問 問3)
子会社株式取得時における資本連結手続上、①のれんが発生する理由、②のれんが一時差異となる理由、③のれんに対し税効果を認識しない理由、をそれぞれ述べなさい。
【解答例】
① のれんは、投資額と子会社の資産及び負債の時価評価の純額の親会社持分額との差額である。
② のれんは、子会社の個別貸借対照表では計上されていないため一時差異である。
③ しかし、のれんに対して子会社が税効果を認識すれば、のれんが変動し、それに対してまた税効果を認識するという循環が生じてしまうため、のれんに対し税効果を認識しない。
【解説】
連結上、子会社ののれんは「差額」で算定されるという点がポイントとなります。税効果も「ズレ」が生じた部分に着目するわけですが、のれんもまた「差額(ズレ)」に着目しています。この説明だけで、ズレ(一時差異)に対して税効果が適用され、またその差額(ズレ)を埋めるためにのれんが計上されて、またそれがズレ(一時差異)となって・・・という循環が容易に想像できますね。
例題4(平成27年 第4問 問1(2))
外貨建自己新株予約権について、①消却した場合の会計処理、および②処分した場合の会計処理を説明しなさい。
【解答例】
① 外貨建自己新株予約権を消却した場合、消却した自己新株予約権の取得時の為替相場による円換算額とこれに対応する新株予約権の発行時の為替相場による円換算額との差額を、自己新株予約権消却損(又は自己新株予約権消却益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する。
② 自己新株予約権を処分した場合、受取対価と処分した自己新株予約権の取得時の為替相場による円換算額との差額を、自己新株予約権処分損(又は自己新株予約権処分益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する。
【解説】
会計処理の説明だけですので解説はありませんが、自己新株予約権については「資本取引と損益取引」という会計理論で出題されることがありますので気をつけてください。資本取引を「報告主体の所有者である株主との取引」と解すれば、自己新株予約権の取引は資本取引に該当しませんので、損益取引として処理されることになります。これは、「自己株式」の取引と対極にある考え方となりますので非常に面白い論点です。
例題5(平成29年 第4問 問題3 問1)
ヘッジ会計の要件充足の判定に関しては、事前テストと事後テストを実施しなければならない。後者の事後テストにおいては、①「ヘッジ取引時以降において、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺される状態」、または②「ヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態」が引き続き認められるか否か、すなわち、ヘッジの有効性を評価しなければならないとされている。そこで、価格変動リスクのヘッジを例として、①の判定基準について具体的な数値基準を示して説明しなさい。
【解答例】
ヘッジの有効性は、原則としてヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額の比率がおおむね80%から125%の範囲内にあれば、ヘッジ対象とヘッジ手段の間に高い相関関係があり、有効であると判定される。
【解説】
「金融商品会計に関する実務指針」第156項からの出題です。例えば、ヘッジ手段の損失額が80でヘッジ対象の利益額が100ならば、相殺は100分の80で80%と測定され、ヘッジ手段の利益額が100でヘッジ対象の損失額が80ならば、相殺は80分の100で125%と測定され、これらの場合はヘッジは有効であるといえます。
例題6(平成30年 第4問 問題1 問2)
その他有価証券の貸借対照表価額は、(A)「期末日の市場価格に基づいて算定された価額」とすることが原則である。ただし、継続適用を条件として、(B)「期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額」を用いることもできる。この(B)の規定が設けられた理由を述べなさい。
【解答例】
その他有価証券は直ちに売却することを目的としているものではないため、その他有価証券に付すべき時価に市場における短期的な価格変動を反映させることは必ずしも求められないと考えられるから。
【解説】
この規定は、「時価の算定に関する会計基準」の適用によりまもなく削除されます。したがって、もう出題されることはありません。
例題7(令和元年 第3問 問題1 問2)
土地のリース取引は、動産のリース取引とは異なり、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当することはなく、所有権移転ファイナンス・リース取引またはオペレーティング・リース取引のいずれかとなる。土地のリース取引が、所有権移転ファイナンス・リース取引以外は、オペレーティング・リース取引と推定される理由を答えなさい。また、土地のリース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引となるのは、どのような場合か二つ答えなさい。
【解答例】
① 土地の経済的耐用年数は無限であるから
② リース契約上,所有権が借手に移転する場合と割安購入選択権の行使が確実に予想される場合
【解説】
「リース取引に関する会計基準の適用指針」第99項からの出題です。リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかについては、(1) 現在価値基準と(2) 経済的耐用年数基準のいずれで判定するわけですが、これらは特に「所有権移転外」のリース取引について重要な判断基準となります。リース期間終了後に所有権が移転しない、すなわち、貸手に返還する場合に、そうであっても「経済的実態が売買取引であるといえるか?」が関心事になります。この点、土地については①経済的耐用年数が無限と考えられるため、所有権が移転しないことを前提として、(1) 現在価値基準や(2) 経済的耐用年数基準によって判断することは不可能です。それゆえ、土地の場合については、②リース契約上,所有権が借手に移転する場合と割安購入選択権の行使が確実に予想される場合にのみ、経済的実態が「売買取引」であると判断できるわけです。
〈執筆者紹介〉
井上 修(いのうえ・しゅう)
慶応義塾大学経済学部卒業。東北大学大学院経済学研究科専門職学位課程会計専門職専攻修了、会計学修士号(専門職)。研究分野はIFRSと日本基準の比較研究、特別損益項目に関する実証研究などであり、2020年度に博士号(経営学)を取得見込み。
福岡大学「会計専門職プログラム」では、現役の大学生が多数、公認会計士試験や税理士試験簿記論・財務諸表論に在学中の合格を果たしている。本プログラムから平成30年度は10名、令和元年度は5名が公認会計士試験に合格。
\合わせて読みたい/
財務会計論で1点でも多くとる解答戦略



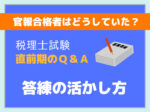

-150x112.jpg)