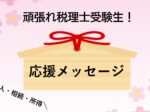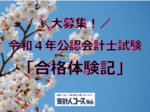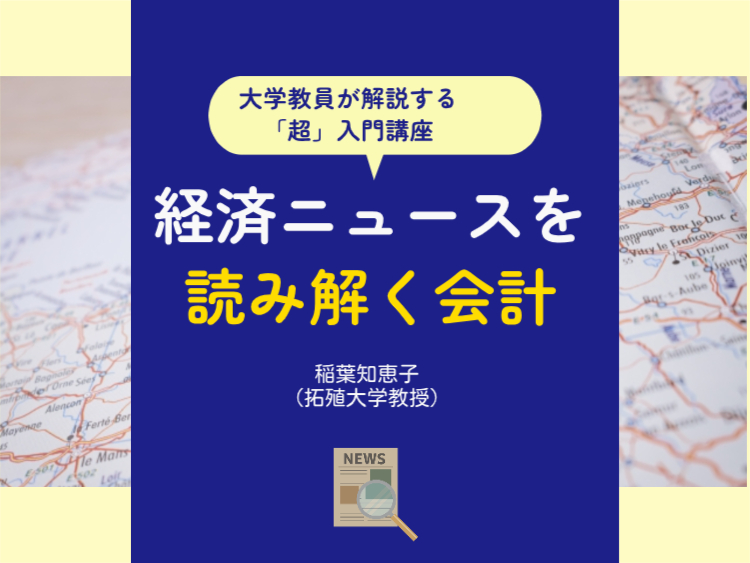
はじめに
こんにちは! 拓殖大学で税務会計論を担当している稲葉知恵子です。
OECDが進める「グローバル・ミニマム課税」は、世界の多国籍企業に大きな影響を及ぼしつつあります。ここで注目されているのは、単に「どれだけ納税しているか」ではなく、「企業がどのように税務に向き合い、透明性を確保しているのか」という姿勢そのものです。
つまり、制度の側からは「最低限の納税」を求める仕組みが強化される一方で、企業の側からは「私たちは責任を持ってこう取り組んでいます」と社会に示すための税務ガバナンス開示が広がっています。両者は直接一本でつながるわけではありませんが、「租税回避を許さない」「透明性を高める」という同じ国際的な潮流の中にあるといえるでしょう。
前回に引き続き「税務戦略の開示」をテーマに、今回は会計開示やESGとの接点に注目してご紹介したいと思います。
前回も触れたように、税務ガバナンスとは、企業が税務コンプライアンス(法令遵守)やタックス・プランニングにどう向き合い、税務リスクをどのように管理・監督するかを統括する仕組みを指します。重要なのは、どのような姿勢で税務マネジメントに取り組んでいるのか、責任体制をどう構築しているのかという点です。
こうした企業の税務に対する向き合い方は、近年では単なる税務コンプライアンスを超えて、企業価値やステークホルダーとの関係性にも結び付く経営課題となっています。
財務諸表における税務情報の開示
税務戦略の開示の中でも、最も身近で基礎となるのが財務諸表です。費用として計上する法人税等の額や繰延税金資産を扱う税効果会計は、企業の税務姿勢を示す重要な開示でもあります。
具体的に言うと、繰延税金資産の計上や取崩しは、将来の課税所得をどの程度見込めるかという経営陣の見積りに基づく会計処理です。こうした判断は企業の収益見通しを示す材料の1つとなります。日経新聞(2025年9月18日付)は、コニカミノルタが米子会社の事業計画見直しに伴い約140億円の繰延税金資産を取り崩した事例を報じました[1]。
この事例は、将来の課税所得見込みに応じて繰延税金資産を取り崩すという判断を通じて、企業が税務リスクを管理しようとする姿勢を示しています。
また、有価証券報告書では「法定実効税率」と「当期実効税率」の差異を注記することが求められています。この差異は、企業がどのようなタックス・プランニングを行い、どのような税務リスクを抱えているのかを投資家に示すレンズとなります。
ESG開示で問われる「税の透明性」
多くの企業は、統合報告書やCSR報告書を通じて非財務情報(会計数値だけでは表せない情報)を社会に発信しています。多くの日本企業は、非財務情報の報告の枠組みとしてGRIスタンダードを採用しています[2]。GRIスタンダードは、企業活動が経済・環境・社会にどのような影響を及ぼしているかを体系的に報告するためのガイドラインで、環境問題や人権、労働、安全衛生など幅広いテーマをカバーしています。
その中でも2019年に新設されたGRI 207「Tax」は、税の透明性を国際的なサステナビリティ報告の一部として位置づけたものです。GRI 207は、大きく4つの開示分野を求めています。
| 207-1 税務へのアプローチ | 企業の税務に関する基本的な方針や戦略 |
| 207-2 税務のガバナンス、管理、リスクマネジメント | 税務に関する取締役会の監督体制や、税務リスクをどのように管理しているか |
| 207-3 ステークホルダーとの対話と税に関する懸念事項の管理 | 税務に関する対話、特に社会や投資家との関わり方 |
| 207-4 国別報告 | 国ごとの収益、利益、税金、従業員数などの定量的な情報 |
このうち207-1、207-2、207-3は定性的な情報であり、企業の姿勢や統治の仕組みを説明することが重視されます。207-4は定量的な情報であり、国ごとの数値を並べることで外部から比較可能な形にします。
従来の財務報告では「納税額」という単一の数値に注目が集まりがちでしたが、GRI 207は「なぜその税額になったのか」という背景や説明責任を求めている点に特徴があります。企業の税務ポリシーや税務ガバナンス体制を含めて社会に示すことが重要になったのです。
こうした開示の流れを受けて、投資家やESG評価機関も税の透明性を企業評価の一部として取り入れるようになっています。実際、オランダの投資家団体VBDOとPwCが実施するTax Transparency Benchmarkでは、税務戦略、ガバナンス体制、国別報告、そして外部保証の有無といった要素がスコア化され、企業の比較評価が行われています[3]。
EU Public CbCRがもたらすインパクト
そしてEUでは、2021年に採択された指令に基づき、Public CbCR(国別報告書の公開制度)が2024年6月22日以降に開始する会計年度から適用されます。対象は、直近2会計年度の連結収益が7億5,000万ユーロを超える多国籍企業です。これにより、企業はどの国でどれだけの収益や税金を計上しているのかといった情報を、社会に向けて公開することが義務付けられます。
日本でも2016年度からCbCRの提出は義務化されていますが、国内制度は非公開であり、提出先は税務当局に限られています。これに対してEUのPublic CbCRは、企業の税務データを「社会に対して開示」する点で画期的です。
公開のメリットは、投資家をはじめとする利害関係者が企業の納税状況を直接検証できることです。責任ある納税を実践する企業にとっては、信頼獲得やESG評価の向上につながる可能性があります。透明性を積極的に高めることは、長期的には企業の社会的評価や持続可能性の強化に資するでしょう。
一方で、課題やリスクも存在します。単年度データに基づくため、一時的な利益変動や繰延税金資産の影響で「低税率=租税回避」と誤解される可能性があります。また、全世界の子会社からデータを収集・統合し、説明責任を果たすことは、企業にとって大きな負担です。
さらに、最新の実証研究(Müller, Spengel & Weck, 2024, Contemporary Accounting Research)は、EUにおけるPublic CbCR導入の発表後、対象企業の株価が有意に下落したことを明らかにしました[4]。投資家がレピュテーションリスクや機密情報流出リスクを懸念した結果と解釈できます。
このように、Public CbCRは透明性を飛躍的に高める一方で、必ずしも企業にとって短期的にプラスばかりとは限らない制度です。企業の情報開示の在り方によって、信頼を高めるチャンスにも、レピュテーションリスクにもなり得ます。
おわりに
税務ガバナンスは、単なるコンプライアンスの問題にとどまらず、企業の姿勢や責任体制そのものを映し出す概念です。その開示は、本稿で見てきた 財務諸表での注記、GRIスタンダードに基づくESG報告、そして EU Public CbCR という3つのルートを通じて、多面的に可視化されます。
透明性を高めることは、責任ある納税を実践する企業にとって信頼を獲得し、長期的な持続可能性を後押しする契機となります。しかし一方で、開示が不十分であったり、単年度の数値が誤解を招いたりすれば、レピュテーションリスクに直結しかねません。いまや、税務ガバナンスを「どう見せるか」も企業の信頼と評価を左右する要素となっているのです。
[1] 税効果会計、財務と税務のズレ調整 将来の稼ぎ落ち込めば取り崩し
会計フォローアップ③. (2025, September 18). 日本経済新聞. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG096Y60Z00C25A9000000/
[2] Global Reporting Initiative. (2024, November 27). GRI Global Adoption by Top Companies Continues to Grow. https://www.globalreporting.org/news/news-center/gri-global-adoption-by-top-companies-continues-to-grow/
[3] PwC. (2024, December 10). Commitment to tax transparency grows, but challenges remain. https://www.pwc.nl/en/insights-and-publications/services-and-industries/tax/commitment-to-tax-transparency-grows-but-challenges-remain.html
[4] Müller, R., Spengel, C., & Weck, S. (2024). How do investors value the publication of tax information? Evidence from the European public country‐by‐country reporting. Contemporary Accounting Research, 41(3), 1893-1924. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1911-3846.12965
<執筆者紹介>
稲葉知恵子(いなば・ちえこ)
拓殖大学商学部教授、博士(経営学)。明治大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。拓殖大学商学部助教、准教授を経て、2024年4月より現職。専門は税務会計。とりわけ、税務ガバナンスと情報開示に焦点を当て、BEPS・BEPS2.0が企業にどのような行動変容をもたらすかを日英比較で研究している。近年は、税務担当人材の育成や新たに求められるガバナンス要素を探る研究に加え、公共部門におけるジェンダー予算編成の研究にも取り組み、透明性・説明責任・ガバナンスという共通概念の深化を目指している。
【主な論文等】
稲葉知恵子(2023)「英国企業によるTax Transparency Report等の特質」『税務会計研究』(34): 215-229.
稲葉知恵子(2023)「日本企業の税務ガバナンスの開示」『會計』203(6): 629-640.
Daniela Pianezzi & Chieko Inaba (2025). Lost in Translation: Exploring Gender Mainstreaming in Japan. Gender, Work & Organization. First published: 16 May 2025. https://doi.org/10.1111/gwao.13275
【インドネシアにて、Accounting and Accountability in Emerging Economiesでの学会報告後】