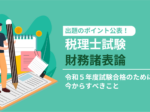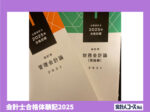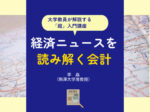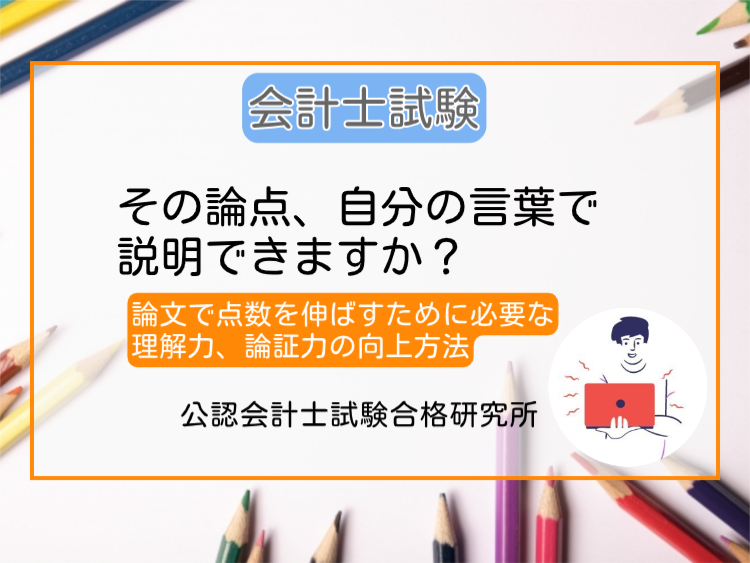
公認会計士試験合格研究所
はじめに
公認会計士試験受験生の皆さん、日々勉強は順調でしょうか。
「公認会計士試験合格研究所」(https://x.com/kcp48336541)です。
勉強していると、論点整理、理解がスッとうまく日もあれば、全然進まない日もありますね。
理解が進まないと、勉強計画、モチベーションが崩れ、学習スピードも落ちて、合格が遠のいてします。
会計士試験においては、論点の「理解漏れ」をなくすことが、最も重要なファクターです。
当記事では、理解力を高め、論点理解を促進するために必要なエッセンスについて解説します。
ほとんどの場合、各種取引や事象、概念の具体的イメージがわいていない
会計士試験で扱う全ての会計基準、もしくは会社法の規定等は、すべて何かしらの「目的」に紐づけられて、定められています。
つまり、因果関係があるということです。
しかし、論点が理解ができず、いまいち腹落ちしないまま、丸暗記を試みて挫折する受験生も多いです。
理解できない原因は、その基準が定められている目的、背景ストーリーを捉えられていないことです。
「具体的に何なのか」ということを把握できず、その結果として、基準や規定等が「もはやなにがなんだかわからない」という状態に陥ってしまっているのです。
基準が定められた背景、ストーリー意識する
IFRSリース会計の使用権資産、負債を例にとって説明します。
【記述①】
使用権という新しい概念を作って(今までオペレーティングリースに該当するものも含め、)リース取引を改めて包括的に定義した。
上記は、「何で?」という基準の背景、ストーリーが抜け落ちています。
これを1回聞いただけでは、理解できません。
聞いても、翌日にはすぐ忘れてしまうでしょう。
【記述②】
従来からファイナンスリース取引に分類されるべきものが、オペレーティングリース取引として区分けされ、本来ならリース債務として計上すべきものが未計上とされていた。つまりリース取引排除が行われた。だから、使用権という新しい概念をつくって、もっと広い概念をリース取引と捉え、使用権に該当するものはオンバランスしようという基準に立て付けをかえた。
上記は背景、ストーリーを意識した記述です。
これだと、すっきりと理解できます。
背景、ストーリーを意識するために、常に「問い」を立てる意識をもつ
リース債務外しの例はわかりやすいですが、基本的にどの会計基準にもストーリーがあります。
そしてそれらの基準のストーリーを意識することが必要です。
常日頃から一つ一つの基準に「問い」を立てる意識を持ちましょう。
それが理解力を少しずつ高めるトレーニングになります。
そう、「頭がいい」状態を自らトレーニングで作りに行くんです。
具体的にどんな「問い」を立てればいいか?
具体的な問いの立て方ついては、はっきり言って、正解はありません。
最初はとんちんかんな「問い」が、少しずつロジカルな、つまり的をえた問いに昇華していくプロセスがあります。
とにかくあらゆる基準、ルールに疑問をもつことからスタートです。
・税金費用の実額は変わらないのに、何で税効果関係なんて面倒なことしてるんだろう?
・資産除去債務って何で資産計上するんだろう?
・PPAってなんか面倒くさいな〜何でこんなプロセスを踏むんだろう?
疑問を持つうちに、ふと閃くこともあります。
・監査報告書のルール覚える嫌だ。こんなに形式をガチガチに決める必要ある?
→あ、そっか。ガチガチに形式化しないと、監査人の責任範囲が明確にできないもんな。保証の水準が、明確になる。
こんな脈絡のない「問い」から、ふと気づきを得ることができます。
そうはいっても、「なんの問いも浮かばない!」ということもあるかもしれません。
そこで、もつべき「問い」の例、指針のようなものをここでいくつか挙げたいと思います。
問い例①「誰の利益、利害を守っているのか?」
会計基準も会社法も、どのルールも最終的には誰かの利害を調整するために存在しています。
税効果会計:
ある3期間、同じ経済事象から売上が発生した。この会社が保有する建物については、会計で定額法を採用し、一方税法で定率法を採用したことで、税金費用が3期間で異なる。同じ経済事象しか発生していないのに、業績が異なって計算されると、投資家は判断を誤る。投資家保護のため、税効果会計がある。
会社法の資本維持原則:
資金調達の段階で、株主には株式譲渡自由の原則が保証されている。そのため株主は市場で自由に株式を売却して、その投下資金の回収を行うことできる。そのため、出資の払い戻しを株主保護のために認める必要性は基本的にない。仮に出資の払い戻しをもし認めるならば、会社財産に毀損が生じ、貸し出しを行なっている債権者に対する返済余力が低下する。そのため、債権者保護の規定があちらこちらに規定されている。
「誰の利益を保証しているか?」この視点をもって問いをたてることで、ストーリーのイメージ力が高まります。
問い例②「その規定は本当に必要?もしその規定がないとどんな問題が起こるだろう?」
会計、監査、会社法の理論や規定は、何かしらの経済問題を解決しうる形で規定されます。
その基準がなかったら、どんな問題が発生するだろう?と想像して見る。
・減損損失の基準がなかったら、どんな問題が起こるか?
→実務上、会社は一度買った工場や機械を、仮に全然使っていなくても、帳簿に高額なまま計上しっぱなしのものが多くあります。その結果、決算書を見た投資家は「資産がたくさんある優良企業だ」と勘違いします(場合によっては安心して投資する)。でも実態は、稼働していない工場、将来キャッシュを生まない資産ばかりなんてことも。会社が仮に突然傾いたときに実態のない固定資産群にはもはや資産性がなく、投資家が判断を誤ります。だから、減損損失の基準の必要性があります。
「減損損失の基準がもしなかったら」と考え、その必要性から基準に対するイメージを膨らませていきます。
・金融商品の会計基準(デリバティブ)がなかったら、どんな問題が起こるか?
→企業は巨額のデリバティブを抱えていても、含み損を隠したまま決算を公表できる。
リスクを知らずに安心して株を持ち続け、ある日突然「実は数千億円の損失がありました」と発表されて株価が暴落したら投資家は困りますよね。
だからこそ、取引の透明性を高め、デリバティブをオンバランスする必要性があるのです。
問い例③ 似た仕組みの異同点から、論点の抽象化と具体化を行う。
先日このようなポストをしました。
Q1. 会社法で規定されている「資金調達手段」にはどんなのがあるでしょう??
Q2. またその資金提供者がどのようにその資金を回収しているか?? パッと言語化できますか?
https://x.com/kcp48336541/status/1964591159017361792
株式と社債。
どちらも会社法で資金調達手段として規定され、比較論証問題として出題されます。
理解の抜け漏れがどれだけあるかが一瞬でわかるので、良問であり今後もこう言った問題は本試験で出題され続けるでしょう。
学習する上では、この論証を読み、異同点を理解しようとするのも必要です。
一方で、角度を変えて考えてみることで、理解はぐっと深まります。
「2つとも資金調達の方法だ。じゃあ、資金調達手段って他には何があるんだろう?逆に投資家はどうやってお金を回収の仕方ってどんな方法でやってるんだっけ?」というように、「資金調達」というワードから抽象的に考え、また調達資金がどうやって回収されていくのかを具体的に考えてみるのです。
人の脳は「問い」が発生すると、それを解決しようと動き出します。
アンテナが貼った状態で、条文を読むと、上記のポストについて、投下資本の回収手段にはさまざまなものがあることが条文からわかります。
そして自分が立てた「問い」から得た答えは、確実に自分の知識として、血肉化され、あらゆる論述問題で力となります。
理論、論証の読解力、問いを立てる力は一朝一夕には身につかない
今、論点理解がなかなか追いつかず、答練の論証で点数が取れない受験生は、ぜひ「問い」をたてることを意識してみてください。
上記はあくまで「問い」の参考例です。
自分なりの「問い」を言語できてくると、理解の精度を高めることができ、どんな角度から試験問題を出題されても合格点をとれる論証ができるようになります。
【執筆者プロフィール】
公認会計士試験合格研究所(執筆者:所長KEN)https://x.com/kcp48336541
公認会計士試験合格研究所では、会計基準、監査論、会社法で規定されているさまざまな概念や定義、またそれらが規定された背景について、中学生でもわかるようなレベルで分かりやすく解説しています。
また、受験勉強のモチベーション維持方法など(合格後の監査法人での仕事の様子や年収、恋愛など)について勉強の休憩時間によめるサクッとしたポスト(ツイート)を行なっています。参考にして見てください。