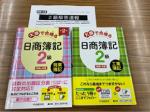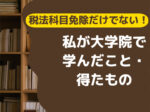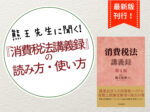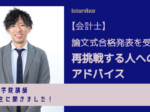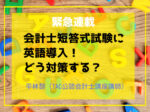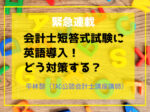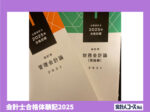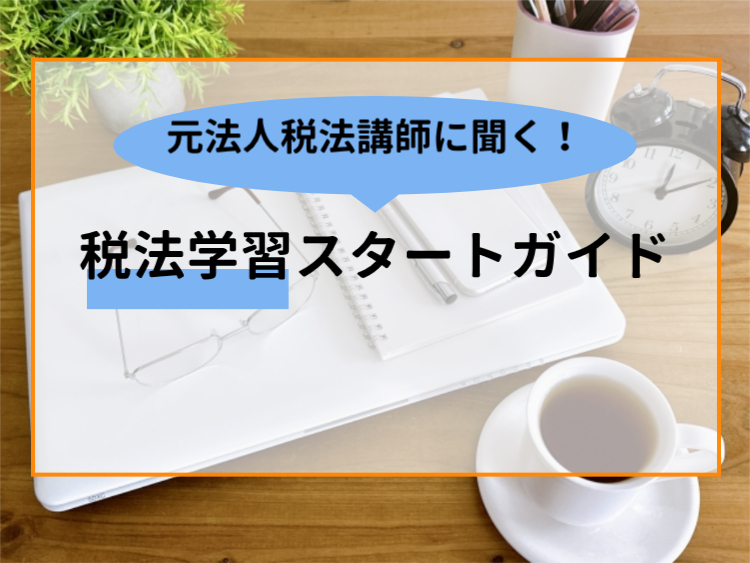
税理士を目指す皆様へ
はじめに
はじめまして。
「税理士を目指す皆様へ」(Xネーム)です。
大手資格予備校で税理士試験法人税法の講師をしていた経験から、法人税法に関するQAや税法科目の攻略法をXで発信しています。
実は私自身、つい最近まで受験生でもあります(今年8月に最終科目である消費税法を受験し、結果待ちの状況)。
一応予備校の模範解答では確実ラインだったので、実務の勉強をスタートしています。
経歴としては、大学時代から税理士を目指し、1年1科目ずつ、簿記論・財務諸表論・法人税法に一発合格しました。
その後、大手資格予備校から声をかけられ、法人税法講師として働きながら、相続税法に合格しています(両立に苦労し、4回かかりました)。
4年ほど務めた講師業は、第75回対策をもって退職、現在は税理士事務所に転職しています。
さて、税理士試験では原則5科目の合格が必要とされています。
登竜門である簿記論・財務諸表論を突破した後、どの科目を選択するか迷う方は多いのではないでしょうか。
講師をしていた時は、よく受講生から質問を受けていました。
そこで本稿では、私自身の受験経験も踏まえ、税法科目の選択順序についてお伝えしたいと思います。
税法科目の選択順序はどうする?
ついこの間まで受験生であり講師であった私の考える税法科目の選択順序ですが、結論としては、「法人税法」→「所得税法or消費税法」→「相続税法or消費税法」の順番が良いと思っています。
このような順番になる理由を下記にまとめました。
法人税法
法人税法の学習において簿記論・財務諸表論の内容や仕訳が度々登場するため、会計科目の知識が新鮮なうちに選択をするのがおすすめです。
また、税理士事務所・税理士法人の顧問先の大部分は法人が占めているため、法人税の知識は実務上必要不可欠です。法人税法を合格していると就職活動で高い評価が得られるので、早期に合格しておくことはキャリア的な面でもメリットがあると思います。
所得税法
法人税は所得税から分離して生まれたという背景があり、根幹となる考え方がよく似ています。所得税法を選択しようと考えている方は法人税法を学習した後に選択するのがおすすめです。
ちなみに、私自身は所得税を受験科目には選択しませんでしたが、知識習得のため第76回対策の講義を受講しています。やはり実務では避けて通れない科目です。
消費税法
税法の中でもかなり処理スピードが求められるため向き不向きがあります。初めての税法に選択しがちですが、内容は比較的難しく、近年の合格率も低いため、他の税法を経験してから選択するのがおすすめです。
また、消費税法の知識がなければ正しく仕訳がきれないため、実務では必須の科目です。勉強の内容が最も実務に直結するのは消費税法だとよく耳にします。
相続税法
税法経験者や官報リーチの方が受験者の大部分を占めるため、受験者のレベルが高い印象があります。理論暗記は出来ていて当たり前で、一歩踏み込んだ理解ができていないと合格は難しいと思います。したがって、税法をある程度経験してから選択するのがおすすめです。
また、実務をする上で必須の科目とは思わないですが、勉強しておくと相続案件をこなすことができます。相続や事業承継は時代の背景から年々需要が高まっているので、相続税法の知識は実務をする上で武器になると思います。
おわりに
各科目のボリュームは「法人税法」が最も多く、「所得税法」「相続税法」「消費税法」の順に少なくなっていきます(法人税法のボリュームを100とすると、所得税法は90、相続税法は70、消費税法は50くらいでしょうか)。
上記の選択順序は、各科目十分な時間が確保できることを前提としたものになっていますが、実際は、仕事や育児、大学などの都合も考えた上で選択をする必要があります。
場合によっては、上記の国税4法以外のミニ税法や大学院免除も検討されると良いと思います。
著者プロフィール
税理士を目指す皆様へ
元大手予備校法人税法講師。簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法に合格済み。令和7年消費税法受験。
X→https://x.com/zeirisiwomezase