
まえさん(20代後半・会社員)
【受験プロフィール】
合格科目と合格年:R3簿記論・財務諸表論、R4消費税法、R5固定資産税、R6法人税法
学習スタイル:独学
▶画像は愛用電卓(本人提供)
税理士を目指したきっかけ
最初のきっかけは、仕事を進めるうえで簿記の知識が必要になったことでした。
そして、せっかくなら簿記の資格の中でも一番難しいものにチャレンジしようと思い、簿記1級に挑戦し見事合格することができました。
その後、簿記の世界に少し興味がわいたので自分で調べてみて税理士という資格に出会いました。
ちょうどそのころ、仕事の中でも税務(主に消費税)の知識を必要とする場面に出会い始めていたのでこれはちょうどいい機会だと思い、税理士試験への挑戦を始めました。
各科目の勉強方法
受験科目ですが、仕事をするうえで必要な知識を得たかったので簿記論・財務諸表論・消費税・法人税は確定で残りの一つを何にするかという感じでした。
自分の中では、理論より計算の方が自信があったので計算を固めやすい固定資産税を5つ目の税法科目として選択しました。
順番はセオリー通り簿財から始め、その後の税法は自身のプライベートの予定などと併せつつ決めました。
全般
以下に勉強法などを書きますが、結局最後は気合です。
理論暗記はつまらないし、計算問題を繰り返し解くのも最後は面倒くさくなってくるので自分自身の気持ちとの勝負になってきます。
こういった小さいことをコツコツ積み重ねられる方が税理士試験に合格していくのだと思いました。
簿記論
受験前々年に簿記1級に合格していたのもあって、専らアウトプット中心で進めました。
TACの外販問題集で個別問題集・総合問題集を中心に過去問や予想問題集を書店で購入し、いろいろなパターンの出題方法に対応できるように勉強しました。
また、解き進める中で自分がしやすいミスのパターンを洗い出し、それを次回以降の問題演習の最初に思い出すことを繰り返してケアレスミスの撲滅に努めました。
財務諸表論
こちらも同じく簿記1級時代に勉強した知識がそのまま生きたので専らアウトプット中心で勉強をしていました。
特に計算は早い段階から過去問レベルで40点取れることが分かったので基本は簿記論の学習に任せ、ひたすら理論の学習に重点を置きました。
恥ずかしながら本試験前のGW期くらいまで本試験で理論が出題されることを知らなかったので理論の学習はそこから急ピッチで仕上げました。
TACの穴埋め式の問題集を購入し、それをひたすら繰り返すことで理論の知識のインプットを進めていきました。
最終的にはTACの外販の理論問題集を駆使して何とか最低限のレベルにまで仕上げることができました。
消費税法
この科目については私の中で唯一1年以上かけて勉強していたので時期を分けて書きます。
R2.10~R3.5(1回目不合格まで)
この時期はまず計算の基礎を固めていました。
TACのみんなが欲しかったシリーズで取引分類や、納税義務など基礎のインプットをしていました。
その後はTACの総合問題集の基礎編である程度の解き方をマスターしましたが、このままでは簿財が全く本試験までに間に合わないことを悟り、簿財に全振りするため消費税の勉強を中断しました。
R3.12~R4.8(合格するまで)
簿財の合格発表を受けて消費税の勉強を再開しました(なぜ本試験後から再開しなかったのかと今になれば思います)。
かなり時期が空いてしまったので一度みんなが欲しかったシリーズに立ち返りました。
その後は総合問題集を応用編まで進めていき計算についてはスピード・正確性とも自信を持てるようになりました。
ただ、ここで一つ問題が発生します。
GWに過去問を解いた際に理論が出題されることを初めて知ります(1年ぶり2回目の気づき、なぜ去年の失敗から学ばなかったのかは本当に謎です)。
そこから急いで理論マスターを購入し、理論暗記を始めましたが残念ながら本試験までに暗記して持っていけたのは10題ほどでした。
その代わり、理論マスターと並行して理論ドクターをやりこみ○×や取引分類の正誤などについてはある程度本試験に太刀打ちできるくらいまで仕上げることはできました。
事例問題に対する対策を固めた結果かはわかりませんが、暗記をした題数は少ないながらもR4年の本試験で合格をすることができました。
固定資産税
上記の通り過去に2度同じ失敗をしたため、今回は一番に過去問を確認し理論の出題があることを確認しました。
そして消費税の結果発表後、すぐに固定資産税の理論マスターを購入し理論暗記をスタートしました。
理論暗記については音読から開始し、ある程度スムーズに読めるようになった段階でタイピングでのアウトプットと音読を並行するようにしていました。
一度で100%覚えようとせず、重ね塗りするようなイメージで何度も何度も繰り返しました。
また、直前期には大原の理論サブノートを購入し言い回しの違う中でも覚えたことを瞬時にアウトプットできるよう赤シートを使って音読を繰り返しました。
計算については、TACの計算問題集を使用しました。
固定資産税は計算パターンがかなり少なくかつ、問題を見たら大体どのパターン化の判別もすぐにできるのでパターンごとにどういった流れで税額を求めに行くのかを深く理解できるように勉強しました。
問題集で0から回答の型を作るのは大変でしたが、ここにしっかりと時間を費やしたことで直前期の模試や他校の計算問題集でも特にうろたえることなく取り組むことができるようになりました。
法人税
法人税は理論の題数が多いこと、自分は理論を固めるまでに時間がかかることなどを踏まえて消費税の時と方針を一転し、理論を固めることを優先した勉強計画にしました。
理論マスターを購入し、固定資産税の時と同様ひたすら音読を繰り返しました。最初のうちは理論マスターを見ながらの音読ですら詰まりながらでしたが、固定資産税の受験直後から開始していたおかげか、年度をまたぐころにはだいぶスムーズに音読できるようになっていました。
その後はタイピングや筆記をうまく織り交ぜながら「覚えたのに試験で書けない」という状態にならないように理論暗記を進めていました。
計算についてはTACのみんなが欲しかったシリーズが法人税には存在しなかったのでネットスクールの教科書を使用し、基礎知識のインプットを年明けくらいから始めました。
法人税の計算では問題文の読解力が大切になってくるので問題中のどの数字を計算に使用するかを常に注意しながら問題を解いていました。
試験勉強していた時に特に意識していたこと
全て書くと長くなりすぎるのでここでは特に意識していたことを書いていきます。
理論暗記は一回で覚えきろうとしない
理論暗記はつらいです。私の中では税理士試験の勉強の中で一番嫌いな時間でした。
特に「一文字違うからやり直し」的なことがどうしても合いませんでした。
そこで私は「気づいたらある程度は覚えている」状態を目指してひたすら音読を繰り返すことにしました。ある程度固まったらタイピングを活用して暗記内容の確認と修正をするようにしました。
こうすることで自分の中で理論暗記がそれほど苦にならなくなりました。
インプットよりアウトプット重視
当然ですが、本試験で回答を答案用紙にうまく表現できなければ合格にはたどり着けません。
そのためにはわかっている状態からそれを表現できる状態まで昇華していく必要があります。
日々の勉強ではそれを常に意識するようにしていました。特に理論は覚えることをゴールにするのではなく、答案として書ける状態をゴールに設定してそれができるようになるまで繰り返し回し続けました。
腱鞘炎対策
税法の試験では約2時間ひたすらに書き続けなければならないので、一度腱鞘炎になってしまうと日々の勉強中から痛みと戦っていかなければならなくなり、かなり不利な状況となってしまいます。
本試験でも腱鞘炎になっているとそれだけで大きく不利になってしまうといって問題ないと思っております(かくいう私も固定資産税の受験をしたときはかなりひどく、本試験は気合で乗り切りその後は1週間くらい筆記ができないような状態でした)。
ここでは少し私がやった腱鞘炎対策を紹介させてもらいます。
○理論暗記のアウトプットをタイピングでやる(効果大。そもそも書かないため。)
○ボールペンを軽く握るよう意識する(効果小。意識だけで対策できたら苦労しない。)
○ボールペンのグリップを柔らかくする(効果中。気晴らしにはなる。)
○日々の勉強ではシャープペンや鉛筆を使う(効果小。ほぼ意味なし。)
○5分おきくらいに手のストレッチをする(効果中。本試験中はこれに頼った。)
模試の結果は気にしすぎない
毎年6~7月くらいに各予備校の模試が開催されます。こちらは独学であればこそぜひ受験すべきと思っているのですが、その結果についてはあまり気にしすぎるものでもないです。特に税法の理論については暗記が進んでいれば高得点がとりやすいのですが、それは逆に直前期の伸び代が少ないことを意味しております。理論暗記が間に合っていないことが私は多かったので「この理論を覚えていればあとX点伸びるから実質A判定」のメンタルで結果を眺めていました。
最後に
税理士試験は年一回の試験です。
残酷ですが、日々の確認テストを全て満点でこなしてきても、模試で満点をとっても、その年一回の試験の日にうまくいかなければ結果は伴いません。
こういった試験で合格しやすいのは、「いい時は100点取れるが悪い時は55点しか取れない」の人より「いい時でも70点しか取れないが悪い時でも60点は取れる」の人だと思っています。
SNSではいい時の100点が目立ちがちですが、独学や社会人の方は特に「他人は他人、自分は自分」のメンタルで落ち着いて日々やるべきことを設定し、合格に向けて勉強を進めていってもらえたらと思います。



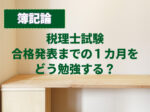

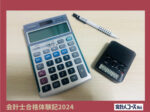
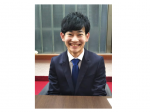







--150x112.jpg)

