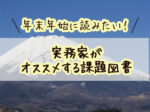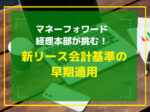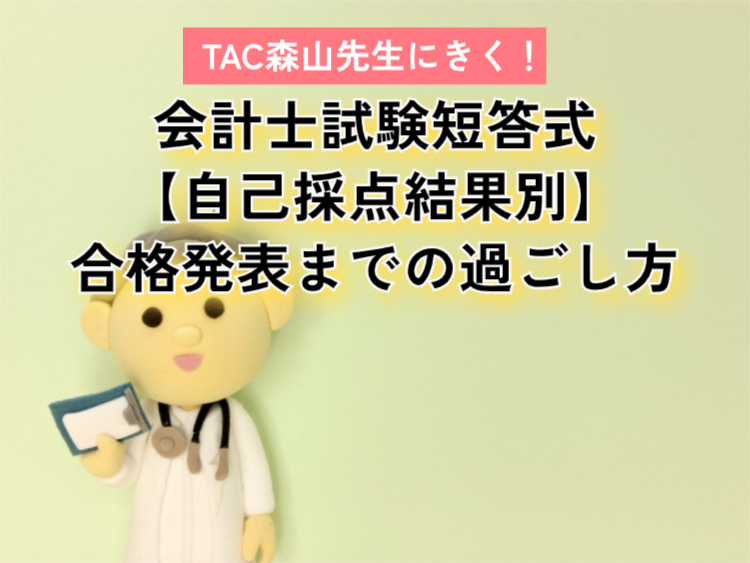
森山一行(TAC公認会計士講座講師)
短答式試験、おつかれさまでした!
皆さんこんにちは。森山一行と申します。
TACの公認会計士講座で財務会計論(理論)の講師を務めております。
先日の短答式試験、本当におつかれさまでした。
森山は予備校で講師業をしている身ですが、この短答式試験だけはもう二度と受けたくありません。
肉体的にも精神的にも過酷な試験です。
全力で受け抜くこと自体、偉業です。
皆さんは既に素晴らしい。
短答式試験後に陥りがちな罠
しかし、ここに罠があります。
特に自己採点がそこそこ以上にいい場合、一種の「やり遂げた感」で気持ちが充実してしまう可能性があります。
(自己採点の結果に関わらず、受け抜くこと自体が偉業なので「やり遂げた感」に浸る誘惑は抗いがたい…)
更に短答士式試験の直後は一種の祝祭感に包まれます。
・毎回必ず何かサプライズが起きます。出題内容が難化しても易化してもサプライズ
・解答速報という燃料を各予備校がガンガン投入
・そしてボーダーラインを巡る議論がリアルの休憩室でもSNS上でも展開
短答式直後は業界をあげて祭り特有の軽躁状態に包まれ、受験生時代の森山もそうでしたが、多くの受験生はその空気に巻き込まれます。
で、皆さん。
そんな祭りには極力参加せず速やかに淡々と次への準備に着手するんですよ!
そりゃそうですよね。来年8月の論文式に合格することが最終目的です。
これを見据えるならば一刻も早く論文式試験の準備に着手することが一番合理的です。
祭りに現を抜かす暇はこれっぽっちもないはず。
そこで本稿では、そんな軽躁状態から離脱するきっかけとして、あなたの自己採点結果を活用した論文対策の基本方針案をお伝えします。
自己採点結果をもとに、論文対策を考えよう
自己採点の結果は、あなたの現状の到達点を示しています。
以下に当てはまるかどうかチェックしてみましょう。
それぞれについて基本方針を「診断」と「処方箋」でお示しします。
1.皆が解ける問題(正答率が高い問題)をきちんと正答できなかった
2.皆が解けなさそうな過度に難しい問題に時間を投入しすぎた
3.科目ごとに得点にばらつきがある。得意科目と苦手科目の差が大きい
4.同一科目内にばらつきがあり、得意論点と苦手論点の差が大きい
「1.皆が解ける問題(正答率が高い問題)をきちんと正答できなかった」人へ
診断:基本的論点の習熟不足。
処方箋:
正答率が高い問題のうち、あなたが正答に辿り着けなかった問題について、テキストに戻って徹底的に復習してください。
その際、試験中の思考プロセスを思い出しつつ、どこでどう間違ったかを明確にすることが大事です。
(だから本試験の記憶が忘れ去られる前にできる限り早期に行ってください。)
明確にするというのは、言語で説明できるようにせよ、という意味です。
短答式と論文式は出題傾向は違います。が、短答式における正答率が高い問題は、短答式でも論文式でも共通して要する基本的な内容を含んでいます。
ここを他の受講生に後れをとっているのは、論文式でも苦戦を強いられるリスクが高いので、ここは徹底的な手当を要します。
「2.皆が解けなさそうな過度に難しい問題に時間を投入しすぎた」人へ
診断:網羅的な知識の不足。
処方箋:
教材を(優先順位を大事にしつつ)できる限り網羅的に身につける覚悟を持ってください。
過度に難しい問題というのは教材に盛込まれていない細かい知識を要する問題です。
「これは教材にない内容の肢だ」「こんな細かい知識は誰も知らないはず」「(こんな教材にない)マニアックな計算は初めて解く」
…要するに「こんなの誰もできないな」という問題ですね。
こんな問題には、どうせ誰も解けないので長考するだけ時間の無駄です。時間を割かず適当な番号をマークして次の問題に行くのが最善です。
しかし、「こんなの誰もできないな」と自信を持って判断するためには、教材の内容を漏れなく網羅的に身につけているという前提条件を要します。
自分の網羅性に自信がないと「これは自分が知らないだけで他の受験生は知っているのかも」という疑念を払拭できず、本試験でこの判断を行うのは難しいです。
この試験は競争試験なので、①皆が解ける問題は確実に解き、②皆ができない問題は最小限の解答に留め、③その間の問題を実力に応じて攻めて得点する、という順番で自身の得点を最大化しなくてはなりません。
②のためには、知識の網羅性は不可欠です。
また、自分の知識の網羅性に自信を持つということは、本試験の緊張感の中で冷静に実力を発揮するための心の支えになります。
(本試験の緊張感の中で冷静に実力を発揮することの難しさは、短答式を全力で戦い抜いたあなたなら、納得のはず。)
「3.科目ごとに得点にばらつきがある。得意科目と苦手科目の差が大きい」人へ
診断:論文式でリスク大
処方箋:
「全科目満遍なくそこそこ」を目指す。
短答式は4科目の合計得点で合否が決まります。不得意科目の後れを得意科目でカバーすることが可能です。
しかし論文式は、大問ごとの素点を偏差値により換算して得点が算定されます。平均点からの乖離が得点に跳ね返ります。
受験生時代の森山がまさにそうでしたが、不得意な科目より得意な科目の方を勉強したくなります。不得意科目は苦痛ですが得意科目は楽しいです。
しかし論文式が偏差値に基づくことを考えれば、得意科目を更に伸ばすことよりも苦手科目を人並に持っていく方が、伸びしろが大きい分、実は楽なはずです。
そしてそうする方が、合格という最終目標を見据えるなら、効果的かつ効率的なはずです。
苦手科目を勉強するのは苦痛です。が、そうすることが合格への王道かつ最短ルートです。
「4.同一科目内にばらつきがあり、得意論点と苦手論点の差が大きい」人へ
診断:論文式でリスク大
処方箋:
「全論点満遍なくそこそこ」を目指す。
上記の3.の問題意識と同一で、得意論点に更に磨きをかけるよりも苦手論点を人並に引き上げるほうが労が少なく得るところが大きいです。
どの論点が問われても人並にできるという実力をまず目指してください。
大問ごとに偏差値に基づき得点が算定されます。また、どの論点が出題されるかは蓋を開けてみるまで判りません。
なので論点ごとに出来不出来にムラがある受験生より、全論点がそこそこの受験生の方が、どのような出題でも安定して得点でき、ひいては論文式で失敗するリスクが低いはずです。
(3.と4.に共通)
得意科目・得意論点を作るのは、全科目全論点をそこそこにしてから取り組むことであり、優先順位を反対にしてはいけませんよ!
1.から4.どれも該当なし
診断:順調ゆえに祭りに浸り論文式へ頭を切替えるのが遅くなるリスク大
処方箋:
一刻も早く租税法、特に法人税法の準備に着手しなさい!
2009年5月の短答式(当時は短答式は5月しかありませんでした。)の翌日から短答式の合格発表まで、森山は頭が切り替わりませんでした。
当時の森山は更に悪いことに、苦手を得意で補うべし、という危険思想に染まっていたので、論文式は散々でした。
皆さんには同じ轍を踏んでいただきたくないので恥を忍んで告白する次第です。
おわりに
合格発表まで本当にあっという間です。
そしてこの時期の過ごし方は、あなたの論文式試験の良否に大きく影響します。
この時期に向いているベクトルの先にあなたのゴールがあります。向きが悪ければ、結果も悪いです。
ベクトルを修正するのは、早いほどいいです。
本稿が軽躁状態からのいち早い離脱に役立てば幸いです。
どこからでも前を向くことができる。ファイト!
プロフィール
森山一行(もりやま・かずゆき)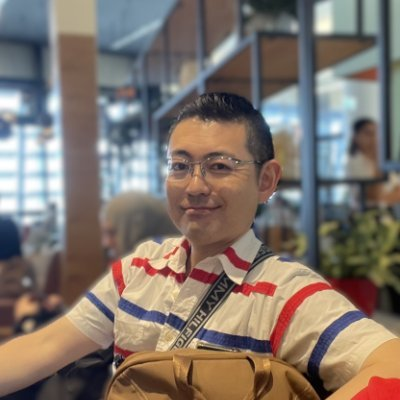
大学は哲学科(美学美術史学)、最初の職場は精神科診療所(精神科ソーシャルワーカー:PSW)。
紆余曲折の果てに奥さんに説得され公認会計士受験。
合格後も紆余曲折が続きあらゆる監査法人に蹴られ、蹴られ、蹴られたのち奇跡のご縁で個人事務所に就職。
そこで再生支援と中小企業会計税務と会社法監査を学び2019年に独立。
独立と併せてTAC公認会計士講座にて同業者製造業開始(財務会計論(理論))。



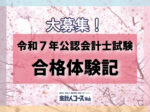

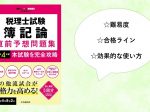
-1-150x112.jpg)