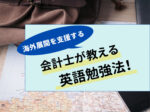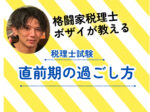投資銀行は財務数値をどう見るか?~第2回: 投資銀行は「キャッシュ・フロー」と「未来」を大事にする
- 2025/11/21
- コラム

藤波由剛(プリンシプルズ株式会社代表取締役CEO)
村橋秀一(公認会計士)
投資銀行は「キャッシュ・フロー」と「未来」への意識が強い
今回は投資銀行が財務数値のどのような点に着目するか紹介したいと思います。
どのような切り口で紹介するかは、なかなか難しいテーマなのですが、まず「投資銀行は『キャッシュ・フロー』と『未来』への意識が強い」という大きな話から始めましょう。
損益とキャッシュ・フローの違い
本論に入る前に、損益とキャッシュ・フローの違いを簡単に説明しましょう。
損益とは、多くの方に馴染みがある「売上-費用=利益」のことです。筆者は新卒時代にシステム会社で法人営業を担当していましたが、そのような財務数値とは縁のない仕事をする自分でも、自分が勤める会社の損益の数字ぐらいは何となく知っていました。
一方で、キャッシュ・フローは「会社のお金の出入り」を意味し、損益と一見似ていますが異なります。
例えば、読者の皆さんの中には「顧客に対して製品を販売し売上を計上したものの、代金の入金は後日行われる」という取引を経験したことがある方もいらっしゃると思います。
ここで会計の世界では、「売上が計上されたか否か」は「損益」の話であり、「代金が入金されたか否か」は「キャッシュ・フロー」の話となります。
言い換えると、「代金が入金されたか否か」は「売上や利益がいくらだったか」とは別の議論として扱われることになります(いわゆる現金主義と発生主義・実現主義の違い)。
損益とキャッシュ・フローの間には多くの「時点のズレ」があり、会社のキャッシュ・フローを把握することは重要であるため、「キャッシュ・フロー計算書」や「資金繰表」は、会社にとって損益計算書に加えて必要なものとなるわけです。
会社の取引はほぼすべてが「お金のやりとり」を伴います。会社は従業員や取引先にお金を払えない=資金繰りが行き詰まると「倒産」してしまいますので、しっかりと手元にお金を確保するため、キャッシュ・フローの把握が重要となります。
投資銀行がキャッシュ・フローを重視する理由
では投資銀行はなぜこの「キャッシュ・フロー」を重視するのでしょうか。筆者の経験では、3つほど理由が思い浮かびます。
キャッシュ・フローはバリュエーションに関連が深い
第一の理由は、キャッシュ・フローはバリュエーション(企業価値評価)に関連が深いということです。
投資銀行の仕事では、「会社の価値」を考える機会が多くあります。金融の世界には、「ある資産の価値は、その資産が将来生み出すキャッシュ・フローの現在価値である」という考え方があり、その考え方に従うと、会社の価値もその会社が生み出す将来のキャッシュ・フローの現在価値で計算することができます。
そのため、投資銀行では「この会社はキャッシュ・フローを生み出す力が強いのか」「将来どれだけのキャッシュ・フローを生み出すのか」を考える機会が多いのです。
キャッシュ・フローを追うと事業の実態を掴みやすい
第二の理由は、キャッシュ・フローを追うと事業の実態を掴みやすいということです。
先ほど、「会計上は売上の計上と代金の入金は別の議論である」という例を紹介しましたが、その他に損益とキャッシュ・フローで差が生じやすい事項の例として設備投資(固定資産の取得)と減価償却があります。
事業の成長に投資は欠かせませんが、投資は投資時点で多額の支払いが生じる(キャッシュ・アウトがある)一方で、損益は減価償却費として遅れて分割して費用計上することになります。
そのため、損益計算書上の減価償却費は小さく利益が出ているように見えても、実際には設備投資の支払いで大きなキャッシュ・アウトがありキャッシュ・フローは赤字、ということがあり得るのです。
会社の取引はほぼすべてが「お金のやりとり」を伴うため、キャッシュ・フローを追うことで、設備投資のような損益では見えにくい事項を含め、会社の実態を掴みやすくなります。
キャッシュ・フローを追うと資金需要を把握できる
第三の理由は、投資銀行は顧客企業の資金調達をサポートすることが大きな仕事のひとつであるということです。
第1回で、投資銀行の仕事のひとつとして株式や債券など有価証券の発行によって顧客企業の資金繰りをサポートすることがあると紹介しました。
顧客に資金需要があるなら増資や債券発行の提案が求められるため、投資銀行は顧客企業の資金需要に敏感です。
資金需要を把握するには、顧客企業の資金繰り=キャッシュ・フローをしっかり把握しなければ、というわけですね。
このような理由で、投資銀行はキャッシュ・フローを重視するのかなと思います。
投資銀行は「未来」を意識する
次に、「投資銀行は『未来』への意識が強い」とはどういうことでしょうか。これは、具体的には、顧客企業やM&Aの対象会社など、ある会社の「将来の」利益やキャッシュ・フローがどのようになるかを常に考えている、と言い換えることができます。
このような発想は、投資銀行に限らず、投資家など「株式」を扱う人、そういった人たちを顧客とする人に共通します。
例えば投資家は、今は業績が悪い会社であっても、将来大きく収益を伸ばす見込みがあるなら「この会社に投資しよう」と考えます。
他の例で増資を考えると、時価発行増資(時価での株式の発行)は増資前から株式を保有している既存株主に不利益をもたらす(発行済株式数が増加することで保有株式の持分割合が希薄化するため)のですが、増資で調達した資金を事業へ投資することで会社の収益が大きく成長すると判断できるなら、投資家はその会社の株式をさらに保有しようと考えます。
投資銀行はこのような投資家と基本的に同じような発想で会社を見るので、常に「未来思考」で会社の事業計画や将来の財務数値をシミュレーションする思考を持っています。
このように書くと、投資銀行で育った筆者には「当たり前」に思えるのですが、他の業界の話を聞くと必ずしもそうではないようです。
例えば、メガバンクなどの商業銀行から投資銀行に転職した人と会話すると、「銀行では将来を見る発想が薄かった」と聞くことがあります。
筆者は銀行で仕事をしたことがないので断言はできませんし、程度の問題かもしれませんが、商業銀行は「過去の財務数値」へのこだわりの方が強いのかもしれません。
投資銀行は金融機関であり仕事の進め方は非常に「堅い」のですが、「未来を考えるDNA」を持つことは投資銀行の大きな特徴なのかなと思います。
投資銀行の財務数値への3つの着眼点
それでは、投資銀行は具体的に財務数値のどのような点に着眼するのでしょうか。人によって意見が大きく分かれると思いますが、筆者はまず以下の3点を意識しています。
はじめに、損益の構造と将来の損益イメージです。
損益を見る時、まず売上高について、過去・将来の成長性を確認します。「市場規模×市場シェア」または「単価×数量」でイメージできるとなお良いですね。
その上で、固変分解(固定費・変動費による費用の理解)を通じて、ビジネスモデルと費用構造の関係を捉えます。
売上高の将来と費用構造のイメージが持てると、将来の利益を想定できます。ここまでが損益で捉えるポイントで、何よりも事業の成長性およびビジネスモデルと費用構造の関係をイメージすることが大事です。
次に意識することは、過去・将来の事業に関連するキャッシュ・フローです。いろいろな視点がありますが、少なくとも「運転資本を要する事業か」「どの程度の設備投資が必要な事業か」は必ず確認します。
これらを理解するには、損益計算書に加えて貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書や、事業計画、設備投資に関連する会社資料などを確認する必要があります。
最後に意識することは、現状の財務状況と将来の財務状況およびキャッシュ・フローのシナリオです。
足元で現金及び預金や換金可能資産等と有利子負債(借入金など)の額がどの程度か、主要な安全性の財務指標(自己資本比率やD/Eレシオなど)がどの程度の水準かを確認します。
その上で、将来の資金繰りや資金需要(事業上のニーズの他に、多額の借入金を返済する予定などもあり得ます)を、これまでの分析とあわせて理解していきます。
おそらく、会計や簿記の勉強をしている方にとって、ここまでの説明に出てきた「言葉」に目新しいものはそれほどないのではないかと思います。
投資銀行の担当者は特別な「魔法の杖」を持っているわけではないので、考えることは至って普通なのです。
一方で、実際にこれらを「未来思考」でどのように会社の分析に適用するかイメージすることは、経験がないと意外と難しいかもしれません。
次回はもう少し詳しく、これらの着眼点を具体的な会社の理解にどのように用いることができるか、紹介したいと思います。
【プロフィール】
藤波由剛(ふじなみ・ゆうごう)
株式会社ワークスアプリケーションズでの法人営業担当を経て、野村證券株式会社にてM&Aアドバイザリーに携わる。2016年にプリンシプルズ株式会社を創業。投資銀行や事業会社の経営企画部門などの法人顧客へ「実務ができるようになる」研修と「実務力を測定する」評価を「BizObi(ビズオビ)」サービスとして提供。財務・バリュエーション領域ではコンテンツ制作・講師を担当。シカゴ大学経営大学院修了(MBA)。東京大学法学部卒業(学士)。私立開成高等学校卒業。共訳『人事と組織の経済学・実践編』(日本経済新聞出版社・2017年)。
村橋秀一(むらはし・ひでかず)
公認会計士。監査法人トーマツおよび東光有限責任監査法人で会計監査、フロンティア・マネジメント株式会社でM&Aアドバイザリー、優先株・ストックオプション評価を含む価値評価や財務DD、野村證券株式会社でM&Aアドバイザリーに携わる。2017年に村橋公認会計士事務所を設立。プリンシプルズ株式会社では、財務・価値評価領域のコンテンツ制作・講師を担当。東京大学大学院経済学研究科金融システム専攻金融工学専門修了(修士)。立命館大学経済学部卒業(学士)。日本公認会計士協会東京会広報委員会副委員長(現任)、日本簿記学会簿記実務研究部会委員(2023・24年)など。