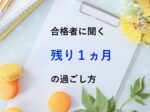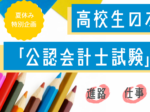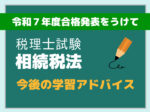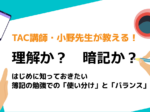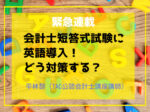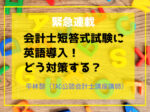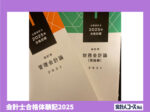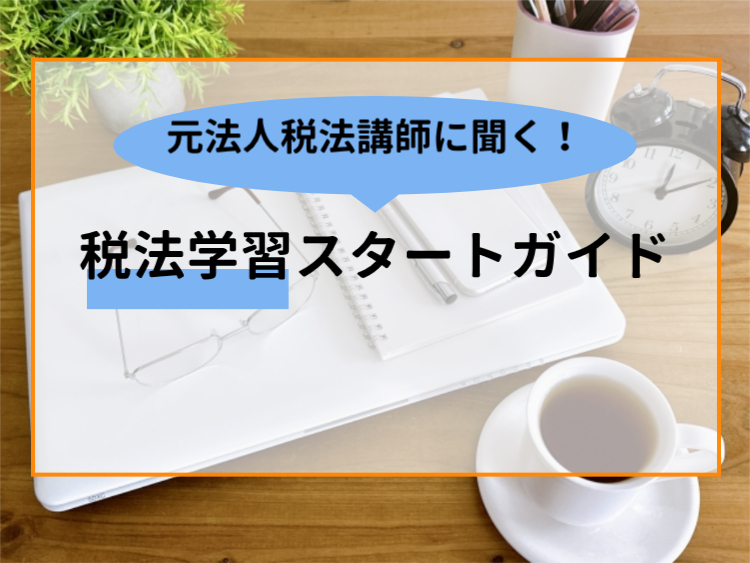
税理士を目指す皆様へ
はじめに
さて、前編では科目選択についてお話しました。
後編では、税法学習のコツについて解説していきます。
理論と計算をリンクさせる
税法は基本的に理論50%・計算50%で構成されています。
勉強をする上での最大のポイントは、『理論と計算のリンク』です。
計算の問題を解答する場合、税額を算定するまでの計算過程を答案用紙に示していきます。
この計算過程には、必ず根拠となるウラ(法令や通達)が存在します。
このウラのことを、税理士試験界隈では「理論」と呼んでいるわけです。
もちろん、試験対策においてこのウラを全て網羅することはできません。
理論テキストにも全てが掲載されているわけではありません。
それでも、計算で学習した内容と理論テキストで暗記する文章を可能な限り結びつけることが必要です。
これが、本当の「理解」であり、「真のインプット」になります。
講師時代、理論と計算を分けて考えてしまう受験生がどうしても多いように感じました。
計算と理論を『リンク』させることで、他の受験生と差をつけられるのではと思います。
効率の良い理論暗記法とは
税法においては、財務諸表論と比べてより精度の高い暗記が必要になります。多くの受験生が膨大な時間を割き乗り越え、または挫折するポイントです。
そこで、効率の良い理論暗記法を下記にまとめました。
文章を理解すること
これは当たり前の話ですが、「とにかく文字を覚えればいいんでしょ」と案外蔑ろにしていしまっている受験生が多いように感じます。
条文は、無駄のない洗練された文章です。
文節ごとにちゃんと意味があります。
1つ1つの文節の意味を理解しながら納得した上で暗記を進めると、暗記のスピードが格段に上がり、また忘れにくくなります。
とにかく音読すること
文章を理解することができたら、あとは文章をひたすら音読します。
「目で文章を見る、口から声を発する、その声を耳で聞き取る」
このように五感をフル活用することで、目で映像を、口で動きを、耳で音を記憶することができるため、効率良く暗記をすることができます。
また、覚えたと思ったら暗記箇所を全て隠して頭からお尻まで暗唱できるか確認を行いましょう。
完璧に暗唱ができたら忘れてもOK
1度完璧に暗唱ができたのであれば、その理論は、定期テストや長期休みなど、再度暗記しなければならない機会までは忘れてしまって大丈夫です。
「初めて習った講義の宿題として1回目、定期テストの対策として2回目、年末年始の長期休みで3回目、模擬試験の対策として4回目・・・」のように完璧に暗唱できたという実績を積み重ねていくうちに、思い出しに必要な時間が縮まり、最終的に長期記憶として定着していきます。
書き起こすのはNG
アウトプットしたくなる気持ちはわかりますが、日常の理論暗記で書き起こすのは効率が悪すぎるのでNGです。
きっちりと暗唱が出来るのであれば絶対に書き起こすことができるのです。
予備校ではミニテストや定期テストがあります。
書き起こす作業は、これらのテストを利用すれば十分練習することができます。
しっかり準備をして臨みましょう。
おわりに
大手資格予備校で講師を務めてひしひしと感じましたが、予備校のカリキュラムはやはりよくできています。
上記のポイントを守りながらカリキュラムに従って暗記を進めれば、本試験の前日に全ての理論が暗唱できるようになるはずです。
ここまで、私自身の受験生としての経験と予備校講師としての経験を踏まえて、税法科目の攻略法をまとめてきました。
これから税法を勉強される方に、なにか1つでも皆様のお役に立てば幸いです。
著者プロフィール
税理士を目指す皆様へ
元大手予備校法人税法講師。簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法に合格済み。令和7年消費税法受験。
X→https://x.com/zeirisiwomezase