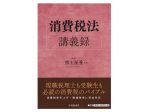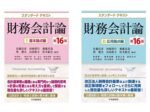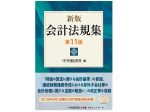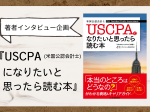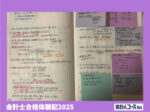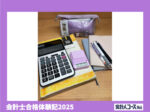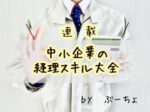読書の秋! TAC会計士講座の森山一行先生がオススメする課題図書
- 2025/9/24
- 書籍・雑誌の紹介
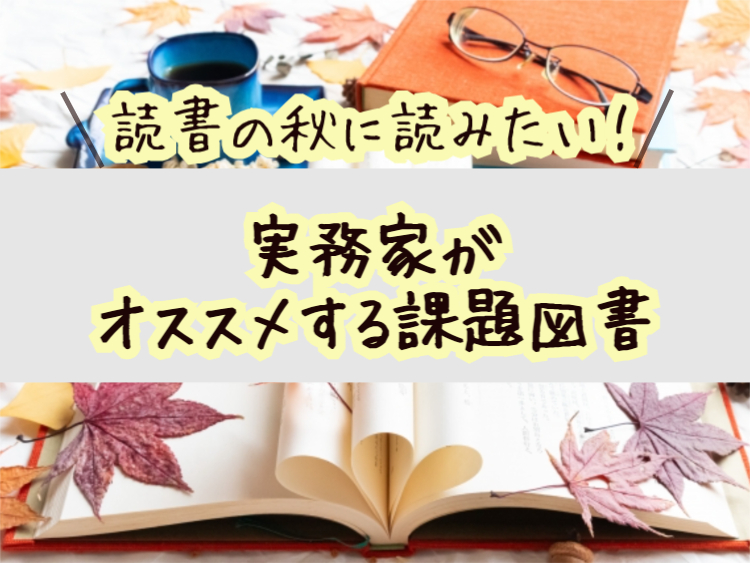
皆さんこんにちは。森山一行と申します。
TACの公認会計士講座で財務会計論(理論)の講師を務めています。
8月は会計系の試験が集中しており、上旬に税理士試験、下旬に会計士試験(論文式)がありました。試験に臨まれた皆さん、本当におつかれさまでした。
きっと死力を尽くされたことと思います。
そして、各試験予備校が出す解答速報がもちろん気になるところと思います。
が、提出してしまった答案はもはや書き換えることができません。また、解答速報に何が書いてあろうが実際の合否は蓋を開けてみないと本当に分からない。
今は、とにかく前を向いて、次の大きなイベントに備えましょう。
そう、就職活動です。
これも本試験と同じく、後悔のないように事前の準備を怠りなくやっておくことが重要です。しかも試験後から本格的な採用面接が始まるまでの期間は、長いようであっという間です。くれぐれも後悔することがないようにしてください。
ところでこの時期、特に初めて就職活動に臨まれる若い層を中心に、「コミュ力」(こみゅりょく)について、俄かに関心が高まります。「コミュニケーション能力」というやつですね。
試験合格者としての求職者は、当然試験を通過した人たちであり一定の能力水準は担保されているはずだ。なので採用面接に通るか否かは「コミュ力」の良否にかかっているはずだ…。
などと、多くの人が考えるようです。
私は採用面接を担当したことがないので実際のところはよくわかりません。
が、「コミュ力」の良否なるもので採用不採用が決まる、という単純な話ではないことはわかります。
でも、複数の人たちが集まり、ある程度同じ方向を向きながら、協力して事に当たるのが職場というものである以上、職場においてある程度のコミュニケーション能力が求めれられるのは、事実でしょう。
既に仕事を経験した方々にとっては、その辺の事情はよくご存じだと思います。
職場における自分のコミュニケーションのあり方を見つめなおすいい機会かもしれません。
そこで、本稿では、皆さんの就活に備え、皆さんのコミュニケーション能力向上に資する本をご紹介します。
とはいえ、この分野のビジネス書籍は巷に溢れています。
ここでは、私の独断と偏見で、ビジネス書籍というカテゴリーの外側から、3冊ご紹介いたします。
オススメ図書①『わかりあえないことからーコミュニケーション能力とは何か』(平田オリザ著、講談社現代新書)
人が誰かとやりとりをするにあたり暗黙の前提としている事柄がたくさんあります。
この暗黙の前提をコンテクスト(「その人がどんなつもりでその言葉を使っているか」の全体像)と呼ぶならば、コミュニケーション能力とは、相手とのコンテクストのずれを上手に処理できることだと思います。
自分にとっての当たり前が相手にとっての当たり前とどうずれているか、を直ちに認識できるならば相当なコミュニケーション上級者でしょう。
それが難しいのは、自分にとっての当たり前は普段の自分自身には意識されない(だから「当たり前」です)からだと思います。
自分にはコミュニケーションの際に当たり前の前提としていることが実はたくさんあるし、相手にも同じようにたくさんあるはず、と意識するだけでもコミュニケーションの行き違いを減らせると思います。
そのようなことを考えるためのヒントがたくさん詰まっているのが本書です。
なお、平田オリザさんは劇作家であり、本書においても演劇の文脈で話が進む場面が多いです。でも、平田オリザさんの作品を観たことがない人にも、普段演劇を見ない人にも、十分興味深く面白い内容です。
オススメ図書② 『意味がわかるとおもしろい!世界のスゴイ絵画』(佐藤晃子著、Gakken)
職場におけるコミュニケーション上、大事なことの一つは、「言いにくいこと」を「言いにくい相手」に「適時」に伝えることだと思います。
自分の失敗を上司に伝える。
既に進めてきてしまっている方向性が実は間違っていたことを仲間に伝える。
耳障りのいいことは誰でもすぐに相手に話せます。
話しにくいことは、実はクリティカルなことが多いので、適時に、つまりなるべく早く伝えねばなりません。
早く伝えた方が、早めにリカバリーでき、最終的にはいいことが多いからです。
そのためには、普段からコミュニケーションしやすい雰囲気を醸成しておくことが大事です。
ところで、そのような雰囲気を醸成する一番手っ取り早い方法は、普段からコミュニケーションの「頻度」を多くしておくことです。
内容ははっきりいって関係ない。
業務の足を引っ張らない程度に、何でもいいから雑談しておくのは緊急事態の際に重要です。
その点で話題を多く持つことに意味があります。
話の引出しが多いに越したことはないのです。
スポーツの話題などはよさそうです。
関心さえ持てば情報源はたくさんあると思います。
歴史の話もよさそうです。
幅広い世代で歴史好きの人は多いです。
ところで森山は、スポーツの話も歴史の話にも相当疎いです。
そこで、唐突ですが、絵画はいかがでしょう。
(森山は会計実務家の中では少数派の「美学美術史学科」出身です。)
入り口としておすすめしたいのが本書です。
75人の画家の作品を1枚ずつ網羅的に紹介してあります。
漢字全てにフリガナが振ってあるような子供向けの本です。
しかし、多くの画家のいろいろな絵画に一気に触れていただき、自分にとって「なんかピンとくる」1枚を見つけていただくのが、絵を好きになる最上の方法です。
この本には、森山が今推している画家であるカルロ・クリヴェッリや、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールやヴィルヘルム・ハマスホイが…全く取り上げられていません。
本書で取り上げられていない多くの画家や作品がたくさんある宝の山が絵画の世界です。時間がある今、是非飛び込んでいただければ幸いです。
オススメ図書③ 『山頭火俳句集』(種田山頭火著、夏石番矢編、岩波文庫)
上記②と同様の文脈で、俳句はいかがでしょうか。
とはいえ、山頭火は通常の五七五の17文字にとらわれない自由律俳句で有名なので、ちょっと変化球かもしれません。
同じ自由律俳句でもう一人有名なのが尾崎放哉です。
山頭火も放哉も、どちらも孤独を表現します。
放哉は悲壮感が漂う、自分自身がどっぷり浸かりこんだその孤独の真ん中から硬い核を抉り出したような雰囲気です。
一方、山頭火はちょっととぼけたような、自分は確かに孤独なんだけれどもそんな自分自身を客観的に見ていてほのかにユーモアがにじみ出ている雰囲気です。
こんな感じです。
咳をしても一人 放哉
ひとりで蚊にくはれてゐる 山頭火
端的に言うと、ネタツイの雰囲気があるのが、山頭火です。
というと山頭火の研究者や信奉者からお𠮟りを受けるかもしれませんが…。
山頭火の句を拝借するとネタツイがいくらでも作れます。
分け入っても分け入っても青い山 山頭火
分け入っても分け入ってもタスクの山 森山
こんなことを言っていると山頭火の研究者や信奉者から冒涜だ!と責め立てられるかもしれませんが・・・恐縮です。
そこはかとないユーモアも、職場におけるコミュニケーションの頻度を高めるには有用でしょう。
やりすぎるとまずいですが。
鋭い言語感覚と教養のみならず、ユーモア感覚までも養うことができる山頭火、この機会にいかがでしょうか。
以上3冊です。
今回の企画で、他の人が余り選ばなさそうなものを選んでみました。
十分に就職活動の準備をしたうえで、せっかく少し時間があるのだから、会計専門書やビジネス書とは違うジャンルにチャレンジいただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【プロフィール】
森山一行(もりやま・かずゆき)
大学は哲学科(美学美術史学)、最初の職場は精神科診療所(精神科ソーシャルワーカー:PSW)。
紆余曲折の果てに奥さんに説得され公認会計士受験。
合格後も紆余曲折が続きあらゆる監査法人に蹴られ、蹴られ、蹴られたのち奇跡のご縁で個人事務所に就職。
そこで再生支援と中小企業会計税務と会社法監査を学び2019年に独立。
独立と併せてTAC公認会計士講座にて同業者製造業開始(財務会計論(理論))。