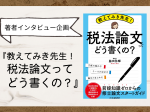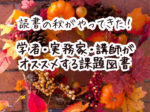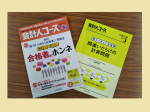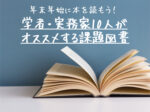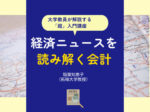読書の秋!ヤスさんがおすすめする課題図書
- 2025/9/9
- 書籍・雑誌の紹介
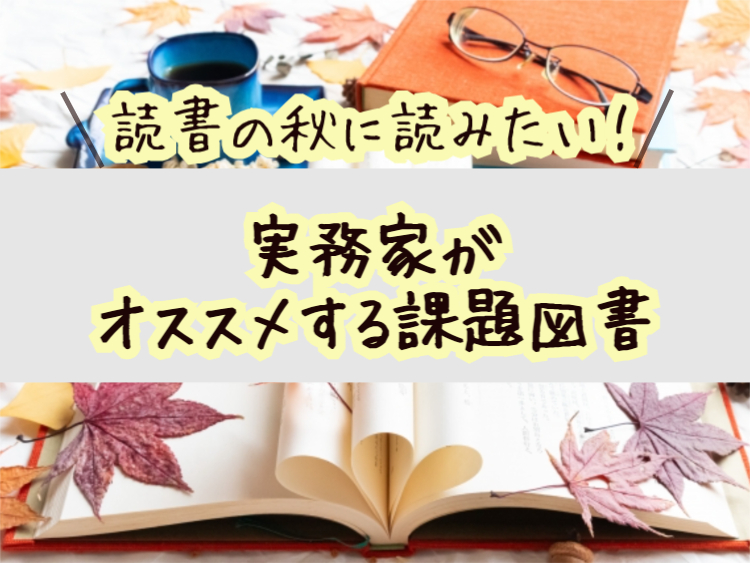
【編集部より】
読書の秋。 「スキルアップがしたい!」、「キャリアやプライベートで新しい発見がしたい!」と考えている人も多いのではないでしょうか。そこで、本企画では、実務家などの読書愛好家から、会計人コースWeb読者の皆さんにオススメする「読書の秋の課題図書」をご紹介いただきました(1日お一人の記事を順不同で掲載します・不定期)。
受験勉強はもちろん、仕事や人生において新しい気づきを与えてくれる書籍がたくさんラインナップされています。ぜひこの機会にお手にとってみてください!
はじめに
「会計系受験生、会計業界の皆様に『新しい発見』があるような書籍の紹介を」という依頼をいただきました。
これまで私は、会計監査や会計・内部統制・開示系アドバイザリー業務に携わってきたので(現在もそうです)、日々会計上の論点や企業の課題に直面します。
その際よく感じるのは、目の前の論点や課題への対処はそれほど難しくなく、関係者がまだ気づいていない論点や課題の早期発見は難しいということです。
また、対応の時間や選択肢が豊富になるので早期発見の重要性を痛切に感じます。
ですので、目の前に見えるモノよりも、今の自分には見えないモノ、あるいは、見えないモノを見るための方法や試行錯誤にとても関心が高いです。
私が書籍を選ぶときも、そういった方法や試行錯誤が記されているものを選びがちです。
今回は、最近私が選び読んだ書籍の中から3冊ご紹介します。
オススメ書籍①『直接原価計算論 学説の変遷とわが国での展開』(高橋賢著、中央経済社)
現在の直接原価計算だけをなぞっても、本質の理解には至りません。実務では教科書通りいかないことが多いので、なぞるだけではなおさら活用が難しいです。
本書では、直接原価計算論が形成されるに至った経緯を、過去の学説の変遷と我が国での展開(何から始まり、どこがどう変わったのか)を丁寧に追って直接原価計算を紐解いています。
また、学説の十分な理解は論文を読むだけでは難しいですが、故人にインタビューすることはできないため、論文をベースに故人の考えたコトを想像するしかありません。
本書はサラッと読めますが、当時の社会情勢、学者の生い立ちや職業、そして、書かれているはずなのに書かれていない内容、それらから、確からしいコトを積み上げて、全体として矛盾がないか、整合しているかを検討し、学説の変遷を辿るといった地道な作業が実施されたに違いないと思えます。
周りが固定費を製品にどう配賦するか考えていた時に、直接原価計算の先駆者Harrisが配賦しないことを思いついたのですが、同書を読んで、社長に詰められているコントローラー(Harris)の姿が私には思い浮かびました。
売上高と利益が対応して推移するような損益計算書を作成する社長からの強い要請を受け、苦肉の策として配賦しないことを思いついたような気がしました。
同書は、このような試行錯誤による確からしいコトの積み上げです。そういえば私も実務で、同じようなことをやっています。
収益認識基準の導入では、従来の実現2要件との比較によって、基準の理解を深めました。
内部統制基準の改訂では、コーポレートガバナンス・コードとの関係やサステナビリティ開示等の国際的な潮流の中で、改訂の意義を考えました。
また、今実施している改正内部統制報告書の事例分析では、経営環境や事業内容からリスクや対応する内部統制を想像して、各企業の報告書を読んでいます。
オススメ書籍②『ガバナンスを語る』(中村直人著、商事法務)
「企業法務のプロによる、リベラルアーツと日本企業のガバナンス論」という本の帯に惹かれて手に取りました。
リベラルアーツは私の好きな言葉です。
「自分の思考の檻から自由(リベラル)になるための技術(アーツ)」を意味すると別の本で知りました。
本書では、民主主義と自由主義の変容、社会構造の変化を踏まえながら、東京証券取引所のBPR1倍未満通知や、政府のサステナビリティに関する有価証券報告書への記載義務による情報開示規制(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標等)も考慮に入れて、日本の最近のガバナンスの在り方を論じています。
規制から自由になり、規制自体を自社にとって役立てるためには、目の前の規制にただ従うだけでなく、諸制度の関係や国際的な潮流の中でガバナンスを考える技術が重要です。
内部統制報告制度(通称J-SOX)の実効性を向上させるために、内部統制をコーポレートガバナンス・コードやサステナビリティ開示等と一緒に検討した際の考察の解像度が、同書を読むことにより上がった気がします。
オススメ書籍③『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』(今井むつみ・秋田喜美著、中公新書)
ヘレン・ケラーは掌に冷たい水を受けて、waterという綴りがその名前だということに気づいたとき、「すべてのモノには名前があるのだ」という閃きを得たというエピソードが印象的でした。
個別事象の理解にとどまらず、一つ上の階層で全体像を理解する閃きって、とても重要だと思います。
閃きにより、理解の深度や学習のスピードは劇的に向上します。
本書は、ことばの習得プロセスの考察を通して、人間の持つ、知識を自律的に拡げていく学習の力にフォーカスしており、そのための閃きのメカニズムの解明を試みています。
私の実務経験では、旧内部統制基準では「補完統制」が、不正リスク対応では「誤謬と不正の関係の整理」が、収益認識基準では開示規定の「履行義務の内容=財又はサービスの内容」が、そして、改訂内部統制基準では「事業計画と開示」が、一つ上の階層で全体像を理解する閃きが生まれた気づきになりました。
おわりに
オススメ3冊は、私にとって「直接原価計算の考え方の生成過程」、「日本の最近のガバナンスのあり方」、そして「人間の学習の力」といった見えないモノを見るための試行錯誤に映りました。
それらの内容だけでなく試行錯誤のアプローチが、私の実務でとても役立っています。
結局、見えないモノを見るためには、あるかないか不確かなモノを見ようとする意思、すなわち好奇心が必要不可欠で、自分が興味を持った書籍を実際に手に取り読んだり、いろいろなことに挑戦したり、一歩踏み込むスタンスが大切だと思います。あと、好奇心を起動させ続けられる体力、カラダを鍛えることも大切(私は水泳をずっと、最近は筋トレも始めました)。
本稿によって、それが読者の皆様に伝われば幸いです。
【プロフィール】
ヤス
公認会計士
大手監査法人でキャリアをスタートさせ、現在も中堅監査法人にて会計監査や会計・内部統制・開示系アドバイザリー業務に携わる。
主な執筆物に『内部統制文書化・評価ハンドブック 6つの重要プロセスと財務報告ガバナンス』(中央経済社2024年)、『収益認識のポジション・ペーパー作成実務 開示、内部統制等への活用』(中央経済社2021年)、『内部統制におけるキーコントロールの選定・評価実務』(共著,中央経済社2010年)がある。