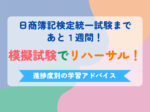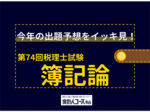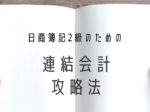新山高一(東京CPA会計学院講師)
【編集部より】
2025年8月5日(火)〜7日(木)の3日間にわたり、令和7年度(第75回)税理士試験が実施されました。
そこで、本企画では、「簿記論」・「財務諸表論」・「法人税法」・「相続税法」・「消費税法」について、各科目に精通した実務家・講師の方々に本試験の分析と今後の学習アドバイスをご執筆いただきました(掲載順不同)。ぜひ参考にしてください!
問題の感想や難易度
受験生の皆さん、本試験お疲れさまでした。
全体的に難易度は高くなく、落ち着いて解いていけば、十分に合格点が取れる問題だったと思います。理論については、法的な理由となる根拠規定をしっかりと解答し、計算については、ケアレスミスをしないことがポイントだったと思います。
早速、問題の感想や難易度について振り返ってみます。
問題の感想や解答のポイント
〔第一問〕
難解なものはありませんでした。
問1の益金算入額と問2⑵の損金不算入額は、間違えてしまう可能性はありますが、根拠規定は解答できるので、まずは規定をしっかりと解答できたかがポイントになるかと思います。
問1
変動対価の問題でした。
変動対価の取扱いがわかっていれば簡単な問題ですが、わからないと益金算入額を間違える可能性がある問題でした。
益金算入額を間違えたとしても、法的な理由となる規定は解答できるので、規定をしっかりと解答できたかがポイントになるかと思います。
問2⑴
完全支配関係がある法人間で行われた寄附に関する取扱いを問う問題でした。
出資関係をしっかりと整理すれば、それほど難しくなかったです。答案構成を考える必要はありますが、完答できたかがポイントになるかと思います。
問2⑵
一般社団法人における交際費の取扱いを問う問題でした。
定額控除限度額が使えるかの判定が難しいですが、こちらも問1と同様に法的な理由となる規定は解答できるので、規定をしっかりと解答できたかがポイントになるかと思います。
問3
欠損金の引継ぎの制限及び特定資産の譲渡等損失の損金不算入の取扱いを問う問題でした。
本試験では初めてとなる無対価組織再編も出題されており、適格合併に該当するかの判定も必要となりますが、欠損金の引継ぎの制限及び特定資産の譲渡等損失の損金不算入の取扱いにつなげるためには、適格合併にしないといけないことからも、適格判定はそれほど難しくなかったかと思います。
欠損金の引継ぎの制限及び特定資産の譲渡等損失の損金不算入の取扱い自体はそれほど難しくないため、こちらも完答できたかがポイントになるかと思います。
〔第二問〕
今年の本試験は、オーソドックスな3月末決算の中小法人の問題でした。
内容自体は、難しくないですが、問題をしっかりと読んでいないと間違えてしまう箇所がいくつかあるので、そのような箇所で間違えていないかがポイントになるかと思います。
また、問題量がやや多く、別表五(一)を作成しないといけないことから、1時間では、全部解けないであろう問題でした。
【資料2】について
保険差益に関する問題で計算自体はそれほど難しくないのですが、機械装置は設備の種類が同じでないと代替資産にならない点に注意が必要です。
そのため、問題をしっかりと読んでいないと間違えてしまうかと思います。
建物はしっかりと解答し、機械装置が圧縮記帳の対象にならないことに気づいたらプラスになるかと思います。
【資料3】について
交換に関する問題も計算自体はそれほど難しくないのですが、交換取得資産である建物Fが建物Hの譲渡直前の用途と違う用途に供していることから、圧縮記帳の適用が出来ない点に注意が必要です。
ただ、保険差益に比べると、同一用途の要件は押さえている受験生も多かったと思うので、ここは、しっかりと正答したいところです。
【資料4】について
租税公課に関しては問われている内容は難しくないので、しっかりと正答したいところです。
【資料5】について
役員給与に関しても問われている内容は難しくないので、しっかりと正答したいところです。
【資料6】について
賃上げ税制は、難解な取扱いはありませんが、対象となる給与の範囲及び助成金を収受している場合の取扱いが問われているため、少々難しい論点だったと思います。
上乗せ判定を行う際の割合などで、しっかりと正答したいところです。
合否を分けたポイント
第一問は、まず根拠となる規定をしっかりと解答できていることがまず大事です。
その上で、問1の益金算入額と問2⑵の損金不算入額でいかに加点できたかが合否のポイントになるかと思います。
第二問は、交換、租税公課、給与の取扱いをしっかりと解答できていることがまず大事です。
保険差益もできれば完答したいですが、まずは建物の取扱いが正答できているかがポイントになるかと思います。
その上で、賃上げ税制でいかに加点できたかが合否のポイントになるかと思います。
予想されるボーダーライン
第1問の問1は6割、問2は⑴で8割、⑵で5割、問3は6割、第2問は6割解けることがボーダーラインかと思われます。
学習のアドバイス
ここ最近の試験は、法人税法の基本的かつ重要な制度や最近改正が行われた制度を問う傾向にあり、この傾向が続いている状態です。
そのため、今後の学習に関しては、今まで通り、これらを意識した学習が必要になってくるかと思います。
理論について
法人税法の理論の勉強方法は、今まで通りの学習方法を継続することとなります。そのため、アドバイスも例年と同じになってしまいますが、次の点を意識して学習するようにしましょう。
① 重要性の高い論点からしっかりと押さえ、時間があれば用語の意義も押さえること
② 押さえる際には、各規定の基本的な考え方もしっかりと理解すること
③ 計算とリンクさせて具体的な金額を計算できるようにすること
④ 最近改正が行われた制度の内容をしっかりと押さえること
①に関しては、重要性の高い論点から押さえることは言うまでもないです。
また、今年の本試験では、問われ方も「この場合の税務上の取扱い」ではなく「○○の取扱い」のような何を解答すべきかがわかる問題でした。そのため、解答すべき規定がはっきりとしているため、規定は正確に解答する必要があります。
そのためにも、規定をしっかりと押さえることも非常に大事となってきます。
なお、用語の意義に関しては、数年前の本試験では、用語の意義を解答させてから、それに関連する規定の取扱いを問う形式の問題が多かったため、その対策となりますが、最近は、用語の意義をストレートに問う問題は減ったため、やや重要性は低いかと思います。ただし、全く押さえないというわけにもいかないため、理論集に記載されているものは解答できるようにしておきましょう。
続いて、②の各規定の基本的な考え方もしっかりと理解することにより、事例形式での出題に対応することができます。
事例形式の問題の場合、規定通りの取扱いが出題されるとは限りません。
その時に、各規定の基本的な考え方をしっかりと理解していれば、解答を導き出せるようになるため、そういった意味でも、各規定の基本的な考え方をしっかりと理解することは大切です。
③に関しては、最近よく出題されています。
計算と理論をしっかりとリンクさせて押さえることが大事です。
④に関しては、最近の本試験のトレンドです。
ただ、改正論点も細かいところを含めるとそれなりにはあるため、まずは重要性の高い論点を押さえることが大事です。
とは言え、基礎がしっかりとしていなければ、問題を解くことはできないため、まずは①及び②を中心に理論の学習は行っていってほしいです。
計算について
計算に関しては、ここ最近の出題傾向は、実務において頻出する論点を中心としており、問われている内容も、基本的な部分が中心であることから、難しい取扱いが問われることは減ってきた印象です。
そのため、今後の学習方法については、次の点を意識してほしいと思います。
① 各論点の基本的なところをしっかりと押さえること
② 解答スピードを上げる
③ 各論点の復習を忘れない
④ 余力がある人は、会計上の処理も押さえること
①に関しては、本試験対策だけでなく、各論点の細目や応用的な取扱いを押さえるためには、基本的な部分が出来ていることが大事なため、しっかりと基礎を固めることが大事です。
そのため、まずは個別問題集をやりこむようにしましょう。それも1回だけではなく、できれば何回も解くことを心掛けたいです。
もちろん、個別問題だけ解けばよいというわけでもなく、各規定とのつながりを理解することも大切であることから、総合問題もしっかりと解くようにしましょう。
総合問題に関しては、年内からいきなり難しい総合問題を解くのではなく、基礎をしっかりと確認する意味でも基本的なレベルの取扱いが出題されている総合問題を解くようにしましょう。
また、次の②にもつながる話なのですが、基礎がしっかりとできていない場合、取扱いを考えることに時間を要し、解答スピードが遅くなります。そういう意味でも、基礎をしっかりと固めることが大事だと思います。
②に関しては、年によっては、問題量が多い時もあるため、解答スピードも上げることが大事です。
解答スピードに関しては、総合問題を何度も解いて、スピードを上げる方法になるかと思います。基礎期や応用期で配付される練習問題などを解いて解答スピードを上げていきましょう。
③に関しては、個別問題や総合問題では、各論点の基本的な部分の出題が多く、細かい論点は、せいぜい1回か2回ぐらいしか出題されていないかと思います。今年の本試験では、保険差益の代替資産の範囲や助成金がある場合の賃上げ税制の取扱いが出題されました。これらの論点は、個別問題や総合問題では、せいぜい1回出題されているかどうかの論点だったかと思います。
そのため、今回の本試験では、急いで問題を解いて圧縮記帳をしてしまったり、助成金の取扱いどうだったっけ?と悩んでしまったりした受験生も多かったと思います。
問題ではなかなか出てこないからこそ、こういった論点は、テキストなどで再度復習する必要があるかと思います。
ただ、定期的に確認する必要はなく、答案練習の時に、問題でその論点が出題されたらテキストで細かい論点を確認していけば良いかと思います。
④に関しては、数年ごとにではあるのですが、簿記の知識が若干必要な問題も出題されており、そこの部分で若干苦戦する受験生が比較的多いことからも、会計上の処理もある程度押さえておくことも大事かと思います。
ただし、簿記の知識が必要な問題は頻繁には出ないので、余力がある人が簡単に確認すれば良いかと思います。
【プロフィール】
新山 高一(にいやま・こういち)
東京CPA会計学院卒業。卒業年の翌年に税理士試験に合格し、その後、同校の講師として、主に法人税法を中心に指導を行っている。初学者でも法人税法がわかりやすく理解できるように、日々奮闘している。
★東京CPA会計学院 税理士講座ホームページ