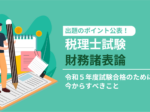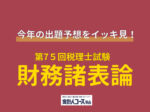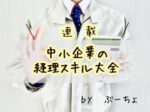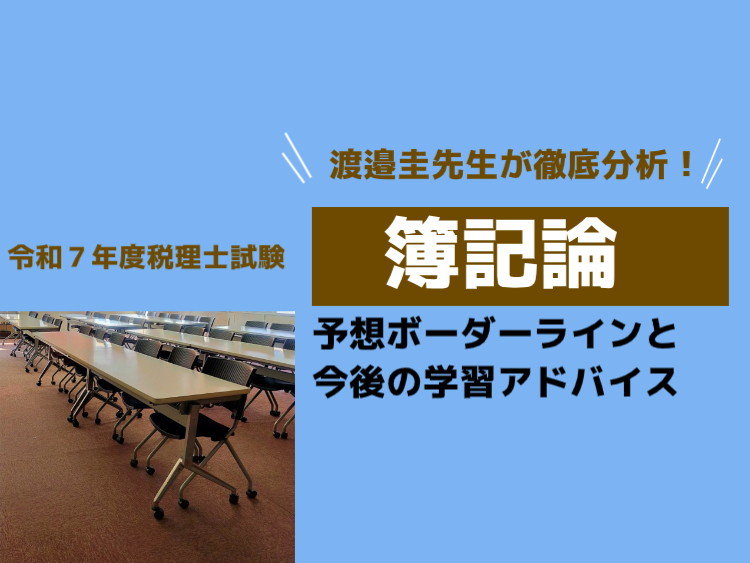
渡邉 圭(千葉商科大学准教授)
【編集部より】
2025年8月5日(火)〜7日(木)の3日間にわたり、令和7年度(第75回)税理士試験が実施されました。
そこで、本企画では、「簿記論」・「財務諸表論」・「法人税法」・「相続税法」・「消費税法」について、各科目に精通した実務家・講師の方々に本試験の分析と今後の学習アドバイスをご執筆いただきました(掲載順不同)。ぜひ参考にしてください!
全体的な難易度とボーダーライン
<予想ボーダーライン>
〔第一問〕 16点
〔第ニ問〕 15点
〔第三問〕 26点
合 計 57点
第75回税理士試験の簿記論は、過去の本試験と比較して一部難易度の高い論点が問われましたが、基本問題を中心に出題されていたと考えます。
しかし、全体的な問題数は多いと思います。
試験時間の制約の中で解答することが求められますので、それを踏まえてボーダーラインを検討しました。
第一問では決算整理後残高試算表作成までの会計処理、第二問では吸収分割(事業分離)とストック・オプション、第三問は損益勘定の作成が問われています。
特に、第三問は最近の本試験で問われていない問題であり、驚いた受験生も多かったと思います。
論点としては、複式簿記の特徴が問われている点、T勘定を使い設問ごとに解答できる点、問題量が少なかった点が見受けられました。
冷静に問題を読み取ることができれば、正答できる箇所が多くありました。そのため、落ち着いて問題を読み取り正答箇所を残せることが合格には必要です。
以上を踏まえて、全体的な難易度B、ボーダーライン予想57点以上、合格確実ライン予想63点以上と予想します。
この点数以外に、各専門学校が公表する解答速報も参考に自己採点をしてください。
税理士試験は日商簿記検定の試験範囲外の論点も出題されます。
簿記論・財務諸表論は理論などの考え方が問われます。
例えば、過去には商品売買の記帳方法の1つである分記法、小売棚卸法や特殊仕訳帳が出題されました。
現行の会計基準上、削除された論点であっても、企業会計原則や連続意見書といった伝統的な会計諸原則が存在しているため、これらを踏まえて学習することをオススメします。
なお、本記事は問題の難易度について次のような基準を設定します。
難しい A 普 通 B 易しい C
〔第一問〕 自己株式、転換社債型新株予約権付社債、圧縮記帳(積立金方式)、外貨建有価証券(その他有価証券)、のれんの償却
難易度:B ボーダーライン予想16点以上、合格確実ライン予想18点以上
第一問では自己株式、転換社債型新株予約権付社債、圧縮記帳(積立金方式)、外貨建有価証券(その他有価証券)、のれんの償却が出題されました。
自己株式は資料に記載されている決算整理後残高試算表を読み取りT勘定や仕訳により整理することで、全問正答が狙える問題です。
転換社債型新株予約権付社債は、行使された割合を算定する方法を見つけるのに時間がかかると思います。
こちらは決算整理後残高試算表の新株予約権の残高から行使割合を算定することができました。
圧縮記帳も決算整理後残高試算表の減価償却費から耐用年数の算定でき、国庫補助金は圧縮積立金の取崩額から計算をすることができます。
正答するためには、直接減額方式と積立金方式の仕訳の理解が求められます。
外貨建有価証券(その他有価証券)は取得時の直物為替相場を求めるのに時間がかかるため正答できなくても良いと考えます。
のれんの償却は、未償却の償却年数が計算しやすいため正答したいです。
上記の内容を踏まえてボーダーラインは16点以上と予想します。
18点以上正答できていれば合格確実ラインと考えます。
〔第二問〕 吸収分割(事業分離)とストック・オプション
難易度:B ボーダーライン予想15点以上、合格確実ライン予想17点以上
本問は吸収分割(事業分離)の移転利益(投資の清算)、分離先企業を支配した(投資の継続)ケース、複数のストック・オプションを付与した場合の問題が問われました。
吸収分割(事業分離)に関しては、基本的な会計処理が問われています。分離先企業を支配した(投資の継続)問題は、その他有価証券評価差額金なども考慮して解く必要があるため、問題の読み取りミスをした受験生も多いと予想します。
こちらの論点は正答できなくても良いと思います。
ストック・オプションは、資本金残高以外の新株予約権の増加・減少(相手の科目を含めて)を正答したいところです。
上記の内容を踏まえてボーダーラインは15点以上と予想します。
17点以上正答できていれば合格確実ラインと考えます。
〔第三問〕 損益勘定の作成(総合問題)
難易度:B ボーダーライン予想26点以上、合格確実ライン予想28点以上
本問は、損益勘定を作成する総合問題です。
普通預金、商品売買、貸倒引当金、リース取引(貸手側)、保守サービス、有形固定資産、投資有価証券、借入金、営業費、人件費、剰余金の配当が出題されました。
閉鎖残高と普通預金の資料を読み取り、各問で求められる収益及び費用の金額を求めて解答する必要があります。
商品売買では、売上高と売上原価を算定が問われていますが、解答するには、売掛金と電子記録債権の資料から推定して解答することができます。
しかし、試験時間の制約があるため、解答ができなくても問題ないと思います。
貸倒引当金と貸誰損失は正答したいです。
リース取引は、リース売上高、リース売上原価は解答しやすかったです。
役務収益と役務原価も同様に正答したいところです。
有形固定資産のうち構築物関連の問題は模試であまり問われていない論点だったと思いますので正答できなくても良いと考えます。
リース取引も減価償却費のみ解答して、解約に関する問題は時間的に正答ができなかった受験生も多いと思いますので、解答せず次の問題に進めても良かったと考えます。
投資有価証券は、当期の償却原価法の会計処理を踏まえて正答できると他の受験生に差がつけられる論点でした。
借入金は為替差損益の金額を正答したいところです。
販売費及び一般管理費は、役員報酬及び給与手当の論点は正答できなくても良いと考えます。
剰余金の配当は利益準備金の金額を含めて解答したい論点です。
以上のことから、解答時間も踏まえてボーダーラインは26点以上、合格確実ライン28点以上と予想します。
次回の税理士試験に向けて
・ボーダーラインまたは合格確実ラインを超えていれば次の科目へ
・ボーダーラインまたは合格確実ラインを下回る場合は受験科目の復習
自己採点の点数に応じて、9月からの試験対策が異なります。
各専門学校が公表しているボーダーラインまたは合格確実ラインを超えていれば、9月から開講される講座を受講して来年度の試験に向けて対策をしましょう。
ボーダーラインまたは合格確実ラインを下回る場合は合格発表まで応用問題集などを使い復習をしながら習得した知識を維持してください。
応用問題集は月に1冊終わらせるペースで構いません。
財務諸表論が未学習であれば9月から講座を受講して簿記論の復習と合わせて学習するのも効果的です。
財務諸表論は、簿記論とは異なり理論の学習があります。
理論問題集の範囲を5月ゴールデンウィークまでに完了するように学習を進めてください。
5月以降は直前予想問題集や各専門学校で模試の答練が開始されます。模試などで、はじめて問われる問題もありますので、理論問題集の学習が完了していないと勉強量が増加します。
そのため、上記の学習期間を参考に理論学習の計画をたてましょう。
次回の受験科目が税法科目の場合は、学習量の関係から9月から講座を受講して学習することをオススメします。
自己採点から次のステップを判断するのは難しいと思いますが、本記事が1つの判断材料になれれば幸いです。
さいごに
本試験の受験、本当にお疲れ様でした。
自己採点をしてボーダーラインの方は過去の自分を褒めてあげてください。
次の受験科目を受験される方は、今回の本試験で活用した学習計画を活かして、さらにステップアップをしましょう!
ボーダーライン以下の方も、合格発表まで結果はわかりません。
上記の講評はあくまで参考資料ですので一喜一憂せず、過去の自分を振り返り、学習過程の反省点があれば改善策を練りましょう。
私が簿記論に合格した時は、本試験で余裕がなく自己採点をするための資料を作成できませんでした。本試験中は基本的な論点が出題されたら確実に正答するように心掛けて解答を作成しました。後で振り返ると、その姿勢が良い結果をもたらしてくれたのかなと思います。
また、家庭、仕事、学業と両立しながらの受験勉強は大変だったと思います。また、猛暑も続いていますので体調を崩されないようにご自愛ください。
勉強で遊びの誘いも断ってきたと思いますので、ご家族、友人とお付き合いをする時間も大切にしながら余暇をお過ごしください。!(^^)!
【執筆者紹介】
渡邉 圭(わたなべ・けい)
千葉商科大学商経学部准教授、博士(政策研究)。2012年4月から会計教育研究所(現・会計教育センター「瑞穂会」)に所属し、日商簿記検定対策3級〜1級講座、税理士試験講座(簿記論・財務諸表論)を担当。2019年4月からは基盤教育機構に所属し、上記の対策講座も兼務、2025年4月より現職。これまでに、日商簿記1級合格者190名、簿記論70名、財務諸表論45名以上(いずれも所属期間の累計者数)の合格者輩出に貢献している。