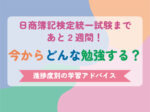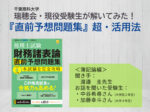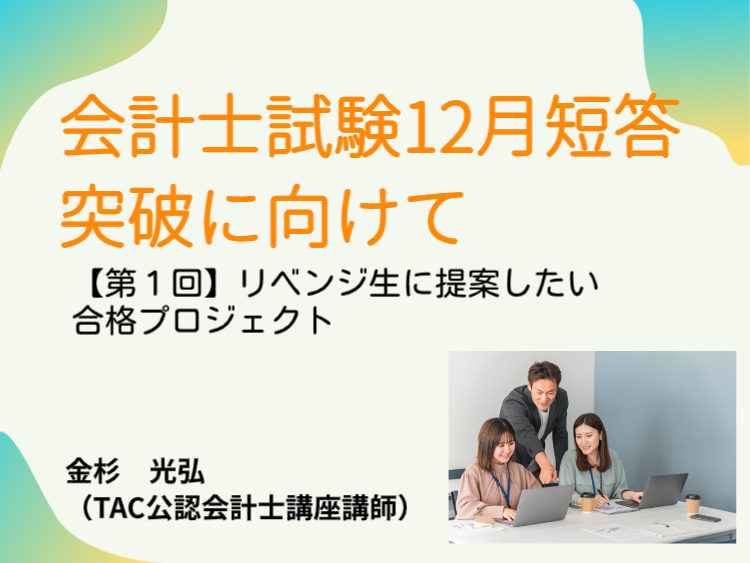
金杉光弘(TAC公認会計士試験講座講師)
はじめに
挫折を乗り越え、再び12月の短答式試験を目指す受験生の皆さんへ。
試験勉強とは、得点という成果(=利益)を最大化するため,各科目を事業部門とみなし,資源(時間と労力)を最適配分することにほかなりません。
ここでは、短答式試験突破を1つのプロジェクトとみなして、対策を会社の経営改善計画風にご提案します。
事業概要
計画期間:2025年7月~12月
決算日:2025年12月14日(延長不可!)
目的:全事業部門の黒字化(=全科目合格点以上の確保)
過年度受験経験者の事業環境分析(SWOT分析)
Strength(強み):すでに一度はインプットを完了している、得意科目がある、学習履歴の確保
Weakness(弱み):苦手論点の放置、期間長期化によるマンネリ
Opportunity(機会):次回試験より試験時間・問題数の調整
Threat(脅威):出題傾向の変化、新規受験者の参入
事業スケジュール
7月~8月:在庫棚卸による欠品確認(=インプット1周による苦手論点のリスト化)
9月~10月:営業部門の強化(=答練等の演習による得点力強化と知識の定着)
11月:OJTを通じたスキルの戦力化(=模試・総合問題による最終調整)
12月:クロージング(=試験本番)
事業戦略(科目別アプローチ)
経理部門(財務会計論)
戦略:頻出論点(個別論点,連結総合)を確実に押さえ、基礎的な問題の取りこぼし回避
目標:計算問題の解答時間早期化、理論問題の根拠説明を可能にする
管理部門(管理会計論)
戦略:出題範囲全体について基礎レベルの知識の質と量の強化
目標:難易度に応じた取捨選択力の精緻化、正答可能な問題の処理速度向上
法務部門(企業法)
戦略:会社法を総体的に理解するとともに、条文ベースで正確に知識を整理する
目標:選択肢判断力の向上、重要条文の正確な記憶
内部監査部門(監査論)
戦略:正しい考え方の理解、正誤判断に必要な知識の正確なインプット
目標:あいまいな理解をなくす、誤った肢と判断する理由を言語化して説明できる
進捗管理
予算策定
「何をどこまでいつまでにやるのか」を決める。
科目別、論点別に、残された時間に応じて手を広げるべき範囲と、そうでない範囲を定める。
何をもって達成とみなすかを時間やページ数で数値化、明文化する。
実績管理
実際にできた内容を記載する。
予算として策定した定量化データに対する達成率を計算し、できなかった理由も記録する。
対応策検討
毎週・毎月の単位で計画を見直し、遅れや改善点を発見する。
問題点は何か(怠惰による未達、計画に無理がある、自己の能力の過大評価など)を検出する。
できなかったことを責めるのではなく、できるように設計図を描き直す。
次週、次月のアクションにつなげる。
モニタリング(成績の評価)
苦手論点の克服数
例えば、重要性がAだが、自分は苦手である論点が、特定の科目に8あったとする。
これを試験までの残り月数で割り(例:いま8月なら11月末まで残り4か月)、月次で2ずつ克服していく。
過去問の正答率
特定の年度(あまり古くないものが望ましい)の過去問を全科目時間を測って解いてみて、その年の合格基準に到達できているか確認する。
模試のスコア
模試や答練は得点の絶対値ではなく、偏差値で合格に必要な水準に届いているか評価する。
また、全科目でバランスよく取れているか、苦手科目を残していないか管理する。
最後に
・アウトプットを通じた実践、反省、修正のサイクルの徹底
・得意科目の維持と苦手科目の強化で全体平均の向上
・コスト過剰となる完璧主義を避け、基本論点を重視
全体最適と現実的な計画の立案と実行で、本試験までに全科目の黒字決算化を目指しましょう!
〈プロフィール〉
金杉光弘(かなすぎ・みつひろ)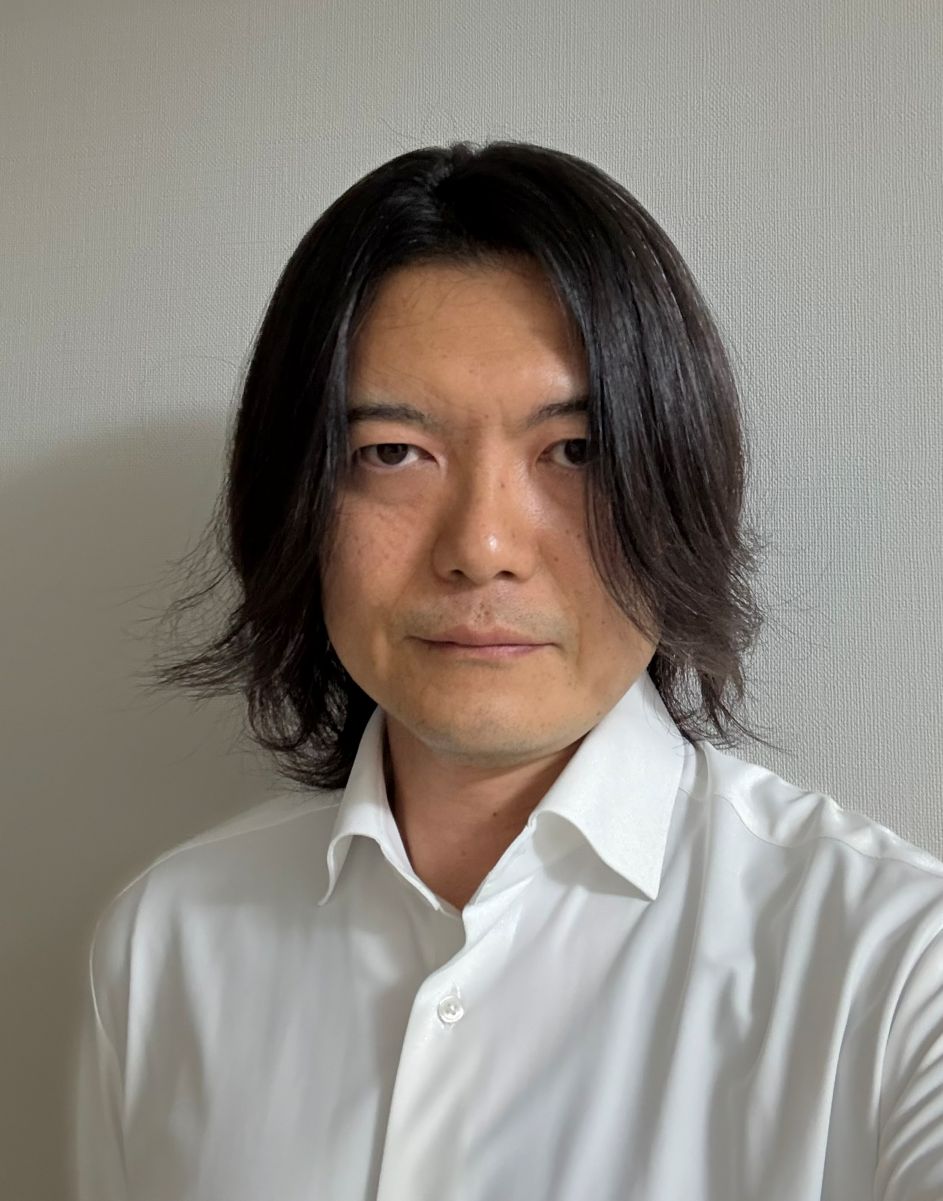
TAC公認会計士講座で財務会計論の講師としてWeb講義、教材開発、問題作成を行う。また,FASS(経理・財務スキル検定)や企業研修なども担当。監査法人にて上場企業、金融機関、IPO等の監査業務を行う他、コンサルティング会社で経営改善計画の策定、アドバイザリー業務など幅広く従事。現在、東京実務補習所運営委員を務めている。
Xアカウント(会計ポエム)https://x.com/kanasugi_tac