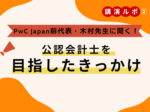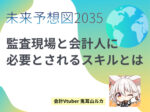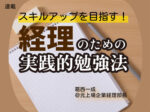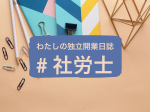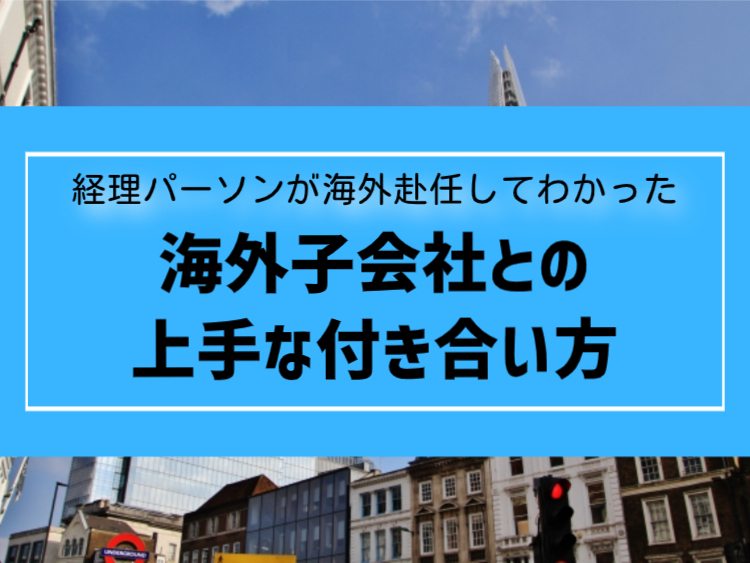
松岡俊(株式会社マネーフォワード執行役員グループCAO)
【編集部より】
国際的に活躍したいと思う経理パーソン向けに、海外子会社との上手な付き合い方について解説していただきます。
第1回:イントロダクション
第2回:日本と海外の経理実務差異~「ジョブ型」
第3回:日本と海外の経理実務差異~残業・有休
第4回:日本と海外の経理実務差異~コミュニケーション
第5回:まとめ~異文化理解を深め、グローバルな協業を円滑に
はじめに
長らくお付き合いいただきました本連載も、いよいよ最終回を迎えました。
第1回では本稿執筆の背景と自己紹介、そして海外経理業務における日本との共通点について触れました。第2回では「ジョブ型」雇用という観点から、第3回では残業・有給休暇・業務品質に関する考え方の違い、そして第4回ではコミュニケーションスタイルといったテーマで、英国駐在経験を基にした日本と海外の経理実務の差異について具体的なエピソードを交えながらお話しました。
最終回となる本稿では、これまでの内容を総括し、これらの共通点と差異点を踏まえた上で、日本企業で働く経理担当者の皆様が明日からの業務に活かせるような具体的な提案をさせていただきたいと思います。
グローバル経理の共通基盤:揺るぎないプロフェッショナリズム
まず、改めて強調したいのは、国や文化が異なっても、経理プロフェッショナルとして求められる普遍的なスキルセットが存在するということです。
第1回でお話しした通り、「簿記は世界共通言語」であり、会計基準の細かな差異はあれど、その根底にある仕訳や勘定科目の概念は万国共通です。
この会計知識は、海外のスタッフと円滑なコミュニケーションを図る上での強力な武器となります。
また、表計算ソフトのスキルも同様です。データの集計・分析といった経理業務に不可欠な作業は、どの国でも発生します。
日本で培った表計算のスキルは、そのまま海外でも通用する強力な武器となるでしょう。
さらに、多くのグローバル企業が導入しているERPシステムに関する知識も、業務の効率化や現地スタッフとの連携において大きな助けとなります。
そして何よりも、傾聴力やプレゼンテーション能力といったソフトスキルは、文化や言語の違いを超えて、円滑な人間関係を構築し、チームをまとめ上げていく上で不可欠な要素です。
これらの共通基盤があるからこそ、私たちは異文化の中でも自信を持って業務に取り組むことができるのです。
文化の交差点で生まれた「差異」とその意味:多様性への理解を深める
一方で、これまでの連載で見てきたように、日本と海外(特に私が経験した英国を中心とする欧米)の経理実務には、数多くの興味深い「差異」が存在します。
ジョブディスクリプションの存在は、その最たる例でしょう。
欧米では各自の職務範囲が明確に定義され、その範囲内で専門性を高めていくキャリアパスが一般的です。
これに伴い、日本では一般的なジョブローテーションに対する考え方や、マネージャーがプレイングマネージャーとして実務にも深く関与する度合いも異なります。
労働時間や休暇に対する意識も大きく異なります。
定時退社が基本で、残業はあくまで例外という考え方、そして有給休暇を長期で取得し、プライベートを充実させる文化は、日本の感覚とは異なるかもしれません。
また、業務の品質に対する考え方も、完璧な100点を目指す日本の文化に対し、欧米では80点程度の品質で効率を重視する傾向が見られました。
コミュニケーションのスタイルも同様です。
問題点を指摘する際にもより慎重な言葉選びが求められます。
会議は情報共有よりも「議論」と「意思決定」の場として明確に位置づけられ、効率性が重視されます。
ハイコンテクスト・ローコンテクストの違いも意識する必要があります。
これらの差異は、どちらが優れているという単純な話ではありません。
それぞれの文化的背景、歴史的経緯、法制度、そして合理性に基づいて形成されてきたものです。
重要なのは、これらの違いを認識し、その背景にある価値観を理解しようと努め、「解像度」を高めることです。
明日から実践できる、日本企業経理パーソンへの提言
では、これらの共通点と差異点を踏まえ、日本企業で働く経理担当者の皆様は、明日からの業務にどのように活かしていくことができるでしょうか。
まず、海外のグループ会社や取引先と連携する際には、以下の点を意識することが有効でしょう。
- 「解像度」向上の継続的な努力: 相手の国の文化、働き方、慣習について、日頃から情報収集を怠らず、理解を深める努力を続けましょう。思い込みや日本の常識を押し付けることなく、敬意を持って接することが円滑な関係構築の第一歩です。
- ジョブディスクリプションの尊重と明確なコミュニケーション: 相手の職務範囲を意識し、依頼する業務内容や目的、期待するアウトプット、期限などを具体的に、かつ明確に伝えることが重要です。
- 時間感覚の違いを前提とした計画: 海外拠点に協力を依頼する際は、彼らの定時退社や長期休暇取得の可能性を念頭に置いた、現実的なスケジュールを策定しましょう。
- 品質基準への理解と建設的フィードバック: 提出された資料に対して、細部にまで完璧さを求めるのではなく、まずは目的を達成できているかという観点から評価しましょう。改善を求める場合も、一方的なダメ出しではなく、共に解決策を見出す姿勢が大切です。
- 文化的背景を考慮した慎重かつ提案型のアプローチ: 特に問題点を指摘する際には、相手の立場や感情に配慮し、提案型のコミュニケーションを心がけることで、相手も受け入れやすくなります。
おわりに:未来へ繋ぐ、経理プロフェッショナルの道
5回にわたり、海外での経理実務経験を通じて得た気づきをお話させていただきました。
本連載が、海外赴任を控えている方、海外拠点と連携されている方、そして日本国内で経理業務に携わる全ての皆様にとって、何かしらのヒントや刺激となり、明日からの業務に少しでもお役立ていただければ、これに勝る喜びはありません。
私自身、5年間の英国経験があるからといって「海外」全般を理解したとは思っていません。
現職に転職してからは、会社の成長に伴い、ベトナムやインドのグループ会社とのやり取りが増えてきました。
ベトナムは同じ「海外」ではありますが、英国とは全く異なる文化です。
「これが海外流だ」といった思い込みをすることなく、今後も柔軟に相手の文化に敬意をもって接していきたいと考えています。
会計という世界共通言語を操り、企業の経済活動を正確に記録・報告し、経営の意思決定を支える経理の仕事は、どの国においても非常に重要であり、誇りを持てる仕事です。
グローバル化がますます進展する現代において、異文化を理解し、多様な価値観を受け入れ、変化に柔軟に対応できる経理プロフェッショナルの重要性は、今後さらに高まっていくでしょう。
この連載を通じてお伝えしてきた私のささやかな経験が、皆様にとって海外で働くこと、あるいは海外のカウンターパートと協働することへの「解像度」を少しでも高める一助となり、今後のグローバルな舞台でのご活躍に繋がることを心より願っています。
第4回に続きニューイヤーパーティーでのひとこま。
【プロフィール】
松岡俊(まつおか・しゅん)
株式会社マネーフォワード
執行役員 グループCAO
1998 年ソニー株式会社入社。各種会計業務に従事し、決算早期化、基幹システム、新会計基準対応 PJ 等に携わる。英国において約 5 年間にわたる海外勤務経験をもつ。2019 年 4 月より株式会社マネーフォワードに参画。『マネーフォワード クラウド』を活用した「月次決算早期化プロジェクト」を立ち上げや、コロナ禍の「完全リモートワークでの決算」など、各種業務改善を実行。中小企業診断士、税理士、ITストラテジスト及び公認会計士試験 (2020 年登録)に合格。