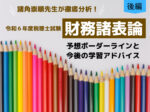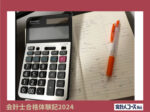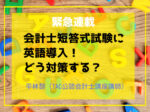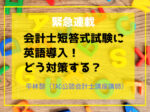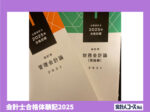【税理士合格体験記】15年諦めずに勉強し、還暦で官報合格!早期退職した夫が家事を担ってくれた
- 2025/2/20
- 合格体験記
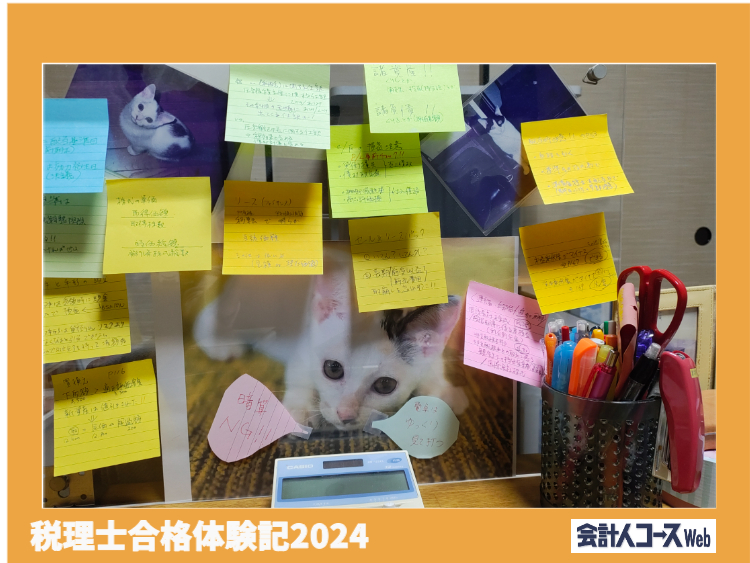
たーぴーきゃっと(60歳)
派遣社員(事業会社人事部勤務)
【受験情報】
合格科目(合格年・受験回数):財務諸表論 (平成22年・1回)/法人税法 (平成28年・5回)/消費税法 (平成30年・6回)/簿記論 (令和4年・10回)/所得税法 (令和6年・1回)
学習スタイル: 大原・TAC(通学・通信)
▶サムネイルはたーぴーきゃっとさんのデスク前パネル(常にポストイットなどいろいろ貼っていた)
リーマンショックで派遣切りに。税理士の勉強を開始
卒業後プログラマからPCインストラクタに転職。
職業訓練や税務大学校での講習で会計ソフトを教えたのが簿記会計との出会いでした(今考えると冷や汗モノのナンチャッテ講義です)。
派遣社員として自動車業界の教育センターに勤務していましたが、2009年リーマンショックにより2010年3月派遣切りに。
結局PCインストラクタ(当時はWordやExcel)だけでは食って行けず、簿記会計方面に仕事の幅を広げていこうとしてまずは簿記2級を目指し大原へ。
ぎりぎりで一発合格し、気を良くして次のステップとして税理士という資格を考え、たまたま法学部出身で受験資格があり、失業中だったこともあり、そのまま昼間の簿財クラスに入り、1年は専念。
始めたころは、数年で資格取って、IT+会計で何からの仕事につなげれば・・・などと、非常にあま~~く考えていました。
基本は1.5時間かけて通学クラスで勉強
始めは大原の通学クラスで学習。
始めた当時は通学クラスがたくさんあったので、夜間や土日のクラスに通い、直前期や模試はTACのものも受講。
そのうちネットが普及してWeb講義中心のクラス編成となり、株主優待の関係でTAC中心に移りました。
よく巷では大原とTACのどちらが良いか、話題になるところ。テキストや講義スタイル、講師のバックボーンなどに違いはありましたが、目指すところは同じなので、どちらでも合格できるとは思います。
あとは受講スタイルや教材の好み、個人的な相性との相談です。
都内に行くのに約1.5時間かかるのですが、特に初学のときは通学一択。
長くなった簿記論は通信で合格できましたが、あとは基本通学での合格でした。
不合格になるのは基礎ができていないから
合格の決め手、というより不合格になるときは、やはり基礎ができていないときでした。
結局、計算については基本問題の数をこなし(特にできない問題はだいたい15回くらい)、少なくとも実力判定公開テストレベルの問題は、満点が取れるまでやるしかないです。
特に簿記論については個別問題を、直前期まで、というか試験前日まででもやるべきでした。
外貨建て、圧縮記帳、税効果会計、特殊商品売買など、最初は嫌いだった問題も、合格した年の試験前日には、すっかり楽しくなっていました。
消費税法は、簡易課税が苦手だったのでこれも2か月間、毎日1題を解きました(ほぼ寝ていても勝手に手が動くくらいに、実際翌日見ても記録はあっても記憶がなかった)。
それから、すべての科目に言えることは、凡ミスをなくす。最後の科目は所得税法でしたが、指差し確認で問題の読み飛ばしと転記ミスを、ほぼゼロにできたと思います。
この当たり前のことができていなくて、合格までに長年かかってしまったのです。
理論について、暗記は当然ですが、理サブや理マスを読んでいると文脈がわからなくなってしまうことが多々あり、法令集で条文に当たるようにしました。
かなり時間はかかり、講師にはお勧めされなかった(というより止められた)けれど、法令集を見ていると条文の並びとか、ほかの条文が目に入ることで規定のつながりが見えてくることがあったので、私にとっては理解の助けになったと思っています。
措置法までは読み切れなかったけれど、これは今後の課題です。
仕事、家事、介護との両立
受験生となって数年間は専念もしくはちょっとパートなどをしていましたが、経理の仕事をするべきと考えて一般事業会社に派遣社員として就業することにしました。
契約前に受験生であることを派遣先にお伝えし、残業はほぼなし、勉強優先の仕事スタイルで働けるところに入りました。
通勤時間で理論や模試の見直し・昼休みに個別問題を少しと、やはり隙間時間は勉強に使いました。
派遣社員だと昼休みに一人で勉強していてもそれほど違和感はなかったです。
また、コロナ禍以降は在宅勤務も多くなり勉強時間の確保は容易になりました。
コロナ禍で外出できずに家にいても全然ストレスはなくて、かえってラッキーだったと思います。
そしてこれは大変重要なことですが、家事はすべて早期退職した夫が受け持ってくれました。
夫の協力なくして合格はなかったと断言できます。
途中父親が病気で療養していた頃にはあまり勉強できない時期が3年ほど続きましたが、試験が終わる日を待っていたかのように8月15日に亡くなった父の「無言のエール」にやっと応えられて、心底ホッとしています。
モチベーションの保ち方
令和に入ってからは「今年で受からなかったらやめる」と毎年言っていました。
しかしながら、簿記論で58点,59点,59点と3年連続で惜敗しやめられず。
やっと受かった矢先に、夫のガン(ステージ4)発覚でいったん諦めました。
平成22年から令和6年までの間に、一年だけ何も受験していない年があります。
が、なんと奇跡的に病気は進行せず、とうとう「還暦官報合格」を目指すことになりました。
自分の頭がついて行けるうちに、周りの皆が生きているうちに、良い報告ができるように、頑張れ!頑張れワタシ!!そう自分に言い聞かせていました。
受験生へのメッセージ
受験を始めてから15年かかり、やっと5科目到達した自分から言えること、それはやはり「諦めないで」という言葉です。とはいえ15年はかけ過ぎですね。短期間で合格できるのが一番です。
でも、コツコツとやっている中で試験だけでなく色々なことに関心が向き、何かに気づき、出会い、新しい何かを得られることもあると思います。
思うように勉強できない期間も必ずあります。
それを乗り越えることでまた少し強くなった自分に自信が持てる。
長い受験生活を振り返って、このように思っています。


-150x112.jpg)