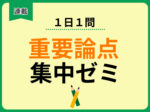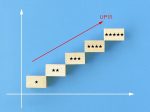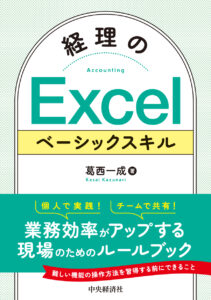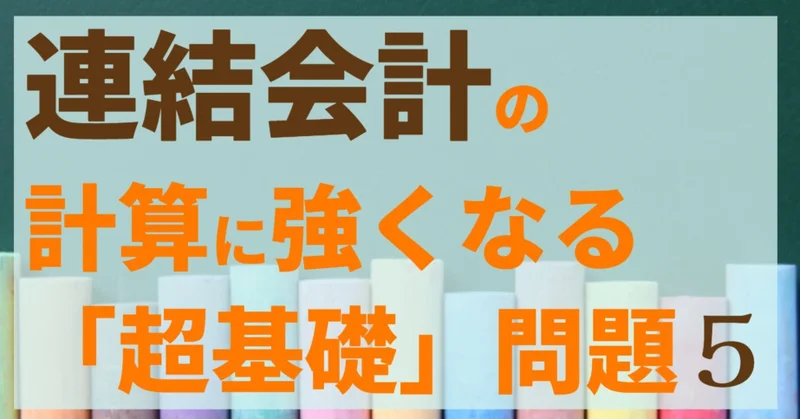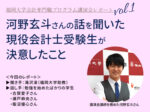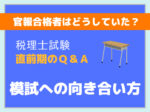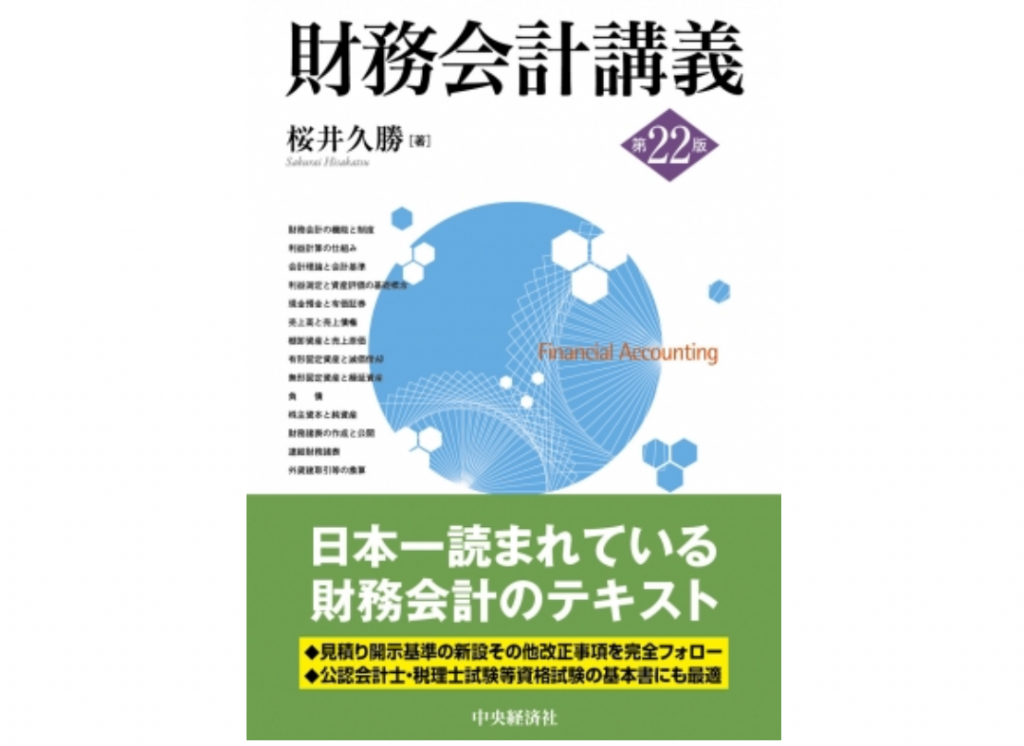
長島正浩
(茨城キリスト教大学経営学部教授)
【編集部より】
税理士試験の財務諸表論、公認会計士試験の財務会計論。
「計算は得意だけど理論はニガテ」という受験生の方は多いですよね。
理論が得意になるためには、個々の論点をただ暗記するのではなく、隣り合った論点を「総合的かつ横断的」に理解することが大事です!
その1つの学習方法が、基本書を使って、キーワードをもとにさまざまな箇所で解説されている内容を横断的に押さえること。
本連載では、長島正浩先生(茨城キリスト教大学経営学部教授)に、代表的な基本書である『財務会計講義』(桜井久勝著)の索引を手がかりに、「総合的かつ横断的」な理解に不可欠な論点を解説していただきます。
ぜひ理論の得点アップにお役に立てください!
修繕引当金、設定しておけばよかった……
いきなりですが、6~7年前に自宅を太陽光発電・IHキッチン・エコキュートにリフォームして、いわゆる「オール電化」にした。すべてうちの家内が主導で。
さらに、その直後に私の車も日産リーフ(100%電気自動車)に乗り換えになった。これも家内の意見で。こうして我が家は動力も含めて完全に「オール電化」となった。
恐ろしいのは、主導権を家内に握られたことである。些細なスマホの充電ですら、電源を握っている家内の許可が必要なのである。ましてや車の充電は、ディーラーなど外部の急速充電設備を利用してこなければならない。我が家に私の居場所はないのである。
しかし、1箇所だけ電気を使わない場所があった。普段は使わない2階のトイレである。シンプルな便器で温水洗浄便座など付いていないから一切電気を使わない。冬は少し寒いが、私にとって一番落ち着く場所であった。昨年の夏までは。
そんな愛着のある便器との別れは突然やってきたのである。家内からLINEが入った。
「2階のトイレが水漏れしてる。5秒に1回ポタっと滴が落ちてるみたい。」(嫌な予感)
「いや、その程度なら放っておいていいんじゃないの?」(あえて冷静を装う)
「業者さんに見てもらったら、部品交換するより便器ごと取り替えたほうが安いらしいよ」(行動が早すぎるっ!)
「あーそれ、修繕引当金設定してるから修繕にしようよ。」(難しいこと言ってみよう)
「何ごちゃごちゃ言ってるの。もう新しいリクシルの便器注文したから。」(泣)
たまに漏らしたり尻に敷かれたりという意味では私と同じ立場の便器よ、さよなら。こうして昨夏、我が家は名実ともに「オールかかあ天下」になったのである。
索引を見てみよう
これまでと同様、お手元に『財務会計講義』がある人は、該当ページを確認していただき、今は手元にないという人は、学習ポイントだけでも眺めていただければ十分である。
「引当金」は、p.219、p.220、p.221にあり、これに「貸倒引当金」のp.142、p.220を加え、(p.220はダブっているので)4箇所の主な内容と学習ポイントを確認していこう。
p.142
【内容】
過去の実績等に基づいて貸倒れ見積高を算定し、当期の販売費の1項目として損益計算書に計上するとともに、その額を貸倒引当金として設定しなければならない。
【学習ポイント】
なぜ、第6章「売上高と売上債権」のところで「貸倒引当金」が登場するのか。「貸倒引当金」は他の引当金と何が違うのか。
p.219
【内容】
……引当金の設定においては、費用・損失の認識と、負債の計上が同時に行われる。このうち収益に対応する費用を計上して期間利益を算定するために、費用・損失の計上を重視するのが収益費用アプローチである。これに対し資産負債アプローチのもとでは、当期までの経営活動の結果として企業が将来に資産を引渡すべき義務を負っていることに注目し、これを負債として認識する側面が重視される。
【学習ポイント】
引当金設定の仕訳をするとき、借方「○○引当金繰入」として、当期の収益に対応する費用・損失が計上され、貸方「○○引当金」として、経済的負担を表す負債が認識される。
p.220
【内容】
適正な期間損益の算定という目的からみて、引当金が妥当なものとして認められるために満たさなければならない要件は、次のとおりである。
【学習ポイント】
企業会計原則・注解18の引当金設定要件を押さえる。(a)将来の資産の減少、(b)収益との対応関係、(c)高い発生確率、(d)客観的な測定可能性 の4つの要件をすべて満たさなければ引当金を設定することはできない。
p.221
【内容】
……評価性引当金は、関連する資産項目からの控除項目として取扱われる。また負債性引当金は、使用されるまでの期間により、流動負債と固定負債に区分される。
【学習ポイント】
引当金の分類について整理する。まず引当金は、「会計上の引当金」と「特別法上の準備金」に分かれる。次に会計上の引当金は、「評価性引当金」と「負債性引当金」に分類され、負債性引当金は「条件付債務」と「会計的負債」に区分できる。