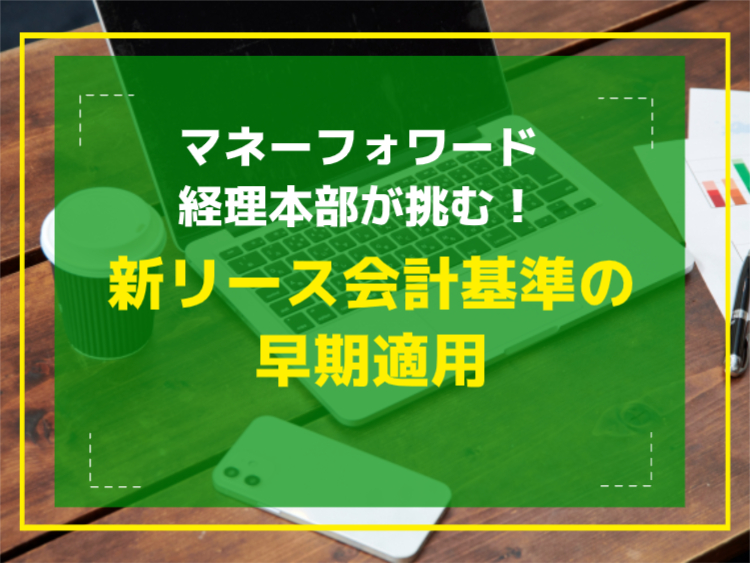
松岡俊(株式会社マネーフォワード執行役員 グループCAO)
【編集部より】
2027年から新リース会計基準が強制適用となります。対応に追われている企業は多いのではないでしょうか? 本連載では、新リース会計基準を早期適用したマネーフォワード経理本部の実例を解説していただきます。
第1回:改正の概要と早期適用をした理由
第2回:リースの範囲はどこまで?
第3回:新リース会計基準の導入が困難な理由
第4回:IFRS第16号導入プロジェクトの教訓
第5回:【実践】プロジェクトの可視化
第6回:【実践】知識のインプット
第7回:【実践】意思決定の加速とリース期間の決定方針
第8回:【実践】契約書の網羅的な洗い出し
第9回:【実践】全社連携と監査法人との協議
第10回:【実践】システム対応とその他の影響の考慮
「リース」の範囲はどこまで?
さて、新リース会計基準への対応において、企業が直面する最大の課題の一つが、そもそも何が「リース」に該当するのかを正しく識別することです。
新リース会計基準は、契約書の名称や形式ではなく、その経済的実態に基づいてリースを判断することを求めています。
これにより、これまでサービス契約や業務委託契約として費用処理されてきた契約の中に、新基準下ではリースとして資産・負債計上が必要となる、いわゆる「隠れリース」が多数潜んでいる可能性があります。
新基準におけるリースの定義は、以下の2つの要件を満たす契約、または契約の一部とされています。
- 特定された資産(Identified Asset)が存在する。
- 顧客がその資産の使用を支配する権利(Right to Control)を有している。
この2つのテストをクリアするかどうかが、リース判定の分水嶺となります。
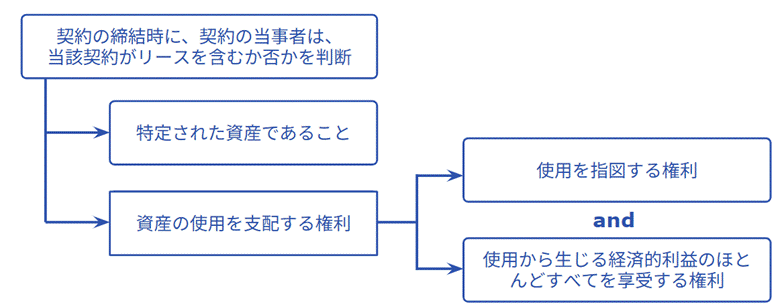
テスト1:特定された資産
リース契約の対象となるには、まずその資産が物理的または契約上、明確に特定されている必要があります。例えば、契約書に資産のシリアル番号や所在地が明記されている場合は「明示的に特定」されていると判断されます。
サプライヤーの「実質的な代替権」の有無もこの判断では考慮する必要があります。
テスト2:支配する権利
特定された資産が存在する場合、次に顧客がその資産の使用を支配しているかを判定します。「支配」は、以下の2つの要素を両方とも満たすことで成立します。
- 経済的利益のほとんどすべてを享受する権利:顧客が、その資産を使用することによって生じる経済的便益(製品の生産、サービスの提供、キャッシュフローの創出など)の大部分を享受できること。
- 使用を指図する権利:顧客が、その資産を「どのように」「何の目的で」使用するかを決定できること。たとえ資産の操作自体はサプライヤーが行う場合でも、その操作方法が顧客の指示によって決定されるのであれば、実質的な支配権は顧客にあると判断される可能性があります。
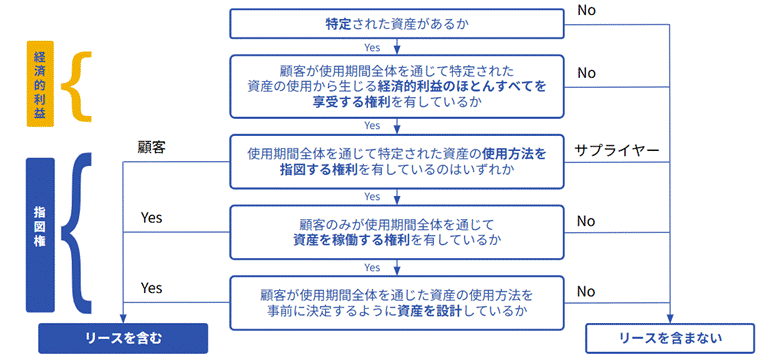
「隠れリース」の探索場所:具体的な契約例
これらの判定基準を念頭に置くと、企業の様々な部門が締結している日常的な契約の中に「隠れリース」が潜んでいる可能性が見えてきます。
外見上は特定のサービス、役務提供をする契約に見えたとしても、そのサービス提供の前提として「特定された資産」の利用を契約上で定めている場合には、その資産もリースの定義を満たす可能性がある、ということです。
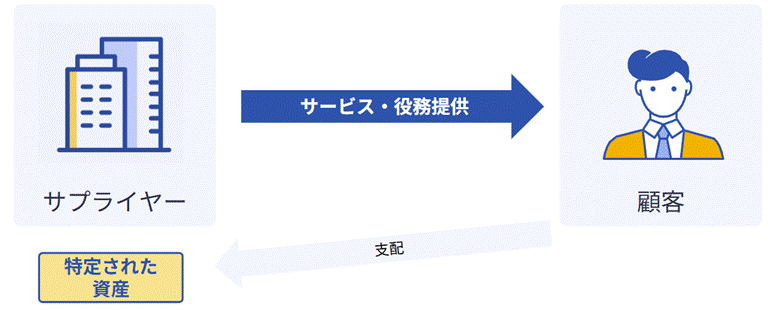
契約は通常、IT、物流、製造、マーケティング、総務などの各事業部門が管理しており、会計部門が管理していることは稀です。
そのため、「隠れリース」の特定には、単なる会計手続きを超え、部門間の壁を越えた全社的な協力体制が不可欠です。この部門横断的な連携が成功するかどうかが、新基準へのスムーズな移行を左右する重要な鍵となります。
【著者プロフィール】
松岡 俊(まつおか・しゅん)
株式会社マネーフォワード
執行役員 グループCAO
1998 年ソニー株式会社入社。各種会計業務に従事し、決算早期化、基幹システム、新会計基準対応 PJ 等に携わる。英国において約 5 年間にわたる海外勤務経験をもつ。2019 年 4 月より株式会社マネーフォワードに参画。『マネーフォワード クラウド』を活用した「月次決算早期化プロジェクト」を立ち上げや、コロナ禍の「完全リモートワークでの決算」など、各種業務改善を実行。中小企業診断士、税理士、ITストラテジスト及び公認会計士試験 (2020 年登録)に合格。




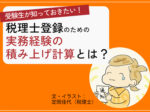






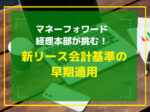



--150x112.jpg)

