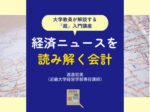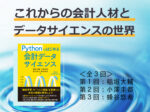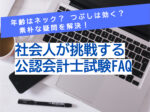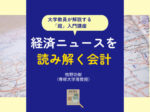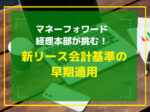林雄次(デジタル士業®・資格ソムリエ®)
【編集部より】
生成AIの発達が目まぐるしい現在。社労士事務所ではどう活用できる?本連載では、『社労士事務所のDXマニュアル』(中央経済社)著者で、デジタル士業®×資格ソムリエ®の林雄次先生にやさしく教えていただきます。
AIには得意・不得意がある
社労士の実務に生成AIを持ち込むとき、最初に押さえたいのは「AIは万能の回答者ではなく、強い領域と任せてはいけない領域がはっきり分かれている」という現実です。
生成AIは、大量の文章から言語のパターンを学習し、質問や指示に対してもっともらしい文章を紡ぎ出します(意味を理解して考えているというわけではありません)。
生成AIは、人がゼロから書き始めると手間のかかる“下書き”や“論点の棚卸し”を一瞬でやってくれる点に価値があります。
一方で、法令の厳密な適用判断や、個別事情が絡む結論の断定は不得手で、場合によっては誤情報を自信満々に提示することもあります(「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、根本的な回避は現時点では困難とされる)。
だからこそ、どの場面で使うと威力を発揮し、どの場面ではブレーキを踏むべきか、最初に地図を持っておくことが重要です。
生成AIが得意にする領域
まず、生成AIがもっとも得意とするのは、言葉の再編成と要点抽出です。
顧問先への案内文やニュースレターの草稿づくり、行政通達の要点の1枚要約、分厚い審査要領から必要な部分だけを取り出して見出しを付ける作業は、AIの守備範囲にぴったりはまります。
就業規則の改定でも、現行条文を与えて「改定理由」「想定される影響」「周知の手順」を見取り図として先に並べさせれば、条文案の比較検討にすぐ着手できます。助成金の検討であれば、企業規模や業種、雇用形態といった前提条件を入力して、「要件に照らしてあり得る候補」「不足資料」「確認が必要な論点」を1次スクリーニングさせることで、調査の入口が明確になります。
研修資料の準備でも、管理職向け・新入社員向けといった受講者像を指定し、意図する行動変容を書き添えておけば、章立て、Q&A、ロールプレイ台本の素案を短時間で複数案出してくれます。
これらについて、いずれも共通しているのは、AIの出力が“完成品”ではなく“たたき台”であるという点です。
人間が最後に肉付けし、根拠を確認し、文体を整える前提で使うと、時間短縮と発想の広がりを同時に得られます。
生成AIが不得意とする領域
その一方で、生成AIに任せてはいけない領域も明確です。
最新の法令・通達・判例の正確な適用判断、すなわち「ある顧問先の具体的事実に、この条文のこの解釈が当てはまるか」という最終判断は、人間の役割から外せません。
AIは言葉の確率から文章をつくるため、誤りでもそれらしく正しそうな結論を示すことがあり、根拠の読み違いや施行日の取り違えに気づかないまま進んでしまう危険があります。
ハラスメントやメンタルヘルスの相談対応のように、個人の尊厳や法的リスクが直ちに関わる場面でも、一次のメモ作成や論点整理までに限定し、重大性の評価や記録の確定は人が行うべきです。
また、個人情報や紛争性の高い情報の無配慮な入力は厳禁です。氏名、住所、社員番号、健康情報、労使トラブルの内容といった機微情報は、社内で管理された閉域環境に限定するか、原則として仮名化・匿名化して扱うべきです。
生成AIを「便利な外注先」と捉えるのではなく、「標準手順で使う道具」として位置づけ、入力してよい情報といけない情報、AIの出力に必ずつけるべき根拠表示、そして人が行う最終レビューの責任範囲を、事前にルール化しておく必要があります。
実務目線での生成AIの「強み」「弱み」
実務の目線で見ると、生成AIの「強み」は2つに集約できます。
第1に、ゼロからイチを作る時間を削ってくれること。
例えば「改正育児・介護休業法の要点を管理職向けにA41枚で」という目的を1文で与えるだけで、見出し、重要ポイント、対象者に何が起きるのか、初期対応のチェックリストが並びます。
第2に、論点の漏れを早期に可視化してくれることです。
就業規則の改定であれば、AIが提示した案の中に「周知・同意のプロセス」や「経過措置」「労使協定の必要性」といった項目が含まれているかをチェックするだけで、検討の抜けを見つけやすくなります。
逆に「弱み」は、事実認定や適用判断の精度と、最新情報の取り扱いです。
法律名の漢字や条番号、施行期日のズレといった“ケアレスミス”が、AIの出力には紛れ込み得ます。
したがって、AIの文章は必ず「根拠条文・通達名・公表日」を人の手で照合し、必要に応じて一次資料を確認する段取りをセットにしておくべきです。
導入初期に注意したいこと
導入初期に有効なのは、「AIにさせる仕事を、最初から“下書き生成と論点整理”に限定する」という割り切りです。
顧問先レターの草稿、通達の一枚要約、規程改定の叩き台、助成金の候補抽出、研修スライドの章立てと台本──この五つを定番ユースケースとしてテンプレ化し、所内で共有するだけで、日々の“書く・まとめる・伝える”にかかる時間は目に見えて縮みます。
テンプレには、対象業種や従業員規模、前提条件、出力形式、そして「最終判断は専門家が行う」「根拠の出典名を必ず付す」といったガードレール文言を最初から埋め込んでおくと、誰が使っても品質が一定に保たれます。
作成された文書には作成者、作成日、参照資料、レビュー者を記録し、所内の文書管理フォルダに版管理ルールで保存しておけば、後から根拠や経緯を問われても説明可能です。
おわりに
最後に、生成AIは“賢い先生”ではなく“疲れ知らずのスタッフ”だと捉えると、付き合い方がすっきりします。
・調べ、並べ、言い換え、見出しをつけ、図表の骨子をつくる――こうした前工程を高速化し、人間は「本当に伝えるべきことは何か」「この顧問先の事情に照らしてどこまで踏み込むか」という価値判断に時間を使う。
・できることとできないことの境界線を最初に引き、使うたびに“根拠の明示と人の最終レビュー”を欠かさない。
この2つを守れば、生成AIは社労士事務所の生産性と付加価値を同時に引き上げる、強力で安全な味方になるはずです。
【プロフィール】
林雄次(はやし・ゆうじ)
はやし総合支援務所代表。IT関連企業に勤務後、「はやし総合支援事務所」開業。中小企業診断士、社労士、行政書士、情報処理安全確保支援士等として企業向け支援を行いつつ、「資格ソムリエⓇ」「デジタル士業Ⓡ」としてさまざまなメディアで活躍中。僧侶の資格も持つ。保有資格・検定は約600を超える。著書に『社労士事務所のDXマニュアル』(中央経済社)、『資格が教えてくれたこと 400の資格をもつ社労士がみつけた学び方・活かし方・選び方』(日本法令)、『かけ合わせとつながりで稼ぐ 資格のかけ算大全』(実務教育出版)など。