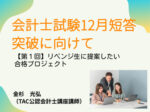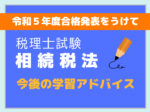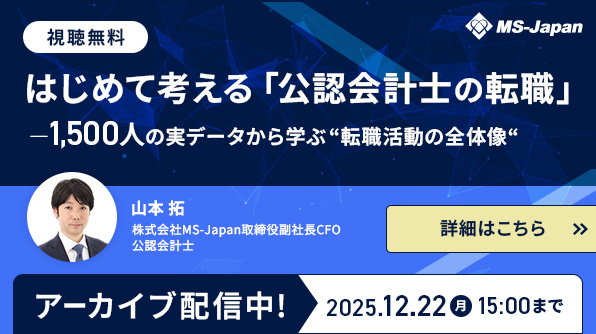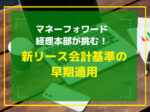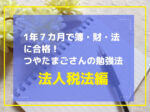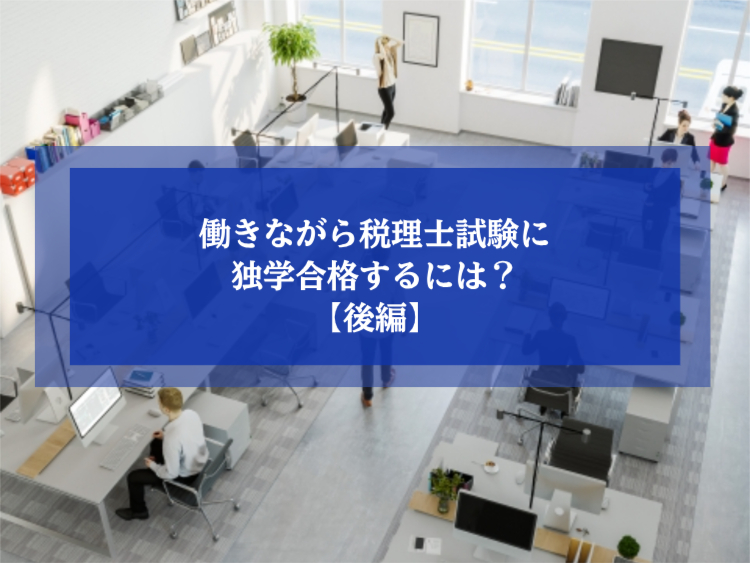
まえさん(20代後半、会社員)
【前編】仕事との両立とモチベーション管理はコチラ
まえさんの合格体験記はコチラ
はじめに
前編では、仕事との両立とモチベーション管理について触れました。
後編では、勉強計画とルーティン、本試験での作戦について書きたいと思います。
勉強計画について
税理士試験の勉強は期間がとても長いので、ざっくり1年を3分割し、それぞれの期間ごとに小さなゴールを作って勉強計画を立てていました。
基礎固め期(9~1月)
この時期には俗にいう基礎固めに集中していました。
理論であれば理論マスターの文言を一言一句暗記すること、計算であれば基本的な計算パターンをインプットすることを意識しながら勉強していました。
この時期のゴールとしては、以下を掲げていました。
理論:理論マスターを赤シートで隠し、重要語句を補いながら口頭でスラスラ読み上げられるようにすること
計算:例題レベルの問題を何も見ずに解けるようになること
実力養成期(2月~GW前)
この時期の目標は、GWに過去問や総合計算問題集の応用編レベルの問題に太刀打ちできる実力をつけることです。
GWは社会人受験生にとって有給休暇を使用せずに試験勉強に時間をかけられる唯一の時期であるため、そこでじっくりと問題演習をできるようにするための勉強をこの時期に進めていました。
この時期のゴールとしては、以下を掲げていました。
理論:短いものについてはベタ書きできるようになる。また、理論ドクターレベルの問題について解答として書くべき箇所が分かる(暗記が間に合ってなくても1-3の理論を書けばいいなど)
計算:個別計算問題集を何も見ずに解けるようになる。総合計算問題集の基礎編で正答率8割をとれるようになる
実力完成期(GW~本試験)
この時期の目標はもちろん本試験合格です。
そのため、理論も覚えるだけでなく書けるように、計算も内容を知ってるだけでなく問題に対する正解を導けるようにということを意識していました。
「本試験合格」をもうすこし細かく見ていくと、以下を掲げていました。
理論:ベタ書き理論については問題を見た時点で何を書けばいいのかを大まかな所要時間とともに判断できる。応用理論については解答要求事項を整理したうえで自分の暗記制度に合わせた解答を作成することができる
計算:本試験レベルの問題(難易度、量とも)を制限時間の9割の時間で8割の正答率を出せるようになる(固定資産税はもちろん10割)
このように、長いスパンを分割してその中で目標やゴールを定めていくと中だるみせずに勉強を進めていけると思います。
科目ごとのルーティンについて
次に、私がルーティンとしていたことを科目ごとに紹介します。
前半ほど勉強方法や時間が固まっていなかったのでルーティンは少なく、後半に行けば行くほど多いです。
ただ、基本的に私の場合、勉強はルーティン化するというより、「できるときにできるだけやる」というスタンスなので、ルーティンと言えるものは他の方より少なめかもしれません。
簿記論・財務諸表論・消費税法受験の年
・週末どちらかは10~15時でカフェに行って勉強
固定資産税受験の年
・勉強開始は計算から、計算の総合問題(土地/建物)を一題解いてから
法人税法受験の年
・平日は就寝前、30分は理論暗記をする
・休日は子供が寝たら計算問題の演習をする
・直前期は会社の昼休憩の時間で理論暗唱
本試験での作戦(特に税法)
本試験では時間がかなりシビアです(特に税法)。
そこで、私は以下のような作戦をとってみました。
ステップ1:事前に理論のベタ書きにどれくらい時間がかかるか(課税仕入れの意義なら5分、評価損の損金計上なら10分など)を把握しておく
ステップ2:解答用紙配布~試験開始後の2~3分ですべての問題に目を通し、ベタ書き理論を完答する前提でかかる時間を計測する
ステップ3:事前に決めた時間配分をベースに計算問題から解き始める
ステップ4:計算問題終了時点の残り時間から1の時間を引いた時間と残りの問題を見比べてどこにどれくらいの時間をかけるかを判断する。その際に、解答が思いつかない個所については1題あたり5分未満でそれっぽい解答を書き、白紙の個所をなるべく減らす
時間がシビアな税法では、どこにどれだけ時間をかけるかで最後の1.2点に差が出ます。
そこで合否が分かれるケースも珍しくありません。
時間配分を考えるには、自分が各タイプの問題に対しどれくらいの時間が必要なのかをあらかじめ知っておくのが重要です。
そこで、直前期では、ステップ1の内容を事前に把握できるように勉強を進めました。
〈プロフィール〉
まえさん@maesan0810
独学で毎年合格を積み重ね、令和6年官報合格。